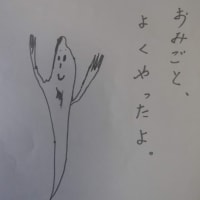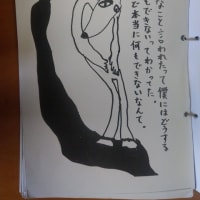『安藤元雄詩集集成』が刊行された。私がその解説を書いているが、そのなかから、傑作中の傑作、「カドミウム・グリーン」について論じたくだりを紹介しよう。なお、詩篇の全文は当該の『安藤元雄詩集集成』もしくは『現代詩文庫・続安藤元雄詩集』にあたられたい。
「カドミウム・グリーン」は、詩集『カドミウム・グリーン』の表題作である。詩集冒頭に置かれ、圧倒的な迫力を放っている。
ここに一刷毛の緑を置く カドミウム・グリーン
ありふれた草むらの色であってはならぬ
ホザンナ
ホザンナ
と わめきながら行進する仮面たちの奔流をよけて
おれがあやうく身をひそめる衝立だ
「ここに一刷毛の緑を置く」と詩行は始まり、絵画行為が暗示されているが、いつのまにか絵は幻想的な現実の光景となり、「おれ」もそこに巻き込まれてゆくという展開。「おれもようやく仮面をかぶることができる」。いや、絵画行為は終始潜在しており、ときおり表層にあらわれる。このいわば複層的な詩の空間のなかに書き込まれているのは、ある擾乱的な街の光景だが、「ホザンナ/ホザンナ/と わめきながら行進する仮面たちの奔流」とあるので、それはどこかキリスト教圏の祭礼の光景だろうか。
絵画行為といえば、読者のなかにはふとベルギーの「仮面の画家」アンソールを想起する向きもあるかもしれない。実は作者自身、この作品の背後にアンソールの大作「キリストのブリュッセル入城」があることを言明している(前橋文学館特別企画展図録『安藤元雄 『秋の鎮魂』から『めぐりの歌』まで』)。仮面をつけた群集が巨大な画面を埋め尽くし、街に歩み入るキリストを迎えているという絵だが、そのさらに背後には、聖書の伝えるイエスのエルサレム入城があり、イエスはそのとき偽善者たちを「白く塗った壁」と呼んだのだった。
ところが第二連、「装甲車は街角からひょいと顔を覗かせ」と、一転してデモか暴動を思わせる展開となり、さらに第三連になると、詩人の個人的な過去の記憶が呼び戻され、絵画行為は記憶と現在つまり時間軸のほうにあらたな次元をひらいてゆく。だが最終連、こうしたすべてがふたたび祭の光景に収束して、
ホザンナ
ホザンナ
カドミウム・グリーン
おれの仮面はまもなく落ちる
と、謎めいたコーダで締めくくられる。「おれの仮面はまもなく落ちる」とは、もちろんそこから素顔があらわれるというような単純な話ではないだろう。仮面とは生そのものの謂かもしれない。
補足的に言えば、文学的記憶もいくつか織り交ぜられ、テクストの厚みをつくりだしている。たとえば第二連に「こおろぎも鳴かない/かつてあの広場で 憂鬱な歩哨のように/おれの通過を許してくれたこおろぎだが」とあるが、これはあきらかにアンドレ・ブルトンの名高い詩篇「ひまわり」の末尾部分を踏まえたもので、安藤元雄とシュルレアリスムとの距離を測ることができる。安藤氏の直上の世代は、飯島耕一や大岡信に代表されるように、シュルレアリスムにほぼ全面的な信頼を置いて、そこから詩の富を引き出そうとしたけれど、安藤氏はそうしたスタンスから一線を画し、やや冷ややかな眼でこの20世紀最大の文学芸術運動を眺めているようだ。というのも、つぎの数行で、夢と行為との一致を思い描いたシュルレアリストたちの理念など、時代の趨勢のまえではひとたまりもないことが暗示されているからである。また、第三連で詩人の前をよぎる「若い女」は、ボードレールの「通り過ぎる女に」のあの忘れがたい場面を起点とする、「通り過ぎる女」の系に連なるものであろう。
こうして、この仮面のパレードが現出させる世界においては、すべてはすべてに流れ込み、嵌入しあい、したがってそれを一定の枠に収めようとする絵画行為は未完に終わるほかない。絵画行為をメタレベル的に詩作のメタファーとみるならば、生と詩作との渦動してやまない関係を、あるいは生から作品へと渡るプロセスそのものにある詩作のダイナミズムを、逆説的ながら起承転結を思わせるきっちりした構成のうちに書き切った見事な傑作、それが「カドミウム・グリーン」なのである。