(人物紹介)
人以外のモノが見える高校生 秋月海
ひょんな事から海の式神となった双子妖怪? ミソカとツゴモリ
視えないが力は強い祖父 秋月コウジロウ
「海を見たかい」
美味しい料理と手作りケーキとコーヒーの店
窓からの夜景が自慢の「カフェ・ソレイユ」へようこそ。
私の名前は「霜月海」
ソレイユのオーナー兼マスターをしています。
この店の従業員はひと癖もふた癖もある人ばかり
体育会系の身体に似合わず可愛いスィーツを作ってくれるシェフ、大川孝之
この店の縁の下の力持ち、営業広報担当のウエイトレス、春野美津子
知る人ぞ知る、コスプレバイト ミソカとツゴモリ
お客様が心からくつろげる優しい空間を提供させて頂きたく思っております。
営業時間は午前11時~午後10時(不定休)
※ランチ営業も始めました。
最後に、他人に相談出来ないようなお悩みを抱えておられるお客様。
一度お電話の上、午後10時以降にご来店下さい。
(要予約、お客様の状態により変わる場合があります)
主な相談内容ーさまざまな原因不明な事柄に悩まされている
恐ろしい事や怖い事がよく起きる
家庭内や身内で不幸な事が続く
骨董品の鑑定 など
「何でも屋」代表 霜月海
この日は営業が終わった後、皆で集まって新商品を決める事になっていた。
「ラズベリーとチョコのムース・季節のアイス添え」
で良くないか?
と言いながら大川シェフが試作品を持ってくる。
「それで、季節のアイスがストロベリーなの?片寄ってない?」
とムースをつつきながら春野マネージャーは言った。
「だから、アイスは苺と抹茶が選べるんだよ」
と大川シェフ
「えー、何か変よ。ねぇ、バランスが悪くない?マスター?」
「そうですね。アイスはバニラにして、抹茶プリンいれて3点にしたら?」
「ーん、それいいかも。小さめにしたら食べやすくて3つならお得感ありね」
「…いけませんか?大川シェフ」
「抹茶プリンかぁ、いいね。それ。今度お前の実家に送ってやろうぜ」
「ありがとうございます。是非お願いします。母も喜ぶでしょう」
と答えた僕を見て嬉しそうに大川は
「よし、抹茶プリンだな」
と言いながら厨房に消えていった。
このソレイユはまだ開店して日が浅い。
試行錯誤の毎日だった。
店の前の駐車場を照らす街灯の下で、桜が花びらを風に舞わせている春の日。
午後11時
駐車場に1台の黒塗りのセダンが入って来る。
運転手つきの車だ。
助手席から降りた男が後部座席のドアを開ける。
コッという小さな音をさせて、スーツを着た女性が降りてくる。
女性は「ソレイユ」のドアを開け中を一瞥してから、霜月を見つけるとサングラスを外して微笑んだ。
「いらっしゃいませ。お待ちしておりました。蔵原さま」
「お久しぶりね。今日は父がどうしてもと、無理を言ったと聞きましたわ」
「どうぞ、こちらへ」
と霜月が窓際の席へ案内をした。
女性に付いてきた男は彼女の少し後ろに立っていた。
その男をチラッと見てから霜月は持っていたメニューを彼女に見せた。
「何になさいますか?」
「そうね、マスターが煎れてくれるならカプチーノにしようかしら」
メニューを素通りした彼女の視線は霜月を見上げた。
「わかりました。しばらくお待ち下さい」
「今日はあの子たちは居ないの?」
「おりますよ。では、私が戻るまでミソカにお連れの方の持つ物を検分させましょう」
と霜月はミソカを呼んだ。
「クラハラ」
とミソカが奥から嬉しそうに走ってくる。
「ミソカちゃん。お久しぶり」
「最近ツゴモリばかりでつまらなかったんですよ~。今日は何ですか?」
「今日はね。古文書よ」
彼女は部下に箱を開けて見せるように指示をした。
男は彼女の座るすぐ横のテーブルに桐の箱を置き、手袋をはめるとゆっくりと蓋を開けた。
古文書は巻き状になっていたが触れるとボロボロになりそうだった。
「カイ。触っていい?」
とミソカが霜月に聞いた。
カプチーノを煎れてテーブルに戻って来た霜月は蔵原に
「お待たせしました」
とカプチーノを出してから、古文書のその状態を見て、
「触れないとわからない?」
とミソカに聞いた。
「ん、ちょっと…」
「そか、じゃ僕を通して視て」
ミソカを見下ろす霜月の左目が金色に光った。
霜月を見上げるミソカの瞳も金色に変わる。
ミソカはその目で古文書を見つめた。
「コレには害をなすようなモノは憑いていないわ。だけど、この出所はコレの価値を見誤っている」
「出所…」
女性はその言葉に納得をしたようだった。
「蔵原さま。ご納得頂けましたか。また私どもをお試しに?」
「え…、ごめんなさいね。少し父がどうしても知りたいと…無理を言いましたわね」
彼女はにっこりと笑った。
霜月は右手を胸に当て、敬意を払うように
「いえ、お構いなく。私どもは蔵原さまには多大なご尽力を頂いておりますので」
感謝しております。と頭を下げた。
「でも、カイくん。もうあれから10年たったのね」
懐かしい呼び名で呼ばれた霜月は
「そうですね」
と、静かに微笑んだ。
「あなた達が父の許に現れた時は本当に驚いたわ」
「…こんな若造が、あの「三鷹」の変わりなど出来るはずが無いと言われましたね」
「あ、あれは私では無く、父がそう言ったのですわよ。私はね。単純に人が空から降りて来たのに驚いたのよ。もう一度、血だらけのあなた達にも驚かされたわね」
彼女は軽やかに笑って言った。
驚いたと言いながら、すぐに対処してしまう彼女に、僕らはそうして何度も助けられていた。
人とは、自分以上の能力を持つ者をこうして使ってゆくのだな。と今更ながら思う霜月だった。
「今日はミソカちゃんに会えて楽しかったわ。カプチーノご馳走さま」
「今度は、是非、大川の居る昼の時間においで下さい。彼らも会いたがっております」
「わかったわ。それでは、またね。ごきげんよう」
「ありがとうございました。蔵原外相によろしくお伝え下さい」
僕は深々と頭を下げた。
そして、ゆっくりと駐車場を出てゆく車を見送った。
舞い散る桜が僕を見ている。
桜は僕らに起きた様々な出来事を全て見てくれている。
「あれから10年…、いや、12年になるか…」
今は、ここで休んでゆきなさい。
と語りかけてくれている気がした。
多分、それは間違ってはいないだろう…。
僕はやっと貴女の声が聴こえるようになった…。
貴女は、全てを無くしたこの身に優しく語りかけてくれる。
僕の左腕は肩から上に上がらない。
これはあの日の代償だ。
それと、バランスが悪いけれど左側の前髪を少し長くしている。
それは僕の左目が光りの加減で金色に見える事があるから…。
そして、僕は「秋月」ではなく「霜月」を名乗っている。
その全てを知ってもなお、桜は優しく、
「大丈夫」と…言ってくれる…。
あれは12年前…。
僕はこの桜を切る事に納得が出来ずにいた。
ここには昔、メゾン「ソレイユ」が建っていた。
今から始まるお話はまだここがメゾンでもなかった頃の事。
僕がまだ何も知らずにいた頃の事。
1話 「スマイルの値段」
高校2年の夏、俺は東京の祖父の家だった古いアパートに居た。
ここは取り壊されてキレイなメゾンとかいうのに建て替えられる。
その工事を見る為にここに来たけど、僕が東京に出て来た一番の目的は、来年、東京の大学を受験する塾の模試と講習を受ける為だった。
この辺りは、都内だが造園関係の業者が多い所為か、落ち着いた雰囲気がしていた。
JRの駅から徒歩で7~8分、ゆるやかな坂の途中にあった。
道路の向こう側には梅の生産農地があって、その先は遠くに都心が見えていた。
ここに来る道を曲がらずにまっすぐ行き、小高い丘を上がりきると公園がある。
そのまま下ると、私鉄の駅があった。
俺はJRの方の駅前ホテルに予約をしていた。
夏中はずっとホテルで過ごして秋に実家に戻る。
夏のお盆明けくらいには、ここの取り壊しがはじまる。
古いアパートとは言っても建物はただの部屋数の多い民家で、普通のアパートとは違っていた。
だから、ここに住む人は間借りか居候みたいになっていたようだ。
祖父がここを離れたのが10年くらい前で、住人の為に残してあったのだが、それも一昨年ここを出た老夫婦を最後に誰も住んでいなかった。
建て直した後の入居案内がもう始まっていた。
俺はここに来てすぐに庭の隅にある桜の木を残す事に決めたので、解体工事前に植木屋を呼んでその木を一時移動させる事になった。
今日は植木屋が来る日だった。
植木屋が来るまで俺は母屋の中に入って中を確かめた。
これはそんな、暑い夏の日の物語。
俺の名は、秋月海(アキヅキカイ)
さっきも言ったが、俺は高校2年。
地元では進学校に通っている。
成績は悪くない方だが、東京の大学を受けるならと夏休みは東京の塾に通う事になった。
ここがメゾンになったら俺は管理人として入る事になっていた。
なので、
いろいろな手続きをしつつ駅前のホテルで2ヶ月近く過ごす予定だった。
俺は祖父の部屋に入った。
家具などはもうすべて片付けられていて何もなかった。
畳もすべて無く、埃の積もった床板がギシギシ鳴っていた。
そこに、
ただ一つ小さな古い鈴が落ちていた。
赤い紐の汚れた小さな鈴だ。
拾い上げて、振ってみても鳴りもしなかった。
最初は業者が落としたものかと思ったが、鮮やかな赤い色があまりにも不釣合いだった。
俺はそれをポケットにしまいガタガタ言わせながら窓を開け、桜の木を見ていた。
俺はずっと小さい頃にここに来た事があった。
桜の時期だったのだろう、舞い散る桜と祖母の姿を覚えていた。
だから、この桜を残す事に決めた。
元々細い幹に枝がひょろひょろと伸びた小さい桜だ。
無理して残す事もないのだが、10年前からほとんど手入れをしていない庭で、益々小さくなっている桜が可哀想に見えたのだ。
だけど、ここに植え戻しても、今度はここには母屋は無いし、目の前は駐車場になってしまうのだけれど、と思っていた。
「大切に預かります、大事に育ててやりましょうね」
と言った植木屋のおじさんの言葉が優しくて嬉しかった。
植木屋は桜を運んで行った。
誰がイルの?
アキヅキ?
アキヅキが帰ったの?
あれ?
そして俺は駅に向かい、電車に乗り深川に向かった。
駅から少し歩くと小さな公園の隣に小さな神社があった。
俺は鈴を取り出した。
ここは懐かしい所
ワタシが生まれた場所
どうしたの?
どうするの?
ココに置いていかれちゃうの?
イヤだ。
置いていかないで。
チリンと、古い小さな鈴はもう鳴らないかと思っていたのに、小さく鳴った。
俺は祭壇で手を合わせて願いを言い鈴をポケットにしまった。
駅に戻り電車に乗った。
鈴は胸ポケットにあった。
外がみえる。
家から出た事がなかったけど
昔の事は覚えている
こんなに人が多いなんて
建物は高いし
ピカピカしてるし
夜になっても
とっても明るい
ホテルについて親父に電話をかけるとまた鈴が鳴ったような気がした。
そこに居るの?
アキヅキ?
会いたいな。
でもアキヅキも
子供も見えないんだよね
「おい、鈴。東京見物出来たか?明日からは当分ここだからな」
「え?」
「おやすみっ!」と
電気が消えた
翌日、塾から戻った海はハンバーガーのセットを晩御飯にしていた。
「ポテト食う?」と目の前の机にあった鈴に言うと、
「食う」と返事がきた。
やがて、その姿も見えてきた。
「お前、女なのか?じゃあ、食うはないよ。食べるって言えよ」
「おいしいーー」と女
「オイ、お前…」
女の姿は着物姿だった。
カフェのような白い丸くてひらひらが付いた短いエプロンをしていた。
そして、何故か着物の丈が短かった。
今風のお化けかこいつは?と思った。
前かがみになると見えそうな短さだったのだ。
髪型はツインテールだし、茶色だし…。
東京の……って違うのかもな。
と呆れて眺めていると、
その女は本当に驚いた顔をして、こう言った。
「ええー、君、ワタシが見えるの?」
「見えるけど」
これが2人の出会いだった。
ポテトを食べながら女は俺に聞いた。
改めて見ると、女というより女の子のが合っている、見た目は14~5歳だった。
この頃の俺は怖いもの知らずで、何も知らないのに知っていると思っていた。
「君はアキヅキの何?」
「俺も秋月だけど」
「コウジロウの何?」
「孫」
「孫?」
「そうなんだ。あれ?なんで私と話せるの?」
「さあね}
「君って何?」
「秋月 海」
「名前じゃなくて何者なの?」
「16歳。高校2年生だけど」
「だから、なんで見えるのーー!」
「…昔から霊とか、人以外のモノが見えるよ」
「ヒト以外のモノ」
「話せるのは珍しいけどね。
あんたこそなに?」
「んーーー、妖怪なのかな。神の成りそこない」
「ふーーん」
彼女は俺をじっと品定めするように見てきた。俺はその視線を見返した。
そして、
「ね。ね。ワタシに名前をくれない?」
と言った。
「名前?なんで」
「そしたらもっと話せるようになるから」
「えー、そんなの面倒くさい。話せなくても俺は気にならない」
今度は俺がこいつの品定めをする番だ。
名を付けてだって?
そんな事を言ってくる妖怪なんて聞いた事がない。
大体、名前はあるはずだ。ソレを言わないでつけてくれとは、胡散臭い。
やっぱり、面倒はごめんだ。
そんな俺の視線に気付いたのか、
「お願い。きっと何かに役に立つから、だって神さまなんだよう。式神で使ってよ」
と言ってきた。
「成りそこないなんでしょ?」
「…うん、でも。お願い」
ヒトの子の俺に手をあわせている。
いったい、こいつは何なんだ。
「なんでそんなにこっちに居たいの?」
「コレがまた食べたいの」と
ポテトの紙容器を見せる。
「あ、俺のポテト!全部食べたのか?」
「うん。くれたじゃない。食う?って。あれはお供えじゃなかったの?」
「いや、俺の晩御飯…」
「でもくれたじゃない」
「確かに食うかって言ったけど…俺の所為なのか、そうだよなぁ……」
迂闊だった。
ただの古い鈴だと思ってた。
まさか何かが出てくるとは思わなかった。
見た所、悪いモノじゃなさそうだし、祖父を知っているならなおさら悪い事はしないだろう…。
…仕方がない。
「名前を付けるよ。俺の名前から取ってもいいか?」
「いい。いい。それすっごく良い。使役してね」
「んーと。なら、ミソカでいい?」
「ミソカ」
「俺の本名、秋月 晦(ミソカ)だからさ」
「あの、もう一人もつけてもらっていい?」
「え、何で?」
「双子の弟がいるのよ」
「んーーっと、じゃあ、ツゴモリ」
「ツゴモリ」
「晦はツゴモリとも読むから」
「ありがと」
「どう致しまして。でもさ、俺、式神なんて使わないから」
「そうなの?そんなに強いのに?」
「別に俺は強くない。見えるだけでじいちゃんの様にはいかない」
「コウジロウは見えなかったじゃない」
「見えなくても十分強かったろ?」
「うん」
と嬉しそうにミソカはうなずいた。
「俺もじいちゃんは尊敬してるから式を使うのはいいんだ。いいけど、俺には同じ事は出来ないからな。それに…俺は嫌なんだ…」
「何が?」
「だってさ、神の成りそこないって言っても神なんだろ?だったら、人間の出来ない事が出来る訳だろ?」
「そりゃあ、出来るわよ。それなりにだけど」
「なら、俺に仕える必要は無いんじゃない?」
「え?違う違う。私達は命令が無いとなーーんにも出来ないの」
「意味わかんね。命令なんて、そんな窮屈な。余計に人に仕える必要ないんじゃない」
「こうしてここに居る事すら出来ないの」
「ここに?じゃ、なんで居るんだ?」
「カイが鈴を持ち出してくれたからよ」
「??鈴は持ち出したけど…」
「そ、それをワタシの居た神社まで持ってって、これからよろしくお願いします。って言ったでしょ?」
「あぁ、言った。お前の神社とは知らなかったし、だた合格祈願に行っただけだ。受験のお願いをしたんだ」
「…あれ、受験だったの?」
「…そうだけど、何か?」
「あれ、私をこれからよろしく。って思ったのに」
「あ?何でそんなお願い…お前と会う前じゃないか、言うわけ無いだろ」
「そっか、それで出て来たのに…」
と、心底がっがりしたような顔をミソカはした。
俺だって、がっかりだった。
「受験のお願いだよ。でもそれも俺の所為か…まさか、鈴から何か出てくるなんて…」
「ワタシが、間違えちゃったからだよ。でも、ミソカってもうもらったから、よろしくね」
と、もう元気になったようだ。
相手をしてられない。
「ポテトなら奉納してやるから、そろそろ消えてくれ」
と、俺は言った。
だが、ポテトと言うと、俺はバーガー1個しか食べてない。
何か買って行こうと部屋を出る事にした。
「またセットで、ポテトを買ってー」とクーポン券を見ながらミソカがうるさく言い、憑いてきた。
「いや、今度はコンビニにする」
「そこにもポテトあるの?奉納してくれるんでしょ?」
と、ミソカが言った。
俺達は駅前に出た。
そして、歩いていると、
「ねぇ、ねぇ、アレおかしくない?」
とミソカが、俺を引っ張った。
言われた方を見ると、駅のすぐ横の踏み切りに女子高生が居る。
「ねぇ、変よね…」
手にカバンを下げて立っていたその子が、カバンを落とした。
そのまま線路に向かって歩いてゆく。
「くそッ!」
俺は彼女に向かって走った。
遮断機を少し持ち上げて、下をくぐる彼女。
俺も遮断機を潜った。
誰かの悲鳴が聞こえる。
目の前で自殺なんてされたくない!
第一、ここで死ぬのは良くない!
だが、あと少しで手が届かない。
電車が来る。
俺では間に合わない。
「ミソカーーー!」
俺のヨコを風が通り過ぎる。
ミソカが彼女を抱えて引っ張る。
俺の手がやっと届き、俺とその子は踏み切り脇へと逃れた。
電車が警笛とブレーキ音と共に駅へすべり込んでゆく。
俺達は踏み切り前ですっころんでいたが、事が大きくなる前に逃げ出た。
駅前のビルの中にある俺がさっき寄ったバーガー店に入った。
ここに来る前に買うつもりだったセットをとりあえず頼むと、2階の隅のテーブルについた。
セットのジュースを彼女に渡して「ここにいて」と言ってから僕は駅前に戻った。
やはり駅前は少し騒ぎになっていた。
僕は急いで彼女のカバンを拾うと、コンビニで消毒と絆創膏を買って戻った。
「そこ、手当てさせてもらっていいかな?」
彼女は膝と肘を擦りむいていた。
手早く手当てを済ませた俺を見て、はじめて彼女が口をきいた。
「慣れてる…ね」
と言った。
「手当てが?こんな怪我しょっちゅうだから」
と答えると、
「違う。女の子の扱いが」
彼女が言う。
「え…なんで、そう思う?」
「普通、女子高生の足やら腕やらって触るのってした事無いんじゃないかと思って。緊張したり興奮したりしないの?」
何を言ってるんだか…この女は。
「そういう意味なら、触った事ないけどさ、今の君は、ただの怪我人じゃん。あぁ、でも、その怪我は俺がさせたようなもんだもんな。手当てするのは当然だろ」
と言って俺は、消毒と傷パッドと絆創膏の入ったコンビニの袋を彼女のカバンに乱暴に突っ込んだ。
そんな事より、この子はさっきの事をどう思っているのだろう。
ついさっきだ。
まだ外は騒がしい。
警察を呼んでいるかもしれない、ここからも早く出た方がよさそうだ。
そう伝えると、
「そっか、わかった」
とあっさりと彼女は言った。
「それにコレ着て、返さなくていいから」
俺はホテルに入る前に買ったユニクロの袋に入ったままのチェックのパーカーを彼女に渡した。
「何で?」
彼女の白い制服の背中にさっき転んだ時についたのだろうブレーキ痕みたいな黒い線がはっきりとついてしまっていた。
そのままじゃ、駅前に出たらばれてしまうかもしれないと説明した。
トイレに行った彼女が着替えて戻って来る。
戻ってきた彼女は礼を言うと飲みかけのジュースを持って出ていった。
俺は持ち帰り用に袋をもらい店を出た。
騒ぎを横目に駅の階段を上がってゆく彼女を確認してからホテルに戻った。
ロビーで缶コーヒーを買い部屋へ上がった。
「疲れた…」
俺はミソカに袋ごとポテトを渡した。
「ねぇ、ワタシといて良かったでしょ?」
「まぁな、俺じゃ間に合わなかったから…」
「ね」
「…ありがとう…」
「お礼なんていらないわ。当然よー」
「…ダメだぁ。マジ疲れた。今日は…寝る」
と俺はベッドに横になった。
「頭痛もするの?」
「ああ…」
「あ、わかった。あんたあの子に何かしたでしょ?」
「人聞きの悪い言い方をするなよ…」
「何したの?」
「何もしていないよ。視ただけだ…。だけど、何も言わないってどういう事だよ。あの子には、何かあるのはわかるけど…。まぁ、もう会う事もないだろうけどさ」
「そっか…」
「ったく。こんなのは、疲れるんだ…イテテ…」
と俺は頭につめたい缶コーヒーを当てた。
「あんた、思ったより良い子だね」
俺の額にミソカが手をあてる。
冷んやりとして気持ちが良かった。
「思ったよりは余計だ。だけど、お前も思ってたより良いかもな」
「思ってたよりが余計だよ」
と2人は笑った。
これがミソカと会った夏の始まりの事件だった。
俺はこの後、あのバーガー屋で短期のバイトを始めた。
そして俺は
「ポテト好きだねぇ」と言われるようになった。
当然それは俺が食べているのではなかったのだが、笑ってごまかしていた。
今日もバイトが終わり、部屋に戻るとミソカが言った。
「ご一緒にポテトはいかがですか?
ついでに、悪霊祓いはいかがですか?」
終
真城 灯火「スマイルの値段」















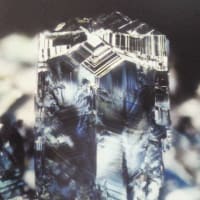

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます