ナショナルギャラリー編短編・リョーマがきた
昨日は不二先輩の誕生日でした。
いろいろ探してみたら、古い私の小説がでてきましたので、ここにしるします。
BLが苦手な方、BLの意味が分からない方は、なるべく見ないでください。
まあ見ても健全な文章ですが。
私、6年前、こんなすげー文章書いてたんだと自分でうひゃあと思いました(笑)
自惚れしてるし(笑)
◆注意◆
エロくないです。
頬にキスはします。くちびるにはしません。
R指定なし。
不二が手塚に抱っこするのも、服着た状態で、です。
※未来設定※
手塚と不二はイギリスのナショナルギャラリーの近くのアパートに暮らしています。奥に不二先輩と裕太が住まう部屋。その隣に手塚の部屋。その隣に跡部の物置(部屋です)があります。ですが、不二は手塚の部屋に入りびたり。半分同棲です。ただ、注意。まだ性行為は行ったことはありません。
※職業※
手塚・・・プロテニスプレイヤー
不二・・・ミラクルドクター
跡部・・・大会社のイギリス支社の課長
裕太・・・看護師
サライ・・・イギリスの貴族の中の貴族だが、医者。
ミラクルドクター不二の弟子。
(私のオリジナル人物)
はじまりはじまり
帽子のつばをさらに沈めるリョーマを目の前に、不二はぷうと頬を膨らました。
「もう。越前てば、いっつも急なんだから」
「ども、ッス」
雲一つない青空。太陽がいろいろな色の光を投げかけ、照っていた。リョーマは風に翻る不二の白衣を、眩しそうに見上げた。
緊急で運ばれてきた男性の心臓手術を終え、不二はほっと一息ついて自分の机でコーヒーを飲んでいた。次の予約の大腸の手術まであと一時間半ほど。それまで暫く身体を休めて備えようと、ちょうど占いの雑誌を手にとって読み始めたとき、サライが悲しげな顔をして不二を呼びにやってきたのだった。
「ねぇドクター不二い」
「あ、サライ。どこ行ってたの」
「ちょっと弟が携帯に電話してきたから、外に。そしたらねテニスバッグ背負った男の子が、ぼくにドクター不二呼んでくれないって言うんですよ」
「へぇ?」
「なんで、やっぱりドクター不二はテニス少年に人気ですね。ぼくは……」
「そんなことないよ。サライはよくやってるし。ボク好きだよ?」
「その好きはぼくが求めてる好きじゃないでしょ。ひどいよ、もぉ」
眉を下げたサライは、本来ならどんな相手だっておとせそうな美男子である。生粋のロンドンっ子、そして女王陛下も一目置いている大金持ちの息子、それがあろうことか絶対におとせない男に恋をしてしまった。
「で? 待ってるのその子?」
その相手は今サライの目の前でにっこりと微笑み、サライに早く続きを言おうねと迫る。それでもひたすらに想っていたいという心は諦めきれず、ため息まじりにサライは答えた。
「はい。アメリカ的な男の子で、背が低い子です。知り合い、ですよね」
――え、越前?! まさかね。
「うーん。とにかく行ってみるよ」
柔らかな動作で立ち上がり、サライに微笑をあげて部屋を出て行くドクター不二。サライは恨めしそうにその華奢な背中を見送った。そして少しでも自分の想う人の体温を感じていたくて、空になった椅子に座って残された占い雑誌をめくった。
うぃぃん。自動ドアが開き、一歩踏み出すと、懐かしいその名称を呼ばれた。ゆっくり、不二は顔を呼ばれた方向へと向ける。
「不二先輩」
「やあ越前」
――くすっ相変わらずの白いフィラの帽子。似合ってる。
病院の待合室に入ってればよかったのに、そう言うと「ういっす」と言って取り合ってくれない。そんな細かいところまで、会ったときから全然変わらなかった。
「ふふっ」
「不二先輩。意味ありげな微笑み、怖いッス」
「そうかな。べつに意味なんてないよ。越前可愛いな、ってこと、強いて言えばね」
「それがあるって言うんス」
とにかく入ろうよ、と促して不二とリョーマは一緒に自動ドアをかいくぐり、適度に冷房の利いた病院の待合室へと入った。
不二が勤めている病院は、イギリスの名のある大学病院である。ここで二年間の研修を受けて、それから不二と裕太はようやく一人前の医師と看護師になるのだった。
といっても、今からもう不二の腕前はすごい。ミラクルドクター不二、そう世間で騒がれ、どんなに難しい手術でも成功率は半端じゃない。裕太と同い年、つまり一歳年下のサライを助手につけ、弟の裕太はその器械出し看護師としてオペを行う。
メスを持つと静かに開眼するヘーゼルの瞳は青い光を帯びて、キラリと不敵に輝く。その凛とした美しさも半端ではなかった。
普段の優しい細い瞳からは想像もできないその美しくも恐ろしい瞳は、半ば同居しているらしいプロテニスプレイヤー手塚国光と一緒にテニスで遊んでいるときにも窺える。遊ぶ、というほどのものでない。その冷たく綺麗な不二の瞳は、彼が本気であるという証拠だ。
――あ、また。不二先輩からいい匂いが。
リョーマはその先輩に憧れ、恋い慕っていたあの頃の自分を思い出した。まだ幼くて小さくて。今も小さいけれどその今とも比べようもないくらい俺は小さくて。そしてふわり、綺麗な柔らかな茶色の髪が揺れてなんともいえない香りが漂ったとき、不覚にも男のその先輩に恋してしまった。ねえ越前、その優しい声が嬉しくて、そして会ったその初日から俺を認めてくれていて。けれど不二先輩はもうその頃から、いや俺が青春学園中等部に入学する以前からずっと、恋情を全て手塚部長に注いでいた。
知ったときのショックは忘れられない。それでも、敵わないと瞳を逸らした自分を、不安げに気遣ってくれた先輩を恋慕う気持ちは捨てられなくて。今も、ちょっとだけ、先輩が好きだ。プロテニスプレイヤー越前リョーマ、物心つく前からの夢だったこと。それは自分で決めたことだと豪語できる。でもね。手塚部長、少しはあんたのおかげでもあるかもしれない。
「ね、越前」
ほらまた。きっと、もう一人の弟みたく俺のこと見ているんでしょうけど。だけど、嬉しいんスよ、その声ほんとに。
「ボクに何の用だったの?」
やんわりした口調、相変わらずッスね。
リョーマはふうと肩で息をつくと、真っ直ぐに不二の瞳をとらえて、そして言った。
「部長――手塚先輩と勝負したいと思って、不二先輩に都合を聞きに来た」
「――え、ボクに?!」
「そう。だって、同棲しているんでしょ?」
サボテンの花の香水を、今日もつけてきた。不二が香水に手を伸ばすようになったということを、ちょっとしたきっかけで手塚が跡部に話したのだが、そうしたら跡部が様々な種類のものを見つけ出しては不二にくれるようになった。
悪いよ。そう言うと、俺様からのささやかな好意だ、受け取れ。そう言って押し付ける。仕方ないから、四分の三の金額は出すということで承知してもらった。
――まったく。でも嬉しいけどね。
サボテンの花はとにかく希少価値。細やかに小学生の時代からサボテンを世話し続けてきた不二ですら、まだ二桁の数しか咲かせていなかった。
今朝は寝惚けてて、そしたら手塚が
「不二、起きろ!」
そう怒鳴って、ベッドから転がりだされた。
「痛い。ひどいよ手塚ぁ」
「痛くはないはずだが。俺が抱き締めているからな」
「えぇっ?」
手塚にお姫様抱っこされていることに気付いて、頬が熱くなるのが自分でも分かる。手塚の漆黒の瞳が、眼鏡をまだかけていないからか、いつもより大きく、そして優しく瞬いた。
――キミって、ボクへの優しさの最大値もってるのかな。
「ずっと、ボクたちの想いが上昇していければいいよね」
スゥっと自然と口から漏れでた言葉に、自分で赤面した。
「ああ。そうだな」
すぐに頷き返してくれたキミが愛しくて。にっこり笑ったら、頬をつんつんと突かれた。ひんやり、キミの指先が冷たい。
「わ、何するのさ」
「おまえはすぐに赤くなる」
また、その台詞に薄紅色に染められて、手塚の瞳が優しく笑ってくれた。
手塚の作った朝ごはんを慌しく食べて、「いってきます」と靴を履いた途端、「待て!」と手塚にまた怒鳴られた。
「な、何さ?」
「おまえ、香水を忘れている」
「あぁ…べつにいいや」
「よくない。俺がかけてやる」
「え、あ、ありがと」
――うわ、手塚ったらかけ過ぎだって。
「よしこれでいい。行ってこい」
「うん、行ってくるね。ばいばい」
手を振って、ドアが閉まったとき、ふんわりした風が香水の匂いをそこらじゅうにぶちまけた。
――やっぱりかけ過ぎだ。
でも手塚がわざわざしてくれたことだから、胸の奥はほんわり暖かくて、不二はこのなんだか不思議な気持ちをかみしめて、病院に向かったのだった。
みんななんとも言わないけれど、越前くらいは何か言うかな。そう思っていたら、越前はちらっと髪を見上げて満足そうな笑みを零した。
――んー?
何に笑ったんだろうね?
「ね、越前。ボクに何の用だったの?」
一瞬の間。
「部長――手塚先輩と勝負したいと思って、不二先輩に都合を聞きに来た」
「――え、ボクに?!」
「そう。だって、同棲しているんでしょ?」
どきっ胸がはねあがる。同棲…ね、確かに。キスすらしてないけどね。
「ど、同棲って手塚が聞いたら怒りそうな響きはらんでるよね」
「ねえ先輩、はぐらかさないでよ。同棲してるんでしょ? だから」
「だから? もしかしてアパートの場所が分からなかったのかな? くす越前ったら」
「な、なに」
「芳香オンチ」
「え。それってどっちの? 不二先輩の匂いならとっくのとうに気付いてますよ。でも俺は昔の、もっとよく先輩見ないと分からないような繊細な匂いのほうが好きッスけど」
「え? え、越前?」
「昔の不二先輩のほうが好きって言ってるんス。だって」
――だって。まだ部長が自分の不二先輩への想い、気付いてなかったから。だから、俺
が先輩のこと好きっていうこと、こんなに自分で切なくなることはなかったから。
「だって結構強いもん今、香水。きっと手塚先輩が今朝無理矢理かけたとか、だよね」
「えぇ! ど、どうして分かるのさっ越前」
「え。やっぱりそうだったんだ……。同棲してるんだ」
「もっもう! 同棲しているってわけじゃないんだから」
「不二先輩。なーんかツンデレッスね」
「誰のせいかな? ふふふ」
「わ、怖いッス、それ。でも安心した」
「え?」
純粋に首をかしげる不二に、リョーマはほぉと見惚れて息をついた。綺麗。茶色の髪が艶やかで、ふわふわ繊細に揺れて綺麗だ、この人。
「不二先輩がずーと同じで。みんなに優しくて、――中でも部長が特別で」
「え越前……」
「俺、だから不二先輩が好きなんだなってこの頃思います」
「越前……それって」
――ボクへの告白? まさか、越前に限ってそんなこと、たぶんないよね。
「好き」って違う意味……だよね。あ、ありがとう越前。
「ありがとう。越前」
にっこり笑った不二の優しい台詞に、リョーマはぐさりと胸が痛んだが、表面上はできる限りの照れ笑いをして、その場は終わった。
――ここか。
ぎりぎりまで近寄って見上げると、その二階建てのアパートがまるで聳え立つ楼閣のように思われた。
――待ってろよ。部長。
道の向こうにはロンドン・ナショナルギャラリーの賑わいがよく見える。
「ふーん。けっこーいい場所じゃん」
風がさあっと吹き過ぎる。後ろから深い足音が近づいて、リョーマは胸が高鳴っていくのを覚えた。
「越前…か。何をしにきた」
低く響く妖艶な声音。
「――あんたと戦いにきた」
振り返るリョーマには、コマ写しのようにその最大の敵の姿が映しだされていた。
大腸手術が無事終わった。患者さんは綺麗な女の人だった、ネイルが姉さんの趣味に似ていると思った。手術室を出る際、裕太にそう言ったら裕太もそうだねと肯いた。
医者は患者を人として見ない、特に外科医は。そうささやかれている言葉ははたして正しいのだろうかとついつい思ってしまう。
――ボクもいつか、そんなふうになるのだろうか。
サライはどうなのかな。眠そうにふわあとあくびした彼に、不二は微笑して近寄っていった。
今日は不二は病院の夜番だった。リョーマが手塚のもとへと向かったのは昼の二時過ぎ。越前の性格からあわせて考えても、二人の草試合は今日の午後行われるはずでそれを見られるよしはないだろうと不二は思った。
「見たかったな」
ぽつんサライの前に来て飛び出した言葉はそれで、不二は少し慌てた。
「あ、えっとねサライ」
「ほんとですね~、ドクター不二」
サライが眠そうに相槌を打った。
「ぼくだってドクター不二と一緒にベッドで寝たいよ」
「サ、サライ?」
どうやら意味が通じない領域に彼がいるのだと察知して、不二はぽんぽんとサライの背中を叩き、そっとその自分とよく似た華奢な背中に微笑んだ。
――お疲れ様。
少しでも休まってくれたらいい、そう思う。サライの気持ちにはたぶん応えてあげられないだろうけれど。
「サライ、今日夜番?」
「え? あれ、えっとぼくが夜番かって? 違いますよ」
「そう。ボクは夜番なんだ。そっか、じゃあ雑誌でも読んでるほかないみたいだね」
「じゃあぼくちょっと誰かと話してきます」
「……えっ」
瞳をこすりながらぱたぱた走っていく後輩を、不二は呆然として見送った。
――嫌われちゃったのかな。ボク何かした…?
でも、確かにボクから離れたほうがサライにはいいかもしれないね。
「はぁ」
こんなときこそ手塚がいてくれたら、どんなに温まるだろうと思ってみたが、そうもいかない。
「手塚ぁ」
髪の毛の痛烈な芳香こそが、今日の手塚の想いだと心の中に言い聞かせ、不二はそっと自分の髪を撫でて気を休めている最中――。
「不二!」
突如した、耳にやすらかなその低い声に、不二はびっくりしてその方向を見上げた――というのはちょうど真上から手塚の声が発せられたのだった。
「て、手塚!? ど、どうしてキミがここに」
「今呼んだだろう」
「それはそうだけど…そんな都合よく」
「そうだな。推測に過ぎないが、俺はおまえが呼べばいつでも存在するのかもしれない」
「え? 手塚どうしたの、何かの台詞?」
「いやなんでもない。それよりもな不二……」
ゆっくりペースで歩いていたら、いつのまにやらオペの仲間たちはみなどこかに行ってしまったようだった。真っ白い廊下にキミが立っていて、ボクが寄り添っている、その二人だけの空間。やっぱりキミといるとあったまる。
「手塚ぁ」
手塚の言葉を遮って、思ったまま不二は手塚にぎゅうと抱きついた。
抱きつかれた手塚は一瞬驚きの表情を見せて、すぐに不二の背に手を伸ばして慈しむように茶色の髪を撫でてやった。
「少し湿っているな…」
茶色の下地に煌く光が眩い。
「手術が終わったばかりだからね」
「そうか」
「うん…」
「不二、話があるのだが」
改めて、真摯に瞳を覗かれて、少しくすぐったい感覚に襲われる。
「あ、そうだったよねごめん。なに?」
「越前に試合を申し込まれた」
「ああそうだろうね」
「そうだろうね、って知っているのか?」
――越前がロンドンにいること自体、不二おまえは知っているのか?
手塚の理由を説明しろというひそめられた眉に、不二はくすくす笑ってしまった。
「今日越前が病院に来たの」
「病院に?」
「うん。で、アパートの場所を聞くんだ。ボクとキミがね同棲してるのかって言ってた。きっと大学病院のほうが道分かりやすかったんじゃないの? 英二とかはボクたちの状況を全部知っているしね、ボクが医者だってことよく知ってた」
「そうか」
「それで試合したの?」
「迷っている」
「えっ」
微かに不二の眉が歪められる。それは本当に微かなために、人から見ればいつもどおりの笑みにしか見えないが、手塚にはそれがよく分かった。少し狼狽する手塚を前に、
「何に」
不二は辛烈な響きを込めて言い放った。
「越前はせっかく来たんだよ?」
「しかし今日は」
「あ~! ドクター不二い!」
「サライ?」
「緊急手術に呼ばれてる。工場で爆発事故。あと五分くらいで救急車がつくって」
「え…。うん、分かった!」
ぱたぱた走っていくサライを追っていた瞳をはずし、不二は手塚のほうへ向き直った。
「手塚。ごめん行かなきゃ」
「そのようだな」
「うん。今日は一応夜番だったけど、このぶんじゃみんなそうかな」
「ああ」
手塚の瞳が今朝よりもまた優しく光った気がして、不二は不思議そうにその光を覗き込んだ。
「頑張ってこい」
「ボク行くね。越前との試合は?」
「おまえが今日いないなら、やることにする」
「もう日が沈むよ」
「知ってる。しかしやれ、というのがおまえの望みだろう」
不二はハッと気付いた。
――ああボク馬鹿だった。手塚の瞳がちょっと潤んでいたりするの、それは。
「んんん。試合は明日、だね。手塚、今日熱あるんでしょ、ごめんね。ボクもっと早くに気付かなくて――」
――だって、手塚が病院に直接来るなんて、めったにないもの。
不二が爪先立ちして手塚の額に額をくっつけると、やはり熱があるのだと確信できた。手塚は胸がきゅーんとなって、「どきどきしているからだ」と呟いたものの口の中だけでそれは終わった。
「今日は早く寝てね。ボク、帰ったらキミの横にすぐに行くから」
「しかしそれでは風邪が」
「関係ないよ。ボクはキミの役に立ちたいの。キミの横に行きたいの。そうでなきゃ、きっとボクすごいひどい病気になっちゃうと思う」
「不二……」
嬉しそうに頷く彼に最上級の微笑みを与えて。
「じゃあもう行くね」
「ああ。待ってる」
ヒグマのシールの貼られた鍵を取り出し、越前に泊まっていくよう言った。散々に迷った。というのは俺の部屋を使わせるか不二の部屋を使わせるか。
「どちらがいい」
「アンタ決めてよ、都合とかあるんじゃないの?」
「相変わらずの奴だな。わかった」
そう言ってポケットをまさぐったときに、決めた。不二と裕太くんの部屋にしよう。
「今日は早く寝てね。ボク、帰ったらキミの横にすぐに行くから。キミの役に立ちたいの。キミの横に行きたいの」
耳の奥に余韻を伴って残る、彼の最上級の甘い囁き。そしてそれとともに思い出されるヘーゼルの瞳に宿る俺だけの為の優しさ。
――明け方、不二は俺の部屋に来る。
手塚は確信していた。自分の中で肯いて、アパートの二階の通路の行き止まりでヒグマのシールのそれを鍵穴に差し込むと、宵のナショナルギャラリー付近から洩れる灯りに銀の色がちかりちかり反射した。
「こっちだ。越前」
そっと空を見上げれば、そちらの方向に風船みたいなオレンジと紫色の太陽があった。
「ウィッース」
その声とともに、ぎいとドアが開いた。
不二兄弟の部屋は、卵、小麦粉、バターやらのお菓子の匂いが立ち込めていた。二人とも毎年の二月十四日のため甘いものには慣れているはずなのに、手塚は眉をしかめ、その後ろでリョーマは軽くむせる、そのくらい強い匂いである。
「ここ、裕太さんの部屋ですか」
きょろきょろ見回しながらリョーマが呟く。手塚が電灯を点けると、テーブルの上に今朝作ったのだろうスコーンがラップにくるまって幾つか置かれているのが見えた。
「ていっても、ベッドが二つ……」
「不二もいるからな」
当然のような手塚の台詞。
「…へぇ」
――アンタと寝てるくせに。しらばっくれないでよね。
眼光を細めるリョーマをよそに、手塚はスコーンを一つ左手にとって眺めながらおもむろに口を開いた。
「ふぅまったく」
「何がッスか?」
「越前。次からはホテルをとって来い」
その言葉にまた、リョーマの眉が挑戦的に歪められる。
「え。次って。ふーん二回も俺がアンタんとこ来るって期待してるんだ」
「違うのか」
テーブルの上にはメモがあり、そこには兄への言付けと思われるものが走り書きされていた。
〈兄貴と手塚さん、それぞれ1個だけだからね!〉
「べつに違わないけど。アンタさえよければまた来たいけど」
――あと、不二先輩がよければ、ね。
「そぅか」
二つ、スコーンを手に持って玄関へと歩いていく手塚に、リョーマは急いで言葉を繋いだ。
「ねぇまだ話終わってないんだけど?」
「なんだ?」
一息吐いて、目の前の相手の眼を捕らえた。
「次、来てやるよ。その代わり」
相手がゆっくりと振り向く。
――う、わ。
振り向くその眼には、微熱があるにも関わらず、うすい眼鏡の奥にいつもどおりの手塚国光という存在の漆黒の底知れぬ力が篭っていた。
――やはりアンタには負けられない。
気圧されつつ、ここに立っているというぞくぞく感。武者震いを相手に気付かれないよう、初めて会った中一からずっと変わらない強い視線を、想いのままに手塚にぶつける。
「次、来てやるよ。その代わり、今回の試合、早くやりたいんだよね。だから明日には風邪治してくれない? そうじゃなきゃ困る」
最大の敵のフィギュアが今はゆっくりと頷く。
「ああ。わかっている」
聞きなれた響きは、リョーマの心で呟いた言葉にぴったり一致していた。
スッ、手塚の左腕がまっすぐ斜めに上がって、二つのうちの一つのベッドを指し示す。漆黒の瞳がそっと自分から離され、ドアが微かに鈍い音を立てて閉まる。取り残されたリョーマはさきほどと打って変わって、おずおずとその指定されたベッドに腰掛けて荷物を降ろした。
何本もの手が差し伸べられて、一人のひとを持ち上げる。合図とともにオペ台に乗せて、そのケガの程度の重い男性の手術が始まった。
「メス」
「はい」
まだ一応は研修医でありながらも、不二兄弟の巧みな連携プレーはこの病院の中でも有数だ。サライはミラクルドクター不二の華麗な外科手術を、医者として真剣に見つめていた。
工場爆発事故は重い。緊急手術室の前の廊下だけでなく、たくさんの廊下に患者がつめこまれ、激しいうめき声をあげる者、ただただ荒い息を繰り返す者、顔色が非常に悪くぐったりするしか今はなすすべがない者、それらのひとたちの周りを早足で歩きつつ緊急医の卵たちが声をあげながら様子を診ている。
不二たちのグループは緊急専門ではないため、駆り出された形となっているが、このときとばかりはそんな区別は漠然どころか無で当たり前なのであった。
「サライ、ちょっとこれあのひとに渡して」
そのいつものグループというのも、人数が半分になっている。頷いてサライが看護師に器具を渡すと、次には隣の台のグループの患者を下ろすのを手伝わされた。
「ありがと」
「次の患者さんは」
――ぼくだって何かしたいのに。
そう先走る気持ちを抑えて、これでも役にうんと立っているのだと自分に言い聞かす。緊急医の中のリーダーが怒鳴って、至るところで医者たちが怒鳴って、看護師が忙しく動き回る。
「ふう、終わった」
ミラクルドクター不二の手術はいつどんな状況でも確かで安定しているとサライは思った。喧騒の手術室の中で彼の声だけが可愛らしい。サライは頬を赤らめ、そして今は大変なときなのだと慌ててぶんぶんと首を横に振った。
「そうですね。よかったですドクター不二」
「じゃ」
裕太がそう言ってぱたぱたとどこかに走っていく。患者さんを台から下ろして、二人は今度は廊下の担当へと回った。
それほど大きな工場ではなかったので、怪我人は五十人まではいかないだろうと思われた。収拾がついてきたから研究医たちご苦労さま、そうリーダーに言われて、サライと不二は眠い目を抑え、病院の待合室を歩いていた。
「ドクター不二。一緒に乗って帰りますよね?」
「うん。いいの?」
「もちろんです。裕太はまだやっているんですよね、看護師大変ですね。あああ、折角ならドクター不二ぃぼくのうちまで一緒に来てくれたっていいのに」
「それは駄目。特に今日はね」
――特に今日はって? なんでですか?
不二が辛そうに欠伸をする。そういえば、このごろドクター不二は夜番続きだったなと気付いて、言及するのは止めた。
――きっと今日手塚さんが来ていたから、関係あるのかも。
まぁいいや、ぼくも眠たいや…。
病院の前にはもう黒いロールスロイスのリムジンが止まっていた。その黒光りが夜の大気にどこまでも透明に跳ね返る。運転席からパーシーが降りてきて、白い手袋を組み合わせながら深々とお辞儀をした。
「サライ坊ちゃま、不二さま」
「うんパーシー」
「今日もお願いね」
言葉少なに二人が乗り込むと、不二は片肘をついてぼんやり窓の外を眺め始めた。横目でその様子を確認し、サライはパーシーに話しかける。
「メルチーは寝てた?」
「はいサライ様。ブランブリエール侯爵がおっしゃっていましたが、眠いのを一生懸命我慢してサライお兄様はいつ戻ってくるの、とばかりおっしゃっていたと」
「可哀相にメルチー」
「次の休みに、バースのバートレット家に行きますよね。メルチー様はバース行きをそれはそれは楽しみにしておりますよ」
「あ、そうだね! ぼくも一緒に休暇とって行くものね」
「はい。久しぶりに従姉弟のジョゼフ様、ジュリア様に会えるともおっしゃっているそうでございます」
「ぼくはクリスティーンに会えるのが楽しみ」
「クリスティーン様はそういえば最近ベールをかぶるようになったとか聞きました」
「え、そうなの?! うわー会ってくれるかなあ。あ…っと、あのね、明日――じゃなくってもう今日、今日はねそういえばメルチーの運勢二番目だったんだよ」
「いいほうから二番目ですか?」
「うん。そう。ドクター不二のうお座は三番目だったよね。ぼくのてんびん座は十番目だった」
ちらっと横を見遣れば、同時に不二もサライを見て、にっこり微笑んだ。
「で、おひつじ座だっけメルチーは?」
「うん、そうだよ」
サライもにっこりと笑う。
「ぼくの占い雑誌、面白かった?」
「もちろん。だってドクター不二のですからね」
ロンドンの夜は冷たく、暗く、そして透明。窓から吹きぬける風がさわさわと車の中の者たちの髪を弄んではまた旅立つ。
「そっかぁ二番目って、いいよね。ほら、よくあるじゃない。最高だとあれって」
不二が静かに言葉を紡ぐ。
「あれって何、ドクター不二?」
「月は満月のあと必ず欠けるよね」
「ええ」
「アーサー王物語でも、円卓の騎士が揃ったときにアーサーとマーチンは顔を見合わせるじゃない。そしてやっぱりその日を境にアーサー王の権威は下降していく。――ってサライ知ってるでしょ」
「はい。でも、ドクター不二がこう、夜にしみじみと語ってくださると雰囲気が違って……ですよ」
「え、なにもう一回言って?」
「なんでもないですよ?」
ぷうと頬を膨らませるあなたが、先輩が愛しくて。
トルストイの弾き語りや、聖杯伝説も織り交ぜた、愛と知の物語。アーサー王は湖の上から始まって湖の上で終わった。そしてアーサー王の妻ギニヴィアはラーンスロットと間違いの恋をしてしまってしかしそれは仕方のないことでそれで――、不二ははぁと深いため息をついてそのロマンスに想いを馳せた。
「もうサライ、言ってよ。ほらボクのアパート見えてきたし」
「ふふ。だから、雰囲気が違って、ドクター不二と夜を一緒に味わってるんだなあと思って嬉しいってこと。言いたかったのは」
「到着いたしました」
「――着いたね」
「――着きましたね」
夜、満天の星空の中に少し欠けた金色の月が優しげに灯っていた。
「じゃねサライ。また」
「じゃ、またドクター不二」
サライの車が視界から見えなくなるまで、不二はアパートの二階から見送るのが常だった。
夜のしじまがゆっくりと不二を包んでいた。
そっと合鍵で手塚の部屋のドアを開ける。ドアノブに手をかけた途端、かぁぁっと不二は心臓がどきどき跳ね上がるのを感じて思わず手の平で胸を押さえた。
――どうしたのかな、ボク。
ぎゅうと自分の指先が胸にくいこみ、僅かな痛みに顔をしかめる。金色の月をもう一度見上げて、それに向かって微笑むと、月もにっこり笑いかえしてくれた気がした。
――ね? 大丈夫。
そっとドアを開け、手塚を起こさないように素早く静かに身体を部屋に入れた。案の定手塚はベッドにくるまってすやすや寝ている。規則正しい息の音が聞こえてくる。不二は暫く立ち尽くして、眠たいのも忘れて嬉しそうに手塚を眺めていた。
――キミの息が織り成す静けさに、ボクあますところなくキスしたい。
途端、自分の唇に意識が馳せて、わけもなく赤面した。
「ただいま……手塚」
自発的に声が洩れた。
普段は空気の揺らぎに敏感なはずの手塚が、起きない。そのことは不思議で、より不二の微笑みを倍増させる。早く風邪を治して越前と試合してもらいたいなと月に願った。
シャワーを浴びて着替えて、ようやく手塚の横に身をすりこませると、ほんのり漂う香りに不二は首を傾げた。
――なんの香りだろう?
手塚の頬に、久しぶりに自分から接吻した。
――ふふ、手塚の味……。
そおっと手を差し伸べていつもどおり手塚を抱く。その胸に自分の頭をうずめると、急に忘れていた眠気が疾風のごとく不二を襲い、すぐに部屋に柔らかな寝息の二重奏がもたらされた。
しばらく経って手塚が眼を覚ました。不二を待って、越前との試合を考えて、ついつい間隔を空けて起きてしまっていたのが、今初めて、不二が傍にいて自分の背中に手を回しているのが分かると手塚もすぅっとまた眠りに引き込まれそうになった。
――やはり不二が傍にいると安心する。
自分も彼の背中に腕を回す。と、繊細な不二の肩が震えて、ヘーゼルの睫毛をのせた瞼が小刻みに揺れ、自分にまっすぐとひらいた。
――花の開花。
いつも思ってしまう。見惚れる。
「すまない、起こしてし」
まった。最後まで言えず、その花の精の声に阻まれた。
「手塚っ、起きたの?」
「ああ。だがもう寝るところだが?」
「そぉ? お水、飲んだら?」
「そうだな…。ああ、水か、欲しいな」
「わかった。待っててね。飲んだほうがいいと思うよ」
「飲む」
ベッドからすっと抜け出し、不二の姿が早くも台所に消える。すぐ、プラスチックのコップを片手に戻ってきて、上半身を起こしている手塚に渡した。
「どうしたの?」
なかなかそのレンジャーのコップに口をつけない手塚を前に、首を傾げて不二が問う。
「いや、ただな」
「ん? なあに手塚」
ため息を吐いて、手塚は半分ほど飲んでから不二にコップを返すのだった。
「いらなかった? でも本当に飲んだほうがいいかと思って…ごめんね」
はぁと吐く手塚の息がいつもより熱い。
「いや」
「――え?」
「ただ、お前が『ボクが飲ませてあげる』と悪戯めいて言わないのが気になってな。言うかと思っていたんだ」
――え、手塚。
キミってそういうこと考えるほうだっけ?
不二は内心焦ったが、表情にはおくびにも出さず、
「くす、いいよ。ボクが飲ませてあげる」
そう言って残り半分を手塚の口に飲ませてあげた。
「ありがとう不二」
「どういたしまして。姉さんもボクによくこうしてくれたな」
ベッドに再び潜り込むと、手塚が心急いたように不二を抱きしめてそしてまた急に離し、二人の間に空間を空けた。
「うん?」
ボクっていつもキミに翻弄される運命なのかも。
「あ…すまない。不二」
「……キミと離れると寒いんだけど?」
手塚はぽつりと何か呟いた。「よく聞こえないよ」、そう言って怒ったように不二は上体を起こして窓から外を見ているふりをしていた。
「やはり風邪がうつると困る」
ぽつんと静寂に包まれた台詞に、不二は思いきり吹き出した。
「え?」
「意地が悪いな。今のはいくらなんでも聞こえただろう。やはり風邪が」
「分かってる。ただ、すごくキミらしくて」
寝転がって優しく手塚に微笑む。
――手塚ってほんと、びっくりするくらいに優しいんだから…。
こんなときくらい、ボクを頼ってくれたっていいのにね。役に立ちたいのに。
なんだかその微笑みに、淋しさもわずか添えてしまったと不二は思った。
「キミらしくて、なんだ?」
「ふふ、面白かった」
淋しい風に言ってしまった。けど、眠いから誤魔化すことなんてムリなんだ、ごめんね。
「不二は甘いな」
――甘い?!
何故だか手塚の瞳がいつもより透度高く純粋な恋情を含んでいるように感じながらも、不二は今の手塚の言葉を反芻してた。
――甘い? それって、
たやすくだまされるってその意味?!
それとも……ボクがsweetnessってゆうこと?
で、でもキミ今、ボクに唇触れてないじゃん?
手塚のこの瞳は、ボクをだましているって語ってない、よね。第一キミがボクをだますなんて考えられない。不二がひとり煩悶していると、隣で手塚がうとうとしてきたのが分かった。
「おやすみ、手塚」
「ああ」
きっとボクのこと好きって意味にとっておこう、そう思って不二も瞳を閉じた瞬間にまた手塚のその艶やかな低い声が不二の耳元で響いた。
「不二、ほんとうに綺麗な匂いだ」
思考が停止する。
「え」
しぼりだした声に応えたのは、手塚の「おやすみ」ただそれだけだった。
ボクの匂いが甘くて綺麗。
キミに言われると最高にどきどきする。
淋しくなんてちっともないや。
やっぱりキミといることって嬉しさの連続なんだね。
不二もつられてうとうとしながら、そういえば越前にも言われていたなあ、そうかさっきボクが感じたほんのりした香りってボクの香りだったんだ、あまり静かだから自分でも感じられたんだろな。そう思って眠りに落ちていった。
夢の中では、キレイなお花畑で見たことあるような顔の妖精さんたちが舞っていた。また別の次元では白いレースのベールがゆれて爽やかな教会の鐘の音が聞こえていた。
プロテニスプレイヤー手塚国光とプロテニスプレイヤー越前リョーマの草試合が、ロンドンナショナルギャラリー近くのテニスコートで行われようとしていた。
とん、とん。
硬い音を立て、黄色いボールが跳ね返る。
ぱしっ。手で掴み、膝が曲がり、肘がまっすぐに伸ばされて、手塚のサーブから試合が始まった。目に見えない速さのボールを、爛々と輝く大きな瞳で捉える背の低いリョーマ。今、まさに再び決戦の幕が開けようとしていた。
ガシッ、とフェンスが軋む。
白い白衣にいろんな色を投げかける眩しい太陽光、茶色の髪がそよ風にたなびき、ほんのりした繊細な甘い香りに傍にいる跡部景吾は眼を開いた。
ミラクルドクター不二はフェンスを掴み、一心にその試合を瞳に焼き付けようとしていた。
2010/04/07、5/26、27、29
昨日は不二先輩の誕生日でした。
いろいろ探してみたら、古い私の小説がでてきましたので、ここにしるします。
BLが苦手な方、BLの意味が分からない方は、なるべく見ないでください。
まあ見ても健全な文章ですが。
私、6年前、こんなすげー文章書いてたんだと自分でうひゃあと思いました(笑)
自惚れしてるし(笑)
◆注意◆
エロくないです。
頬にキスはします。くちびるにはしません。
R指定なし。
不二が手塚に抱っこするのも、服着た状態で、です。
※未来設定※
手塚と不二はイギリスのナショナルギャラリーの近くのアパートに暮らしています。奥に不二先輩と裕太が住まう部屋。その隣に手塚の部屋。その隣に跡部の物置(部屋です)があります。ですが、不二は手塚の部屋に入りびたり。半分同棲です。ただ、注意。まだ性行為は行ったことはありません。
※職業※
手塚・・・プロテニスプレイヤー
不二・・・ミラクルドクター
跡部・・・大会社のイギリス支社の課長
裕太・・・看護師
サライ・・・イギリスの貴族の中の貴族だが、医者。
ミラクルドクター不二の弟子。
(私のオリジナル人物)
はじまりはじまり
帽子のつばをさらに沈めるリョーマを目の前に、不二はぷうと頬を膨らました。
「もう。越前てば、いっつも急なんだから」
「ども、ッス」
雲一つない青空。太陽がいろいろな色の光を投げかけ、照っていた。リョーマは風に翻る不二の白衣を、眩しそうに見上げた。
緊急で運ばれてきた男性の心臓手術を終え、不二はほっと一息ついて自分の机でコーヒーを飲んでいた。次の予約の大腸の手術まであと一時間半ほど。それまで暫く身体を休めて備えようと、ちょうど占いの雑誌を手にとって読み始めたとき、サライが悲しげな顔をして不二を呼びにやってきたのだった。
「ねぇドクター不二い」
「あ、サライ。どこ行ってたの」
「ちょっと弟が携帯に電話してきたから、外に。そしたらねテニスバッグ背負った男の子が、ぼくにドクター不二呼んでくれないって言うんですよ」
「へぇ?」
「なんで、やっぱりドクター不二はテニス少年に人気ですね。ぼくは……」
「そんなことないよ。サライはよくやってるし。ボク好きだよ?」
「その好きはぼくが求めてる好きじゃないでしょ。ひどいよ、もぉ」
眉を下げたサライは、本来ならどんな相手だっておとせそうな美男子である。生粋のロンドンっ子、そして女王陛下も一目置いている大金持ちの息子、それがあろうことか絶対におとせない男に恋をしてしまった。
「で? 待ってるのその子?」
その相手は今サライの目の前でにっこりと微笑み、サライに早く続きを言おうねと迫る。それでもひたすらに想っていたいという心は諦めきれず、ため息まじりにサライは答えた。
「はい。アメリカ的な男の子で、背が低い子です。知り合い、ですよね」
――え、越前?! まさかね。
「うーん。とにかく行ってみるよ」
柔らかな動作で立ち上がり、サライに微笑をあげて部屋を出て行くドクター不二。サライは恨めしそうにその華奢な背中を見送った。そして少しでも自分の想う人の体温を感じていたくて、空になった椅子に座って残された占い雑誌をめくった。
うぃぃん。自動ドアが開き、一歩踏み出すと、懐かしいその名称を呼ばれた。ゆっくり、不二は顔を呼ばれた方向へと向ける。
「不二先輩」
「やあ越前」
――くすっ相変わらずの白いフィラの帽子。似合ってる。
病院の待合室に入ってればよかったのに、そう言うと「ういっす」と言って取り合ってくれない。そんな細かいところまで、会ったときから全然変わらなかった。
「ふふっ」
「不二先輩。意味ありげな微笑み、怖いッス」
「そうかな。べつに意味なんてないよ。越前可愛いな、ってこと、強いて言えばね」
「それがあるって言うんス」
とにかく入ろうよ、と促して不二とリョーマは一緒に自動ドアをかいくぐり、適度に冷房の利いた病院の待合室へと入った。
不二が勤めている病院は、イギリスの名のある大学病院である。ここで二年間の研修を受けて、それから不二と裕太はようやく一人前の医師と看護師になるのだった。
といっても、今からもう不二の腕前はすごい。ミラクルドクター不二、そう世間で騒がれ、どんなに難しい手術でも成功率は半端じゃない。裕太と同い年、つまり一歳年下のサライを助手につけ、弟の裕太はその器械出し看護師としてオペを行う。
メスを持つと静かに開眼するヘーゼルの瞳は青い光を帯びて、キラリと不敵に輝く。その凛とした美しさも半端ではなかった。
普段の優しい細い瞳からは想像もできないその美しくも恐ろしい瞳は、半ば同居しているらしいプロテニスプレイヤー手塚国光と一緒にテニスで遊んでいるときにも窺える。遊ぶ、というほどのものでない。その冷たく綺麗な不二の瞳は、彼が本気であるという証拠だ。
――あ、また。不二先輩からいい匂いが。
リョーマはその先輩に憧れ、恋い慕っていたあの頃の自分を思い出した。まだ幼くて小さくて。今も小さいけれどその今とも比べようもないくらい俺は小さくて。そしてふわり、綺麗な柔らかな茶色の髪が揺れてなんともいえない香りが漂ったとき、不覚にも男のその先輩に恋してしまった。ねえ越前、その優しい声が嬉しくて、そして会ったその初日から俺を認めてくれていて。けれど不二先輩はもうその頃から、いや俺が青春学園中等部に入学する以前からずっと、恋情を全て手塚部長に注いでいた。
知ったときのショックは忘れられない。それでも、敵わないと瞳を逸らした自分を、不安げに気遣ってくれた先輩を恋慕う気持ちは捨てられなくて。今も、ちょっとだけ、先輩が好きだ。プロテニスプレイヤー越前リョーマ、物心つく前からの夢だったこと。それは自分で決めたことだと豪語できる。でもね。手塚部長、少しはあんたのおかげでもあるかもしれない。
「ね、越前」
ほらまた。きっと、もう一人の弟みたく俺のこと見ているんでしょうけど。だけど、嬉しいんスよ、その声ほんとに。
「ボクに何の用だったの?」
やんわりした口調、相変わらずッスね。
リョーマはふうと肩で息をつくと、真っ直ぐに不二の瞳をとらえて、そして言った。
「部長――手塚先輩と勝負したいと思って、不二先輩に都合を聞きに来た」
「――え、ボクに?!」
「そう。だって、同棲しているんでしょ?」
サボテンの花の香水を、今日もつけてきた。不二が香水に手を伸ばすようになったということを、ちょっとしたきっかけで手塚が跡部に話したのだが、そうしたら跡部が様々な種類のものを見つけ出しては不二にくれるようになった。
悪いよ。そう言うと、俺様からのささやかな好意だ、受け取れ。そう言って押し付ける。仕方ないから、四分の三の金額は出すということで承知してもらった。
――まったく。でも嬉しいけどね。
サボテンの花はとにかく希少価値。細やかに小学生の時代からサボテンを世話し続けてきた不二ですら、まだ二桁の数しか咲かせていなかった。
今朝は寝惚けてて、そしたら手塚が
「不二、起きろ!」
そう怒鳴って、ベッドから転がりだされた。
「痛い。ひどいよ手塚ぁ」
「痛くはないはずだが。俺が抱き締めているからな」
「えぇっ?」
手塚にお姫様抱っこされていることに気付いて、頬が熱くなるのが自分でも分かる。手塚の漆黒の瞳が、眼鏡をまだかけていないからか、いつもより大きく、そして優しく瞬いた。
――キミって、ボクへの優しさの最大値もってるのかな。
「ずっと、ボクたちの想いが上昇していければいいよね」
スゥっと自然と口から漏れでた言葉に、自分で赤面した。
「ああ。そうだな」
すぐに頷き返してくれたキミが愛しくて。にっこり笑ったら、頬をつんつんと突かれた。ひんやり、キミの指先が冷たい。
「わ、何するのさ」
「おまえはすぐに赤くなる」
また、その台詞に薄紅色に染められて、手塚の瞳が優しく笑ってくれた。
手塚の作った朝ごはんを慌しく食べて、「いってきます」と靴を履いた途端、「待て!」と手塚にまた怒鳴られた。
「な、何さ?」
「おまえ、香水を忘れている」
「あぁ…べつにいいや」
「よくない。俺がかけてやる」
「え、あ、ありがと」
――うわ、手塚ったらかけ過ぎだって。
「よしこれでいい。行ってこい」
「うん、行ってくるね。ばいばい」
手を振って、ドアが閉まったとき、ふんわりした風が香水の匂いをそこらじゅうにぶちまけた。
――やっぱりかけ過ぎだ。
でも手塚がわざわざしてくれたことだから、胸の奥はほんわり暖かくて、不二はこのなんだか不思議な気持ちをかみしめて、病院に向かったのだった。
みんななんとも言わないけれど、越前くらいは何か言うかな。そう思っていたら、越前はちらっと髪を見上げて満足そうな笑みを零した。
――んー?
何に笑ったんだろうね?
「ね、越前。ボクに何の用だったの?」
一瞬の間。
「部長――手塚先輩と勝負したいと思って、不二先輩に都合を聞きに来た」
「――え、ボクに?!」
「そう。だって、同棲しているんでしょ?」
どきっ胸がはねあがる。同棲…ね、確かに。キスすらしてないけどね。
「ど、同棲って手塚が聞いたら怒りそうな響きはらんでるよね」
「ねえ先輩、はぐらかさないでよ。同棲してるんでしょ? だから」
「だから? もしかしてアパートの場所が分からなかったのかな? くす越前ったら」
「な、なに」
「芳香オンチ」
「え。それってどっちの? 不二先輩の匂いならとっくのとうに気付いてますよ。でも俺は昔の、もっとよく先輩見ないと分からないような繊細な匂いのほうが好きッスけど」
「え? え、越前?」
「昔の不二先輩のほうが好きって言ってるんス。だって」
――だって。まだ部長が自分の不二先輩への想い、気付いてなかったから。だから、俺
が先輩のこと好きっていうこと、こんなに自分で切なくなることはなかったから。
「だって結構強いもん今、香水。きっと手塚先輩が今朝無理矢理かけたとか、だよね」
「えぇ! ど、どうして分かるのさっ越前」
「え。やっぱりそうだったんだ……。同棲してるんだ」
「もっもう! 同棲しているってわけじゃないんだから」
「不二先輩。なーんかツンデレッスね」
「誰のせいかな? ふふふ」
「わ、怖いッス、それ。でも安心した」
「え?」
純粋に首をかしげる不二に、リョーマはほぉと見惚れて息をついた。綺麗。茶色の髪が艶やかで、ふわふわ繊細に揺れて綺麗だ、この人。
「不二先輩がずーと同じで。みんなに優しくて、――中でも部長が特別で」
「え越前……」
「俺、だから不二先輩が好きなんだなってこの頃思います」
「越前……それって」
――ボクへの告白? まさか、越前に限ってそんなこと、たぶんないよね。
「好き」って違う意味……だよね。あ、ありがとう越前。
「ありがとう。越前」
にっこり笑った不二の優しい台詞に、リョーマはぐさりと胸が痛んだが、表面上はできる限りの照れ笑いをして、その場は終わった。
――ここか。
ぎりぎりまで近寄って見上げると、その二階建てのアパートがまるで聳え立つ楼閣のように思われた。
――待ってろよ。部長。
道の向こうにはロンドン・ナショナルギャラリーの賑わいがよく見える。
「ふーん。けっこーいい場所じゃん」
風がさあっと吹き過ぎる。後ろから深い足音が近づいて、リョーマは胸が高鳴っていくのを覚えた。
「越前…か。何をしにきた」
低く響く妖艶な声音。
「――あんたと戦いにきた」
振り返るリョーマには、コマ写しのようにその最大の敵の姿が映しだされていた。
大腸手術が無事終わった。患者さんは綺麗な女の人だった、ネイルが姉さんの趣味に似ていると思った。手術室を出る際、裕太にそう言ったら裕太もそうだねと肯いた。
医者は患者を人として見ない、特に外科医は。そうささやかれている言葉ははたして正しいのだろうかとついつい思ってしまう。
――ボクもいつか、そんなふうになるのだろうか。
サライはどうなのかな。眠そうにふわあとあくびした彼に、不二は微笑して近寄っていった。
今日は不二は病院の夜番だった。リョーマが手塚のもとへと向かったのは昼の二時過ぎ。越前の性格からあわせて考えても、二人の草試合は今日の午後行われるはずでそれを見られるよしはないだろうと不二は思った。
「見たかったな」
ぽつんサライの前に来て飛び出した言葉はそれで、不二は少し慌てた。
「あ、えっとねサライ」
「ほんとですね~、ドクター不二」
サライが眠そうに相槌を打った。
「ぼくだってドクター不二と一緒にベッドで寝たいよ」
「サ、サライ?」
どうやら意味が通じない領域に彼がいるのだと察知して、不二はぽんぽんとサライの背中を叩き、そっとその自分とよく似た華奢な背中に微笑んだ。
――お疲れ様。
少しでも休まってくれたらいい、そう思う。サライの気持ちにはたぶん応えてあげられないだろうけれど。
「サライ、今日夜番?」
「え? あれ、えっとぼくが夜番かって? 違いますよ」
「そう。ボクは夜番なんだ。そっか、じゃあ雑誌でも読んでるほかないみたいだね」
「じゃあぼくちょっと誰かと話してきます」
「……えっ」
瞳をこすりながらぱたぱた走っていく後輩を、不二は呆然として見送った。
――嫌われちゃったのかな。ボク何かした…?
でも、確かにボクから離れたほうがサライにはいいかもしれないね。
「はぁ」
こんなときこそ手塚がいてくれたら、どんなに温まるだろうと思ってみたが、そうもいかない。
「手塚ぁ」
髪の毛の痛烈な芳香こそが、今日の手塚の想いだと心の中に言い聞かせ、不二はそっと自分の髪を撫でて気を休めている最中――。
「不二!」
突如した、耳にやすらかなその低い声に、不二はびっくりしてその方向を見上げた――というのはちょうど真上から手塚の声が発せられたのだった。
「て、手塚!? ど、どうしてキミがここに」
「今呼んだだろう」
「それはそうだけど…そんな都合よく」
「そうだな。推測に過ぎないが、俺はおまえが呼べばいつでも存在するのかもしれない」
「え? 手塚どうしたの、何かの台詞?」
「いやなんでもない。それよりもな不二……」
ゆっくりペースで歩いていたら、いつのまにやらオペの仲間たちはみなどこかに行ってしまったようだった。真っ白い廊下にキミが立っていて、ボクが寄り添っている、その二人だけの空間。やっぱりキミといるとあったまる。
「手塚ぁ」
手塚の言葉を遮って、思ったまま不二は手塚にぎゅうと抱きついた。
抱きつかれた手塚は一瞬驚きの表情を見せて、すぐに不二の背に手を伸ばして慈しむように茶色の髪を撫でてやった。
「少し湿っているな…」
茶色の下地に煌く光が眩い。
「手術が終わったばかりだからね」
「そうか」
「うん…」
「不二、話があるのだが」
改めて、真摯に瞳を覗かれて、少しくすぐったい感覚に襲われる。
「あ、そうだったよねごめん。なに?」
「越前に試合を申し込まれた」
「ああそうだろうね」
「そうだろうね、って知っているのか?」
――越前がロンドンにいること自体、不二おまえは知っているのか?
手塚の理由を説明しろというひそめられた眉に、不二はくすくす笑ってしまった。
「今日越前が病院に来たの」
「病院に?」
「うん。で、アパートの場所を聞くんだ。ボクとキミがね同棲してるのかって言ってた。きっと大学病院のほうが道分かりやすかったんじゃないの? 英二とかはボクたちの状況を全部知っているしね、ボクが医者だってことよく知ってた」
「そうか」
「それで試合したの?」
「迷っている」
「えっ」
微かに不二の眉が歪められる。それは本当に微かなために、人から見ればいつもどおりの笑みにしか見えないが、手塚にはそれがよく分かった。少し狼狽する手塚を前に、
「何に」
不二は辛烈な響きを込めて言い放った。
「越前はせっかく来たんだよ?」
「しかし今日は」
「あ~! ドクター不二い!」
「サライ?」
「緊急手術に呼ばれてる。工場で爆発事故。あと五分くらいで救急車がつくって」
「え…。うん、分かった!」
ぱたぱた走っていくサライを追っていた瞳をはずし、不二は手塚のほうへ向き直った。
「手塚。ごめん行かなきゃ」
「そのようだな」
「うん。今日は一応夜番だったけど、このぶんじゃみんなそうかな」
「ああ」
手塚の瞳が今朝よりもまた優しく光った気がして、不二は不思議そうにその光を覗き込んだ。
「頑張ってこい」
「ボク行くね。越前との試合は?」
「おまえが今日いないなら、やることにする」
「もう日が沈むよ」
「知ってる。しかしやれ、というのがおまえの望みだろう」
不二はハッと気付いた。
――ああボク馬鹿だった。手塚の瞳がちょっと潤んでいたりするの、それは。
「んんん。試合は明日、だね。手塚、今日熱あるんでしょ、ごめんね。ボクもっと早くに気付かなくて――」
――だって、手塚が病院に直接来るなんて、めったにないもの。
不二が爪先立ちして手塚の額に額をくっつけると、やはり熱があるのだと確信できた。手塚は胸がきゅーんとなって、「どきどきしているからだ」と呟いたものの口の中だけでそれは終わった。
「今日は早く寝てね。ボク、帰ったらキミの横にすぐに行くから」
「しかしそれでは風邪が」
「関係ないよ。ボクはキミの役に立ちたいの。キミの横に行きたいの。そうでなきゃ、きっとボクすごいひどい病気になっちゃうと思う」
「不二……」
嬉しそうに頷く彼に最上級の微笑みを与えて。
「じゃあもう行くね」
「ああ。待ってる」
ヒグマのシールの貼られた鍵を取り出し、越前に泊まっていくよう言った。散々に迷った。というのは俺の部屋を使わせるか不二の部屋を使わせるか。
「どちらがいい」
「アンタ決めてよ、都合とかあるんじゃないの?」
「相変わらずの奴だな。わかった」
そう言ってポケットをまさぐったときに、決めた。不二と裕太くんの部屋にしよう。
「今日は早く寝てね。ボク、帰ったらキミの横にすぐに行くから。キミの役に立ちたいの。キミの横に行きたいの」
耳の奥に余韻を伴って残る、彼の最上級の甘い囁き。そしてそれとともに思い出されるヘーゼルの瞳に宿る俺だけの為の優しさ。
――明け方、不二は俺の部屋に来る。
手塚は確信していた。自分の中で肯いて、アパートの二階の通路の行き止まりでヒグマのシールのそれを鍵穴に差し込むと、宵のナショナルギャラリー付近から洩れる灯りに銀の色がちかりちかり反射した。
「こっちだ。越前」
そっと空を見上げれば、そちらの方向に風船みたいなオレンジと紫色の太陽があった。
「ウィッース」
その声とともに、ぎいとドアが開いた。
不二兄弟の部屋は、卵、小麦粉、バターやらのお菓子の匂いが立ち込めていた。二人とも毎年の二月十四日のため甘いものには慣れているはずなのに、手塚は眉をしかめ、その後ろでリョーマは軽くむせる、そのくらい強い匂いである。
「ここ、裕太さんの部屋ですか」
きょろきょろ見回しながらリョーマが呟く。手塚が電灯を点けると、テーブルの上に今朝作ったのだろうスコーンがラップにくるまって幾つか置かれているのが見えた。
「ていっても、ベッドが二つ……」
「不二もいるからな」
当然のような手塚の台詞。
「…へぇ」
――アンタと寝てるくせに。しらばっくれないでよね。
眼光を細めるリョーマをよそに、手塚はスコーンを一つ左手にとって眺めながらおもむろに口を開いた。
「ふぅまったく」
「何がッスか?」
「越前。次からはホテルをとって来い」
その言葉にまた、リョーマの眉が挑戦的に歪められる。
「え。次って。ふーん二回も俺がアンタんとこ来るって期待してるんだ」
「違うのか」
テーブルの上にはメモがあり、そこには兄への言付けと思われるものが走り書きされていた。
〈兄貴と手塚さん、それぞれ1個だけだからね!〉
「べつに違わないけど。アンタさえよければまた来たいけど」
――あと、不二先輩がよければ、ね。
「そぅか」
二つ、スコーンを手に持って玄関へと歩いていく手塚に、リョーマは急いで言葉を繋いだ。
「ねぇまだ話終わってないんだけど?」
「なんだ?」
一息吐いて、目の前の相手の眼を捕らえた。
「次、来てやるよ。その代わり」
相手がゆっくりと振り向く。
――う、わ。
振り向くその眼には、微熱があるにも関わらず、うすい眼鏡の奥にいつもどおりの手塚国光という存在の漆黒の底知れぬ力が篭っていた。
――やはりアンタには負けられない。
気圧されつつ、ここに立っているというぞくぞく感。武者震いを相手に気付かれないよう、初めて会った中一からずっと変わらない強い視線を、想いのままに手塚にぶつける。
「次、来てやるよ。その代わり、今回の試合、早くやりたいんだよね。だから明日には風邪治してくれない? そうじゃなきゃ困る」
最大の敵のフィギュアが今はゆっくりと頷く。
「ああ。わかっている」
聞きなれた響きは、リョーマの心で呟いた言葉にぴったり一致していた。
スッ、手塚の左腕がまっすぐ斜めに上がって、二つのうちの一つのベッドを指し示す。漆黒の瞳がそっと自分から離され、ドアが微かに鈍い音を立てて閉まる。取り残されたリョーマはさきほどと打って変わって、おずおずとその指定されたベッドに腰掛けて荷物を降ろした。
何本もの手が差し伸べられて、一人のひとを持ち上げる。合図とともにオペ台に乗せて、そのケガの程度の重い男性の手術が始まった。
「メス」
「はい」
まだ一応は研修医でありながらも、不二兄弟の巧みな連携プレーはこの病院の中でも有数だ。サライはミラクルドクター不二の華麗な外科手術を、医者として真剣に見つめていた。
工場爆発事故は重い。緊急手術室の前の廊下だけでなく、たくさんの廊下に患者がつめこまれ、激しいうめき声をあげる者、ただただ荒い息を繰り返す者、顔色が非常に悪くぐったりするしか今はなすすべがない者、それらのひとたちの周りを早足で歩きつつ緊急医の卵たちが声をあげながら様子を診ている。
不二たちのグループは緊急専門ではないため、駆り出された形となっているが、このときとばかりはそんな区別は漠然どころか無で当たり前なのであった。
「サライ、ちょっとこれあのひとに渡して」
そのいつものグループというのも、人数が半分になっている。頷いてサライが看護師に器具を渡すと、次には隣の台のグループの患者を下ろすのを手伝わされた。
「ありがと」
「次の患者さんは」
――ぼくだって何かしたいのに。
そう先走る気持ちを抑えて、これでも役にうんと立っているのだと自分に言い聞かす。緊急医の中のリーダーが怒鳴って、至るところで医者たちが怒鳴って、看護師が忙しく動き回る。
「ふう、終わった」
ミラクルドクター不二の手術はいつどんな状況でも確かで安定しているとサライは思った。喧騒の手術室の中で彼の声だけが可愛らしい。サライは頬を赤らめ、そして今は大変なときなのだと慌ててぶんぶんと首を横に振った。
「そうですね。よかったですドクター不二」
「じゃ」
裕太がそう言ってぱたぱたとどこかに走っていく。患者さんを台から下ろして、二人は今度は廊下の担当へと回った。
それほど大きな工場ではなかったので、怪我人は五十人まではいかないだろうと思われた。収拾がついてきたから研究医たちご苦労さま、そうリーダーに言われて、サライと不二は眠い目を抑え、病院の待合室を歩いていた。
「ドクター不二。一緒に乗って帰りますよね?」
「うん。いいの?」
「もちろんです。裕太はまだやっているんですよね、看護師大変ですね。あああ、折角ならドクター不二ぃぼくのうちまで一緒に来てくれたっていいのに」
「それは駄目。特に今日はね」
――特に今日はって? なんでですか?
不二が辛そうに欠伸をする。そういえば、このごろドクター不二は夜番続きだったなと気付いて、言及するのは止めた。
――きっと今日手塚さんが来ていたから、関係あるのかも。
まぁいいや、ぼくも眠たいや…。
病院の前にはもう黒いロールスロイスのリムジンが止まっていた。その黒光りが夜の大気にどこまでも透明に跳ね返る。運転席からパーシーが降りてきて、白い手袋を組み合わせながら深々とお辞儀をした。
「サライ坊ちゃま、不二さま」
「うんパーシー」
「今日もお願いね」
言葉少なに二人が乗り込むと、不二は片肘をついてぼんやり窓の外を眺め始めた。横目でその様子を確認し、サライはパーシーに話しかける。
「メルチーは寝てた?」
「はいサライ様。ブランブリエール侯爵がおっしゃっていましたが、眠いのを一生懸命我慢してサライお兄様はいつ戻ってくるの、とばかりおっしゃっていたと」
「可哀相にメルチー」
「次の休みに、バースのバートレット家に行きますよね。メルチー様はバース行きをそれはそれは楽しみにしておりますよ」
「あ、そうだね! ぼくも一緒に休暇とって行くものね」
「はい。久しぶりに従姉弟のジョゼフ様、ジュリア様に会えるともおっしゃっているそうでございます」
「ぼくはクリスティーンに会えるのが楽しみ」
「クリスティーン様はそういえば最近ベールをかぶるようになったとか聞きました」
「え、そうなの?! うわー会ってくれるかなあ。あ…っと、あのね、明日――じゃなくってもう今日、今日はねそういえばメルチーの運勢二番目だったんだよ」
「いいほうから二番目ですか?」
「うん。そう。ドクター不二のうお座は三番目だったよね。ぼくのてんびん座は十番目だった」
ちらっと横を見遣れば、同時に不二もサライを見て、にっこり微笑んだ。
「で、おひつじ座だっけメルチーは?」
「うん、そうだよ」
サライもにっこりと笑う。
「ぼくの占い雑誌、面白かった?」
「もちろん。だってドクター不二のですからね」
ロンドンの夜は冷たく、暗く、そして透明。窓から吹きぬける風がさわさわと車の中の者たちの髪を弄んではまた旅立つ。
「そっかぁ二番目って、いいよね。ほら、よくあるじゃない。最高だとあれって」
不二が静かに言葉を紡ぐ。
「あれって何、ドクター不二?」
「月は満月のあと必ず欠けるよね」
「ええ」
「アーサー王物語でも、円卓の騎士が揃ったときにアーサーとマーチンは顔を見合わせるじゃない。そしてやっぱりその日を境にアーサー王の権威は下降していく。――ってサライ知ってるでしょ」
「はい。でも、ドクター不二がこう、夜にしみじみと語ってくださると雰囲気が違って……ですよ」
「え、なにもう一回言って?」
「なんでもないですよ?」
ぷうと頬を膨らませるあなたが、先輩が愛しくて。
トルストイの弾き語りや、聖杯伝説も織り交ぜた、愛と知の物語。アーサー王は湖の上から始まって湖の上で終わった。そしてアーサー王の妻ギニヴィアはラーンスロットと間違いの恋をしてしまってしかしそれは仕方のないことでそれで――、不二ははぁと深いため息をついてそのロマンスに想いを馳せた。
「もうサライ、言ってよ。ほらボクのアパート見えてきたし」
「ふふ。だから、雰囲気が違って、ドクター不二と夜を一緒に味わってるんだなあと思って嬉しいってこと。言いたかったのは」
「到着いたしました」
「――着いたね」
「――着きましたね」
夜、満天の星空の中に少し欠けた金色の月が優しげに灯っていた。
「じゃねサライ。また」
「じゃ、またドクター不二」
サライの車が視界から見えなくなるまで、不二はアパートの二階から見送るのが常だった。
夜のしじまがゆっくりと不二を包んでいた。
そっと合鍵で手塚の部屋のドアを開ける。ドアノブに手をかけた途端、かぁぁっと不二は心臓がどきどき跳ね上がるのを感じて思わず手の平で胸を押さえた。
――どうしたのかな、ボク。
ぎゅうと自分の指先が胸にくいこみ、僅かな痛みに顔をしかめる。金色の月をもう一度見上げて、それに向かって微笑むと、月もにっこり笑いかえしてくれた気がした。
――ね? 大丈夫。
そっとドアを開け、手塚を起こさないように素早く静かに身体を部屋に入れた。案の定手塚はベッドにくるまってすやすや寝ている。規則正しい息の音が聞こえてくる。不二は暫く立ち尽くして、眠たいのも忘れて嬉しそうに手塚を眺めていた。
――キミの息が織り成す静けさに、ボクあますところなくキスしたい。
途端、自分の唇に意識が馳せて、わけもなく赤面した。
「ただいま……手塚」
自発的に声が洩れた。
普段は空気の揺らぎに敏感なはずの手塚が、起きない。そのことは不思議で、より不二の微笑みを倍増させる。早く風邪を治して越前と試合してもらいたいなと月に願った。
シャワーを浴びて着替えて、ようやく手塚の横に身をすりこませると、ほんのり漂う香りに不二は首を傾げた。
――なんの香りだろう?
手塚の頬に、久しぶりに自分から接吻した。
――ふふ、手塚の味……。
そおっと手を差し伸べていつもどおり手塚を抱く。その胸に自分の頭をうずめると、急に忘れていた眠気が疾風のごとく不二を襲い、すぐに部屋に柔らかな寝息の二重奏がもたらされた。
しばらく経って手塚が眼を覚ました。不二を待って、越前との試合を考えて、ついつい間隔を空けて起きてしまっていたのが、今初めて、不二が傍にいて自分の背中に手を回しているのが分かると手塚もすぅっとまた眠りに引き込まれそうになった。
――やはり不二が傍にいると安心する。
自分も彼の背中に腕を回す。と、繊細な不二の肩が震えて、ヘーゼルの睫毛をのせた瞼が小刻みに揺れ、自分にまっすぐとひらいた。
――花の開花。
いつも思ってしまう。見惚れる。
「すまない、起こしてし」
まった。最後まで言えず、その花の精の声に阻まれた。
「手塚っ、起きたの?」
「ああ。だがもう寝るところだが?」
「そぉ? お水、飲んだら?」
「そうだな…。ああ、水か、欲しいな」
「わかった。待っててね。飲んだほうがいいと思うよ」
「飲む」
ベッドからすっと抜け出し、不二の姿が早くも台所に消える。すぐ、プラスチックのコップを片手に戻ってきて、上半身を起こしている手塚に渡した。
「どうしたの?」
なかなかそのレンジャーのコップに口をつけない手塚を前に、首を傾げて不二が問う。
「いや、ただな」
「ん? なあに手塚」
ため息を吐いて、手塚は半分ほど飲んでから不二にコップを返すのだった。
「いらなかった? でも本当に飲んだほうがいいかと思って…ごめんね」
はぁと吐く手塚の息がいつもより熱い。
「いや」
「――え?」
「ただ、お前が『ボクが飲ませてあげる』と悪戯めいて言わないのが気になってな。言うかと思っていたんだ」
――え、手塚。
キミってそういうこと考えるほうだっけ?
不二は内心焦ったが、表情にはおくびにも出さず、
「くす、いいよ。ボクが飲ませてあげる」
そう言って残り半分を手塚の口に飲ませてあげた。
「ありがとう不二」
「どういたしまして。姉さんもボクによくこうしてくれたな」
ベッドに再び潜り込むと、手塚が心急いたように不二を抱きしめてそしてまた急に離し、二人の間に空間を空けた。
「うん?」
ボクっていつもキミに翻弄される運命なのかも。
「あ…すまない。不二」
「……キミと離れると寒いんだけど?」
手塚はぽつりと何か呟いた。「よく聞こえないよ」、そう言って怒ったように不二は上体を起こして窓から外を見ているふりをしていた。
「やはり風邪がうつると困る」
ぽつんと静寂に包まれた台詞に、不二は思いきり吹き出した。
「え?」
「意地が悪いな。今のはいくらなんでも聞こえただろう。やはり風邪が」
「分かってる。ただ、すごくキミらしくて」
寝転がって優しく手塚に微笑む。
――手塚ってほんと、びっくりするくらいに優しいんだから…。
こんなときくらい、ボクを頼ってくれたっていいのにね。役に立ちたいのに。
なんだかその微笑みに、淋しさもわずか添えてしまったと不二は思った。
「キミらしくて、なんだ?」
「ふふ、面白かった」
淋しい風に言ってしまった。けど、眠いから誤魔化すことなんてムリなんだ、ごめんね。
「不二は甘いな」
――甘い?!
何故だか手塚の瞳がいつもより透度高く純粋な恋情を含んでいるように感じながらも、不二は今の手塚の言葉を反芻してた。
――甘い? それって、
たやすくだまされるってその意味?!
それとも……ボクがsweetnessってゆうこと?
で、でもキミ今、ボクに唇触れてないじゃん?
手塚のこの瞳は、ボクをだましているって語ってない、よね。第一キミがボクをだますなんて考えられない。不二がひとり煩悶していると、隣で手塚がうとうとしてきたのが分かった。
「おやすみ、手塚」
「ああ」
きっとボクのこと好きって意味にとっておこう、そう思って不二も瞳を閉じた瞬間にまた手塚のその艶やかな低い声が不二の耳元で響いた。
「不二、ほんとうに綺麗な匂いだ」
思考が停止する。
「え」
しぼりだした声に応えたのは、手塚の「おやすみ」ただそれだけだった。
ボクの匂いが甘くて綺麗。
キミに言われると最高にどきどきする。
淋しくなんてちっともないや。
やっぱりキミといることって嬉しさの連続なんだね。
不二もつられてうとうとしながら、そういえば越前にも言われていたなあ、そうかさっきボクが感じたほんのりした香りってボクの香りだったんだ、あまり静かだから自分でも感じられたんだろな。そう思って眠りに落ちていった。
夢の中では、キレイなお花畑で見たことあるような顔の妖精さんたちが舞っていた。また別の次元では白いレースのベールがゆれて爽やかな教会の鐘の音が聞こえていた。
プロテニスプレイヤー手塚国光とプロテニスプレイヤー越前リョーマの草試合が、ロンドンナショナルギャラリー近くのテニスコートで行われようとしていた。
とん、とん。
硬い音を立て、黄色いボールが跳ね返る。
ぱしっ。手で掴み、膝が曲がり、肘がまっすぐに伸ばされて、手塚のサーブから試合が始まった。目に見えない速さのボールを、爛々と輝く大きな瞳で捉える背の低いリョーマ。今、まさに再び決戦の幕が開けようとしていた。
ガシッ、とフェンスが軋む。
白い白衣にいろんな色を投げかける眩しい太陽光、茶色の髪がそよ風にたなびき、ほんのりした繊細な甘い香りに傍にいる跡部景吾は眼を開いた。
ミラクルドクター不二はフェンスを掴み、一心にその試合を瞳に焼き付けようとしていた。
2010/04/07、5/26、27、29















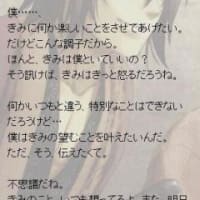

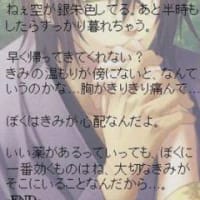

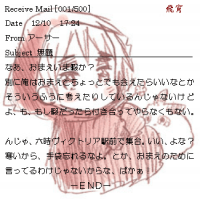
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます