
経済オタク的な者が日本の農業を批判する時に必ず言う事は、
1.日本の農業は規模が小さいから効率が悪い。欧米のように大規模な農業を目指すべきだ。
2.日本の農業は欧米より補助金漬けである。
であります。
インターネットが普及していない時代においては、大前研一などが上のようなたわ言をほざいていてもつっこめる方は少なかったのですが、現在ではちょっと検索するだけで、それがたわ言であることがわかります。
どこぞのアホがよく引用する山下一仁氏の記事にも、欧米の農業が補助金漬けであったことが書かれています。
WTOの行方 米、EUの農業「談合」に反発した途上国 RIETI 経済産業研究所
http://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamashita/01.html
EUは1968年、市場価格よりも高い農産物価格を農家に保証する共通農業政策 (CAP)を成立させた。高水準の農産物価格の保証により、生産は刺激され、ワインの湖やバターの山という過剰在庫が発生し、それを海外輸出で処理したため、80年代には農産物の純輸入国から純輸出国へと立場を変えた。米国はEU市場のみならず、EU以外の市場も奪われた。域内の価格が国際価格よりも高いEUの輸出は輸出補助金によって実現した。ケネディ・ラウンド以降ガット交渉上の最大の争点は、輸出利益を奪われた米国とEUの間のCAP、とりわけ、その輸出補助金をめぐってであった。
経済オタクのアホどもは、日本農産物の関税率をよく批判しますが、このような輸出補助金についての知識は皆無のようです。
自分にとって都合の良い情報しか頭に残ることは無いのでしょうね。
輸出補助金で発展途上国の農業を攻撃するより、関税で自国の農業を保護するほうがまだマシなやり方ではないかと私は思いますけどね。
大規模な農業が効率が良いかと言えば、確かに生産のための機械や資材を節約するためには大規模な農業のほうが効率が良いように思えます。
しかし、生産した農産物が生産コストより高く売れなければ、大規模な農業ほど損失が大きいことは、少し考えればわかることです。
輸出補助金をつけなければ成り立たないような欧米の農業こそが、補助金漬けの農業なのですな。
ちなみにこんな記事もある。
米国:大規模農業事業者が作物補助金獲得に狂奔、違法行為も―GAO報告
http://www.juno.dti.ne.jp/~tkitaba/agrifood/namerica/news/04061001.htm
納税者が支える農業補助金が、まともに農業活動をしていない人々に支払われている可能性がある。米国議会検査院(GAO)が16日、このように指摘する報告書を公表した。会社、パートナーシップ(*)、合弁企業、これらの大規模農業事業者が連邦政府の作物補助金の大きな部分を刈り取っており、受給資格を得るために、これらの取引や農場運営組織が計略的に利用されている恐れがあると言う。
「大規模農業が効率の良い農業である」と言う言葉は迷信にしか過ぎないのに、経済オタク的な財界人どもは、大規模農業をなぜか最近やりたがっている。
米国の例を見て、自分たちも補助金で喰って行きたいと考えているかも知れませんね。
つくづく思うのですが、バブルで失ったお金の総額はどの程度になるのでしょう?
経済オタク的な財界人に農家を非難する資格があるかしら?
(´ヘ`;) う~ん・・・
***** この情報に価値を感じたら *****
 ← Click!してね。
← Click!してね。
1.日本の農業は規模が小さいから効率が悪い。欧米のように大規模な農業を目指すべきだ。
2.日本の農業は欧米より補助金漬けである。
であります。
インターネットが普及していない時代においては、大前研一などが上のようなたわ言をほざいていてもつっこめる方は少なかったのですが、現在ではちょっと検索するだけで、それがたわ言であることがわかります。
どこぞのアホがよく引用する山下一仁氏の記事にも、欧米の農業が補助金漬けであったことが書かれています。
WTOの行方 米、EUの農業「談合」に反発した途上国 RIETI 経済産業研究所
http://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamashita/01.html
EUは1968年、市場価格よりも高い農産物価格を農家に保証する共通農業政策 (CAP)を成立させた。高水準の農産物価格の保証により、生産は刺激され、ワインの湖やバターの山という過剰在庫が発生し、それを海外輸出で処理したため、80年代には農産物の純輸入国から純輸出国へと立場を変えた。米国はEU市場のみならず、EU以外の市場も奪われた。域内の価格が国際価格よりも高いEUの輸出は輸出補助金によって実現した。ケネディ・ラウンド以降ガット交渉上の最大の争点は、輸出利益を奪われた米国とEUの間のCAP、とりわけ、その輸出補助金をめぐってであった。
経済オタクのアホどもは、日本農産物の関税率をよく批判しますが、このような輸出補助金についての知識は皆無のようです。
自分にとって都合の良い情報しか頭に残ることは無いのでしょうね。
輸出補助金で発展途上国の農業を攻撃するより、関税で自国の農業を保護するほうがまだマシなやり方ではないかと私は思いますけどね。
大規模な農業が効率が良いかと言えば、確かに生産のための機械や資材を節約するためには大規模な農業のほうが効率が良いように思えます。
しかし、生産した農産物が生産コストより高く売れなければ、大規模な農業ほど損失が大きいことは、少し考えればわかることです。
輸出補助金をつけなければ成り立たないような欧米の農業こそが、補助金漬けの農業なのですな。
ちなみにこんな記事もある。
米国:大規模農業事業者が作物補助金獲得に狂奔、違法行為も―GAO報告
http://www.juno.dti.ne.jp/~tkitaba/agrifood/namerica/news/04061001.htm
納税者が支える農業補助金が、まともに農業活動をしていない人々に支払われている可能性がある。米国議会検査院(GAO)が16日、このように指摘する報告書を公表した。会社、パートナーシップ(*)、合弁企業、これらの大規模農業事業者が連邦政府の作物補助金の大きな部分を刈り取っており、受給資格を得るために、これらの取引や農場運営組織が計略的に利用されている恐れがあると言う。
「大規模農業が効率の良い農業である」と言う言葉は迷信にしか過ぎないのに、経済オタク的な財界人どもは、大規模農業をなぜか最近やりたがっている。
米国の例を見て、自分たちも補助金で喰って行きたいと考えているかも知れませんね。
つくづく思うのですが、バブルで失ったお金の総額はどの程度になるのでしょう?
経済オタク的な財界人に農家を非難する資格があるかしら?
(´ヘ`;) う~ん・・・
***** この情報に価値を感じたら *****
 ← Click!してね。
← Click!してね。



















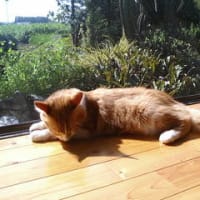
「いい」加減でいこう お金とは何か?
http://blog.kansai.com/gekikaracolumn/339
当時の日本にとっては大陸中国は憬れの国だったのだ。ただ中国を真似て銭を作ったはいいがほとんど使い道がなかった。そりゃそうだ。銭で物を売買するなんて概念がなかったからだ。だからこの銭を見てもみんな使い道のわからない不思議な珍品にしか見えなかった。で、珍品となるとこれを集めたくなるのが人情。コレクター心理である。そこで天武天皇は特に賭博(双六)に入れあげていたのでこの銭を賭けの対称にする事で集めようと思った。結果、日本初の銭はゲーセンのメダルのごとく賭けの対象となり、天皇以下宮中の役人たちがみんな双六の賭けの対象に使ったのだ。
----------
○経営所得安定対策等大綱
http://www.maff.go.jp/syotoku_antei/index.html
それでも、欧米に比べれば微々たる物ですが。
ご隠居さんはいつも勘違いしていますが、専業農家や大規模農家の方が経営は苦しいので、その階層を補助するのが目的です。
現在交渉中のWTO農業交渉ですが(どうやら今回も流れそう…)、「輸出補助金」は撤廃…とかいいながら、アメリカは自国の農業保護体制は変わらない模様です。
○農業改革でWTO自由化交渉に貢献?世論をミスリードする根拠なきマスコミの主張
http://www.juno.dti.ne.jp/~tkitaba/globalisation/agritrade/news/05102401.htm
↑日経新聞社説に対する反論ですが、バブル時代から農業への考え方は変化していないんでしょうね。
実際は農地を増やすときに借金しますから生産コストと借入金の返済金額以下で売るとキャッシュが回りませんよ。
WTO。どうなるか分かりませんが、もし関税の上限なんか入れられたら、今以上に価格が下がるので大きな農家ほど経営できなくなります。
農水省は農家を潰そうとしている。言われても仕方がないでしょうね。
農水省の存在価値っていったい・・
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%94%A3%E6%A5%AD%E7%9C%81
2001年(平成13年)1月6日の中央省庁再編において、通商産業省の廃止に伴いその後継存続機関として新設されたもの。産業政策、通商政策、産業技術、貿易などを所管する。
・
・
・
また、他省庁の所掌分野にすぐに首をつっこんで無責任な政策を打ち出すことが多く霞ヶ関では外務省と並んで非常に嫌われている。裏金作りのテクニックに関しても外務省と双璧であるといわれている。
------
農林水産業以外の産業を管理するのが経済産業省なわけですが、そこが貿易について管理しているところも問題であると思います。
必然的に農産物を犠牲にして工業製品を輸出するような貿易になりますわな。
商社としてはラクしても売れる日本の工業製品を輸出して、それで得た外貨で農産物を輸入すればラクして稼ぐことができます。
たしかにそうといえばそうなのですが、反収は絶対増えませんよね。
面積が大きいとどうしても効率の悪すぎる畑は潰していったり作付けしなかったりするようになるし、妥協してしまう農業になりがちです。
家族3人での労働だと50haが限界で、それ以上だと作物をこぼしても放置したり雑草ばかりの農地になりがちです。また同じ作物(特に小麦)を連作することになってしまいます。
それが効率の良い農家なのか?
農家は補助金漬けといわれますが、農業生産技術は欧米に必ずしも劣っているわけではないし、むしろ他を取り巻く環境が悪いだけだと思っています。
日本の物価と関税率が欧米と一緒だったら日本の農業なんて補助金なんていらないはずです。
米国の農家の収入はその4~5割が補助金だと言う話です。
日本の農家で、そのような農家が存在しますかね?
経済オタクどもの言う補助金漬けの農業は、実際には欧米の農業なのですが、ど~もその辺の情報がマスコミを通じて国民に伝わることはないようですね。
以下、ご参考:
他国には「農業予算削れ」、自国農業だけ「手厚く保護」
身勝手きわまるアメリカの新農業法(1)
http://www.nouminren.ne.jp/dat/200206/2002060308.htm
暴落に約四兆円の補てん予算を計上
さらに大きな違いは、暴落に対する全額国費による補てんです。短期融資制度は生産費を考慮に入れていない制度ですから、これだけではとうてい生産費を償うことはできません。
そこで九六年農業法がまったく予定していなかった農家救済策(緊急直接支払い)が九九年から登場し、廃止された不足払制度の代わりの役割を果たしてきました。九九年から二〇〇一年までの間、単年度の予算措置として注ぎ込まれてきた暴落補てんは三百五十五億ドル、三兆七千億円強にのぼります。
その結果、日本の価格保障予算が一九八〇年比で半分以下に激減したのに対し、アメリカの価格・所得補償予算は十一倍近くになっているのです。また“世界のパン篭”と呼ばれてきたアメリカの農民の所得のうち、実に四割から五割は、こうした政府補助金によって満たされているのです。
日本だけが国際基準から取り残された
http://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamashita/03.html
農家に直接支払われる補助金の額は日本は極端に少ないわけで、日本の農業予算は農業関連の企業のための予算であることを暴露されています。
大規模な農業でも儲けが無いことは財界人の方々もご存じないはずがありません。(知らなければ無能の証明です。--;)
自分では耕す気の無い財界人の方々が農業を最近やりたがっているのは、農業予算に自分たちがたかりたいため。
安い農地を多量に買い漁って、その面積により直接支払いの補助金で稼ごうって腹です。
http://www.yorozuya-online.gr.jp/shoku/shokuryoji.htm
■農地の減少と耕作放棄地
日本の耕作面積は1972年が568万㌶、1997年には497万㌶に減少しています。この25年間に開墾や干拓で59万㌶の農地が増えていますが、一方で133万㌶の農地が消えています。道路や宅地、工場用地などの転用されたり、営農条件が悪いということで耕作を止めたりしたのが原因です。
---------
減反政策などを続けながら、開墾や干拓の事業は続けている。耕地整備事業なども同様にですね。
結局、農業予算は名義は農家のものであっても、実体は土建業者のためにあったわけです。
この程度のカラクリが分からない輩が政治経済を語る資格なしです。
ね。ご隠居さん。(* ^ー゜)ノ
日本の農家で、そのような農家が存在しますかね?
我が家の帳簿を見て唖然としたのですが、麦作なんとかという収入があって小麦収益の二倍くらいになってました。
つまり7割方税金に頼っているということで米国よりももらっていることになります。
ただしそれには関税で補っている面もあります。
関税が少なくなるようになれば政府の懐が厳しくなるので補助金制度が変わりました。
これは規模の小さい農家から切り捨てるような制度といえます。
しかし小麦は大規模農業の輪作体型には欠かせない基幹作物なのでなかなかやめることができないのです。