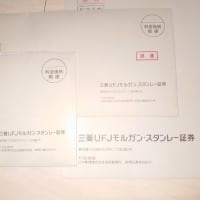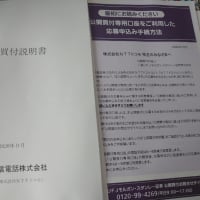| 帝国データバンクによると、2023年度のステーキ店の倒産件数が過去最高を更新したようだ。主要食材である米国産牛は、ウクライナ紛争や干ばつなど異常気象の影響で生産コストが急騰し、加えて円安の影響などで輸入価格が急上昇するなど、経営環境の急激な悪化が原因である。 貿易統計によると、ステーキ店などで使用が多いサーロインなどの米国産牛肉価格は、2023年度平均だと5年間で1.4倍に、米国産より安価な豪州産も5年間で1.3倍と急上昇している。 低価格を売りとしたステーキ店や小規模店では急激な仕入れ価格の上昇ペースに耐えられないケースも出ているようだ。低価格で楽しめたステーキ店には、とてつもない逆風が吹いており、生き残りに必死の様相を呈している。 ◆知名度は高い「いきなりステーキ」 立ち食いのスタイルで注目を浴び、店舗数を拡大していった「いきなりステーキ」(株式会社ペッパーフードサービス)。一時期は500店舗まで迫ったが、急速に勢いが衰え、約320店舗の撤退を余儀なくされ、2024年3月時点で185店舗(国内181、海外4店舗)しか残っていない。 売上は145億8700万円(2023年12月期決算)で外食売上ランキングは54位と、いつの間にかブロンコビリー(47位。後述)に店舗数で追い抜かれたようだ。 いきなりステーキは当初、立ち食いでも原価が5〜7割をアピールポイントにし、一世を風靡。ステーキの量をお客さんが自由に決められるオーダーカット制の導入で、手軽にお手頃価格でステーキを食べられる店を標榜していた。 ◆特許出願が認められた珍しいケース いきなりステーキ 狭小店舗に積極的に出店し、お客さんを高回転させるため原価は高く、粗利益率は低い。賃料など管理費用を低減させ、固定費を低くした効果もあり、損益分岐点の低い店づくりをしていた。 しかし、それとは別の理由で苦戦を強いられていると筆者は思う。いきなりステーキは特許出願(提供方法の新規性、利用可能性、進歩性)が認められた外食業界では珍しい店である。通常の外食業界は、新たな試みをしても差別化が困難で、模倣も容易だ。 いきなりステーキは知的所有権を保有し、それをビジネスモデル特許(ステーキの提供システム)として2014年6月に申請したのである。特許庁がなかなか発明と認めなかったが、補正をして2016年6月にやっと登録された時も話題になった。すぐに異議申し立てがされたが、最終的にはこの特許が維持されることとなった。 ◆「オーダーカット」も廃止。低迷の原因は? いきなりステーキ そこまでして特許登録をしたのに、この逆風のために名物のオーダーカットを廃止し、提供方法の変更を余儀なくされたいきなりステーキ。でも業績悪化に陥った真因は、成長期における出店戦略の失敗ではなかろうか。それが起因となって順風満帆だった経営が傾いてしまったのではと分析する。 筆者の近所でも、1キロ商圏内に2店舗あり、しかも同じ看板で客を奪い合うカニバリゼーション状態が発生していた。いくら消費者に急速に人気が出た業態でも、性急に店舗展開をするのはリスクが高すぎる。需要と競争の実態を見極めなければ取り返しのつかないことになるが、よほどの自信があったのか、出店に強くアクセルを踏んだようだ。 案の定、やっぱりステーキ(89店舗・2022年5月末時点)など、同タイプのステーキ店の参入が相次ぎ、いきなりステーキの経営は厳しくなったようだ。また、戦略と管理の一体的推進が経営力で車の両輪の関係だが、やみくもに出店を急ぐがあまり、店舗の運営管理が追いつかず、撤退しないといけなくなった店もあったようだ。 いくら高級料理であるステーキを身近な料理にしたとしても、頻繁に食べられるものではないのは当然だ。筆者が焼肉店を経営していた時、売上予算を達成するためには、何人のお客さんが必要で、客単価はいくら必要かと計算した時、既存顧客の来店頻度は月に一度程度に設定していたものである。 ◆奮闘するブロンコビリーとビッグボーイ! そういった店を取り巻く環境が厳しい中で奮闘するのが、ステーキやハンバーグをメインにした「ブロンコビリー」と、「ビッグボーイ」だ。 ブロンコビリーは1978年に故・竹市請公氏が開業した「ステーキハウスブロンコ」を母体として、1983年にレストランチェーンを運営する株式会社ブロンコビリーを設立した。コスパが高いステーキチェーンとして人気で、東海地方を中心に、全店直営の郊外型店舗で139店舗(2024年4月1日現在)を展開している。 2023年12月期の売上は233億7700万円、営業利益は16億4400万円、営業利益率は7%となっており、収益性は大型店の中では高いほうであろう。財務の安定性においては、自己資本比率81.5%と盤石である(2023年度決算より)。売上規模は外食ランキング47位となっているが、多くのファンがおり、勢いがある店で注目されている。 ◆新鮮なサラダバー、かまど炊きのお米 ブロンコビリーといえば、炭火焼きによるステーキやハンバーグだが、提供される時のシズル感が食欲を掻き立ててくれ、食卓を楽しませてくれる。また、サラダバーの鮮度やクオリティは競合他店との差が明白である。 常時20種類ある新鮮サラダバーは、営業開始時間の早い時間帯に行くと、お客さんが一気に向かい、長蛇の列ができている。女性だけでなく、健康志向の男性にも人気で、価格と内容のバランスから見てもコスパが高い店である。サラダバーは客席からも見える複数のモニターに現在の映像が映されている。これは、お客さんにモニターを通じて推奨されていると共に、サラダの減り状態をスタッフが共有し、迅速に準備と補充をしているようだ。 また、各店にかまどを設置してあり、そこで炊き上げ提供される新潟県魚沼産のコシヒカリは大かまどで炊きあげ、顧客に提供しており、これもまた人気だ。かまどならではの強い火力と高い保湿性が味の違いを生んでおり、ご飯が見た目でも光っており美味しい。他でこういう提供をしている店はあまりないように思う。[ ◆働きやすい環境のため「全店一斉休業」 ブロンコビリーではオープンキッチンで調理するコックさんの仕事ぶりが客席から見られるなど、演出にも力を入れており、楽しい雰囲気を醸成している。接客サービスも元気で丁寧であり、接遇5原則(挨拶・表情・身だしなみ・言葉遣い・立ち振る舞い)が徹底されている。オールドアメリカン風の装飾品や演出による雰囲気も最適だと思う。 昨年から実施している全店の一斉休業を今年も設けており、従業員の慰労にも努めている。東海地区を拠点に関東・関西地区で全139店舗を展開する同店は、全従業員の働きやすい環境づくりのためにも努力している。 とはいえ、決して順風満帆ではなく、人に関して苦労した過去があった。2013年には当時相次いだSNSでの“悪ふざけ投稿”騒動で閉店する店もあり、そこから社長が、人材育成の大切さを思い知り、人が会社の未来を決めることを改めて確信したそうだ。 企業理念が現場に浸透していなかったことへの反省から、現場の若手社員の悩みを直々に聞く目的で、酒を酌み交わしながらの合宿研修を毎月実施しているようである。賃金以外で労働意欲を喚起し、店内の一体感を醸成して顧客満足度を向上させるのが目的とのことだ。 ◆アフターコロナでも客数は前年比2桁増 顧客の囲い込みと再来店を促す仕掛けも徹底強化している。顧客にアプリのダウンロードを促し、そのアプリには来店金額に応じたポイントを付与し、貯めて使う楽しみを顧客に提供している。また会計の際に人数分の特典付きのスクラッチ券を配布し、再来店の動機づくりをしている。 こういった販促が功を奏し、筆者の地元では営業開始時間前に早く行って並ばないと、入店に時間を要するといったイメージが定着しており、必ず営業時間前の早い時間に行っていた。 これは決算書を見ても一目瞭然で、客数の推移をみると、コロナが収束して客数が回復していた前年に対しても、今年の第一四半期は、110%と2桁成長で著しく増えている。 ◆ビッグボーイの巻き返し! 一方で、昔から馴染みある「ビックボーイ」も人気である。ビッグボーイは1932年にアメリカで創業し、日本での経営権は2002年12月にダイエーからゼンショーグループに譲渡された。 ビッグボーイもブロンコビリーとほぼ同時期の1978年にスタートしたステーキハンバーグをメインにしたファミリーレストランである。こちらもアメリカ風の店舗に、調理場が客席から見えるオープンキッチンで手こねハンバーグやステーキ類などを焼き上げる工程を楽しむことができる。 ゼンショーグループは外食売上ランキング首位で、牛丼(すき家)、親子丼(なか卯)、ステーキ&ハンバーグ(ココス・ビッグボーイ)、回転寿司(はま寿司)、スパゲティ(ジョリーパスタ)など、多種多様な業態を傘下に持つ外食最大手である。 M&Aを駆使した成長戦略で、連結売上7799億円、総店舗数1万283店舗、傘下に19ブランド(2023年3月末時点)を保有する規模を誇っている。収益性は営業利益217億円、営業利益率は2.8%と、他業態を展開してリスク分散を図っているが、リターンも分散しているようである。 ◆ロードサイドを中心に約200店舗を展開 ちなみに、単一業態に事業を集中する外食売上ランキング2位のマクドナルドは、売上は首位ゼンショーの半分以下の3819億円だが、営業利益は408億円で10.7%と2桁以上の高収益率である。 財務状態を見ても、自己資本比率が28.2%のゼンショーに対して72.8%と高いマクドナルドでは、資本の安定性に大きな開きがあり、両社の戦略の差が如実に数字に表れている。 その外食最大手企業のゼンショーの傘下で、再起を図ろうとする株式会社ビッグボーイジャパンの店舗数は、207店舗で、店舗別内訳はビッグボーイ179店舗、ヴィクトリアステーション28店舗である(2022年8月時点)。郊外型のロードサイド店舗を中心に出店し、フードバー(スープ・サラダ・カレー)がセットされ食べ放題が堪能できる。特にカレーバーは人気を博しており、メイン料理の前にたらふく食べる強者も存在し、圧倒される。 ◆店舗を訪れて心配していたことは… キッズ特典が多く来店ごとの特典を楽しみにするなどお子さんにも人気が高い店で、親御さんが週末に連れて行くというパターンの店である。筆者も昔からなじみがあるので、定期的によく通っていた。ただ、各店けっこう老朽化が進み、複数個所の修繕が必要なのに放置されており、心配したものだった。なぜ資本力のある外食最大手企業の傘下になったのに、この状態を放置しているのかが不思議だった(たまたま筆者の周りの店舗がそうだっただけかもしれないが)。 多くの業態を傘下に有するゼンショーのブランド・ポートフォリオ戦略(各ブランドの勝ち負けを定量的・定性的に分析し、自社の企業価値を高めるために、ブランドの入れ替えをして、持続的な成長を達成すること)の中で、収益性や成長性の観点から、経営資源を配分する価値がないと評価されているのかなと心配していた。 ビッグボーイの魅力はスープバー(コーンスープや中華スープ)とカレーバーだと思う。一時期、カレーバーのある店が増えたが、今は少なくなっている。カレーの味も安定的に美味しくこれだけでも価値があると思う。 ◆外食版DXを推進するビッグボーイ 筆者の体感ではあるが、昔は、メインであるステーキやハンバーグ料理の提供が遅く、待っている間にお客さんは何度も、サラダやスープのお替りをして、メイン料理が来た時はすでにお腹がいっぱいになったという例も多かった。お客さんが何度もスープバーやサラダバーに向かう姿を見て、料理提供が早かったら原価がもっと低く低減させられるのではと思ったものだが、今は改善されている。 ビッグボーイはブロンコビリーと違い、人手不足の中でロボットなど外食版DXを推進し、省力化投資に力を入れている。元気ある従業員の接客から生み出す活気ある店内雰囲気のブロンコビリーとは真逆の路線のようだ。 店に入って案内もロボット、オーダーもタッチパネル、料理提供は配膳ロボット、会計はセルフレジと人とは接しない非接触型の運営となっている。若干、寂しい感じもするが、今はこういうレストランの形態に慣れてしまったお客さんも多く、特に違和感がなく食事を満喫されているようだ。 ◆運営スタイルは真逆だった両チェーン ビッグボーイは客席案内〜水・お絞りの提供〜注文〜料理提供〜レジ会計(人の応援あり)までの一連のプロセスがデジタル機器などを使ったセルフサービスで行っている。一方、ブロンコビリーは人によるフルサービスである。 その省力化投資で、筆者の訪問時は、ビッグボーイはランチのピーク時でもホール2人、キッチン3人、配膳ロボット2台で約110人収容の大型店を回しており、料理提供には配膳ロボットがフル活動している。人はフードバー(サラダ・カレー・スープ)の補充や片付けに専念しており、人と機械の協働体系が構築されている。 一方のブロンコビリーは、こちらも筆者の訪問時は、7人の定数で運営していた。パートさんの最低賃金と4時間程度の時間保障などの人件費総額とロボットの1時間あたりのリース費用(約95円)とを勘案し、それらを投入して店が得る効果を考えたら、どちらの運営スタイルがいいかは難しいところで、経営者の店舗経営に対する理念の違いであろう。 ◆ステーキ業界のなかで生き残りをかける ここまで説明してきたように、いきなりステーキが苦境に立たされる一方で、好調なブロンコビリーとビッグボーイ。だが、両チェーンとも店舗規模も同じ大型店でメニューもほぼ同様だが、運営スタイルは真逆であるのだ。 飲食店は1年で3割、2年で半分が廃業するなど、開業は容易でも存続は難しい業界であり、10年生存率は1割とのことである。そういったスクラップ&ビルドが頻繁の環境の中で、奮闘する各飲食店。いきなりステーキ・ブロンコビリー・ビッグボーイも、それぞれが厳しい経営環境の中で生き残り策を講じているようだ。 これからも、顧客提供価値を磨き上げ、さらなる商品・サービスの充実を追求し、顧客満足度を高めながら、自店の利益を確保する原点に立ち返り頑張ってもらいたい。(日刊SPA!) |
いきなり!ステーキは出店のスピードに問題があったのと同様に、固定客を逃したのが問題でしょう。
食べた肉の重さによる得点(肉マイレージ)を簡単に改悪。
その客を軽く考えているところが問題です。