
妖艶なエコノミスト・浜矩子が19日付毎日新聞に、衆院選について談話を寄せた。
表題は「落ちこぼれる 人々救済を」である。
浜矩子は、08年11月2日のフジTV新報道2001に出演し、国家の行方の夢と希望ついて、
『グローバル時代は、最もローカルで、最も弱いものが、最も傷つく時代です。(政治は)そこにも夢が花開いてゆくような形に持ってゆかなければなりません。』と語った。
ビッグイシューにも連載する浜矩子に相応しい。
「落ちこぼれる 人々救済を」は、彼女の言う『ドン・キホーテのマニフェスト』なのかも知れない。
以下に、全文を転載させていただいた。(19日付毎日新聞第4面)
■落ちこぼれる人々 救済を
今回の衆院選は、グローバル化による大競争社会の行き過ぎが明らかになる中、日本がどのような社会づくりをするかを選択する歴史的な選挙だ。
政治家と官僚が特定の人々の利益を重視し、内輪の論理で進めてきた従来の政治手法では、時代の変化には対応できない。これに国民が気付き、変化を求めている。
昨年のリーマン・ショックで明らかになったのは、格差拡大や派遣労働者の増加が進む一方、そうした人々を支え守るための安全網作りを政治が怠ってきたという現実だ。
グローバル化による競争時代の到来は必然で、それ自体は否定できない。ただ、落ちこぼれる人々を救い、再び社会に参加できる国をつくるため、政治の役割はいっそう重要になる。
各党のマニフェスト(政権公約)を見ても単なる仕事リストにとどまり、大きな国家像がないのは不満だが、有権者はどういう国をつくるべきなのかを念頭に、候補者を吟味すべきだ。(浜矩子、談)
浜矩子語録目次Ⅱへ
表題は「落ちこぼれる 人々救済を」である。
浜矩子は、08年11月2日のフジTV新報道2001に出演し、国家の行方の夢と希望ついて、
『グローバル時代は、最もローカルで、最も弱いものが、最も傷つく時代です。(政治は)そこにも夢が花開いてゆくような形に持ってゆかなければなりません。』と語った。
ビッグイシューにも連載する浜矩子に相応しい。
「落ちこぼれる 人々救済を」は、彼女の言う『ドン・キホーテのマニフェスト』なのかも知れない。
以下に、全文を転載させていただいた。(19日付毎日新聞第4面)
■落ちこぼれる人々 救済を
今回の衆院選は、グローバル化による大競争社会の行き過ぎが明らかになる中、日本がどのような社会づくりをするかを選択する歴史的な選挙だ。
政治家と官僚が特定の人々の利益を重視し、内輪の論理で進めてきた従来の政治手法では、時代の変化には対応できない。これに国民が気付き、変化を求めている。
昨年のリーマン・ショックで明らかになったのは、格差拡大や派遣労働者の増加が進む一方、そうした人々を支え守るための安全網作りを政治が怠ってきたという現実だ。
グローバル化による競争時代の到来は必然で、それ自体は否定できない。ただ、落ちこぼれる人々を救い、再び社会に参加できる国をつくるため、政治の役割はいっそう重要になる。
各党のマニフェスト(政権公約)を見ても単なる仕事リストにとどまり、大きな国家像がないのは不満だが、有権者はどういう国をつくるべきなのかを念頭に、候補者を吟味すべきだ。(浜矩子、談)
浜矩子語録目次Ⅱへ










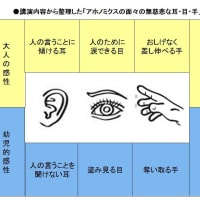

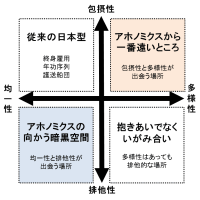

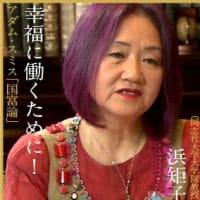











▼民主党は、マニフェスト案において、『原則として製造現場への派遣を禁止』とす
る一方で、『専門業務以外の派遣労働者は常用雇用』としています。『専門業務』の
『常用雇用』が除外され、かつ『専門業務』に技術者 (エンジニア) 等が含まれると
すれば、これは看過できない大きな問題です。
技術者 (エンジニア) 等の非正規雇用 (契約社員・派遣社員・個人請負等) を明確
に禁止しなければなりません。
改正前の労働者派遣法に関する「政令で定める業務」の内容は、技術の進展や社会
情勢の変化に対し時代遅れになっており、非正規雇用の対象業務を、全面的に見直す
必要があります。
また、派遣社員だけではなく、「契約社員」・「個人請負」等を含む非正規雇用を
対象としなければなりません。
【理由】
●技術者等の非正規雇用が『製造現場』の技能職に比べて、賃金・雇用・社会保険等
において有利だという誤解があるならば、そのようなことは全くない。長時間労働
など過酷な労働環境に置かれている割には低賃金の職種で、雇用が安定しているか
というと、『製造現場』の技能職以上に不安定である。
技術者等が『製造現場』の技能職に比べて過酷な労働環境に置かれているにもかか
わらず、非正規雇用として冷遇されるのであれば、技術職より技能職の方が雇用・
生活が安定して良いということになり、技術職の志望者が減少して人材を確保でき
なくなる。努力して技術を身につけるメリットがなくなるため、大学生の工学部・
理学部離れ、子供の理科離れが加速する。一方、技能職の志望者は増加し、技能職
の就職難が拡大する。
●技術者等の非正規雇用が容認されると、マニフェスト案『中小企業憲章』における
『次世代の人材育成』と、『中小企業の技術開発を促進する』ことが困難になる。
また、『技術や技能の継承を容易に』どころか、逆に困難になる。さらに、『環境
分野などの技術革新』、『環境技術の研究開発・実用化を進めること』、および、
『イノベーション等による新産業を育成』も困難になる。
頻繁に人員・職場が変わるような環境では、企業への帰属意識が希薄になるため、
技術の蓄積・継承を行おうとする精神的な動機が低下する。また、そのための工数
が物理的に必要になるため、さらに非効率になる。事業者は非正規労働者を安易に
調達することにより、社内教育を放棄して『次世代の人材育成』を行わないように
なる。技術職の魅力が低下して人材が集まらなくなるため、技術革新が鈍化、産業
が停滞する。結局、企業が技能職の雇用を持続することも困難になる。
●派遣社員だけではなく、「契約社員」・「個人請負」等を含む非正規雇用を対象と
しなければ、単に派遣社員が「契約社員」・「個人請負」等に切り替わるだけで、
雇用破壊の問題は解決しない。
企業は派遣社員を「契約社員」や「個人請負」等に切り替えて、1年や3年で次々
に契約を解除することになり、現状と大差ない。
▲上記の様に、『製造現場への派遣を禁止』するにもかかわらず、技術者等の非正規
雇用 (契約社員・派遣社員・個人請負等) を禁止しないのであれば、技能職より雇用
が不安定となった技術職の志望者が減少していきます。そして、技術開発・技術革新
や技術の継承が困難になるなどの要因が次第に蓄積し、企業の技術力は長期的に低下
していきます。その結果、企業が技能職の雇用を持続することも困難になります。
これを回避するには、改正前の労働者派遣法に関する「政令で定める業務」の内容
を見直して技術者等の非正規雇用を禁止し、むしろ技術者等の待遇を改善して、人材
を技術職に誘導することが必要です。これにより、技術者等は長期的に安心して技術
開発・技術革新に取り組むことに専念できるようになります。その成果として産業が
発展し、これにより技能職の雇用を持続することが可能になります。
もしも、以上のことが理解できないのであれば、管理職になる一歩手前のクラスの
労働者ら (財界人・経営者・役員・管理職ではないこと) に対し意識調査をするか、
または、その立場で考えられる雇用問題の研究者をブレーンに採用して、政策を立案
することが必要です。