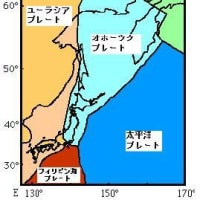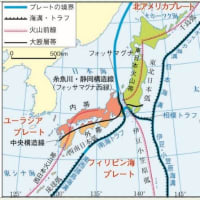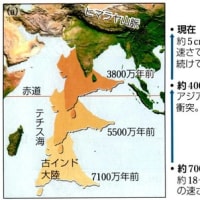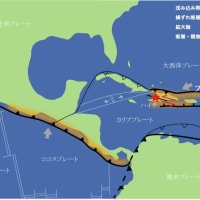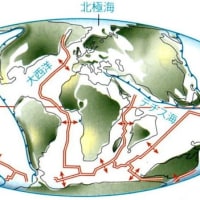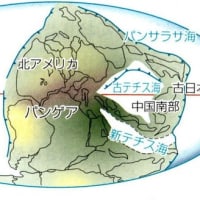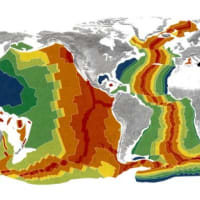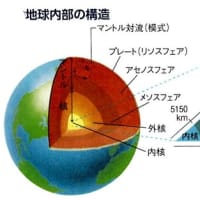食糧管理法が存続する限り、政府は農民から米を全量買い上げなくてならず、生産過剰の米は政府が保管した。都市のサラリーマン並みの所得を保障するためには、米の生産コストの削減、米から他作物への転換、そして離農促進による農地の集中と機械化、それらを具体化する農業政策として、農業基本法が施行された(1961年)。
農業基本法の3大政策として、生産政策、価格・流通政策、構造改善政策があった。
Ⅰ.生産政策(農業基本法第8条~第10条。特に第9条)
① 農業生産の選択的拡大
選択的拡大とは、米作から、需要増加と価格上昇の期待される野菜・果樹・畜産などに転換することである。食糧管理法は政府が農民から米を買い集め、国民に配給する戦時法制である。戦争が終わり、米の生産過剰の状態が続くと、政府は買い集めた米を民間倉庫を借り上げて保管しなければならず、食糧会計は赤字に陥ってしまった。
米の生産過剰をなくすため、米作から、野菜・果樹・畜産などに転換を進める政策が、農業基本法の根幹であった。


果樹の栽培は、米のように栽培年から収穫できない。果樹の栽培開始から収穫まで、5年は待たなくてはならない。5年間は果樹からの収入がないのである。しかも、果樹は価格変化が激しいし、豊凶の差も大きい。米ほどの安定収入を得ることはできない。
落下したりんごが消毒薬の散布直後であり、それを拾って食べた母子の死亡したニュースがあった。消毒を散布した者が、適切な消毒散布量と時期を理解していないために起こった悲劇であった。新しい知識を必要と農業に、適切な政策や営農指導がなされなかった。
② 農業の生産性の向上
米作で高収入を得るためには米価の高いことが当然だが、水田面積が広く、農業機械を使ってコスト削減ができること、化学肥料・農薬により高品質の米をつくること、などである。
農業機械のうち、田植え機80万円、トラクター170万円、コンバイン230万円、脱穀機70万円などである。値段が高い、故障しやすい、使用期間が短い、燃料を大量に消費する、ということで、農業機械をそろえれば、その支払いは、1haの供出米の収入では不可能である。1haからの米作収入は100万円程度であり、機械の寿命を考えると、農機具メーカーのために働いているようなものである。
そこで、若い農業後継者のいる農家を中核農家とし、中核農家に水田を集めて、大規模機械化農業を推進した。
しかし、農地放出を要請された老夫婦の農家は後継者がいないのに、農地を貸すことも売ることも拒否した。それは、農地改革でただ同然で手にいれた農地を、住宅団地用地・工場用地・道路などに売却すると、巨額のカネを得たからである。億単位のカネを得る農家もあった。安い価格で近所の中核農家に売ったり貸したりすると、カネ儲けの機会を失うことになった。
生産性向上のための中核農家の育成に、有効な政策はなかった。アメリカ型の大規模機械化農業をモデルにした、中核農家の育成に失敗した。

農家の人口が急速に減少したのは、出稼ぎあるいは兼業が増加したからである。しかし、農家戸数の減少割合は小さい。これは農業をやめたり、兼業になっても、農地を簡単には売らない、ということである。中核農家への農地を集中し、大規模専業農家を育成する農業基本法は、根本から誤っていたことになる。
③ 農業基盤整備、資本装備、農業生産の調整
これらの具体的政策を農業の構造改善と呼ぶことがある。
農業基盤整備とは、大型農業機械を農地に入れるため、農道を建設することである。あるいは農業用水を得るために農業用ダムと水路を建設することである。水田1区画を0.3haずつの大きさにあぜ道を造り変えることでもある。費用の大半が政府補助金行われた。各農家の負担金を少なくすることが、農村を基盤とする政治家の腕の見せ所であった。農村では農業基盤整備の名目で、冬の農閑期に大規模土木事業が行われ、出稼ぎに行かなくても現金収入を得ることができた。それで基盤整備の分担金を払ったり、農業機械を買ったりした。
資本装備とは、農家が自己資金であっても借金であっても、調達可能なカネのことである。農協が、農地を担保にいくらでもカネを貸した。農協には、政府資金が全農を通して、いくらでもカネが流れた。農家は農協から多額の借金をして、農機具を買って農業をすることもできたし、多少は贅沢な暮らしもできた。返済は、米を供出した時に清算したし、農閑期には農業基盤整備事業のアルバイトがあった。それに、米価が毎年上がるので、借金生活が苦にならなかった。
農業生産の調整とは、農協と役場が中心になり、米作農家に米から他の作物に転換させることであった。必要なカネはいくらでも貸すことを切り札に、農家に、米作からの転換を勧めた。野菜・果樹・畜産などのどれに転換させるかは、農家との話し合いで決まった。しかし、農家が戸別に転換しても、大産地を形成できず、販売先を確保できなかった。農業生産の調整も、群馬県の嬬恋村を除き、失敗に終わった。

群馬県嬬恋村(つまこいむら)は、標高700~1,400mに広がる高原である。夏キャベツ・秋キャベツを中心とした高原野菜が作付けされている。このうち863haが国営パイロット事業により造成された農地である。農道の整備、収集倉庫の設置とともに、計画的な栽培体系が確立された。平成元年度から始まった国営パイロット事業では、404haの農地造成が平成9年度に完了した。これは連作障害を避けるため、規模拡大と併せて輪作体系を確立し、農作物の安定供給と経営の安定化を図るため実施された。嬬恋村は野菜産地として成功した。巨額の国費がつぎ込まれたモデル事業として、大量の野菜供給が可能になって、東京・横浜と安定供給契約を結んだこと、食品大手企業との契約栽培ができたことが、野菜産地として成功した理由である。
Ⅱ.農産物の価格・流通(農業基本法11条~14条)
① 価格の安定
米価の国家統制の食糧管理法を野菜・果樹・畜産に拡大することには、都市住民からの反対が強かった。しかし、生産過剰になれば、米のような長期保存は不可能な作物ばかりで、農家は損を覚悟の安売りかなかった。その代わり、気候の異変で特定産地で品不足になると、作物は値上がりをし、他産地は儲けることができた。すべての産地が等しく儲けることは、消費の急拡大が進まない限りは不可能であった。
政府と農民が半額ずつ出し合う農業共済制度があり、台風・冷夏・晩霜・干ばつのような被害を
受けた農家には6割~8割の損失を補填された。
災害に対しては、共催の補償制度があったが、農産物の生産過剰による値下がりには補償がなかった。いわゆる豊作貧乏である。野菜・果樹・畜産農家の脱落は、災害よりは、清算過剰による市場価格の値下がりが原因であった。農家の創意・工夫・努力は産地間競争を激しくし、野菜・果樹・畜産農家を淘汰する結果となった。
各種農業賞を受賞するような優れた産地が、他産地に真似られて没落というケースが」も多く、野菜・果樹・畜産などの有名産地が生き残って、都市サラリーマン並みの収入を得ることは、米作よりはるかに困難であった。
② 農産物の流通
農業基本法12条は、農協に優越的な地位を与えている。米からの転作を目的とする農業基本法の具体化には、農協の協力が不可欠であった。むしろ、農協単位に新しい農業を創造しなくてはならなかった。農協は新しい農業の主体であった。
国は、需要の高度化及び農業経営の近代化を考慮して農産物の流通の合理化及び加工の増進並びに農業資材の生産及び流通の合理化を図るため、農業協同組合又は農業協同組合連合会が行なう販売、購買等の事業の発達改善、農産物取引の近代化、農業関連事業の振興、農業協同組合が出資者等となつている農産物の加工又は農業資材の生産の事業の発達改善等必要な施策を講ずるものとする。
農協には、農業基本法が期待するような実力はなかった。政府からの補助金を農家に配分する単純な仕事はできたが、農協と農民が、農協を単位として、ともに新しい農業像を考える能力はなかった。
果樹はりんご、みかん、もも、ぶどう、さくらんぼなど、いずれも市場がすぐにあふれて生産過剰が近くて、産地間競争が起こって脱落の相次ぐことは明白であった。
野菜も果樹も同様の恐れがあった。
小麦のように輸出品が安価良質の場合、日本の農業は太刀打ちできなかった。そのため、国(政府)は日本の農業に大きな影響のある農産物の輸入を規制した。
1960年代の高度経済成長期、日本の安価良質な工業製品が世界に輸出され、経済発展を続けた。日本の農産物市場が余りに閉鎖的であるとして、海外からは米・果実・畜産品の市場開放を求められた。特に国内市場の大きい、バナナ・オレンジ・牛肉の輸入が、日本とアメリカの貿易問題に発展した。
Ⅲ.農業構造の改善(農業基本法21条)
① 農業生産の基盤整備
農業基本法は、米作面積を減らすことが最大目標であった。しかし、農業基本法には米作を除外するとは書いていないので、米作の基盤整備に重点が置かれた。水田の区画、あぜ道、水路、農道などがつくられた。特に農道は農業機械の通行に便利なように、飛行場の滑走路のような農道が建設された。実際に空港としても利用可能な農道もあった。

大分農道空港。一部の農道は農産物を大都市に高速輸送する目的で、小型航空機専用滑走路の規格でつくられた。片道しか貨物がないために輸送コストが高く、実際にはどの空港もほとんど使用されなかった。全国8カ所の農道空港は1988年に運用開始、1897年に空港としての利用が停止された。
② 環境整備
具体的には何を示すのか明確でないので、環境整備を名目に、農家には多額の補助金が貸し出され、のちに農家の経営の重荷になった。
例えば養鶏。5羽10羽の庭先養鶏ではなく、1000羽以上の大型経営の場合、農家は補助金による養鶏が可能であった。養鶏場は朝早くからうるさいので、養鶏場を集落から離して建設する資金に充てられた。
養豚場から流れ出る汚水が不潔のため、100頭以上の飼育をする場合、養豚農家は水処理施設をつくる補助金を得ることができた。
③ 経営近代化
趣味的経営ではなく、経済的自立の可能な農業経営をめざすことである。1ha程度の米作では、経営が成り立たないから、米作も農業もやめさせて、中核農家に農地を集中させることが、政府のねらいであった。
米、りんご、みかん、ぶどう、キャベツ、たまねぎなど、何を栽培してもよいのだが、産地間の価格競争を勝ち抜くような経営を実現しようとした。しかし、食糧管理法で価格の保護された米作が最も安定していて、経営近代化は、米作と出稼ぎによって進められた。
--------------------------------------------------------------------------------
食糧管理法は1942年につくられた戦時法制であり、戦後は米の価格引きあげの法的根拠となった。小規模米作農家の経営がなりたったのは、食糧管理法によって政治米価が続いたからである。1994年に廃止されて、米は原則的には自由な流通ができることになった。
農業基本法(旧農業基本法)は1961年に米の生産過剰対策と、農民所得の向上を目的に施行された。米からの転作、農業近代化にはある程度の役割を果たしたが、輸入食料の増加のために急速に時代遅れとなり、1999年に廃止された。代わりに、食料・農業・農村基本法(新農業基本法)が施行された。

農業基本法の3大政策として、生産政策、価格・流通政策、構造改善政策があった。
Ⅰ.生産政策(農業基本法第8条~第10条。特に第9条)
① 農業生産の選択的拡大
選択的拡大とは、米作から、需要増加と価格上昇の期待される野菜・果樹・畜産などに転換することである。食糧管理法は政府が農民から米を買い集め、国民に配給する戦時法制である。戦争が終わり、米の生産過剰の状態が続くと、政府は買い集めた米を民間倉庫を借り上げて保管しなければならず、食糧会計は赤字に陥ってしまった。
米の生産過剰をなくすため、米作から、野菜・果樹・畜産などに転換を進める政策が、農業基本法の根幹であった。


果樹の栽培は、米のように栽培年から収穫できない。果樹の栽培開始から収穫まで、5年は待たなくてはならない。5年間は果樹からの収入がないのである。しかも、果樹は価格変化が激しいし、豊凶の差も大きい。米ほどの安定収入を得ることはできない。
落下したりんごが消毒薬の散布直後であり、それを拾って食べた母子の死亡したニュースがあった。消毒を散布した者が、適切な消毒散布量と時期を理解していないために起こった悲劇であった。新しい知識を必要と農業に、適切な政策や営農指導がなされなかった。
② 農業の生産性の向上
米作で高収入を得るためには米価の高いことが当然だが、水田面積が広く、農業機械を使ってコスト削減ができること、化学肥料・農薬により高品質の米をつくること、などである。
農業機械のうち、田植え機80万円、トラクター170万円、コンバイン230万円、脱穀機70万円などである。値段が高い、故障しやすい、使用期間が短い、燃料を大量に消費する、ということで、農業機械をそろえれば、その支払いは、1haの供出米の収入では不可能である。1haからの米作収入は100万円程度であり、機械の寿命を考えると、農機具メーカーのために働いているようなものである。
そこで、若い農業後継者のいる農家を中核農家とし、中核農家に水田を集めて、大規模機械化農業を推進した。
しかし、農地放出を要請された老夫婦の農家は後継者がいないのに、農地を貸すことも売ることも拒否した。それは、農地改革でただ同然で手にいれた農地を、住宅団地用地・工場用地・道路などに売却すると、巨額のカネを得たからである。億単位のカネを得る農家もあった。安い価格で近所の中核農家に売ったり貸したりすると、カネ儲けの機会を失うことになった。
生産性向上のための中核農家の育成に、有効な政策はなかった。アメリカ型の大規模機械化農業をモデルにした、中核農家の育成に失敗した。

農家の人口が急速に減少したのは、出稼ぎあるいは兼業が増加したからである。しかし、農家戸数の減少割合は小さい。これは農業をやめたり、兼業になっても、農地を簡単には売らない、ということである。中核農家への農地を集中し、大規模専業農家を育成する農業基本法は、根本から誤っていたことになる。
③ 農業基盤整備、資本装備、農業生産の調整
これらの具体的政策を農業の構造改善と呼ぶことがある。
農業基盤整備とは、大型農業機械を農地に入れるため、農道を建設することである。あるいは農業用水を得るために農業用ダムと水路を建設することである。水田1区画を0.3haずつの大きさにあぜ道を造り変えることでもある。費用の大半が政府補助金行われた。各農家の負担金を少なくすることが、農村を基盤とする政治家の腕の見せ所であった。農村では農業基盤整備の名目で、冬の農閑期に大規模土木事業が行われ、出稼ぎに行かなくても現金収入を得ることができた。それで基盤整備の分担金を払ったり、農業機械を買ったりした。
資本装備とは、農家が自己資金であっても借金であっても、調達可能なカネのことである。農協が、農地を担保にいくらでもカネを貸した。農協には、政府資金が全農を通して、いくらでもカネが流れた。農家は農協から多額の借金をして、農機具を買って農業をすることもできたし、多少は贅沢な暮らしもできた。返済は、米を供出した時に清算したし、農閑期には農業基盤整備事業のアルバイトがあった。それに、米価が毎年上がるので、借金生活が苦にならなかった。
農業生産の調整とは、農協と役場が中心になり、米作農家に米から他の作物に転換させることであった。必要なカネはいくらでも貸すことを切り札に、農家に、米作からの転換を勧めた。野菜・果樹・畜産などのどれに転換させるかは、農家との話し合いで決まった。しかし、農家が戸別に転換しても、大産地を形成できず、販売先を確保できなかった。農業生産の調整も、群馬県の嬬恋村を除き、失敗に終わった。

群馬県嬬恋村(つまこいむら)は、標高700~1,400mに広がる高原である。夏キャベツ・秋キャベツを中心とした高原野菜が作付けされている。このうち863haが国営パイロット事業により造成された農地である。農道の整備、収集倉庫の設置とともに、計画的な栽培体系が確立された。平成元年度から始まった国営パイロット事業では、404haの農地造成が平成9年度に完了した。これは連作障害を避けるため、規模拡大と併せて輪作体系を確立し、農作物の安定供給と経営の安定化を図るため実施された。嬬恋村は野菜産地として成功した。巨額の国費がつぎ込まれたモデル事業として、大量の野菜供給が可能になって、東京・横浜と安定供給契約を結んだこと、食品大手企業との契約栽培ができたことが、野菜産地として成功した理由である。
Ⅱ.農産物の価格・流通(農業基本法11条~14条)
① 価格の安定
米価の国家統制の食糧管理法を野菜・果樹・畜産に拡大することには、都市住民からの反対が強かった。しかし、生産過剰になれば、米のような長期保存は不可能な作物ばかりで、農家は損を覚悟の安売りかなかった。その代わり、気候の異変で特定産地で品不足になると、作物は値上がりをし、他産地は儲けることができた。すべての産地が等しく儲けることは、消費の急拡大が進まない限りは不可能であった。
政府と農民が半額ずつ出し合う農業共済制度があり、台風・冷夏・晩霜・干ばつのような被害を
受けた農家には6割~8割の損失を補填された。
災害に対しては、共催の補償制度があったが、農産物の生産過剰による値下がりには補償がなかった。いわゆる豊作貧乏である。野菜・果樹・畜産農家の脱落は、災害よりは、清算過剰による市場価格の値下がりが原因であった。農家の創意・工夫・努力は産地間競争を激しくし、野菜・果樹・畜産農家を淘汰する結果となった。
各種農業賞を受賞するような優れた産地が、他産地に真似られて没落というケースが」も多く、野菜・果樹・畜産などの有名産地が生き残って、都市サラリーマン並みの収入を得ることは、米作よりはるかに困難であった。
② 農産物の流通
農業基本法12条は、農協に優越的な地位を与えている。米からの転作を目的とする農業基本法の具体化には、農協の協力が不可欠であった。むしろ、農協単位に新しい農業を創造しなくてはならなかった。農協は新しい農業の主体であった。
国は、需要の高度化及び農業経営の近代化を考慮して農産物の流通の合理化及び加工の増進並びに農業資材の生産及び流通の合理化を図るため、農業協同組合又は農業協同組合連合会が行なう販売、購買等の事業の発達改善、農産物取引の近代化、農業関連事業の振興、農業協同組合が出資者等となつている農産物の加工又は農業資材の生産の事業の発達改善等必要な施策を講ずるものとする。
農協には、農業基本法が期待するような実力はなかった。政府からの補助金を農家に配分する単純な仕事はできたが、農協と農民が、農協を単位として、ともに新しい農業像を考える能力はなかった。
果樹はりんご、みかん、もも、ぶどう、さくらんぼなど、いずれも市場がすぐにあふれて生産過剰が近くて、産地間競争が起こって脱落の相次ぐことは明白であった。
野菜も果樹も同様の恐れがあった。
小麦のように輸出品が安価良質の場合、日本の農業は太刀打ちできなかった。そのため、国(政府)は日本の農業に大きな影響のある農産物の輸入を規制した。
1960年代の高度経済成長期、日本の安価良質な工業製品が世界に輸出され、経済発展を続けた。日本の農産物市場が余りに閉鎖的であるとして、海外からは米・果実・畜産品の市場開放を求められた。特に国内市場の大きい、バナナ・オレンジ・牛肉の輸入が、日本とアメリカの貿易問題に発展した。
Ⅲ.農業構造の改善(農業基本法21条)
① 農業生産の基盤整備
農業基本法は、米作面積を減らすことが最大目標であった。しかし、農業基本法には米作を除外するとは書いていないので、米作の基盤整備に重点が置かれた。水田の区画、あぜ道、水路、農道などがつくられた。特に農道は農業機械の通行に便利なように、飛行場の滑走路のような農道が建設された。実際に空港としても利用可能な農道もあった。

大分農道空港。一部の農道は農産物を大都市に高速輸送する目的で、小型航空機専用滑走路の規格でつくられた。片道しか貨物がないために輸送コストが高く、実際にはどの空港もほとんど使用されなかった。全国8カ所の農道空港は1988年に運用開始、1897年に空港としての利用が停止された。
② 環境整備
具体的には何を示すのか明確でないので、環境整備を名目に、農家には多額の補助金が貸し出され、のちに農家の経営の重荷になった。
例えば養鶏。5羽10羽の庭先養鶏ではなく、1000羽以上の大型経営の場合、農家は補助金による養鶏が可能であった。養鶏場は朝早くからうるさいので、養鶏場を集落から離して建設する資金に充てられた。
養豚場から流れ出る汚水が不潔のため、100頭以上の飼育をする場合、養豚農家は水処理施設をつくる補助金を得ることができた。
③ 経営近代化
趣味的経営ではなく、経済的自立の可能な農業経営をめざすことである。1ha程度の米作では、経営が成り立たないから、米作も農業もやめさせて、中核農家に農地を集中させることが、政府のねらいであった。
米、りんご、みかん、ぶどう、キャベツ、たまねぎなど、何を栽培してもよいのだが、産地間の価格競争を勝ち抜くような経営を実現しようとした。しかし、食糧管理法で価格の保護された米作が最も安定していて、経営近代化は、米作と出稼ぎによって進められた。
--------------------------------------------------------------------------------
食糧管理法は1942年につくられた戦時法制であり、戦後は米の価格引きあげの法的根拠となった。小規模米作農家の経営がなりたったのは、食糧管理法によって政治米価が続いたからである。1994年に廃止されて、米は原則的には自由な流通ができることになった。
農業基本法(旧農業基本法)は1961年に米の生産過剰対策と、農民所得の向上を目的に施行された。米からの転作、農業近代化にはある程度の役割を果たしたが、輸入食料の増加のために急速に時代遅れとなり、1999年に廃止された。代わりに、食料・農業・農村基本法(新農業基本法)が施行された。