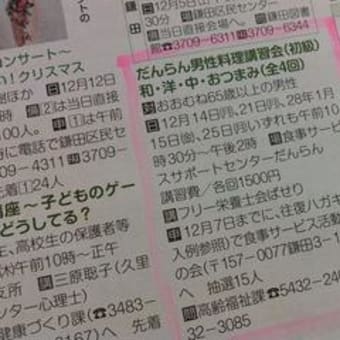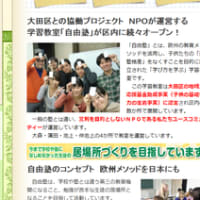人が自力でなんとかしなくちゃ、と思って仲間と一緒に何かの活動をしようとする時に、もともとの長年の知り合い同士から始まるケースって、意外と少ないし、必ずしもうまくいくわけではありません。
活動を立ち上げ、継続・発展させていく仲間ってどうやって見つかっていくんでしょう。
・・・ということに今、取り組むことになり、さまざまなケースを見ています。
全員当事者である場合もあります。
高次機能障がい者の支援団体などはほとんどが家族です。
本当に切実で、つらいものです。でも、そんなことばかり言っていられないということで立ち上がる団体。
社会から少し外れてしまった若者の支援を、とにかく一人二人で始めて、活動を続ける中で、善意の人や協力者が集まってくる場合も。
スタート時期の大変なところを少人数でここまでにするのは、並大抵ではないです。
それに相手が人ですし、若者ですから、思いがすれ違ったり、許容量を超えちゃうような人が来たり。でも排除すべきではないという中で、いろんな悩みが発生します。
・・って、評論家のように簡単に言うのもはばかられるほど。
とにかく、ぎりぎりの思いの中で、必死で活動を続けている人が大勢います。
可能なら、同じ思いで何かをしたいという人同士が数人集まって仲間になり、何か具体的なものを作っていけると、もっと気楽に活動が作れるし、いろんな集まりが社会の中にたくさんあることで救われる人が増えるだろうと思っています。
でも、仲間作り。どんなきっかけなら一番いいのでしょう。
キーワードは、やはり、「共感」、「学び」、そしてそこから生まれる「つながり」「連帯感」に希望を見いだせるのではないかと思っています。
その集まりに合った、そしてテーマに沿った「学び」を、共感をもって協働でつくり上げていくプロセスがけっこう有効なのではと。
仲間になるかもしれない相手を、より深く知るきっかけであり、思いを共有する時間であり、次に進むための知識になります。
一度、何人かで力を合わせて何かを始める、貢献する、助かる人がいる、何かが変わる、という体験をしてみるといいと思っています。
そこから自信が生まれ、生活が楽しくなります。つまり、何らかの活動が決して人のためではなく、自分のためにあることがわかってくると、さらにいい循環になっていきます。
お金を稼ぐことはもちろん重要です。でもそれ以外に、できれば身近な地域にいる人たちとつながり、異なる意見を聞いたり、議論することで、社会や人と関係性を持ちやすくしておくことは自分と家族にとっての投資あるいは貯金のようなものです。
社会とつながることに損得を考えずに、一歩踏み出してみると、思いもよらなかった楽しいことや発見が必ずあります。
一方で、大変なこと、失敗と思えることも必ずありますが、それは進歩していることの証であり、恐れず仲間と解決の道を探ればいいのです。
○大人のための学びの共同体づくりに、私がよく活用する本は、
『「学び」で組織は成長する』(吉田新一郎著、光文社新書、2006年1月)
さまざまな学びのスタイルが網羅されているので、必ず、今回はコレが合ってるかなというヒントを中から拾い出すことができます。
最新の画像もっと見る
最近の「NPO」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事