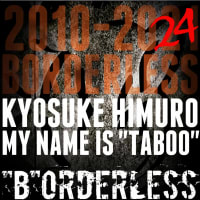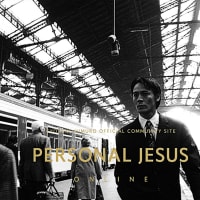先日も少し触れたように、
氷室はBOφWY時代のアルバム『JUST A HERO』の歌詞に関して、
その時の精神状態が大きく左右しており、
あの頃の詞は今の俺には書けないと言っていた。(1991年 月刊カドカワ4月号参照)
アルバム『JUST A HERO』の歌詞は、文句なしに秀でている。
その意味を解読することさえも、
このアルバムの前では愚劣な行為と言おうか、ナンセンスというか、、
例えば、「聴く音楽」と「感じる音楽」があるとすれば、
まさに、それらの歌詞は、
「理解する歌詞」ではなく「感じる歌詞」という、
そんな高等な場所に存在すると言ったところであっただろう。
その昔、全盛期と言われていた頃の小室哲哉氏のインタビューで、
メロディー&ワードメーカーと言われた自身のアイデアは、
どうやって考えられるのかという問い対し、
「勝手にわいてくる」みたいな話をしているのをテレビで観た記憶がある。
そんな小室氏の、「勝手にわいてくる」という例えと、
氷室のいう、「その時の精神状態」という心理は、
どことなく一致する部分があるのではないかと俺は思う。
たとえば、『ミス・ミステリー・レディ』で、
「セピアの影」と一言呟いただけで、
その後の言葉が、まるで何かに取りつかれたように閃くかのような、
そんな、"研ぎ澄まされた感覚"を憶えていたのではないかという察し。
何かを真似てみようと思い、構えて考えるアイデアは、
例えそれの全てを真似ようとはしなくても、
そのアプローチを意識した時点で見透かされてしまうだろう。
そう、重要なのは、何かに近づけてみせるというアプローチではなく、
一番大外の部分に存在する輪郭、、、すなわち、コンセプトなのである。
アプローチを意識しすぎてしまうそれというモノは、
どことなくギクシャクした感があり、全体の流れ、シルエットが滑らかではない。
理路整然とした一致が見えぬ、
何か継ぎはぎをしたかのような感じといったところだろうか。
あえて強調するけれど、ここで言う理路整然とは、
その時の、特異な精神性の話に繋がるもののことであり、
すなわち、その時の精神状態が、迷い無き一貫したものであるなら、
自ずと、それは理路整然とした形を「結果的に成す」のだと言う話をしているのだ。
いかにコンセプトに、己のセンスという名の精神性を乗せることが出来るか、
重要なのはそこなのである。
自らの世界感、、精神性ありきで閃いた物は、
実に滑らかで、
崇高で、
誰にも似ていなく、
ただその前では平伏すしかない。
あの頃の氷室京介自身が、
その時の自分、精神性、、
或いはメロディー(ミス・ミステリー・レディ)に感化されていなければ、
あそこまでの歌詞は書けなかったかもしれないだろう。
今の氷室京介が感化されている物はなんであるのか。
そこに迷いが無く、そして、なんの貪りも無く、
誇らかにありのままに思いを表現できたのなら、
これからの氷室が綴るワードは、
きっと俺たちの心さえも感化するのではないだろうか。
そう、
突き詰めればすなわち、
貪りという煩悩さえもリアルに白状できたことが "貪りも無し" だとすれば、
まさに、
「めちゃくちゃアグリーな、めちゃくちゃ酷いアルバム」
という『PUNKS』を、貫き通すことが出来るのだから。
まずは、6月、
『ENEMY'S INSIDE』。
その最強のセンスの全貌を待とうではないか。

 amazon.co.jp
amazon.co.jp