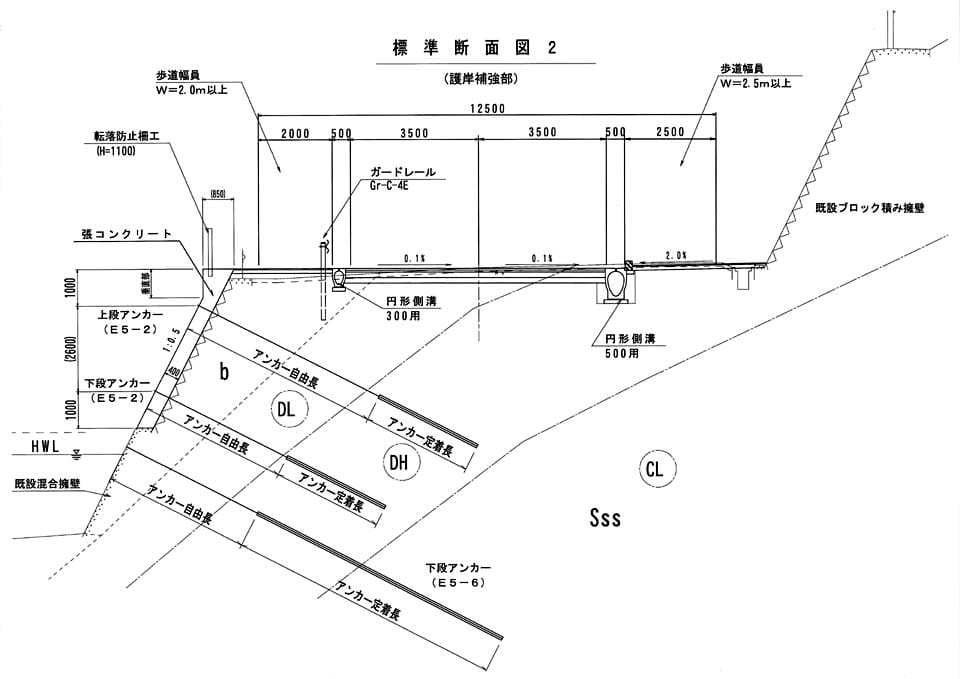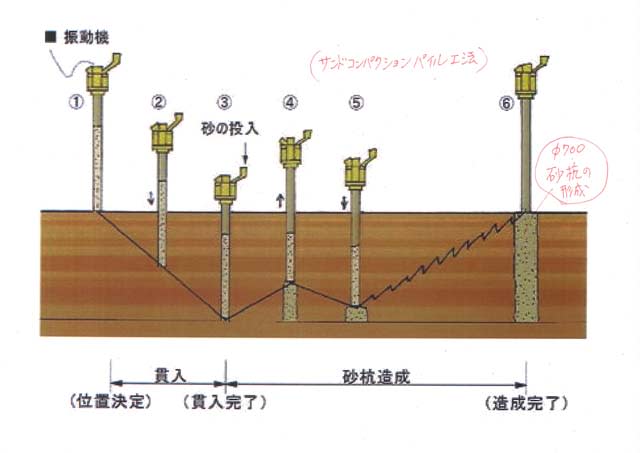現在、昨年度(H24年度)に僕が設計しました、
県道の路肩崩落による道路災害復旧工事が施工されています。
先日は、その現場確認(立会)に行ってきました。
設計概要
(当該路線の概要)
・ 一級河川沿線で高低差14mの急峻な山つき一般県道
・ 市街地と集落を結ぶバス路線および緊急輸送路である
(崩壊の状況と要因)
昨年7月のゲリラ豪雨により発生した、風水害を要因とする
道路谷側斜面崩落により、路肩が法尻(河床)まで一気に崩落した。

(河川下流 → 上流方向)

(河川上流 → 下流方向)

(残幅員は3m程度・・・崩落肩は脆弱化して二次災害の恐れあり)
(設計条件)
① 片側交互による現道交通の確保
② 交通解放による二次災害の防止
③ 河川断面(河積)の確保および非出水期限内(5月中)での施工
そのほか、
・ 緊急輸送路であるため地震時は「Ⅰ種地盤-大規模」とする水平震度kh=0.16
・ 輪荷重P=10KN/m2
・ 漁協との取り決めで渓流釣り・観光など河川景観・環境への配慮も行う
※当然ですよね・・・「Ⅰ種地盤」はボーリング調査より判断
(復旧方針)
・ 一次復旧として、崩落した現況斜面の補強を実施し
早期に「大型車両通行」の安全を確保し交通解放
・ 本復旧として、「一次復旧」を活かした本復旧とすること(取壊し工なしとする)
※当然ですね・・・
(対策工法)
・ 一次復旧工:掘削を伴わない永久構造の「補強土壁工」(安全率Fs=1.2以上)

(土砂混在個所の脆弱斜面ではロックボルトを90mm削孔としています)
・ 本復旧工:(一次復旧工で土圧を抑制したため)風化防止の「張コンクリート擁壁工」

(本復旧は河川管理者(県)との協議を重ねて許可・決定しています)
尚、壁高が16mを超えるため、地震時慣性力のみ考慮する。
さて、
本復旧工にあたっての工法比較検討については、以下の工法が考えられました。
その比較工法案と検討結果を、以下に簡単に列記する。
[設計条件=背面土圧は考慮しない、水平震度kh=0.16(慣性力のみ)、輪荷重P=10KN/m2]
第1案:軽量盛土工(EPS)・・・
水に弱いため河川HWLまで基礎擁壁が必要で工事費が高価。
また、直壁であるため河川断面および流水阻害、現況取り合いが不自然となるため「NG」
第2案:大型ブロック積み ・・・
壁高H<10mは「机上お絵かき」と「数字のお遊び適当空想論な構造計算」と
「バカじゃね?」的な莫大な金かければできましたが、施工実績なしのため瞬殺「NG」
第3案:張コンクリート擁壁・・・
やっぱり現場打ちコンクリートは施工の自由度が高くて安いよね!「採用、矢沢OKです」
第4案:モタレ式擁壁・・・
H<8m以上は壁天端の高盛土(EPSなど)で対応しなければならず、
鼻で笑われて当然「NG」
第5案:補強土壁(ジオテキスタイル)・・・
壁高16mとなると「控え」が豪快・・・河川張出しと、
天端部で駐車場付コンビニ経営することが許されれば・・・
冗談はさておき、1.5車線的整備「待避所」で提案も、鼻で笑われて「NG」
------------------------------------------------------------------
ところで、
設計時に提案していた「施工時留意点」は以下の事項です。
[張コン擁壁の基礎地盤の確認]
今回の設計では、基礎地盤条件として
擁壁の一般的な支持力であるq=300KN/m2(地震時はその1.5倍)としています。
当計画の擁壁では、
根入れを含めて壁高H>16mであるため、自重だけでも相当な重さになります。
さらに地震時では、「自重+慣性力」で支持地盤への荷重は局所的に345KN/m2にもなります。
また、擁壁設置個所が河川の水衝部ということを考えれば、
最低でもN値<30の「軟岩層以上の均一的な分布」であってほしいと考えていました。
そんな「施工時留意点」から、当日の現場確認と相成りました。
では、
ここからは、現場状況をみなさんと一緒に観ていきます(笑)
崩壊当時はこんな感じでした・・・

(河川側より撮影・・・斜面の立木もろとも一気に崩落してました)
↓
しかし、今現在は・・・

(切土補強土工法で崩壊斜面を補強・・・一次復旧終了しています。)


(写真左・・・一次復旧が終了し、基礎工の床掘りが終了しました)
(写真右・・・釣り人の皆様には大変申し訳ありません、瀬替えさせていただきます)


(上流→下流方向) (床掘りの結果、予定通りの黒い頁岩層が露出し一安心です)
斜面上部(道路)の現在の様子です。

(一次復旧まで終了)

(一次復旧まで終了)
いやー、現場って、ホントにおもしろいですね。
施工屋(工事屋)さんと、
「こうなっちゃうけど、どーする?」や「ここでこうしたいんだけど、できる?」など、
あーだこーだ、相談しながら現場を造っていくって、
ホント、おもしろいです!
今後、また現場におもしろい事象がでたらアップします!
そして、
完成したら、また「劇的ビフォー・アフター」シリーズでご報告します!(笑)
ps・・・・
いま流行ってきている’設計・施工一括発注方式(デザインビルド方式)’、
僕はこれ、大賛成です!
またまた登場!RCサクセション
「昼間のパパは男だぜー♪」
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cYk9Z6u7bd8