
雑誌を飾る建築写真には透明人間ばかりだ。右の写真にもいますよ。
このごろの建築、実に壁が薄い。
○妹島和世の「梅林の家」
壁は外壁も間仕切り壁もすべて16ミリの鉄板。たった16ミリの構造壁。柱はもういらないようだ。子どもが段ボールで家をつくるみたいに鉄板を組み立てる。ちなみに壁仕様は鉄板16ミリにウレタン吹付けが15ミリの上、石膏ボード張りで、壁厚は全部で50ミリ。これでいいらしい。
○ヨコミゾマコトの「富広美術館」
鉄板9ミリがやはり構造壁だ。こちらはリブが付いて少し壁厚は厚く、ウレタンも30ミリとってあるがそれでも全部で86ミリ。
○藤本壮介の「T-house」
木造の構造用合板12ミリが壁厚だ。柱と呼べるものは45ミリ角の間柱しか見当たらない。
○安藤忠雄の「hhstyle.com」
裏原宿では、安藤先生までもが鉄板16ミリの構造壁仕様になり、折り紙のような建築と仰る。
どうやら、明らかに柱は避けられ、嫌われている。
このごろの建築、実に壁が薄い。
○妹島和世の「梅林の家」
壁は外壁も間仕切り壁もすべて16ミリの鉄板。たった16ミリの構造壁。柱はもういらないようだ。子どもが段ボールで家をつくるみたいに鉄板を組み立てる。ちなみに壁仕様は鉄板16ミリにウレタン吹付けが15ミリの上、石膏ボード張りで、壁厚は全部で50ミリ。これでいいらしい。
○ヨコミゾマコトの「富広美術館」
鉄板9ミリがやはり構造壁だ。こちらはリブが付いて少し壁厚は厚く、ウレタンも30ミリとってあるがそれでも全部で86ミリ。
○藤本壮介の「T-house」
木造の構造用合板12ミリが壁厚だ。柱と呼べるものは45ミリ角の間柱しか見当たらない。
○安藤忠雄の「hhstyle.com」
裏原宿では、安藤先生までもが鉄板16ミリの構造壁仕様になり、折り紙のような建築と仰る。
どうやら、明らかに柱は避けられ、嫌われている。















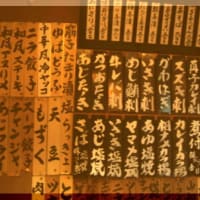




何か落ち着かない感じを受けてしまう私です。
日本の敷地の狭さも影響して、壁を薄く・・・
なんていうわけでもないのでしょうが。
部分的に使うのは面白いと思いますが、
私はやっぱり木造軸組の建物がとっても
好きな人間なのです。
人それぞれということかしら・・・
先日、藤本壮介さんの講演会に行きまして、単純な私は彼の空間概念に直ぐに洗脳されました。それは、建築は絶対的なものではなく、それに溶け込む人間の存在によって初めて成り立つような、弱さと曖昧さを持ち合わせた空間(というよりむしろ場)ということらしいです。(多分。)
T houseの場合、木造型枠の片面だけに薄い石膏ボードをはった壁(!?)で空間を仕切ることで、真っ白な表空間と間柱むき出しの裏空間が出来、それらの隣接する空間が相互に依存し合うことでお互いは成立し、またそれらが中央付近で溶け合うことで生まれる曖昧さのようなものを意図して設計されたようです。
つまり、薄い壁は彼の概念を空間化するための1つの手段に過ぎないのですが、私もそんな空間概念を表現するような、他の建築言語を模索できたらいいなと思いつつ、初の本格的な設計製図Ⅰに突入しました。
ここ3、4年の間に、本屋には狭小住宅を発端に随分と建築を紹介する雑誌が増えていますね。一般の人にも建築家やデザインが身近になったことは喜ばしい事ではあります。しかし実はその逆勾配で、イメージ化された建築文化は貧しく画一化され、喜んでばかりいられない場面に立ち会う事も多いです。
僕も藤本壮介氏の話は聞いた事があります。鮎の言ってくれた言葉は全て彼の言葉ですね。建築家Aは建物に説明を添えます。そしてそれを見る人は、そのAの言葉を通してしか建物を見れなくなってしまいがちです。ああ、Aのいう事はこういうことか、と。建物の前に、スッと立てるように訓練したいものです。
例えば、僕が通った大学の製図室は6人ワンブースとしてパーテションが大空間を仕切っていた。パーテションの厚さは12ミリ程度。それらのブースの中央で先生に課題を見せたりした。
例えば、病院の4人部屋、6人部屋は、個人をカーテンで仕切る。カーテン一枚となると隣人は、イビキがうるさいくらいではすまなく、息づかいから体調まで分かってしまう。
じゃあ、この仕切りと彼の壁は、何が違うのか?または同じなのか?「中央付近で溶け合うことで生まれる曖昧さのようなもの」という言葉にだけ反応しないようにしたいです。
ある作品に目がとまりました。
その時の私の心にスッポリはまったのです。その画家さんは、あなたが感じとったイメージでいいと言ってくれました。
見る人が自由に感じていいのだと。
画家としてのイメージがあって描かれたはずなのにね。
建築、特に住宅は、
そこに暮らす人にとって一番よい空間であることが大事だと私は思ってます。
すべてはそこから始まり、設計するがわの何かがプラスされていくものではないかしら。
まぁ、それが難しかったりするのだけど。
f^_^;
藤本壮介氏もネットで拝見しました。
皆様のコメント読んで
いろいろ勉強させてもらえること
嬉しく思います。
期待してます。
頑張ってくださいね。