昨年の2月頃から当ブログでも何度も意見を書いてきました。
食味が異なるというのは「主観」の問題でもあるので、これからはそれを決めつけることはしないようにします。
小生は生産や流通にかかわる者として、どうしても譲れないというか、納得できないことがあります。
それは、
表 示
のことです。
DNA鑑定で異なる米なのだから表示は変えるのが当然ではないでしょうか?
表示問題、他の米が混ざらないようにするコンタミ問題、そしてDNA鑑定による検査。
(弊社の工場でも、コンタミ対策の工事を昨年6月に実施しました。米が混ざらないようにするための工事に多額の投資をしました)
それらが行われている中で、玄米袋にはBL表示がありますが、精米し小分けしたパッケージには「BL」の文字はどこにもない。
コシヒカリとコシヒカリ新潟BL1号から○号を「品種群」として「ひとつに括る」ことにしたのです。
ここに問題がある。
これは、買う人に正確な情報を伝えないことを意味します。
他の論争はこの段階ではもう言いません。
新潟の米作り生産者には責任ありません。
生産者の声を聞いたと言っても、組織・団体、行政が方向性を決めてあることを異なる方向に持って行くのは基本的に無理でしょう。
販売側に対しては、卸代表に説明があった程度で、小売店や量販店に説明はしていないでしょう。(していたとしてもほんの一部)
買ってくれるお客様がいて成り立っているのに、それを軽視していると思うのです。
JAS法、DNA鑑定、表示問題、消費者に正確な情報を知らせる時代なのに・・・。
再度、言いますが表示さえ「コシヒカリ新潟BL」「新潟コシヒカリ」と変えていたならなにも問題にしません。

食味が異なるというのは「主観」の問題でもあるので、これからはそれを決めつけることはしないようにします。
小生は生産や流通にかかわる者として、どうしても譲れないというか、納得できないことがあります。
それは、
表 示
のことです。
DNA鑑定で異なる米なのだから表示は変えるのが当然ではないでしょうか?
表示問題、他の米が混ざらないようにするコンタミ問題、そしてDNA鑑定による検査。
(弊社の工場でも、コンタミ対策の工事を昨年6月に実施しました。米が混ざらないようにするための工事に多額の投資をしました)
それらが行われている中で、玄米袋にはBL表示がありますが、精米し小分けしたパッケージには「BL」の文字はどこにもない。
コシヒカリとコシヒカリ新潟BL1号から○号を「品種群」として「ひとつに括る」ことにしたのです。
ここに問題がある。
これは、買う人に正確な情報を伝えないことを意味します。
他の論争はこの段階ではもう言いません。
新潟の米作り生産者には責任ありません。
生産者の声を聞いたと言っても、組織・団体、行政が方向性を決めてあることを異なる方向に持って行くのは基本的に無理でしょう。
販売側に対しては、卸代表に説明があった程度で、小売店や量販店に説明はしていないでしょう。(していたとしてもほんの一部)
買ってくれるお客様がいて成り立っているのに、それを軽視していると思うのです。
JAS法、DNA鑑定、表示問題、消費者に正確な情報を知らせる時代なのに・・・。
再度、言いますが表示さえ「コシヒカリ新潟BL」「新潟コシヒカリ」と変えていたならなにも問題にしません。













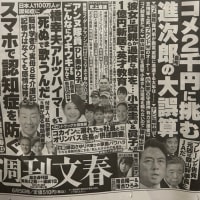







新潟県の農家に責任は無いと言うのは、実際にBLに高い評価を与え、推進してきた農家も多数いらっしゃるのであたらないと思います。
新潟県、全農新潟が決めていることを覆すのは、現実的に一人の生産者では無理だろうということです。
大きな力が動いているので・・・・
以前にこのブログで、生産者も販売業者も同罪だと書いた記憶がありますが、そうは言ってもと思ったのでありました。
そのあたりを汲んでくださいまし。
消費者に正確な情報が伝わってない訳ですから。
しかし消費者がBLについて誤った認識で、
新潟コシBLを知ってしまうと大変ですよね。
ただでさえ今のご時勢BSEの問題にしろ遺伝子組み換え、DNA、農薬、といったキーワードには非常にシビアというか敏感ですから。
実際、業界紙などはかなり取り上げているけど、一般消費者は見ないだろうし、一部ニュースで取り上げられたのを見たけど深く突っこんではいないし。
新潟だってある意欲のある農家の方が新潟○報にBL批判の投稿をしたりしましたが...
肝心要の地元紙ですら問題定義しようとすらしない。
※まぁ正確にはできないんだろうけど。
スポンサー、J○だろうから。。。
生産者サイドでも我々の地域ではBL離れ(昨年BL作った方も従来コシに戻す)をする農家が増えました。
集荷割合だと5:5位になっちゃうのです。
コシBL心配です。。。
ネット上を見ても、思い込みと伝聞、推測を基にした情報が乱れ飛んでいますから。
客観的な事実に基づく書き込みはほとんど無いと思います。
この事態は県や全農のPR不足が招いたことには違いないけど・・・。
食味試験にしても、1:1の食味試験をする場合には、同一生産者が隣接圃場で同じ栽培基準で栽培されたものを検体にしなければ無意味です。
一部地域(南魚沼では幅1キロ・長さ20キロの帯状の範囲)での品質低下を品種(BL)のせいにする根拠も全くありません。
しかし、ネット上では上記の無意味な事柄が事実であるかのような書き込みが非常に多く見られることは残念でなりません。