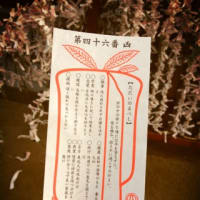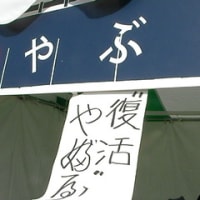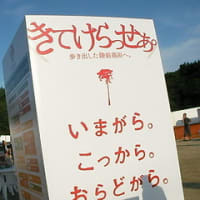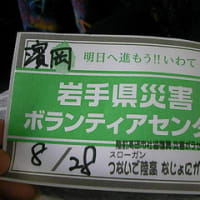昨日は、IPCCレポートを根掘り葉掘り読む会に参加してきました。
新しい参加者の方が5名おられ、うちお二人は、来年度から大学生ということで、いつもになく「♪フレッシュ!フレッシュ!フレ~ッシュ!♪」な雰囲気で良かったです
前半(午前中)は、先月16日に東京で開催された「サステイナビリティ学連携研究機構(IR3S)公開討論会~徹底討論・温暖化問題-ポスト京都議定書を見据えた日本の戦略-」の報告でした。
ここでも少しご案内しましたが、神戸大学サイエンスショップからH口さんが傍聴に行かれたので、その報告がありました。
登壇者のプレゼンテーションの内容や、パネル討論の様子などを、資料も交えながらざっくりと報告していただきました。
...うーん...もちろん、簡単な報告だけですべてを判断できませんが、パネル討論の様子については、正直ちょっと頭を抱えてしまいました。何だか10年前の議論を聞いているみたいで...。
つまり、「10年前にやっといてくださいよ」っていう議論。
今頃、「世界をリードする」とか「アジアのリーダーになる」とか言っても、誰も本気にしませんよねぇ。
会場はほぼ満席で、2階席まで埋まる勢いだったそうです。多くの聴衆を前にして感覚が狂っちゃったんでしょうか?閉めのコトバでは「一人一人が意識して頑張る」みたいな話も出ちゃったそうで...。まぁ、もちろんそうなんでしょうけど...
賢そうに言うと、「需要側でのエネルギー効率改善」ってことなんですが、これって家庭においては、電化製品の買い替え促進、車の買い替え促進、クーラーのフィルターの掃除促進みたいな話?これってどうやって定量化するのかな?総計でしかわからないですよね(あるいは自己申告?)。
個々のエネルギー使用を制限するには、何といっても「値上げ」がいちばん効率がいいと思いますよ。それが出来るのかどうかが課題ですが。
関連して、一次エネルギー供給の構成についてもモノ申すのですが、集中型エネルギー利用はもってのほか。冗談じゃありませんよ。分散型にすべきです。
分散型にしていただければ、ワタクシは高いほうの電力(まぁ例えば太陽光とか風力ってことですけど)を選択的に使って、省エネ生活を邁進いたしますわ!
あっはい。経済界へのリップサービスなのか、「省エネ立国になるべし」という意見があったそうです。国内ではすでに十分「省エネ立国」じゃんというツッコミもありますけど...?
つまり海外への技術移転の話であれば、特にインドや中国に対してはビジネスライクにいきましょうってことでしょうか。
いやいや資料を読むと、「日本のODA(円借款)に豊富な支援実績があり、日本が強みを有する」みたいな話があります。
マラケシュ合意(2002年1月)では禁止されていた「CDM事業(クリーン開発メカニズム事業)へのODA活用」が、2004年4月のDAC合意によって認められるようになったみたいですね。
うーむ。意義はわかりますよ、意義は。
んでも、事例がいくつかあがっていたんですが、何で「インド:デリー高速輸送システム建設事業」が、ODA活用されちゃうんですかね?
好き勝手してるな。
あと、住さんが言われたそうですが、温暖化に関わる世界の動きを、世界大戦後の軍縮の動き(たとえばこういうのですかね?)になぞらえるのは強引すぎるのだろうと思います。ちょっと、その真意が図りかねます。
まぁ気持ちはわからないでもないですが。
勉強会のあと、少し時間があったので、開催されていた「第一回神戸大学ESDシンポジウム」に参加してきました。「ESD概念の奥行きを探る」というタイトル。
奥行きというか、広がりというか、何でもありというか。
いや、そうではなく(拡散ではなく)、相互依存であると気づくことなのだという佐藤さんの意見が心に残りました。因果ではなく関係性なのだとか。それはシステム思考でもあるのだとか。
ふーん。ちょっと考えよう。
ただ、しかし、ようするにESDは「教育」ですから、アクションとしては、様々な個人レベルをどう巻き込むかの話。ワタシとしては、ぜひとも政府レベルを「教育」してほしいんですけどね