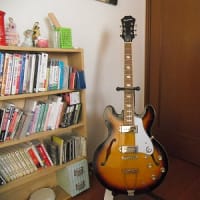第52回京都旅歩きラストミッション
「不思議な神社」~古きや今や拾遺物語より~ 作 大山哲生
一
昭和四年のこと。
三校の学生であった島本佐助は歴史の研究をしていた。
今日も洋服に下駄といういでたちで、学校に来てはできたばかりのベンチに腰掛けてなにやら物思いにふけっていたのだった。
そこに、梶田清治郎が通りかかった。梶田は島本と同じ研究室で歴史の研究している学生なのであった。梶田は最近流行っている洋服を着ている。
「おい島本、どうした。柄にもなく物思いにふけったりして」
「ああ、梶田か。物思いになんかふけっているものか。ちょっと疲れただけさ」
「この間から図書室で調べ物をしているんだが、京都には珍しい名前の神社があるぜ」
「ほう、それは興味がある」
「京都の西のほうにある月読神社という」
「なるほど、珍しい名前の神社だな」
「どうだ、お互いにその神社について調べて、来週の月曜日にここに持ち寄ることにしないか」
「そりゃいい。最近少し頭がなまっていたところだ」
それから、梶田も島本も図書館にこもって月読神社について熱心に調べたのであった。
二
次の月曜日。
「島本、どうだ。こっちはたくさん調べたぞ」
「貴様なんぞに負ける俺ではないが、先週はちっとばっかし酒を飲み過ぎてしまってあまりはかどらなかった」
「まず、月読神社は何を祭っているかだが」
「日本書紀には月読神社の成り立ちが書いてある。元々の月読神社の創建伝承では「月神」というものが壱岐の有力者によって壱岐で祭られたという記述がある」
「月神とはなにの神様だい」
「それもちゃんと調べてある。確か、潮の干満を司る神様らしい」
「おい、この文明の時代だから潮の干満と月とが関係あるとわかるが、今から1500年前になぜ潮の干満と月が関係あるとわかったんだろう」
「つまり、京都や奈良が権力の中心になる以前から、壱岐には相当高い文明があったとみえる」
「そういうことだ。壱岐、恐るべしだな」
三
「今の話を整理するとだな、月読神社はまず壱岐で作られた」
「それがどうして京都にあるんだ」
「日本書紀によると、昔えらい人が壱岐に寄ったときに月神がその人にとり憑いて、『山背の地を我が月神に奉れ』と言った。その言葉通り京都の西の方に社を建てた。これが京都の月読神社の由来らしい」
「そうすると壱岐の月読神社が先で、京都の月読神社は後ということになるな」
「そういうことだ。壱岐の月読神社は、京都の月読神社の元宮と言われている」
「さっきの壱岐の神様が京都に分家してきた話だが」
「昔、えらい人に月神が取り憑いた話か。実はその後も月神は桂の木に取り憑いたという記録がある」
「なるほど、月神とは憑神ということであったのか」
「それはおもしろいところに気がついた。月の語源を調べて見ると『次ぎ』『尽き』というのがでてくるが『憑き』というのも考えられるな」
「そうだな、なかなかよい発想だ。すこししゃべり疲れたな。どうだ、河原町のカフェでもいかないか」
「いいねえ」