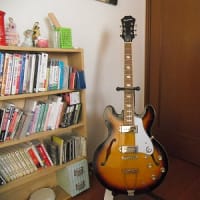創作話 「さよなら悦ちゃん」 作 大山哲生
私が大学三年の時の話である。
一
私は史跡同好会に入っていた。三年の時は、十数名の大山グループのグループ長をしていた。私のグループの一年生に桜内悦子がいた。
桜内悦子は、小柄で目が大きく印象に残る子だった。
私は、悦子のことが気になった。
六月ころになると、私は悦子をかわいいと意識するようになった。悦子はグループ活動の時は私のそばにいるようになり、史跡のことをいろいろと質問してきた。
私は悦子のことが好きになっていた。私はグループ長として、他のグループ員にも公平に声をかけたつもりだったが、いつしか私と悦子の間柄は同好会内の知るところとなった。
私はこれが恋人のいる生活かと舞い上がった。だから、噂を意に介さなかったしもちろん否定もしなかった。
私は、悦子も私を好きなのだろう思った。
二
八月の合宿は長崎であった。私、悦子も含めて総勢五十名ほどの参加であった。長崎でもグループ単位で行動したから、私は悦子を含め八名ほどで長崎の名所を訪ねてまわった。長崎でも悦子は私のそばを歩き私とよく話した。
私は、悦子も私を好きなのだと勝手に確信した。だから、大浦天主堂に行ったときに悦子が私と離れて遠い目をしてぼんやりしているのが破局のはじまりだとは、想像だにしなかった。
三
十月になると、悦子はグループ活動には来たが私とは話さなくなった。そして、私のグループの吉水茂人とつきあっているという噂が流れてきた。
それは事実だった。私は見事に振られたのであった。大変ショックであった。失恋という言葉に意味はこのときはじめて実感した。なぜだ、私たちはむつまじく話していたではないか。長崎の合宿では打ち解けて周りからもうらやましがられるほどの仲だったではないか。私は悶々とした。
しかし、一方では私はどこか冷めていた。もう一人の自分が『くだらないことに首をつっこむからさ』とささやくのだ。結局のところ私は恋人というステイタスに酔っていただけなのかもしれなかった。
私は、友人の下宿でいわゆる「失恋記念のやけ酒」を飲んだが、別に酒を飲まなくても自分のとるべき行動はわかっていた。このときも今日だけはやけ酒を飲んで主人公になれるという自分勝手な理屈に酔っていただけなのであった。
四
ある日、先輩の畑中律子さんに会った。畑中先輩は魅力的で美しい人であったが、先輩というのは神様みたいな存在であったから、恋愛の対象としては考えたことはなかった。
「大山君、悦ちゃんに振られたんだって」
「ええ、そうなんです」と私は失恋の痛みを大げさに話し、畑中さんに聞いてもらった。それは心地よい時間であった。美しい畑中先輩が真剣な眼差しで私を見つめてくれている。その優しさに酔いたいがために失恋の話をしているのだった。
その後、私は畑中先輩と西山の地蔵院を訪れた。畑中先輩が私を元気づけようとしてくれているのがよくわかった。
「大山君、ここは竹の寺と呼ばれていてね。竹は風が吹いたらしなるけれどもすぐに元にもどるでしょ。大山君も一度や二度の失恋でくじけていてはだめ。この竹のようにまた上を向いて伸びていかなきゃ」
「先輩、ありがとうございます。でも、心の痛みはなかなかとれません」と私は少し畑中先輩に甘えてみた。畑中先輩は、いろいろと言葉を尽くし慰めてくれた。
「今日は元気がでました。ありがとうございます。竹のようにがんばります」
私は畑中先輩に礼を言って別れた。
でも私はどこか冷めていた。自分がどうせねばならないかはわかっていた。それは厳しい道のりではあったが、方法はそれしかなかった。畑中先輩にいろいろ聞いてもらったけれど、結局は畑中先輩のやさしさがほしいだけなのであった。
その後、悦ちゃんとの思い出が私の中で美化されて『さよなら悦ちゃん』という歌を作詞作曲して勤務する中学校の部活発表会で自演した。六番まであるという実に未練たらしく冗長のものであった。
五
定年退職後、思い出の地蔵院に行ってみることにした。
竹が天から降ってきたかのごとく美しい竹林を形成している。畑中先輩は、私に竹のようにしなっても上に伸びろと言ってくれたけれど、私の考えは違う。
私という人間は竹のようにいかにも隣にもたれるかのように生きてきたけれど、もう一人の自分のささやきに従い、一本の竹のように孤高に常に自分の出した答えだけで生きてきた。それは、半面孤独でもあったけれど、私は頑固者だからやっぱり自分の答えでしか歩めなかったのであった。
私は地蔵院を歩きながら、自分のとるべき道はわかっていたのに人に頼るふりのできた若い日の自分を、懐かしく思い出していた。