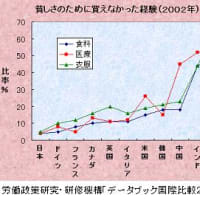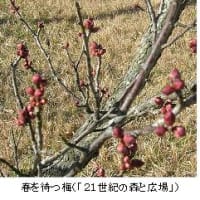≪冬夜読書≫ 山田方谷
頽壁雪五尺 崩れた壁のあばら家に雪三尺
寒空月一輪 寒空には(皓々たる)月一輪
堅凝天地気 堅く凝る(凝縮)天地の気が
鍾在読書人 鍾(集)りて読書の人に在り
≪前会長“金は株売却し返済する”──大王製紙の井川前会長(47)は、去年からことしにかけてグループ企業7社から無担保で106億円余りを引き出し、このうち59億円以上が今も返済されていない。東京地検特捜部は、井川前会長からすでに任意で事情を聴いており、関係者によると、前会長はグループ企業から金を個人的に借り入れたことを認めたうえで、「返済していない金は株を売却するなどして返す」と主張しているという。又、引き出された金はほぼ全額が海外のカジノに使われた疑いがあるということで、大王製紙は、井川前会長がグループ企業に巨額の損害を与えたと判断し、21日、会社法の特別背任の疑いで特捜部に告発する方針だ。≫(11/21 NHK)
∇良寛の「冬夜読書」は懐かしさと郷愁を呼ぶが、山田方谷のは、貧窮厳寒の中に、高遠の志操を一層貫かんとする孤高の士を連想させる。老生の好む五言絶句である。山田方谷は、幕末の備中(岡山県)松山藩の儒者にして、藩主板倉勝静侯の政治顧問として、松山藩政を改革した人物。越前の河合継之助も傾注して学んだ“炎の陽明学者”である。彼の「理財論」は、藩政の堕落・沈滞は、上下交々目前の利財にのみに関心が埋没しているため、却って風紀が乱れ、文教が廃れ、小手先の対策に腐心し、「事外に立って」根本的改革を為しえていないためだ、と痛烈に批判している。──上掲の愚劣にして低俗なる前会長を戴いた大王製紙や、巨額の損失隠しが発覚した「オリンパス」、さらに言えばギリシャに端を発する欧州不安等々も、共通する背景には、潜在して見えなかった“嘘=損失隠し”が表面化したこと。純経営行為に非ざる経営陣の不正や国家財政破綻の隠匿という、上長の凡そ社会的、道徳的に逸脱した風紀の乱れが、壊滅的な危機を招来した。今朝の朝日新聞「ザ・コラム」に、大野博人編集委員が良い記事を書いていた。
∇2年前、当時大手格付け機関ムーディーズが、東電に21段階で上から3番目のAa2を与え、ギリシャ国債も6番目としていた。又、スタンダード・アンド・プア-ズもそれぞれ、3番目と7番目を与え、「投資適格」の評価をしていた。ところがフランスのヴィジオという格付け会社は、09年リポートで、東電を5段階評価で下から2番目、ギリシャは、欧州連合で最低ランクを付けていた。結果大手格付け会社は大はずれ、ヴィジオは当てた。何故か。≪採点には、財務力のデータより、組織として健全に機能しているかどうかを意味するコーポレートガバナンス(企業統治)や環境、雇用への気配りなどを見る≫のだそうだ。例えば、≪東電でとりわけ評価が低かったのが「企業統治部門」。100点満点中たったの2点だった。社外取締役の数や独立性、役員報酬、監査などで問題点があったり情報開示が不十分だったりしたため≫だという。≪ギリシャは「民主的な仕組み」に問題ありとされ、報道の自由、腐敗防止などがEU内では最低になった。≫ 公開された財務諸表は、監査がきちんと行なわれていることが前提だが、問題企業や国々では、そも/\そこに「隠蔽行為」があるのだから、そんなものだけで「格付け」すること事態が無意味だ。「大学」に曰く、≪国は利を以て利と為さず。義を以て利と為す≫と。
【理財論】 山田方谷
≪理財に関する関心や論議が、今日より密な時はない。しかるに国家が窮状なのも今日より厳しい時はない。やれ田畑の税だ、山・海・関所、はては舟・車・畜産にとあらゆることに税を課し、少しでもとれるものにはかき集めるに暇ない。しかも役人・武士の俸給をカットし、経費節減策とて貢賦、祭事、交際費、輿馬宮室等々僅かであっても減じている。理財に関して綿密なることかくの如しである。しかもこれらを実行すること数十年、しかるに当国の窮状は益々救うことができないでいる。国庫はがらんとして何も無く、あるのは積もり重なる債務ばかり。それは「理財」について智恵が未だ足りないからなのだろうか。未だ術策が奏効してないからなのか。やっていることが未だ荒すぎて綿密さに手抜かりがあるからだろうか。
─いや、皆、非だ。そうではない。そもそも善く天下の事を制する者は、「事の外にたって、事の内に屈しない」ものだ。しかるに今日の財を理(おさ)める者は、ことごとく「財の内に屈し」ている。思うに、世は泰平にして諸外国からの脅威があるわけでもなく、諸侯諸臣は座して安寧を貪っていられる。だからただ、「財用」だけが目下の患いとなる。したがって、上下の心は一に財のみに集まる。日夜営々としてその患いを救うことばかり謀って、その他のことを知ろうとしない。人心は日毎に邪して、しかも正すことができない。風俗は日に薄くなり、しかも厚くすることができない。官吏は日に汚れ、民物は日毎疲弊してなおかつ取り締まることができない。文教はどんどん廃れ、武備も緩み、だからといってこれらを振興し、引き締めることもできない。
─これらを列挙して改善を促す者がいても、「財用が不足しているからやりたくてもできない。そんな余裕などはない」と反って来るのがお決まりだ。嗚呼、これらのことをやることこそが経国の大法であるのにそれを捨て置いて修めず、綱紀が乱れ、政令が廃っている。一体これで財用の道を何によって通ぜんとしょうとしているのだろうか。そして毫釐瑣末の事を計って増減している。これは「財の内に屈する者」というのではなかろうか。何故財用の理が益々密になっているのに窮状が益々厳しくなっている事実(の根本)を怪しまないのだろうか。…≫。
頽壁雪五尺 崩れた壁のあばら家に雪三尺
寒空月一輪 寒空には(皓々たる)月一輪
堅凝天地気 堅く凝る(凝縮)天地の気が
鍾在読書人 鍾(集)りて読書の人に在り
≪前会長“金は株売却し返済する”──大王製紙の井川前会長(47)は、去年からことしにかけてグループ企業7社から無担保で106億円余りを引き出し、このうち59億円以上が今も返済されていない。東京地検特捜部は、井川前会長からすでに任意で事情を聴いており、関係者によると、前会長はグループ企業から金を個人的に借り入れたことを認めたうえで、「返済していない金は株を売却するなどして返す」と主張しているという。又、引き出された金はほぼ全額が海外のカジノに使われた疑いがあるということで、大王製紙は、井川前会長がグループ企業に巨額の損害を与えたと判断し、21日、会社法の特別背任の疑いで特捜部に告発する方針だ。≫(11/21 NHK)
∇良寛の「冬夜読書」は懐かしさと郷愁を呼ぶが、山田方谷のは、貧窮厳寒の中に、高遠の志操を一層貫かんとする孤高の士を連想させる。老生の好む五言絶句である。山田方谷は、幕末の備中(岡山県)松山藩の儒者にして、藩主板倉勝静侯の政治顧問として、松山藩政を改革した人物。越前の河合継之助も傾注して学んだ“炎の陽明学者”である。彼の「理財論」は、藩政の堕落・沈滞は、上下交々目前の利財にのみに関心が埋没しているため、却って風紀が乱れ、文教が廃れ、小手先の対策に腐心し、「事外に立って」根本的改革を為しえていないためだ、と痛烈に批判している。──上掲の愚劣にして低俗なる前会長を戴いた大王製紙や、巨額の損失隠しが発覚した「オリンパス」、さらに言えばギリシャに端を発する欧州不安等々も、共通する背景には、潜在して見えなかった“嘘=損失隠し”が表面化したこと。純経営行為に非ざる経営陣の不正や国家財政破綻の隠匿という、上長の凡そ社会的、道徳的に逸脱した風紀の乱れが、壊滅的な危機を招来した。今朝の朝日新聞「ザ・コラム」に、大野博人編集委員が良い記事を書いていた。
∇2年前、当時大手格付け機関ムーディーズが、東電に21段階で上から3番目のAa2を与え、ギリシャ国債も6番目としていた。又、スタンダード・アンド・プア-ズもそれぞれ、3番目と7番目を与え、「投資適格」の評価をしていた。ところがフランスのヴィジオという格付け会社は、09年リポートで、東電を5段階評価で下から2番目、ギリシャは、欧州連合で最低ランクを付けていた。結果大手格付け会社は大はずれ、ヴィジオは当てた。何故か。≪採点には、財務力のデータより、組織として健全に機能しているかどうかを意味するコーポレートガバナンス(企業統治)や環境、雇用への気配りなどを見る≫のだそうだ。例えば、≪東電でとりわけ評価が低かったのが「企業統治部門」。100点満点中たったの2点だった。社外取締役の数や独立性、役員報酬、監査などで問題点があったり情報開示が不十分だったりしたため≫だという。≪ギリシャは「民主的な仕組み」に問題ありとされ、報道の自由、腐敗防止などがEU内では最低になった。≫ 公開された財務諸表は、監査がきちんと行なわれていることが前提だが、問題企業や国々では、そも/\そこに「隠蔽行為」があるのだから、そんなものだけで「格付け」すること事態が無意味だ。「大学」に曰く、≪国は利を以て利と為さず。義を以て利と為す≫と。
【理財論】 山田方谷
≪理財に関する関心や論議が、今日より密な時はない。しかるに国家が窮状なのも今日より厳しい時はない。やれ田畑の税だ、山・海・関所、はては舟・車・畜産にとあらゆることに税を課し、少しでもとれるものにはかき集めるに暇ない。しかも役人・武士の俸給をカットし、経費節減策とて貢賦、祭事、交際費、輿馬宮室等々僅かであっても減じている。理財に関して綿密なることかくの如しである。しかもこれらを実行すること数十年、しかるに当国の窮状は益々救うことができないでいる。国庫はがらんとして何も無く、あるのは積もり重なる債務ばかり。それは「理財」について智恵が未だ足りないからなのだろうか。未だ術策が奏効してないからなのか。やっていることが未だ荒すぎて綿密さに手抜かりがあるからだろうか。
─いや、皆、非だ。そうではない。そもそも善く天下の事を制する者は、「事の外にたって、事の内に屈しない」ものだ。しかるに今日の財を理(おさ)める者は、ことごとく「財の内に屈し」ている。思うに、世は泰平にして諸外国からの脅威があるわけでもなく、諸侯諸臣は座して安寧を貪っていられる。だからただ、「財用」だけが目下の患いとなる。したがって、上下の心は一に財のみに集まる。日夜営々としてその患いを救うことばかり謀って、その他のことを知ろうとしない。人心は日毎に邪して、しかも正すことができない。風俗は日に薄くなり、しかも厚くすることができない。官吏は日に汚れ、民物は日毎疲弊してなおかつ取り締まることができない。文教はどんどん廃れ、武備も緩み、だからといってこれらを振興し、引き締めることもできない。
─これらを列挙して改善を促す者がいても、「財用が不足しているからやりたくてもできない。そんな余裕などはない」と反って来るのがお決まりだ。嗚呼、これらのことをやることこそが経国の大法であるのにそれを捨て置いて修めず、綱紀が乱れ、政令が廃っている。一体これで財用の道を何によって通ぜんとしょうとしているのだろうか。そして毫釐瑣末の事を計って増減している。これは「財の内に屈する者」というのではなかろうか。何故財用の理が益々密になっているのに窮状が益々厳しくなっている事実(の根本)を怪しまないのだろうか。…≫。