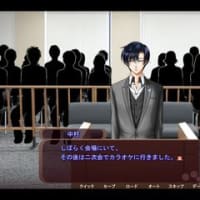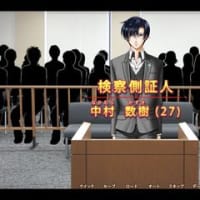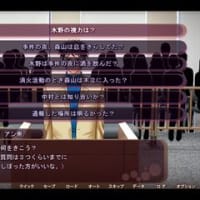第1 設問1(以下、刑事訴訟法は条文数のみで表記する)
1. 捜査①の適法性
(1)ごみ袋を持ち去った行為について
甲がごみ集積所に置いたゴミ袋は、甲が所有権を放棄し、「遺留した物」にあたるため、これを持ち去ったPらの行為は、領置(221条)として適法である。
(2)メモ片を復元した行為について
ア 強制処分該当性
(ア) Pらはゴミ袋を甲がごみ集積所に置いたことを確認した後に回収、中身のメモ片を復元しているため、かかる行為が甲のプライバシー権を侵害する強制処分(197条1項但書)とならないか問題となる。
(イ) この点、個人の意思を制圧するような処分でなくても、私人の重大な権利を侵害することあり得る。そうであるとすると、かかる処分についても、国会によって強制処分をあらかじめ法定し(憲法41条)、司法権による事前審査を行う(憲法35条)ことにより人権を保障する、強制処分法定主義及び令状主義の趣旨が合致するものといえる。
そこで、重大な権利を侵害するような処分は、強制処分にあたるものと解する。
(ウ) これを本件についてみるに、公道上のごみ集積所にごみ袋を置くことは、何者かにゴミ袋が持ち去られる可能性があることに鑑みれば、その中身についてプライバシー権を相当程度放棄しているものといえる。
よって、甲の置いたゴミ袋を持ち去る行為は重大な権利を侵害するものとはいえず、強制処分にはあたらない。
イ 任意処分としての限界
(ア) 強制処分にあたらないとしても、何らかの権利を制約する可能性があるため、捜査比例の原則(憲法13条後段)に照らし、(a)必要性、(b) 緊急性、(c)相当性のない行為は任意処分の限界を超え違法となる。
(イ) 本件被疑事件のけん銃の密売は、密行性があり通常の捜査方法では証拠を入手することは困難であったことから、(a)必要性が認められる。
次に、本件の密売は組織的に行われ、このままでは多数のけん銃が取引されることになり、それが犯罪に使用されるおそれもあるため、一刻も早く証拠収集を行う(b)緊急性も認められる。
そして、本問のゴミ袋を公道上のごみ集積所に置かれ、所有権とともにプライバシー権も相当程度放棄されているから、その中身を復元する行為も上記の必要性及び相当性に照らせば(c)相当な行為といえる。
(ウ) 以上のように、捜査①のメモ片を復元する行為は任意捜査(197条1項本文)として適法である。
2. 捜査②の適法性
(1) Pらが甲のマンションのごみ集積所に対入りゴミ袋内を確認し、メモ片を持ち帰った行為について
ア 強制処分該当性
(ア) Pらは、証拠収集のため、私有地である甲のマンションの敷地内にあるごみ集積所に立ち入り、甲の出したゴミ袋の中身を確認している。かかる行為が令状(218条1項)なくして行われた捜索差押えとして違法とならないか。重大な権利侵害があるか否か検討する。
(イ) この点、ごみ集積所はマンションの敷地内にあるものの、居住部分とは離れた場所にあり、しかもその出入り口は施錠されておらず、誰でも出入りすること可能な場所にあった。そうであるとすると、ごみ集積所は住居ほどのプライバシー性を有しておらず、重大な権利侵害があったとはいえない。
(ウ) したがって、かかるPらの行為は令状なく行われた捜索差押えにはあたらない。
イ 任意処分としての限界
(ア) では、かかる行為が(a)必要性、(b) 緊急性、(c)相当性を有する任意処分(197条1項)として適法といえるか。
(イ) まず、前述のように、本件被疑事件は通常の捜査では証拠収集が困難であるけん銃の密売事件である。しかも捜査①によって、その重要な証拠となるメモ片が発見されており、同様なメモ片収集するために、本問のような捜査を行い証拠収集する(a)必要性があった。
また、甲がいつメモ片の入ったゴミ袋を投棄し、それがいつ回収されてしまうかは不明であり、事前に令状を請求することも困難であったといえるから、甲がゴミ袋を投棄したあとすぐに中身を確認し、メモ片を回収する(b)緊急性も認められる。
そして、上記の必要性・緊急性に鑑みると、甲がゴミ袋を投棄したのを確認後、短時間において誰でも出入り可能な倉庫内に立ち入り、ゴミ袋の中身を確認・メモ片を回収する程度の行為は、甲及びマンションの住人のプライバシー権に対する制約の程度も低く、相当である。
(ウ) したがって、かかるPらの行為は、任意処分として適法である。
(2) メモの復元行為について
メモの復元行為は、前述の通り、任意処分(197条1項本文)として適法である。
3. 捜査③の適法性
(1) 捜索差押えによって押収した乙の携帯電話のデータを復元する行為は、「押収物」に対する「必要な処分」(222条1項、111条1項)として適法といえるか問題となる。
(2) この点、同条項の趣旨は、捜索差押えの実効性を確保する点にあるから、「必要な処分」とは、(a) 捜索差押えの実効性を確保するために必要、かつ(b)相当性を有する処分をいうものと解する。
(3) これを本件についてみるに、本件被疑事件は密行性のある証拠収集が困難なけん銃密売事件であり、その取引は電話連絡を通じて行われていたことから、乙の携帯電話内のデータにはその証拠が存在する可能性が高かった。そして、そのデータは何者かによって消去されていたのであるから、捜索差押えの実効性を確保するためにデータを復元する(a)必要性が認められる。
そして、所有者である乙はPらの捜査に協力的であり、携帯電話のデータの提供には承認していたものといえ、しかも、乙は死亡しており、二度とその携帯電話が使用されることはないのであるから、本問の処分によるプライバシー権などの権利の制約は認められず、相当性も有する。
(4) 以上により、本問の復元行為は、捜索差押えの実行性を確保するために必要かつ相当な「必要な処分」として適法である。
第2 設問2
1. 甲及び乙の会話部分の証拠能力について
(1) 法律的関連性
ア 本件捜査報告書の甲及び乙の会話部分に伝聞法則(320条1項)の適用があり、原則として証拠能力が否定されないか。
この点、伝聞法則の趣旨は、伝聞証拠の介在する危険性を反対尋問等でチェックできない点にあるから、要証事実との関係で供述内容の真実性が問題となる場合にのみ伝聞法則の適用があるものと解する。
イ 本件被疑事件においては、設問1で得られた以外に有力的な客観的証拠が不足していることから、本件捜査報告書の要証事実は甲の犯人性であると解する。したがって、本件捜査報告書の甲の供述内容が問題となるため、かかる部分につき伝聞法則の適用がある。
もっとも、乙はPらの指示通り会話をしていることから、その内容の真実性は問題とならず、またICレコーダーによる甲・乙の会話の記録は、正確性を有する機械的記録であるから、伝聞法則の適用はない。
ウ では、甲の会話部分が伝聞例外にあたり証拠能力は認められるか。
この点、甲の会話部分は再伝聞にあたるが、その内容は甲にとって「不利益な事実の承認」にあたり、信用の情況的保障があるから(324条1項、322条1項)、再伝聞性が否定される。
また、本件捜査報告書は、Kが五官の作用によりICレコーダーの内容を認識・記録したものであるから、321条3項に基づき、Kがその作成名義と記載内容の真実性を証言すれば証拠能力が認められる。
エ 以上により、本件捜査報告書中の甲・乙の会話部分は伝聞例外として証拠能力が認められる。
(2) 証拠禁止
ア 甲・乙の会話部分は私人である乙がICレコーダーに録音して収集された証拠であるが、司法の廉潔性の確保の観点から証拠とすることが相当でない重大な違法がある場合には、違法収集証拠として証拠能力が原則として否定されるものと解する。
イ では、本件のおとり捜査が令状なく行われた強制処分として違法といえるか。
この点、Pらが乙に指示してけん銃の取引を働きかけたとしても、それ自体は甲の自己決定権を侵害するものとはいえない。よって、強制処分にはあたらない。
ウ 次に、任意処分として適法といえるか。
この点、本件は密行性のあるけん銃密売事件であり、通常の方法では証拠収集は困難であったといえるから、証拠収集の必要性及び緊急性が認められる。
そして、甲は機会があればけん銃の密売を行う意図にあったから、このような者に対して違法なけん銃の密売を働きかける行為も捜査として相当性を有するものといえる。
エ 以上のように、本件のおとり捜査は任意処分として適法であるから、甲・乙間の会話部分は違法収集証拠として証拠能力を否定されない。
2. 甲・丙間の会話部分の証拠能力について
(1) 甲・丙間の会話部分については、甲・乙間の会話部分のように乙の説明部分が存在しないため、甲の供述が自己に「不利益な供述」にあたるとはいえないようにも思える。
しかし、甲が要求している300万は、甲と乙が交渉を行ったけん銃2丁の代金と同額であるため、甲のいう「物」とはけん銃をさすものといえるため、甲の供述部分は自己に「不利益な供述」として伝聞例外にあたり証拠能力が認められる。
(2) そして、丙の供述がPらの指示通りに行われているため、その真実性が問題とならない点、及び捜査に違法性がない点は、上記1と同様である。
以上
【言い訳】
圧倒的な分量に圧倒されました刑事訴訟法。バランスよく書かなければならないのに、いつも通り、前半が厚くなりすぎに。基本的に大問は2問分まとめて構成するため、そのしわ寄せは設問2どころか刑法まで…。お疲れ様でした。
設問1については、もちろん重判掲載判例なんて存じ上げません。これ領置で全部適法じゃね?って思っていました。ちなみに、強制処分の規範を厚く書いたのは、単に事前に準備していたので書きたかったからです。捜査③も何が問題点か分からなかったので、みんなが書きそうな「必要な処分」を書いてごまかしました。一応、死んだ乙のプライバシーに配慮してみたりしましたが、ローの先生に的外れとの指摘を受けました。そりゃそうだ。
設問2は、最初違法収集証拠排除のことだけを書こうと思いましたが、資料の詳細さから伝聞も書くことに。しかし、時間がないために、一番やってはいけない問題点からの逃走を図り、伝聞の内容はスカスカに。「乙はPらの指示通り会話をしていることから、その内容の真実性は問題とならず…」ってどういうことやねん。まぁ、甲と乙と丙の違いなんて本番じゃ気づけなかったんですけどね。
おとり捜査もてきとーです。秘密録音は構成の時には気づいていたのに、焦って書き落とし。
結局2時間半かけてこの内容です。時間配分ができない状態で試験に挑んだのはやはり自殺行為でしたね。もちろん同様のミスは最終日の公法系でも起こるのでした…。
1. 捜査①の適法性
(1)ごみ袋を持ち去った行為について
甲がごみ集積所に置いたゴミ袋は、甲が所有権を放棄し、「遺留した物」にあたるため、これを持ち去ったPらの行為は、領置(221条)として適法である。
(2)メモ片を復元した行為について
ア 強制処分該当性
(ア) Pらはゴミ袋を甲がごみ集積所に置いたことを確認した後に回収、中身のメモ片を復元しているため、かかる行為が甲のプライバシー権を侵害する強制処分(197条1項但書)とならないか問題となる。
(イ) この点、個人の意思を制圧するような処分でなくても、私人の重大な権利を侵害することあり得る。そうであるとすると、かかる処分についても、国会によって強制処分をあらかじめ法定し(憲法41条)、司法権による事前審査を行う(憲法35条)ことにより人権を保障する、強制処分法定主義及び令状主義の趣旨が合致するものといえる。
そこで、重大な権利を侵害するような処分は、強制処分にあたるものと解する。
(ウ) これを本件についてみるに、公道上のごみ集積所にごみ袋を置くことは、何者かにゴミ袋が持ち去られる可能性があることに鑑みれば、その中身についてプライバシー権を相当程度放棄しているものといえる。
よって、甲の置いたゴミ袋を持ち去る行為は重大な権利を侵害するものとはいえず、強制処分にはあたらない。
イ 任意処分としての限界
(ア) 強制処分にあたらないとしても、何らかの権利を制約する可能性があるため、捜査比例の原則(憲法13条後段)に照らし、(a)必要性、(b) 緊急性、(c)相当性のない行為は任意処分の限界を超え違法となる。
(イ) 本件被疑事件のけん銃の密売は、密行性があり通常の捜査方法では証拠を入手することは困難であったことから、(a)必要性が認められる。
次に、本件の密売は組織的に行われ、このままでは多数のけん銃が取引されることになり、それが犯罪に使用されるおそれもあるため、一刻も早く証拠収集を行う(b)緊急性も認められる。
そして、本問のゴミ袋を公道上のごみ集積所に置かれ、所有権とともにプライバシー権も相当程度放棄されているから、その中身を復元する行為も上記の必要性及び相当性に照らせば(c)相当な行為といえる。
(ウ) 以上のように、捜査①のメモ片を復元する行為は任意捜査(197条1項本文)として適法である。
2. 捜査②の適法性
(1) Pらが甲のマンションのごみ集積所に対入りゴミ袋内を確認し、メモ片を持ち帰った行為について
ア 強制処分該当性
(ア) Pらは、証拠収集のため、私有地である甲のマンションの敷地内にあるごみ集積所に立ち入り、甲の出したゴミ袋の中身を確認している。かかる行為が令状(218条1項)なくして行われた捜索差押えとして違法とならないか。重大な権利侵害があるか否か検討する。
(イ) この点、ごみ集積所はマンションの敷地内にあるものの、居住部分とは離れた場所にあり、しかもその出入り口は施錠されておらず、誰でも出入りすること可能な場所にあった。そうであるとすると、ごみ集積所は住居ほどのプライバシー性を有しておらず、重大な権利侵害があったとはいえない。
(ウ) したがって、かかるPらの行為は令状なく行われた捜索差押えにはあたらない。
イ 任意処分としての限界
(ア) では、かかる行為が(a)必要性、(b) 緊急性、(c)相当性を有する任意処分(197条1項)として適法といえるか。
(イ) まず、前述のように、本件被疑事件は通常の捜査では証拠収集が困難であるけん銃の密売事件である。しかも捜査①によって、その重要な証拠となるメモ片が発見されており、同様なメモ片収集するために、本問のような捜査を行い証拠収集する(a)必要性があった。
また、甲がいつメモ片の入ったゴミ袋を投棄し、それがいつ回収されてしまうかは不明であり、事前に令状を請求することも困難であったといえるから、甲がゴミ袋を投棄したあとすぐに中身を確認し、メモ片を回収する(b)緊急性も認められる。
そして、上記の必要性・緊急性に鑑みると、甲がゴミ袋を投棄したのを確認後、短時間において誰でも出入り可能な倉庫内に立ち入り、ゴミ袋の中身を確認・メモ片を回収する程度の行為は、甲及びマンションの住人のプライバシー権に対する制約の程度も低く、相当である。
(ウ) したがって、かかるPらの行為は、任意処分として適法である。
(2) メモの復元行為について
メモの復元行為は、前述の通り、任意処分(197条1項本文)として適法である。
3. 捜査③の適法性
(1) 捜索差押えによって押収した乙の携帯電話のデータを復元する行為は、「押収物」に対する「必要な処分」(222条1項、111条1項)として適法といえるか問題となる。
(2) この点、同条項の趣旨は、捜索差押えの実効性を確保する点にあるから、「必要な処分」とは、(a) 捜索差押えの実効性を確保するために必要、かつ(b)相当性を有する処分をいうものと解する。
(3) これを本件についてみるに、本件被疑事件は密行性のある証拠収集が困難なけん銃密売事件であり、その取引は電話連絡を通じて行われていたことから、乙の携帯電話内のデータにはその証拠が存在する可能性が高かった。そして、そのデータは何者かによって消去されていたのであるから、捜索差押えの実効性を確保するためにデータを復元する(a)必要性が認められる。
そして、所有者である乙はPらの捜査に協力的であり、携帯電話のデータの提供には承認していたものといえ、しかも、乙は死亡しており、二度とその携帯電話が使用されることはないのであるから、本問の処分によるプライバシー権などの権利の制約は認められず、相当性も有する。
(4) 以上により、本問の復元行為は、捜索差押えの実行性を確保するために必要かつ相当な「必要な処分」として適法である。
第2 設問2
1. 甲及び乙の会話部分の証拠能力について
(1) 法律的関連性
ア 本件捜査報告書の甲及び乙の会話部分に伝聞法則(320条1項)の適用があり、原則として証拠能力が否定されないか。
この点、伝聞法則の趣旨は、伝聞証拠の介在する危険性を反対尋問等でチェックできない点にあるから、要証事実との関係で供述内容の真実性が問題となる場合にのみ伝聞法則の適用があるものと解する。
イ 本件被疑事件においては、設問1で得られた以外に有力的な客観的証拠が不足していることから、本件捜査報告書の要証事実は甲の犯人性であると解する。したがって、本件捜査報告書の甲の供述内容が問題となるため、かかる部分につき伝聞法則の適用がある。
もっとも、乙はPらの指示通り会話をしていることから、その内容の真実性は問題とならず、またICレコーダーによる甲・乙の会話の記録は、正確性を有する機械的記録であるから、伝聞法則の適用はない。
ウ では、甲の会話部分が伝聞例外にあたり証拠能力は認められるか。
この点、甲の会話部分は再伝聞にあたるが、その内容は甲にとって「不利益な事実の承認」にあたり、信用の情況的保障があるから(324条1項、322条1項)、再伝聞性が否定される。
また、本件捜査報告書は、Kが五官の作用によりICレコーダーの内容を認識・記録したものであるから、321条3項に基づき、Kがその作成名義と記載内容の真実性を証言すれば証拠能力が認められる。
エ 以上により、本件捜査報告書中の甲・乙の会話部分は伝聞例外として証拠能力が認められる。
(2) 証拠禁止
ア 甲・乙の会話部分は私人である乙がICレコーダーに録音して収集された証拠であるが、司法の廉潔性の確保の観点から証拠とすることが相当でない重大な違法がある場合には、違法収集証拠として証拠能力が原則として否定されるものと解する。
イ では、本件のおとり捜査が令状なく行われた強制処分として違法といえるか。
この点、Pらが乙に指示してけん銃の取引を働きかけたとしても、それ自体は甲の自己決定権を侵害するものとはいえない。よって、強制処分にはあたらない。
ウ 次に、任意処分として適法といえるか。
この点、本件は密行性のあるけん銃密売事件であり、通常の方法では証拠収集は困難であったといえるから、証拠収集の必要性及び緊急性が認められる。
そして、甲は機会があればけん銃の密売を行う意図にあったから、このような者に対して違法なけん銃の密売を働きかける行為も捜査として相当性を有するものといえる。
エ 以上のように、本件のおとり捜査は任意処分として適法であるから、甲・乙間の会話部分は違法収集証拠として証拠能力を否定されない。
2. 甲・丙間の会話部分の証拠能力について
(1) 甲・丙間の会話部分については、甲・乙間の会話部分のように乙の説明部分が存在しないため、甲の供述が自己に「不利益な供述」にあたるとはいえないようにも思える。
しかし、甲が要求している300万は、甲と乙が交渉を行ったけん銃2丁の代金と同額であるため、甲のいう「物」とはけん銃をさすものといえるため、甲の供述部分は自己に「不利益な供述」として伝聞例外にあたり証拠能力が認められる。
(2) そして、丙の供述がPらの指示通りに行われているため、その真実性が問題とならない点、及び捜査に違法性がない点は、上記1と同様である。
以上
【言い訳】
圧倒的な分量に圧倒されました刑事訴訟法。バランスよく書かなければならないのに、いつも通り、前半が厚くなりすぎに。基本的に大問は2問分まとめて構成するため、そのしわ寄せは設問2どころか刑法まで…。お疲れ様でした。
設問1については、もちろん重判掲載判例なんて存じ上げません。これ領置で全部適法じゃね?って思っていました。ちなみに、強制処分の規範を厚く書いたのは、単に事前に準備していたので書きたかったからです。捜査③も何が問題点か分からなかったので、みんなが書きそうな「必要な処分」を書いてごまかしました。一応、死んだ乙のプライバシーに配慮してみたりしましたが、ローの先生に的外れとの指摘を受けました。そりゃそうだ。
設問2は、最初違法収集証拠排除のことだけを書こうと思いましたが、資料の詳細さから伝聞も書くことに。しかし、時間がないために、一番やってはいけない問題点からの逃走を図り、伝聞の内容はスカスカに。「乙はPらの指示通り会話をしていることから、その内容の真実性は問題とならず…」ってどういうことやねん。まぁ、甲と乙と丙の違いなんて本番じゃ気づけなかったんですけどね。
おとり捜査もてきとーです。秘密録音は構成の時には気づいていたのに、焦って書き落とし。
結局2時間半かけてこの内容です。時間配分ができない状態で試験に挑んだのはやはり自殺行為でしたね。もちろん同様のミスは最終日の公法系でも起こるのでした…。