国立競技場で演じられた「国民の歴史の絵巻物」が、密林の様子で始まり、それを開墾する人々の演技で歴史の初めを描いているのは、とても興味深い。西アフリカにおける森林というのは、私たちが森林に対して抱くような、自然の恵みや緑の情景ではなかった。それは暗黒で果てしなく広がり、人間に敵対し、文明の介入を阻むものであった。
今でも、原生林を前にすると分る。熱帯の原生林では、木々は頑強に高々とそびえ、広がった枝々は折り重なって、地上に光が届くことを許さない。薄暗い地上にもびっしりと植物が生え、蔓性の籐や蔦が絡み合い、人が分け入って行くのには大変な困難があった。さらに密林の主人公は動物たちであり、豹やヒヒや狼や鰐やその他の肉食獣たちが襲ってきた。毒蛇、害虫はそこかしこに待ち構え、おまけにマラリア・黄熱病などの熱病も蔓延していた。
人が道を拓き、畑を開墾しても、常夏で多雨多湿の気候にあっては、少し油断した隙にたちまち雑木が生え、人々の活動の痕跡を埋めてしまう。熱帯雨林は、人々の移動を阻み、したがって人間の文明生活の進出を阻む、頑強な鉄条網のようなものであった。
これに対して、内陸部の乾燥地帯に至れば、密林は姿を消し、広く平らな台地に、灌木が点在するだけになる。熱帯雨林に比べて土地は痩せているし、乾季が長くて生活は厳しいにしても、粟や稗などの雑穀は収穫できるし、村々は発達する。何より、移動が容易であり、交易なども盛んに行い得た。交易という意味では、サハラ砂漠は、阻むものがない理想的な交易路である。ラクダと飲み水さえ確保すれば、何百キロ、何千キロという距離を、ほぼ直線で旅し、大量の貨物を運搬することができた。
こういう条件を考え合わせれば、私たちが現在考えるアフリカの姿とはかなり違ったアフリカの文明構造が、見えて来るであろう。つまり私たちは、アフリカといえば、真ん中に不毛のサハラ砂漠が広がり、その周辺にある乾燥地域の土地は痩せて農作物は乏しく、貧困の広がる地域だと考える。それに対して南側のギニア湾(大西洋)に面した一帯は、雨も多く植物もよく育ち、農業生産も豊かで人口稠密な地域である、と考えている。
現代のアフリカとしては、その姿で正しい。しかし、文明社会がアフリカに進出し始めた頃には、それは全く逆だったのだ。人々は南側の広大な密林には入って行けず、そうした密林の周辺部で、開墾を進めながら農産物などを作っていた。つまり、およそ人間社会の営みは、むしろ乾燥地帯側に発達していった。村々の形成、つまり人口の集積は内陸部(北部)にあり、密林地域(南部)は人跡未踏の地となっていた。
さらに西アフリカの内陸部には、ニジェール川という恵みの川が流れている。この大河は、全長4千2百キロに及び、最西のギニアに水源を発し、大陸を西から東に、文字通り横断している。川筋は大きく乾燥地帯に折れこみ、今のマリ、ニジェールを通過して、ナイジェリアに至っている。中流域では、広大なデルタ沖積地、つまり肥沃な穀倉地帯を形成していた。また、東西をつなぐ、物資運搬路にもなっていた。
だから、西アフリカの歴史は、サハラ砂漠南縁の内陸、ニジェール川流域からはじまる。一方で、現在のギニア、コートジボワール、ガーナにあたる地帯は、熱帯雨林地帯なので、密林が広がり人を寄せ付けなかった。しかし、この地帯は、重要な輸出品を産する宝庫であった。一つは、金である。今一つは、コラと呼ばれる木の実である。コラは、口に含んで齧ると覚醒作用がある嗜好品であり、とくにアラブ世界の人々が求めた。西アフリカの南側で産出される、金とコラは、サハラ砂漠の隊商によって、盛んに北方に向けて輸出され、西アフリカに富をもたらした。
やがて、その富を蓄積し、帝国が形成される。西アフリカの帝国は、豊かな恵みと交易路を提供する、ニジェール川沿いに形成されていった。そして、帝国の村々で生産された産品は、サハラ砂漠の南側に沿って、あたかも港のように発達した交易都市から、砂漠に伸びる交易路を伝って、北アフリカそして欧州へと運ばれた。サハラ砂漠は、人々に航路を提供する大洋のようなものであった。その航路は、南側の森林地帯と、北側の地中海・アラブ世界をつなぎ、無数のラクダの隊商が、貨物船団のように行き来していた。
そうした帝国として、まず登場したのは、ガーナ王国である。ガーナと名前がついているけれども、現在のガーナからは遠く離れた、現在のモーリタニア、マリのニジェール川流域あたりの領域に散らばっていた、小王国の連合体であったと考えられる。8世紀ころのアラブの地誌に、「ガーナという黄金の国」があったと記されているとのことであり、8世紀ころには成立していたらしい。そして、おそらく13世紀ごろまでには勢力を失った。
次いで、マリ帝国が現れる。これは本格的な帝国となった。9世紀頃に起源を有するこの帝国は、マンデ系の民族を統一し、他の民族を支配した。13世紀には、英雄スンジャータ王(Soundiata Keïta、在位?-1255年)が現れ、ニジェール川上流のニアニに首都を定め、周辺の部族を統合した。14世紀になり、ニジェール川中流にむけ東進して版図を広げていった。トンブクトゥやジェンネなどが、ニジェール川の船運を柱に、帝国の交易都市として栄えた。トンブクトゥは岩塩を、ジェンネは金を、それぞれ貿易する拠点として発達した。
とりわけ、金の産出はすごかったようである。ニジェール川の上流地域(現ギニア)には、現在でも無数の金鉱山がある。それらの金鉱山から金を掘り出し、「ニンジンが生えるように金が採れる」と言われた。マリ帝国の最盛期に君臨した、ムーサ王(Mansa Moussa、在位1312年-1337年)は、1324年に8千人から1万人の隊列を組み、5百人の奴隷とともにメッカ巡礼を行った。ムーサ王は、ロバ40頭に乗せて、大量の金を持参、道中のあちこちで金の贈り物をした。そのために、カイロの金相場が下落したという逸話がある。
マリ帝国は、スレイマン王(Mansa Souleiman、在位1341年-1360年)の時代に最盛期を迎え、西は今のセネガル、ギニアから、モーリタニア、マリ、ニジェールに至るまでの、ニジェール川流域一帯を版図にして栄えた。その後、14世紀後半からは、版図内の小王国の離反が続き、とくに北からの遊牧民トゥアレグ族や、今のブルキナファソ東部に生まれた騎馬民族モシ族(イェンネガの伝説を参照)の攻勢を受けて弱体化した。その後も小国として存続したけれども、結局、1645年に滅亡した。
(続く)
今でも、原生林を前にすると分る。熱帯の原生林では、木々は頑強に高々とそびえ、広がった枝々は折り重なって、地上に光が届くことを許さない。薄暗い地上にもびっしりと植物が生え、蔓性の籐や蔦が絡み合い、人が分け入って行くのには大変な困難があった。さらに密林の主人公は動物たちであり、豹やヒヒや狼や鰐やその他の肉食獣たちが襲ってきた。毒蛇、害虫はそこかしこに待ち構え、おまけにマラリア・黄熱病などの熱病も蔓延していた。
人が道を拓き、畑を開墾しても、常夏で多雨多湿の気候にあっては、少し油断した隙にたちまち雑木が生え、人々の活動の痕跡を埋めてしまう。熱帯雨林は、人々の移動を阻み、したがって人間の文明生活の進出を阻む、頑強な鉄条網のようなものであった。
これに対して、内陸部の乾燥地帯に至れば、密林は姿を消し、広く平らな台地に、灌木が点在するだけになる。熱帯雨林に比べて土地は痩せているし、乾季が長くて生活は厳しいにしても、粟や稗などの雑穀は収穫できるし、村々は発達する。何より、移動が容易であり、交易なども盛んに行い得た。交易という意味では、サハラ砂漠は、阻むものがない理想的な交易路である。ラクダと飲み水さえ確保すれば、何百キロ、何千キロという距離を、ほぼ直線で旅し、大量の貨物を運搬することができた。
こういう条件を考え合わせれば、私たちが現在考えるアフリカの姿とはかなり違ったアフリカの文明構造が、見えて来るであろう。つまり私たちは、アフリカといえば、真ん中に不毛のサハラ砂漠が広がり、その周辺にある乾燥地域の土地は痩せて農作物は乏しく、貧困の広がる地域だと考える。それに対して南側のギニア湾(大西洋)に面した一帯は、雨も多く植物もよく育ち、農業生産も豊かで人口稠密な地域である、と考えている。
現代のアフリカとしては、その姿で正しい。しかし、文明社会がアフリカに進出し始めた頃には、それは全く逆だったのだ。人々は南側の広大な密林には入って行けず、そうした密林の周辺部で、開墾を進めながら農産物などを作っていた。つまり、およそ人間社会の営みは、むしろ乾燥地帯側に発達していった。村々の形成、つまり人口の集積は内陸部(北部)にあり、密林地域(南部)は人跡未踏の地となっていた。
さらに西アフリカの内陸部には、ニジェール川という恵みの川が流れている。この大河は、全長4千2百キロに及び、最西のギニアに水源を発し、大陸を西から東に、文字通り横断している。川筋は大きく乾燥地帯に折れこみ、今のマリ、ニジェールを通過して、ナイジェリアに至っている。中流域では、広大なデルタ沖積地、つまり肥沃な穀倉地帯を形成していた。また、東西をつなぐ、物資運搬路にもなっていた。
だから、西アフリカの歴史は、サハラ砂漠南縁の内陸、ニジェール川流域からはじまる。一方で、現在のギニア、コートジボワール、ガーナにあたる地帯は、熱帯雨林地帯なので、密林が広がり人を寄せ付けなかった。しかし、この地帯は、重要な輸出品を産する宝庫であった。一つは、金である。今一つは、コラと呼ばれる木の実である。コラは、口に含んで齧ると覚醒作用がある嗜好品であり、とくにアラブ世界の人々が求めた。西アフリカの南側で産出される、金とコラは、サハラ砂漠の隊商によって、盛んに北方に向けて輸出され、西アフリカに富をもたらした。
やがて、その富を蓄積し、帝国が形成される。西アフリカの帝国は、豊かな恵みと交易路を提供する、ニジェール川沿いに形成されていった。そして、帝国の村々で生産された産品は、サハラ砂漠の南側に沿って、あたかも港のように発達した交易都市から、砂漠に伸びる交易路を伝って、北アフリカそして欧州へと運ばれた。サハラ砂漠は、人々に航路を提供する大洋のようなものであった。その航路は、南側の森林地帯と、北側の地中海・アラブ世界をつなぎ、無数のラクダの隊商が、貨物船団のように行き来していた。
そうした帝国として、まず登場したのは、ガーナ王国である。ガーナと名前がついているけれども、現在のガーナからは遠く離れた、現在のモーリタニア、マリのニジェール川流域あたりの領域に散らばっていた、小王国の連合体であったと考えられる。8世紀ころのアラブの地誌に、「ガーナという黄金の国」があったと記されているとのことであり、8世紀ころには成立していたらしい。そして、おそらく13世紀ごろまでには勢力を失った。
次いで、マリ帝国が現れる。これは本格的な帝国となった。9世紀頃に起源を有するこの帝国は、マンデ系の民族を統一し、他の民族を支配した。13世紀には、英雄スンジャータ王(Soundiata Keïta、在位?-1255年)が現れ、ニジェール川上流のニアニに首都を定め、周辺の部族を統合した。14世紀になり、ニジェール川中流にむけ東進して版図を広げていった。トンブクトゥやジェンネなどが、ニジェール川の船運を柱に、帝国の交易都市として栄えた。トンブクトゥは岩塩を、ジェンネは金を、それぞれ貿易する拠点として発達した。
とりわけ、金の産出はすごかったようである。ニジェール川の上流地域(現ギニア)には、現在でも無数の金鉱山がある。それらの金鉱山から金を掘り出し、「ニンジンが生えるように金が採れる」と言われた。マリ帝国の最盛期に君臨した、ムーサ王(Mansa Moussa、在位1312年-1337年)は、1324年に8千人から1万人の隊列を組み、5百人の奴隷とともにメッカ巡礼を行った。ムーサ王は、ロバ40頭に乗せて、大量の金を持参、道中のあちこちで金の贈り物をした。そのために、カイロの金相場が下落したという逸話がある。
マリ帝国は、スレイマン王(Mansa Souleiman、在位1341年-1360年)の時代に最盛期を迎え、西は今のセネガル、ギニアから、モーリタニア、マリ、ニジェールに至るまでの、ニジェール川流域一帯を版図にして栄えた。その後、14世紀後半からは、版図内の小王国の離反が続き、とくに北からの遊牧民トゥアレグ族や、今のブルキナファソ東部に生まれた騎馬民族モシ族(イェンネガの伝説を参照)の攻勢を受けて弱体化した。その後も小国として存続したけれども、結局、1645年に滅亡した。
(続く)



















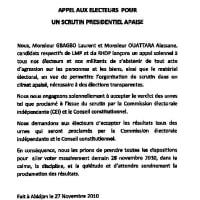
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます