以前にもご紹介した、ノーベル賞作家V.S.ナイポールの小説「ヤムスクロの鰐」の中で、ウフエボワニ大統領が語る寓話というのがある。
ウフエボワニ大統領が語るには、小さい時にヤムスクロの王宮に住み、長(おさ)になる訓練を受けていたという。そこに一人の「捕虜」がいて、子供たちの勉強の世話をしていた。そしてこの奴隷だか捕虜から、今でも忘れられない、次のような寓話を教わった、と言う。
「昔、一人の農民がいた。ある年のこと、作物もよく売れたので、ひと仕事終えてから市場の中をぶらぶらしていると、ある店先に美しいナイフが置いてあった。農民はすっかり気に入って、買って帰った。そして、片時も離さず大事にしていた。彼は鞘を作り、真珠や貝殻で飾りをつけた。ある日、彼が木を切っていたとき、そのナイフで指も切ってしまった。その痛みで、彼はナイフを地面に投げ捨て、悪態をついた。しかしその後、ナイフを拾い上げ、刃に付いた血をぬぐい、腰に下げた鞘に戻した。」
これだけの話である。本の中で、ナイポール自身も、「このそっけなく短い話の要点はなんだったのだろう」と疑問を呈している。そして、権力の行使と赦免について、ウフエボワニ大統領の思想を物語る寓話であった、と彼は解釈している。権力により排斥される人間も、かつては善人で人の役に立っていた。だから、そのことを忘れず、赦免するのだ、という指導者の慈悲を言いたいのだ、と捉えている。
私は、小説のこの個所を読んだ時に、別のことに驚いた。それは、ウフエボワニ大統領が、「小さい時にヤムスクロの王宮に住み、長(おさ)になる訓練を受けていた」ということである。私はそれまで、ウフエボワニ大統領は農場経営者であり、組合運動の組織者であると思っていた。ところが、それ以前に王族の一人として、アフリカの帝王学を学ぶ境遇にあったのだ。20世紀のはじめになってなお、奴隷だか捕虜だかがいるような、そういう世界に少年時代を過ごしていた人なのだ。
調べてみると、たしかにそのとおりだった。いや、バウレ族の王族であっただけでなく、なんと王様になっていた。しかも5歳の時に。5歳にして父親が亡くなり、次いで王であった伯父が亡くなった。そして、バウレ族の風習、つまり伯父から甥へ王位を継承する方式に従って、子供であるにもかかわらず、一族の王になった。だから少年時代に、王として教育を受けてきた。
その後、ウフエボワニはフランス植民政府に見出され、セネガルの「仏領西アフリカ医学学校」を出て医療関係の道に進む。ウフエボワニは優秀であったが、当時はアフリカ人には正式な医者になることが認められていなかった。1936年に、彼は医者の道をあきらめ、王として地元の首長の仕事に専念するようになる。そして、彼はその頃、おそらくコートジボワールでも一二を争う広大な農場を相続し、その経営に従事した。爾後、アフリカ人農場経営者の立場から、農場経営者組合を立ち上げ、フランス国民議会議員に選出されていく、という経過は、昨日の記事で書いたとおりである。
こうした背景から、何が読み取れるか。ウフエボワニ大統領は、フランスでの政治過程に身を乗り出す前に、アフリカの政治文化を十分に身に付けた人間だったのだ。セネガルの初代大統領サンゴール(Léopold Sédar Senghor)は、その後20年間大統領職を続けるという、彼と極めて類似した経歴をたどった。ウフエボワニ大統領は、そのサンゴール大統領と、そりが合わなかったことは有名である。文学者であり、仏高等師範学校やパリ大学を卒業し、フランスのエリートとして政治に乗り出して行ったサンゴール大統領について、ウフエボワニ大統領はこう評している。
「私は40歳でフランスを見出し、彼は40歳でアフリカを知ったのだ。」
つまり、ウフエボワニは、自分はアフリカを知る政治家であり、サンゴールはアフリカに降り立った政治家だ、と言いたいのである。それは、自分こそが、アフリカの政治土壌も、社会風土も知っている政治家である、という意味ではなかったか。
アフリカの人々のものの考え方や世界観をふまえたときに、ウフエボワニとして、「独立国」なる制度がどういう形で受け取られるのか、その運営がどういう宿命をたどるのか、おそらく見通せるところがあったように思う。コートジボワールの人々の心には、伝統社会のしきたりや価値観が、もう血の中に濃く溶け込んでいる。欧米の作りだした民主主義や人権思想といったものを、欧米人がこれ以外にあり得ないと信じてアフリカに押し付けても、いびつな接ぎ木にしかならないということである。
コートジボワールの人々の大半は、村々に住む。その伝統社会に住む人々が、「国民国家」の「一市民」として、「民主主義」を実践する主体になりうるのか。アフリカの風土を知り尽くしたウフエボワニとしては、1960年の時点で、大いに疑問があったであろう。いや、村々の人々の側から見れば、国の独立といっても、それは植民政府がなくなり、かわりに「黒いフランス人」の政府ができたというだけなのかもしれない。それらは、どんなに新しい色で人々を包もうとしても、しょせん包み紙でしかない。制度とも認識されず、成文化もされていないけれど、人々の生活や心の中にははるか昔から続く、治世と秩序の伝統がある。それを十分に分かっているから、ウフエボワニ大統領は、独立を躊躇したのだと思う。
ウフエボワニ大統領が自分の思想として語った先の寓話について、農民とナイフを、フランスとコートジボワールの関係であると捉えることが出来るかも知れない。でも、その前に、いったいどういう教訓があるのかないのか、なんだかふんわりしているところにこそ、すでにアフリカがある。
50年前の今日、コートジボワールは独立を宣言した。
ウフエボワニ大統領が語るには、小さい時にヤムスクロの王宮に住み、長(おさ)になる訓練を受けていたという。そこに一人の「捕虜」がいて、子供たちの勉強の世話をしていた。そしてこの奴隷だか捕虜から、今でも忘れられない、次のような寓話を教わった、と言う。
「昔、一人の農民がいた。ある年のこと、作物もよく売れたので、ひと仕事終えてから市場の中をぶらぶらしていると、ある店先に美しいナイフが置いてあった。農民はすっかり気に入って、買って帰った。そして、片時も離さず大事にしていた。彼は鞘を作り、真珠や貝殻で飾りをつけた。ある日、彼が木を切っていたとき、そのナイフで指も切ってしまった。その痛みで、彼はナイフを地面に投げ捨て、悪態をついた。しかしその後、ナイフを拾い上げ、刃に付いた血をぬぐい、腰に下げた鞘に戻した。」
これだけの話である。本の中で、ナイポール自身も、「このそっけなく短い話の要点はなんだったのだろう」と疑問を呈している。そして、権力の行使と赦免について、ウフエボワニ大統領の思想を物語る寓話であった、と彼は解釈している。権力により排斥される人間も、かつては善人で人の役に立っていた。だから、そのことを忘れず、赦免するのだ、という指導者の慈悲を言いたいのだ、と捉えている。
私は、小説のこの個所を読んだ時に、別のことに驚いた。それは、ウフエボワニ大統領が、「小さい時にヤムスクロの王宮に住み、長(おさ)になる訓練を受けていた」ということである。私はそれまで、ウフエボワニ大統領は農場経営者であり、組合運動の組織者であると思っていた。ところが、それ以前に王族の一人として、アフリカの帝王学を学ぶ境遇にあったのだ。20世紀のはじめになってなお、奴隷だか捕虜だかがいるような、そういう世界に少年時代を過ごしていた人なのだ。
調べてみると、たしかにそのとおりだった。いや、バウレ族の王族であっただけでなく、なんと王様になっていた。しかも5歳の時に。5歳にして父親が亡くなり、次いで王であった伯父が亡くなった。そして、バウレ族の風習、つまり伯父から甥へ王位を継承する方式に従って、子供であるにもかかわらず、一族の王になった。だから少年時代に、王として教育を受けてきた。
その後、ウフエボワニはフランス植民政府に見出され、セネガルの「仏領西アフリカ医学学校」を出て医療関係の道に進む。ウフエボワニは優秀であったが、当時はアフリカ人には正式な医者になることが認められていなかった。1936年に、彼は医者の道をあきらめ、王として地元の首長の仕事に専念するようになる。そして、彼はその頃、おそらくコートジボワールでも一二を争う広大な農場を相続し、その経営に従事した。爾後、アフリカ人農場経営者の立場から、農場経営者組合を立ち上げ、フランス国民議会議員に選出されていく、という経過は、昨日の記事で書いたとおりである。
こうした背景から、何が読み取れるか。ウフエボワニ大統領は、フランスでの政治過程に身を乗り出す前に、アフリカの政治文化を十分に身に付けた人間だったのだ。セネガルの初代大統領サンゴール(Léopold Sédar Senghor)は、その後20年間大統領職を続けるという、彼と極めて類似した経歴をたどった。ウフエボワニ大統領は、そのサンゴール大統領と、そりが合わなかったことは有名である。文学者であり、仏高等師範学校やパリ大学を卒業し、フランスのエリートとして政治に乗り出して行ったサンゴール大統領について、ウフエボワニ大統領はこう評している。
「私は40歳でフランスを見出し、彼は40歳でアフリカを知ったのだ。」
つまり、ウフエボワニは、自分はアフリカを知る政治家であり、サンゴールはアフリカに降り立った政治家だ、と言いたいのである。それは、自分こそが、アフリカの政治土壌も、社会風土も知っている政治家である、という意味ではなかったか。
アフリカの人々のものの考え方や世界観をふまえたときに、ウフエボワニとして、「独立国」なる制度がどういう形で受け取られるのか、その運営がどういう宿命をたどるのか、おそらく見通せるところがあったように思う。コートジボワールの人々の心には、伝統社会のしきたりや価値観が、もう血の中に濃く溶け込んでいる。欧米の作りだした民主主義や人権思想といったものを、欧米人がこれ以外にあり得ないと信じてアフリカに押し付けても、いびつな接ぎ木にしかならないということである。
コートジボワールの人々の大半は、村々に住む。その伝統社会に住む人々が、「国民国家」の「一市民」として、「民主主義」を実践する主体になりうるのか。アフリカの風土を知り尽くしたウフエボワニとしては、1960年の時点で、大いに疑問があったであろう。いや、村々の人々の側から見れば、国の独立といっても、それは植民政府がなくなり、かわりに「黒いフランス人」の政府ができたというだけなのかもしれない。それらは、どんなに新しい色で人々を包もうとしても、しょせん包み紙でしかない。制度とも認識されず、成文化もされていないけれど、人々の生活や心の中にははるか昔から続く、治世と秩序の伝統がある。それを十分に分かっているから、ウフエボワニ大統領は、独立を躊躇したのだと思う。
ウフエボワニ大統領が自分の思想として語った先の寓話について、農民とナイフを、フランスとコートジボワールの関係であると捉えることが出来るかも知れない。でも、その前に、いったいどういう教訓があるのかないのか、なんだかふんわりしているところにこそ、すでにアフリカがある。
50年前の今日、コートジボワールは独立を宣言した。



















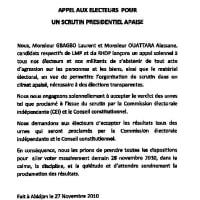
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます