青年海外協力隊員となって出かけていっても、そこに仕事が耳を揃えて待っているわけではない。派遣先の役所などは、ただ手伝ってくれ、それだけだ。どんな仕事をしたらいいのか、何が一番手助けになるのか、それは自分で見つけ、自分で工夫しなければならない場合が大半である。遠藤幸治さんは、ブルキナファソの西部バンフォラ市の保健行政局に来てくれと頼まれた。そこで仕事をしながら、何が一番役に立つ活動かをいろいろ考えた。そして、これだという結論に達した。下宿先のスペースを使って、日本食堂を開店したのである。
遠藤さんがこちらに来て手伝ってくれといわれたのは、公衆衛生の検査の仕事であった。街中で食品を扱う飲食店などの、衛生状態を定期的に調べに行く。バンフォラは、交通の要所にあって人々の往来が活発な町である。こちらで「マキ」と呼ばれている小さな食堂が、たくさん開店している。料理や配膳が衛生的に行われているか、掃除などがきちんと行き届いているかを調べることは、食中毒や伝染病などを予防するために、とても大事である。
飲食店でのさまざまな検査を行い、それをデータベースに記録していく。日本のように、上下水道やトイレなどの設備が、どこでも整っているわけではないから、なかなか水準に達しないところも多い。検査結果が悪い場合は、その経営者や従業員に、保健行政局まで出頭させ、公衆衛生についての指導を行う。さらに何ヶ月か経って、再び視察に訪れ、検査を行って改善具合を見る。そうした地道な努力で、保健行政局は市民の食品衛生を守ってきた。
局の同僚たちと一緒に、衛生検査のためにまわるマキの数は、市内約200店。それらの飲食店を訪れるうち、遠藤さんは、どうやったら食品衛生が保てるのかを、もっと具体的に教える必要があると考えるようになった。一番重要だと思われたのは、食器洗いである。食器は、汚れを落とし(洗い)、洗剤を落とし(すすぎ)、さらに消毒をする必要がある。多くの食堂では、洗いとすすぎは行っているが、消毒をしていない。食器洗いの水槽も、洗い用とすすぎ用の2槽しかないのが普通だ。
保健行政局は、そういうマキに、消毒用を含めて3槽を用意しろ、と指導する。しかし、多くの飲食店は屋台を少し大きくした程度であり、狭い台所で料理から洗い物までをこなしている。言葉で行政指導しても、なかなか実行には至らない。遠藤さんは、3槽にしなくても、プラスチックのたらいを一つ用意して、ジャベルという殺菌作用のある液体を薄めて皿をその中に通すだけで、十分消毒ができるのに、と考えた。その方式を普及させるため、遠藤さんが考えたのが、日本食堂を開店することだ。
私は、土曜日の昼下がりに、遠藤さんの日本食堂に出かけた。遠藤さんは、土曜日の午後だけ食堂を開く。お客さんは、市内の飲食店の従業員である。平日の勤務で町じゅうのマキを回るとき、マキの店主や従業員たちに土曜日にうちにいらっしゃいと誘う。それで土曜日ごとに、およそ10人くらいが食堂を訪れる。昼の仕事が終わった後、夜の仕事までの休憩時間に、やってくる。そして遅めの昼食を注文する。遠藤さんは、実費だけとって、餃子やチャーハンや、その他日本のお惣菜料理を出す。私が行ったときは、もう午後も遅くなっていたので、お客はおばさんが一人だけであった。遠藤さんの食堂が、普通のレストランと違うのは、ここからである。
お客の従業員たちは、自分でお皿を洗うのである。その洗い方を遠藤さんが指導する。そう、洗剤で洗って、その洗剤をすすぐ。ここまでは、従業員たちは自分の店でもやっている。さて、その横に、さらにプラスチックのたらいが置いてある。そこに水を張って、ジャベルを少量たらす。ジャベルは1本500フラン(100円)ほどで、どこの雑貨屋にも売っている。その液体に、すすぎ終わった食器類を浸すだけ。それだけの作業を追加しさえすれば、食中毒などの危険が大きく減じる。遠藤さんは、そういうふうに店主や従業員たちに伝える。この日本食堂は、公衆衛生を指導するための、模擬食堂なのだ。
門には「Yan Saniya」と看板が出ている。どういう意味ですか。
「ここ綺麗、という意味です。地元の言葉です。」
と、調理服を来た遠藤さん。マキの店主や従業員たちは、実際にやってみることで、どうやれば清潔が保てるかを体得する。一度でも訪れてくれた人々は、ジャベル方式を自分の店でも採用するようになっている。
食堂は、マキの従業員どうしの情報交換や交流の場所にもなっている。日本の料理文化の紹介の場にもなっている。遠藤さんの日本食堂は、バンフォラの町ではちょっと有名になって、新しい活動の可能性も広がりつつある。 日本食堂「ヤン・サニヤ」と遠藤さん
日本食堂「ヤン・サニヤ」と遠藤さん
 自宅を食堂に
自宅を食堂に
 食事に来てくれたお客様
食事に来てくれたお客様
 皿洗いの練習場
皿洗いの練習場
 ジャベル洗浄液
ジャベル洗浄液



















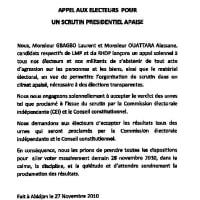
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます