日本映画祭で上映した「学校」の中で、先生が夜間中学の生徒に、「幸福」とは何かを問う場面があった。どん底人生の苦労ばかりで学校に行けなかった男が、50歳を越えて、読み書きを学びたいと、夜間中学に通い始めた。しかし、重病に倒れ、闘病の末他界する。人生最後の入院生活が、人生はじめての安らぎの日々であった。教室に届いた男の訃報に、生徒たちが議論をはじめる。幸福とは何か。
「私の人生は、不幸ばかりだった」と、焼肉屋のおばさんが言う。おばさんは在日韓国人で、日本語の読み書きが出来ずに苦労してきた。
「そんなことない、オモニには家族も友達もいっぱいいるじゃないか。」
と、ビル清掃業をしている青年が反論する。亡くなった男には、家族も身寄りもなかった。
そして、青年は言う。
「勉強したら、自分の不幸をより思い知ることになるだけだ。」
男は勉強をしたけれど、かえって不幸を知っただけで終わったのだろうか。
しばらく議論が続いた後、いつも少し反応の悪い青年が言う、「お金だ。」
そうだなあ、お金がいっぱいあれば幸せだよな、と先生。
「違う。幸せとは、お金のように、使ったら無くなる物じゃない」
と、登校拒否児だった若い女性が反論する。
「生きたい、とか、生きてて良かったと感じる、それが幸せだという気がする。」
その言葉に、先生も生徒もはっとする。そういう生き方ができるようにと、勉強するのだ。男は人生の最後に、生きてて良かったと感じることが出来たかもしれない。
私は、この場面を見ながら、数週間前に出会った、HIV陽性の女性たちのことを思い出していた。ブルキナファソの西部の都市バンフォラで、「ラキエタ(RAKIETA)」というバス会社が、社会貢献として運営支援している「エイズ対策センター」を訪れたときのことである。センターは、HIV感染とエイズについての啓蒙活動や、罹患者やエイズ孤児などへの支援活動を行っていた。さらにこの病気で苦しむ人々に、自ら生活を支えていくための手段、つまり手工芸などの技術を習得するための支援をしていた。
HIVとエイズは、この地方に住む人々に、深刻な影響を与えていた。バンフォラ市は、コートジボワールとの国境近くで、交通の要衝であるため、商業・輸送などの経済活動が盛んで、人々の往来が多い。だから、この病気が伝わりやすい。さらに悪いことに、コートジボワールが紛争で混乱した結果、HIVに感染した人たちが流入してくることにもなった。
そして、この病気は、女性や子供を直撃する。女性は夫から感染し、子供もHIV感染者として生まれることが少なくない。そして、夫が先に死んでしまうと、遺された女性と子供は、まず周囲の偏見と差別の中で、厳しい経済問題に直面する。未亡人は、夫が遺した財産を、夫の実家や親戚に奪われることが普通だからだ。生活手段を奪われ、弱りゆく身体を支えながら、病気とたたかい、子供を育て、生きていかなければならない。
私が「エイズ対策センター」を訪ねたとき、そういう何とも悲惨な運命に陥った女性たちが、中庭に十数人集まっていた。何人かの女性は、明らかに症状が進んでいた。免疫力の低下から体力が失われ、身体を支えるのがやっとになっていた。それでも、そういう女性も含めて、多くの女性たちが、村からの長い距離を歩いて、この施設にやってきていた。何のために。支援にすがるために。そうではない。
「村にいれば、私たちは村人たちのお荷物です。このセンターには、何とか自分の力で生きる方法を授けてほしい、と思って来ています。自分で技術や収入の道を身につけることが出来れば、人々のお荷物じゃなく生きることができる。体が弱くて、もう畑には行けないけれど、それでも、ちゃんと生きていく力がほしい。裁縫などの手作業が出来れば、それでも何とか生きていけるだろうから。」
私に向かって力説する中年の女性の横で、もうしゃべる気力もなくなったのだろうか、痩せ細った若い女性が目だけで合図をする。その通りだ、と。
その中年女性は続けて、次のように言った。
「もう長くない命かもしれないけれど、生きているかぎり、自立(autonom)していたい。体力がだんだん無くなるのが自分で分かります。だから、動けるうちになんとか頑張りたい。」
「自立」という言葉を、この最も悲惨な境遇の人々から聞くとは。
私はこちらに赴任して以来、多くの人々から支援を求められる立場にあった。自家用車を持っているような人でさえ、日本は何を援助してくれるか、ということばかり私に聞いてきた。ところが、ここに集う女性たちは、はるかに貧しい身なりをしながら、あの身障者の施設で出会った人々と同様、自分の力で生きることを求めていた。病気によって次第に弱りつつあると知りながらも、他人の慈悲にすがって生きていくようなことはしたくない、と訴えていた。そして、絶望の運命に生きながら、絶望の目ではなかった。憐れを誘うような、物乞いの目では決してなかった。どうして、このような目が出来るのだろうか。私には分からなかった。
だから、「学校」の場面で、「生きていて良かった」という言葉が出てきたとき、それを幸福ということに直接結び付ける映画の解釈は、少し安っぽいと思いながらも、私は何かが理解できたように思ったのだ。貧困や悲惨のなかにあっても、その中で少しでも良く生きようとすること、自分の生き方を前向きに変えていこうとすることが、その人間に尊厳を与えるのだ、と。エイズに身を蝕まれながら、いやそれだからこそ、女性たちは生きていく力を求めていた。自分を高めて、人一倍しっかりと生きようとしていた。
映画の中で、西田敏行扮する先生は、黒板の前に呆然と立ち、生徒たちに向かって、「いい授業だった、ありがとう」と言って教壇から降りた。私は、彼がなぜそう言ったのかも、理解できた。
「私の人生は、不幸ばかりだった」と、焼肉屋のおばさんが言う。おばさんは在日韓国人で、日本語の読み書きが出来ずに苦労してきた。
「そんなことない、オモニには家族も友達もいっぱいいるじゃないか。」
と、ビル清掃業をしている青年が反論する。亡くなった男には、家族も身寄りもなかった。
そして、青年は言う。
「勉強したら、自分の不幸をより思い知ることになるだけだ。」
男は勉強をしたけれど、かえって不幸を知っただけで終わったのだろうか。
しばらく議論が続いた後、いつも少し反応の悪い青年が言う、「お金だ。」
そうだなあ、お金がいっぱいあれば幸せだよな、と先生。
「違う。幸せとは、お金のように、使ったら無くなる物じゃない」
と、登校拒否児だった若い女性が反論する。
「生きたい、とか、生きてて良かったと感じる、それが幸せだという気がする。」
その言葉に、先生も生徒もはっとする。そういう生き方ができるようにと、勉強するのだ。男は人生の最後に、生きてて良かったと感じることが出来たかもしれない。
私は、この場面を見ながら、数週間前に出会った、HIV陽性の女性たちのことを思い出していた。ブルキナファソの西部の都市バンフォラで、「ラキエタ(RAKIETA)」というバス会社が、社会貢献として運営支援している「エイズ対策センター」を訪れたときのことである。センターは、HIV感染とエイズについての啓蒙活動や、罹患者やエイズ孤児などへの支援活動を行っていた。さらにこの病気で苦しむ人々に、自ら生活を支えていくための手段、つまり手工芸などの技術を習得するための支援をしていた。
HIVとエイズは、この地方に住む人々に、深刻な影響を与えていた。バンフォラ市は、コートジボワールとの国境近くで、交通の要衝であるため、商業・輸送などの経済活動が盛んで、人々の往来が多い。だから、この病気が伝わりやすい。さらに悪いことに、コートジボワールが紛争で混乱した結果、HIVに感染した人たちが流入してくることにもなった。
そして、この病気は、女性や子供を直撃する。女性は夫から感染し、子供もHIV感染者として生まれることが少なくない。そして、夫が先に死んでしまうと、遺された女性と子供は、まず周囲の偏見と差別の中で、厳しい経済問題に直面する。未亡人は、夫が遺した財産を、夫の実家や親戚に奪われることが普通だからだ。生活手段を奪われ、弱りゆく身体を支えながら、病気とたたかい、子供を育て、生きていかなければならない。
私が「エイズ対策センター」を訪ねたとき、そういう何とも悲惨な運命に陥った女性たちが、中庭に十数人集まっていた。何人かの女性は、明らかに症状が進んでいた。免疫力の低下から体力が失われ、身体を支えるのがやっとになっていた。それでも、そういう女性も含めて、多くの女性たちが、村からの長い距離を歩いて、この施設にやってきていた。何のために。支援にすがるために。そうではない。
「村にいれば、私たちは村人たちのお荷物です。このセンターには、何とか自分の力で生きる方法を授けてほしい、と思って来ています。自分で技術や収入の道を身につけることが出来れば、人々のお荷物じゃなく生きることができる。体が弱くて、もう畑には行けないけれど、それでも、ちゃんと生きていく力がほしい。裁縫などの手作業が出来れば、それでも何とか生きていけるだろうから。」
私に向かって力説する中年の女性の横で、もうしゃべる気力もなくなったのだろうか、痩せ細った若い女性が目だけで合図をする。その通りだ、と。
その中年女性は続けて、次のように言った。
「もう長くない命かもしれないけれど、生きているかぎり、自立(autonom)していたい。体力がだんだん無くなるのが自分で分かります。だから、動けるうちになんとか頑張りたい。」
「自立」という言葉を、この最も悲惨な境遇の人々から聞くとは。
私はこちらに赴任して以来、多くの人々から支援を求められる立場にあった。自家用車を持っているような人でさえ、日本は何を援助してくれるか、ということばかり私に聞いてきた。ところが、ここに集う女性たちは、はるかに貧しい身なりをしながら、あの身障者の施設で出会った人々と同様、自分の力で生きることを求めていた。病気によって次第に弱りつつあると知りながらも、他人の慈悲にすがって生きていくようなことはしたくない、と訴えていた。そして、絶望の運命に生きながら、絶望の目ではなかった。憐れを誘うような、物乞いの目では決してなかった。どうして、このような目が出来るのだろうか。私には分からなかった。
だから、「学校」の場面で、「生きていて良かった」という言葉が出てきたとき、それを幸福ということに直接結び付ける映画の解釈は、少し安っぽいと思いながらも、私は何かが理解できたように思ったのだ。貧困や悲惨のなかにあっても、その中で少しでも良く生きようとすること、自分の生き方を前向きに変えていこうとすることが、その人間に尊厳を与えるのだ、と。エイズに身を蝕まれながら、いやそれだからこそ、女性たちは生きていく力を求めていた。自分を高めて、人一倍しっかりと生きようとしていた。
映画の中で、西田敏行扮する先生は、黒板の前に呆然と立ち、生徒たちに向かって、「いい授業だった、ありがとう」と言って教壇から降りた。私は、彼がなぜそう言ったのかも、理解できた。



















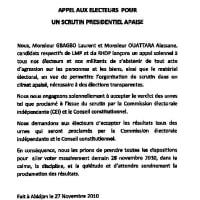
もし人が肯定的にまたは積極的に自分の人生を生きていたら人はどんな状況にいようとも幸せと感じるのではないでしょうか。二次元思考で貧乏だから不幸で金持ちだから幸せだと思うほど人生は単純ではなく本当に多種多様ですね。