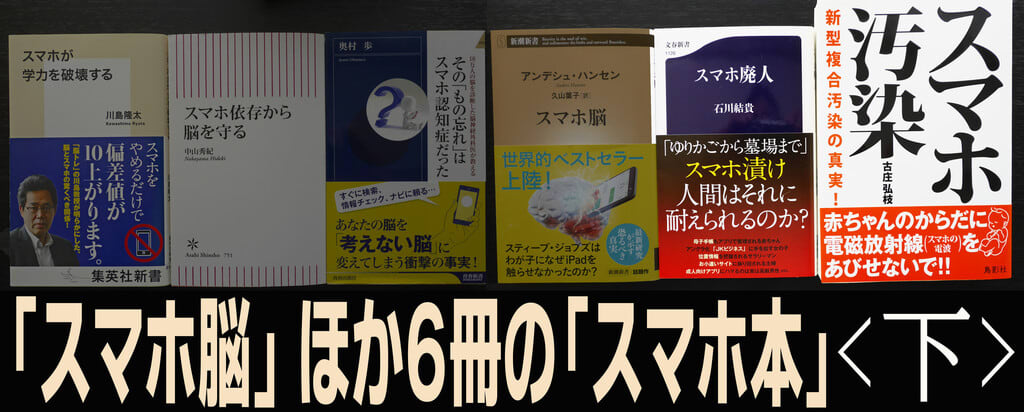
<下> 書評:「スマホ脳」ほか “スマホ問題” の本6冊 <下>
5.「スマホ廃人」 石川結貴 文春新書 2017

かなりインパクトのあるタイトルではある。(笑)
実は、似たようなタイトルの記事をこのブログでも書いたことがあるので、もしや、同様の切り口で論じているのかと思いきや、視点はまったく違っていた。
スマホ依存症、“国家的人体実験” 進行中! 10年後は廃人続出?
上の当ブログの記事は4年前の記事であるが、当時から当ブログでのスマホの捉え方は一貫して “電磁波問題” の一環である。(笑)
しかし、この本では、残念ながら、他の多くのスマホ本と同様、電磁波問題はまったく “スルー” であって、もっぱら “スマホの依存性” を問題視している “スマホ元凶論” である。
スマホの強い依存性、中毒性をさまざまな階層の人々の事例を通して描き出している。ご苦労さんである。(笑)

著者、石川結貴氏の強みは、足を使った地道な取材とインタビューのようだ。たしかに本書中でも専門家から市井の人々までさまざまな人々から “貴重な言葉“ を引き出していて、そこそこ面白く読ませる。
著者は4年前(2017 年)の本書の 序文で以下のように言っている。
「内閣府の「消費者動向調査」によると、スマホの世帯普及率(67.4%)がガラケーを上回ったのは 2015 年で、私たちの生活にスマホが浸透したのは、ここ数年の話と言える。
押し寄せる進化と変化に対し、多くの人は息つく間もなく、ほとんど無防備に向き合っている。私たちはスマホとともに、この先どこへ向かうのか、果たしてそこに、想定外の事態が待ってはいないだろうか。」p.10
読んでいくと、4年前とは思えないくらいに今日の状況を先取りして語っているように感じる。逆に言うと、今日の状況は、この本が書かれた頃よりもはるかに先を行っている状況になっていると考えられるわけで、ちょっとコワい気がする。(笑)
第1章の「子育ての異変」 では、以下のような話が語られる。(太字、画像は引用者)
「取材の際にも、「教えてもいないのに、子供がスマホを操作をすぐに覚えた」とか、「ひとりでどんどん使っている」といった声がたくさん上がるが、要はスマホを与えさえすれば幼児はたやすくおもちゃ代わりにしてしまう。」p.29


これが、4年前の 2017 年である。話はさらに続く。
「外出先でもスマホは必須アイテムだ。特に病院や役所などの公共の場所では、子どもが騒いで周囲の迷惑にならないようにと必ず使わせている。スーパーで買い物をする際、「お菓子が欲しい!!」と駄々をこねる娘たちに対し、お気に入りのゲームをさせて落ち着かせることもある」p.32


なるほど・・・。(笑)
「家事の間もスマホを与えておけば安心だ。子どもがおとなしく座っているうちに揚げ物をしたり、食器を洗ったり、ベランダで洗濯物を干したりできる。単に家のことが片付くという話ではなく、子どもが調理器具にさわってヤケドをするような危険も防止できるから「一石二鳥」だと笑う。」p.32


あまりにも説得力がありすぎて(笑)、ちょっとコワくなるのはわたしだけであろうか? 次には子育てママのナマの声がそのまま引用される。
「「世間では、スマホなんかに頼って子育てをして、と批判もあるでしょう。でもそれは、今の子育てを知らない人の考えだと思いますね。以前から子どもをおとなしくさせるのに、テレビを見せたり、お菓子を食べさせたりしたでしょう。そういう形がスマホに替わっただけの話です。現実に役に立っているし、子どもも喜んでいる。わたしのストレスだって減るから、結果的には子育てがうまくいくことになるんじゃないでしょうか。」」p.33


ムムムムム・・・。いやはや、庶民の論理のしたたかさに、ちょっとクラクラしそうである。(笑)しかも、これは4年前である!さらに追い打ちをかけるように別のママの声が続く。
「「ママ友同士でもこどものスマホ利用を話題にすることがありますが、私の周囲ではみんな肯定派です。いつでもどこでも使えるし、子どもの反応もいい。なんといってもお金と手間がかからないことが大きいです。クレヨンやノート、おもちゃ、絵本、そういうものを買わなくてもスマホだけあればいろんな遊びができます。しかも新作がどんどん出るので、飽きっぽい子どもにはピッタリだと思います。ちょっと遊ばせてまた次、今度はこれと試そうってできるから、タダで使えるおもちゃ箱を持っているようなものですよ。」」p.34


うーむ、スマホ依存もここまで開き直られて自己正当化されると、「もう勝手にしろや!どうぞ、どうぞ!」と言いたくなる。まあ、これが現実なのであろう。(笑)


そして、これは4年前の 2017 年の話なので、4年後の現在(2021年)では、母親と幼児のスマホ依存はさらに深まっていて、もはや “スマホなしの子育て” はあり得ないくらいになっているのではないか?(笑)
第4章の「エンドレスに飲み込まれる人々」 では、以下のような話が語られる。(太字、画像は引用者)
「ところが今、自分の意思とは無関係に、否応なくスマホを手放せない人たちが現れている。業務用、会社支給のスマホを使うことで位置情報やリアルタイムの状況を管理され、延々と拘束されてしまうのだ。」p.165
“デジタル的監視社会” は中国のことかと思っていたら、自由と民主主義の日本でもじわじわと同等の監視システムが “政府” よりも “民間” から広がりつつあるようだ。(笑)
「スマホを使った勤怠管理や行動把握、場合によっては物理的、精神的な監視下に置かれるような状況も出現している。」p.165
「飲食店向けの店舗管理を行う会社で営業職をする山本(仮名・30歳)は、「会社支給のスマホを使うと、自分が奴隷になったような感覚です。」と嘆息した。現在地や移動ルートがスマホのGPS 機能で上司に把握され、一日の行動を監視されているという。」p.166
これはほとんど ジョージ・オーウェルの「1984年」の世界 だ。(笑)
この話は2017 年の話だ。4年後の今の状況をちょっとネットで調べてみた。以下は 2021年 のデータである。

「スマホの会社支給は半数以下」と言っているが、“半数近くもある” ことに驚くのは、わたしだけであろうか?


しかも、昨今では、“業務用に特化したスマホやタブレット” もかなり出回っているではないか!もう逃げ場はない!(笑)






「スマホの危険性」 とは?
さて、一般的に、携帯電話やスマホの 「危険性」、「ヤバさ」 というと、日本では
1)「ネット上で金銭や個人情報等が騙し取られること」 と、
2)「特に未成年がネット犯罪に巻き込まれること」
の2つが問題になるようだ。



どちらも、要するに “ネット犯罪の被害者になる可能性” であり、日本ではそれを 「スマホの危険性」 と言っているようなのだ。この 「危険性」 とは、けっきょく金銭的被害、精神的被害、性的被害のいずれかである。
なぜか日本では スマホの電磁波による物理的で日常的な “健康被害” については、ほとんど問題にされない。
実際、この「スマホ廃人」 という本でも、「スマホの危険性」 として、特に未成年の女子のケースを取り上げているが、“電磁波による健康被害” については、まったく言及がない。あまりにも庶民目線で問題を追っているとこうなるのだろう。実際、海外の動向への目配りが乏しく、せいぜいが「スティーブ・ジョブズは子供にスマホを与えなかった」 というような話どまりだ。(笑)けっきょく、日本の大衆の度の過ぎたスマホ依存を面白おかしく紹介しているのにとどまっている印象だ。
たしかに、“ネット犯罪の被害者になる可能性” は存在することは存在するが、これが主たる危険性と認識されている日本に対して、海外では別の危険性も問題になっていることも触れるべきではないか?
以下の検索結果は日本語と英語で比べたものである。images で検索すると、カテゴリー別になって表示されるので、全体像を把握しやすいメリットがある。それをさらに色分けしてみた。

日本語で 「スマホの危険性」 を検索した結果では、ネット犯罪、つまりセキュリティ関連の危険性(黄色の枠)が圧倒的に多く、カテゴリの半数を超える。“oppo” や “中華スマホ” が出てくるのは、個人情報が中国に盗まれるという、セキュリティ上のリスクによるものであろう。
そして、次に来るのは、「歩きスマホ」等の、スマホによる不注意事故(緑の枠)のリスクに関したものである。スマホの危険性としては、主なものはこの2種類だけである!
以下は、英語で検索した結果である。ただし、なぜかフランス語の検索結果も混じっている。

■ 黄色の枠 は、日本にもある “セキュリティ上のリスク” であり、未成年(teens, children, teenagers)に対する懸念が海外でも現れている。しかしそれでも全体の4分の1ほどだ。
■ 赤枠 は、“電磁波” “健康” に関したリスクである。これは日本語での検索ではほとんど出てこないものだ。この重要なカテゴリーが丸ごと抜け落ちて、黄色と緑の枠だけになっているのが日本なのだ。
■ 紫色の枠 は、“スマホ依存” の危険性である。これは今回取り上げたほとんどのスマホ本の中心的テーマでもあり、事実としてはたしかに日本にも存在している。しかし、日本語で「スマホの危険性」で image 検索してもカテゴリとしては出てこないのだから、問題意識としては日本では表面化していないことを物語っていると言える。しかし、海外(英語、フランス語圏)では、“addiction 依存” “スマホ依存 smartphone addiction” としてキーワード化している。
日本では、“歩きスマホ” で人にぶつかることを除けば、“ネット犯罪“ に巻き込まれるリスクこそが “スマホの危険性” の最大のものと認識されているようだ。
海外でももちろんネット犯罪は存在し、当然その被害もあるが、“スマホの危険性” としては、“電磁波” や “依存性” も問題になっている。
“セキュリティ上のリスク” はたしかに存在するが、誰もが日常的にその被害を受けているわけではなかろう。スマホを使う老若男女が 金銭的被害、精神的被害、性的被害 を日々こうむっていると言えるだろうか?せいぜい、「そういうことも起きるかもしれないから、注意しよう」 という程度のことだろう。
しかし、スマホの電磁波による直接的で物理的な被害である、“健康被害” はスマホを使う老若男女が日々リアルタイムでこうむっている実害である。


ただ、電磁波が人間の目には見えないだけである。さまざまな健康障害が発生しているのだが、まさか目にも見えない電磁波が原因だとは思わないのだ。しかし、海外では目に見えなくても、実際に健康被害に関連付けられて問題視されているという現実がある。


どうやら日本ではマスコミと電通が巧妙に操作して、最も重大な “電磁波の危険性” を隠蔽するために “ネット犯罪の危険性” を過剰に警告している疑いすらあるように思う。つまり、スマホ、携帯電話、WiFi、インターネットといった “無線通信インフラに関しての危険性” には、セキュリティ(PCウイルスワクチン、フィルタリング等)の向上で十分に対処できるような錯覚を与えているのだ。手品のような “問題のすり替え” である。(笑)
さて、今回取り上げた6冊の “スマホ本” の中で “電磁波の危険性” を問題視している唯一と言っていいほどの本が、以下の最後の本である。
6.「スマホ汚染」 古庄弘枝 鳥影社 2015
この本のサブタイトルは「新型複合汚染の真実!」 であり、ノンフィクションライターである著者の問題意識はかなり広範で、しかも掘り下げも深い。今まで見てきた5冊のスマホ本はすべて新書本であるが、この本は単行本で 500 ページもある労作である。




タイトルに 「スマホ」 が入っているが、スマホが最も身近な電磁波源であり、著者は電磁波の危険性を特に問題視しているからである。
それでは、この本は電磁波の本なのかと言うと、そうとも言えない。著者が危険とみなすものは、まだ他にもある。
右の、本の赤い帯の裏表紙部分をご覧いただきたい。
著者は、今日 “環境破壊” がさまざまなレベルで進んでいることに警鐘を鳴らしている。もちろん、その筆頭は “電磁波環境の破壊” である。その最も身近な例として、スマホがあるということだ。電磁波(電磁放射線)には以下のように自然のものと、人工的なものとがある。

著者にとって、電磁波問題はスマホに限定されない。当然だろう。スマートメーターも、WiFiも、5Gも、ユビキタス社会も根は同じで、“人工の電磁波” が問題なのである。
それでは、人工の電磁波の何がいけないのか? すでに上でも論じたが、筆頭は “健康被害” である。以下のリストをじっくりご覧いただきたい。あなた自身に該当する項目はゼロだろうか?

すでに前記事で取り上げた4冊目の 「その「もの忘れ」はスマホ認知症だった」 奥村歩 青春新書 2017 では、以下のような文があった。
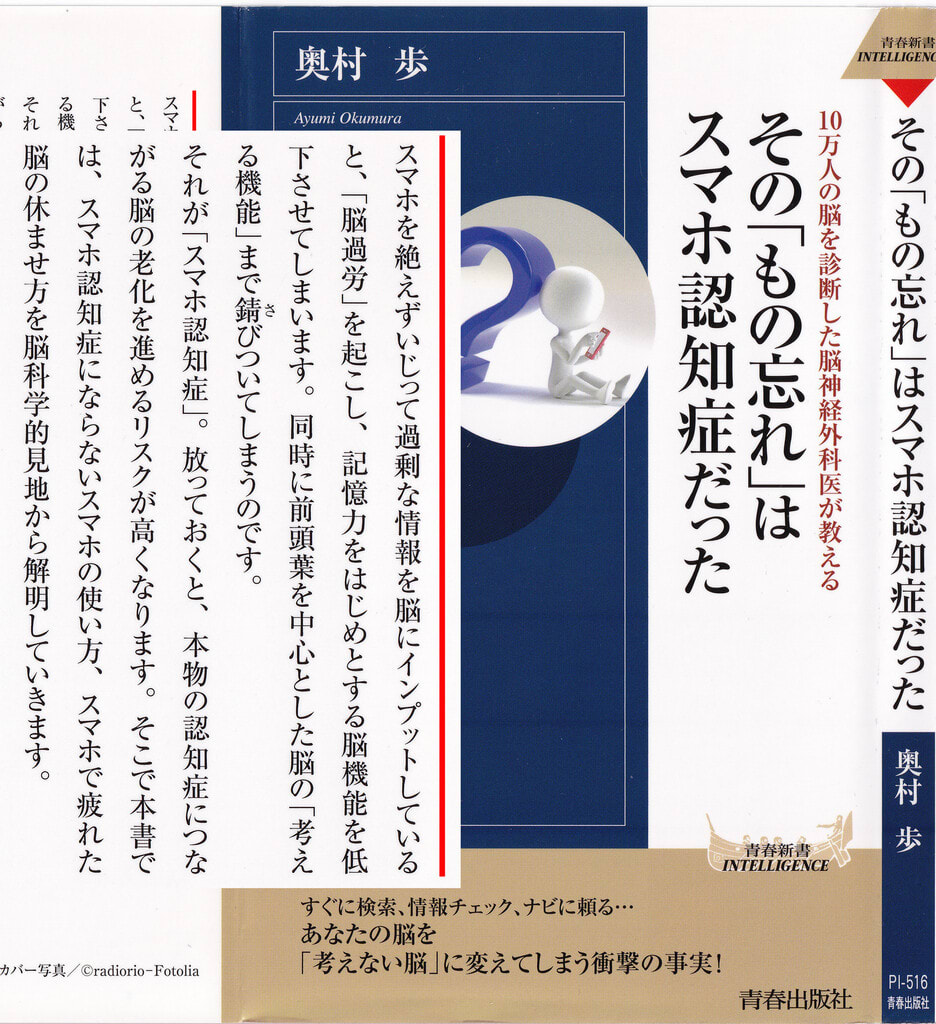
「「スマホ認知症」や「脳過労」の患者さんは、記憶力低下やもの忘れ以外にも、決まって多くの体調不良を訴えられます。具体的に症状を挙げると、だるさ、疲労感、頭痛、めまい、不眠、肩こり、腰痛、冷え、動悸、息切れ、吐き気、便秘、下痢、胃痛、腹痛、食欲不振など。」p.44
ほとんどの “スマホ本” は、“電磁波源” としてのスマホの有害性、危険性に触れようとしない。まるで、“電磁波問題” が “マスコミ業界におけるタブー” であることをあらかじめ知っていて必死に避けているかのようなのだ。(笑)
なお、電磁波源としては、基地局アンテナ や WiFi や 5G といった、スマホ使用を可能ならしめるインフラ全体としての電磁波環境を想定すべきである。
“スマホ” は誰の目にも見え、文字通り手で触れることもできる。しかし、それを “ワイヤレス通信端末” として機能させている “電磁波じたい” は目には見えないのだ。
現代社会において、多くの人たちはこうした目に見えない濃密に錯綜する有害な電磁波の海に浸かって生活している。しかし、どっぷり浸かっていても、目には見えないので、ほとんどの人はそんなものはあたかも存在していないかのようにして毎日生活している。
ここが多くの “スマホ本” に共通する “スマホ元凶論” の落とし穴であり、多くの人々の盲点なのだ。医師や精神科医はたしかに専門家であろうが、電磁波は専門外だ。そして、専門家ほど自分の専門外のことについて語ることはタブーと思って、自分のタコツボから脱け出せない。そして、自分の専門分野から一歩も出ずに “スマホ元凶論” でほとんど説明ができる錯覚に陥るのだ。
アフリカから日本に来た人が、「おみやげに何がほしいですか」と聞かれて「水道の蛇口」と答えたことがあるという。蛇口をひねるだけで安全な水がいくらでも出てくる “恩恵の源泉” だからだ。

スマホを問題にする多くの人々は、電磁波を使ったワイヤレス通信のインフラが視野に入っていないので、端末に過ぎない “スマホ” という道具が “恩恵の源泉” から今度は “諸悪の根源” に変わっただけなのだ。水道の端末に過ぎない “蛇口” しか見えていないのと同じなのである。(笑)


さて、「スマホ汚染」の著者は、特定の分野の専門家ではない強みもあってか、より広い視野で物事や問題を見ることが出来ているように思える。実際、海外の動向への目配りも怠らない。
この本の目次をお見せすれば、どれだけ広く、深く掘り下げているかがわかろう。とは言え、本書は大著であるので、12章あるうちの5章までである。それでも大変な量だ。それぞれの章に赤で見出しをつけてみた。



「その「もの忘れ」はスマホ認知症だった」の著者は、以下のように語っていた。
「そして、「スマホ認知症」や「脳過労」をちゃんと治さずに、こうした不調症状を放っていると、ほとんどの方がうつ病に移行していくようになる」p.44-45
こう語る著者は「日本うつ病学会」の会員でもある。
脳波は超微弱な電磁波である。
スマホ、WiFi の電磁波は非常に強く激しいマイクロ波という電磁放射線である。
強烈な人工的電磁放射線が人間の脳や精神状態に何らかの悪影響を与える可能性は皆無だろうか?
1から5までのスマホ本のすべてにおいて、子どものスマホ使用に関しては、たしかに強い警告がなされている。子どもの方が “スマホという依存物” に対して大人よりも無防備だから、はまりやすいからというのがその理由のようだ。そして、「スティーブ・ジョブズは子供にはスマホやタブレットを与えなかった」という話などにつなげて、ネット時代の輝かしいヒーローの権威にひれ伏しているのだ。(笑)

しかし、今まで見てきたスマホ元凶論の5冊のいずれも、“子どもの方が大人よりも電磁波に対して、より無防備で、より悪影響を受けやすい” という “物理的、解剖学的現実” についての言及はいっさいないのだ。

そもそも 「電磁波」 という単語すら、1~5の新書版の5冊にはいっさい出てこないのだ。けっきょく “スマホ” を “ポケットに入る蛇口” のようにしか捉えられていないのだ。情けない限りである。(笑)



さて、最後に紹介した 「スマホ汚染」 は、実は6年前に出版された 2015 年に、すでにわたしは読んでいる。今回、他の5冊を読んだ後にあらためて読み直したが、最初に読んだ時のインパクトがよみがえってきた。わたし自身、この本の影響を受けていると思う。振り返ってそう思う。スマートメーターの危険性を知ったのもこの本のお陰であったと思う。
この本は、スマホを入り口として “電磁波問題” を広く扱っているという意味で、他のスマホ本の中でも頭一つ抜きん出ていると言える。6年経った今でもそうなのだ。
残念なことだが、他のスマホ本が 「群盲象を撫でる」 のレベルにとどまっているのだ。
スウェーデン人は除外するとして(笑)、他の新書本の著者たちは執筆前に 「スマホ汚染」 を読んでいないのだろうか?もし読んでいないとしたら、同じく 「スマホ」 を含んだ書名の本を書く立場として、まったく調査不足、勉強不足であろう。
仮に読んでいなくても、スマホという “無線通信端末” についての本を書くのであれば、それを機能させている “電磁波” について何らかの言及があってしかるべきであろう。
逆に、読んでいるのだが、それでも電磁波については敢えていっさい触れていないのだとしたら、非常に偏屈な発想であり、却って視野の狭さをさらけ出す結果になっている。
“スマホ” には以下の3つの側面がある、とすでに書いた。
1)ワイヤレス同時通信端末(多機能携帯電話)
2)依存物
3)有害な電磁波源
スマホの “電磁波源” としての側面と言うと、“点” のイメージがあるが、実際は社会を覆う “面” である。つまり、“電磁波環境” なのである。より正確に言えば、“社会のワイヤレスインフラを支える人工的電磁波層” である。
この “人工的な電磁波層” は、現代の科学技術をもってしても、人間を含む生命全般にとって無害なかたちで成立させることは不可能である。ということは、そうした “人工的な電磁波層=スマホの電磁波” は、原理的に 人体や地球の生命全般にとって有害かつ危険なものである。
そして、この “人工的電磁波層” は “5G” などによって、ますます濃密に人間社会にのしかかっているのだ。
非常に危険なものなのであるにもかかわらず、この電磁放射線は単に「目に見えない」というだけで、問題にされていない。それどころか、目に見えない電磁放射線の危険性を語ると、“オカルト扱い” するおかしな人間もいるほどだ。(笑)
しかし、原子力(核)発電所が事故の際に放出する “放射線” も帯域は異なるが、同じ “電磁放射線” であり、同じように目に見えないことを忘れてはいけない。

以下の1~5のスマホ本は、“ごく狭い可視光線の帯域” の範囲で物事を見ているようなものだ。
それに対し、6のスマホ本は “より広い不可視の帯域” までも視野に入れて物事を論じていると言える。
1.「スマホ脳」 アンデシュ・ハンセン 新潮新書 2021 ★★★☆☆
2.「スマホ依存から脳を守る」 中山秀紀 朝日新書 2020 ★★★☆☆
3.「スマホが学力を破壊する」 川島隆太 集英社新書 2018 ★★★☆☆
4.「その「もの忘れ」はスマホ認知症だった」 奥村歩 青春新書 2017 ★★★☆☆
5.「スマホ廃人」 石川結貴 文春新書 2017 ★★★☆☆
6.「スマホ汚染」 古庄弘枝 鳥影社 2015 ★★★★★
















