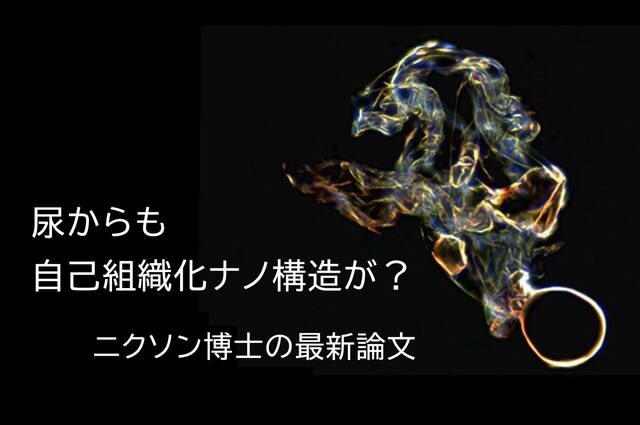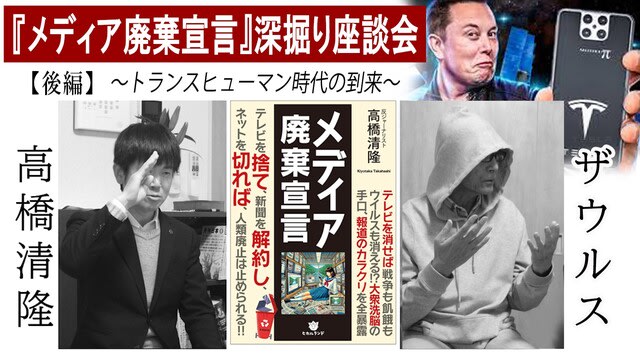13年間 gooブログで続けてきましたが、このたびWordPressブログに引っ越しましたので、以下にご案内いたします。● 引っ越し先URL: https://zaurus25.com/● ブログタイトルは従来と同じ 「ザウルスの法則」● 従来より見やすく、検索しやすくなりました ● 記事も画像もコメントもほぼすべて再現しています● goo ブログじたいが11月に完全終了します● こちらに書き込ん . . . 本文を読む
原題:Self-Assembling Nanostructures in Blood and Urine: Implications for Bioaccumulation and Detoxification「血液と尿における自己組織化ナノ構造:生物蓄積と解毒への影響」この論文は34ページに及ぶ非常に長いものなので、この紹介記事では要約だけにして、別に日本語に翻訳したPDF をダウンロードできる . . . 本文を読む
謎の MAC アドレスを深掘りする?(2)ノイズの中の信号前記事(1)よりも深掘りしており専門的で難解だが、興味のある読者はきっとわくわくするような内容である。元記事:Back to the MAC (Part 2): The Signal in the Noise==============================MACに戻る(パート2):ノイズの中の信号デビッド・ニクソン こんにちは、 . . . 本文を読む
謎の MAC アドレスを深掘りする?(1)接種者の体内からのブルートゥース信号以下の記事は、COVIDワクチン内の反応媒体が自己構築する様子を世界で初めて動画撮影に成功して公開した David Nixon 博士の最近の記事の翻訳である。元記事: Back to the MAC内容はBluetooth に関するもので、かなりテクニカルで難解であるが、非常に重要な内容であることは間違いない。私自身理解 . . . 本文を読む
以下は、オーストラリアのデビッド・ニクソン医学博士の記事である。ザウルスも高く評価する「Invisible Rainbow」の著者アーサー・ファーステンバーグ氏が今年2月に死亡しており、その原因がどうも誤ったアーシングと思われるという記事である。ファーステンバーグ氏は自身が電磁波過敏症でもあり、電磁波の危険性について警鐘を鳴らす世界的にも知られた研究者であった。その彼が自らの電磁波被害を軽減する目 . . . 本文を読む
『メディア廃棄宣言』深掘り座談会 後編 ~トランスヒューマン時代の到来~以下の記事は、前記事 “「メディア廃棄宣言」深掘り座談会 前編“ に続く後編である。この座談会の企画と当日の司会を務めた山田宏道氏が執筆したものであり、ザウルスはここでは場所の提供だけをしている。=============================================== . . . 本文を読む
昨年11月に高橋清隆著の「メディア廃棄宣言」が出版された。以下の記事は、昨年12月に収録した座談会「メディア廃棄宣言」の企画と当日の司会を務めた山田宏道氏が執筆したものであり、ザウルスはここでは場所の提供だけをしている。==========================================================寺野ザウルス氏、 高橋清隆氏、 司会:山田宏道『メディア廃棄宣言 . . . 本文を読む
抗生剤に耐性を持つ細菌が増加、無線周波数電磁波が原因という報告も (元記事:加藤やす子ウェブマガジン)スウェーデンのオッレ・ヨハンソン博士は、抗生物質の効かない多剤耐性菌が増える原因といてWi-Fiや携帯電話の電磁波への被曝が関与している可能性を警告する文書を発表しました。ヨハンソン博士は、カロリンスカ研究所神経科学部の元・研究者で電磁波被曝による皮膚への影響について研究し、スウェーデン王立工科大 . . . 本文を読む
未接種の10代の血液中でナノテク構築物が急成長? トランスヒューマンは電子奴隷?
以下にアナ・ミハルシア氏の最新の記事をご紹介する。いちばん重要な個所は赤字にしてある。
青字は本記事へのザウルスによる注、その他
原題:ナノボットとマイクロロボットのミセルメッシュネットワークがCOVID19未接種の10代の血液を変換Nanobot and Microrobot . . . 本文を読む
「接種して世界を救う」と思ってた? 大義に弱い日本人?
大挙してコロナワクチンを打っていた国民の大半にとって、ワクチン接種は単に「恐ろしい感染症の予防」というネガティブなだけのものではなかった?
21世紀の人類が直面した 「人類存亡の未曽有の危機」 を、「ワクチンという人類の叡智の結晶」 によって乗り越えるという「壮大でヒロイックなドラマ」として捉えていたひとがかなりいた?
. . . 本文を読む