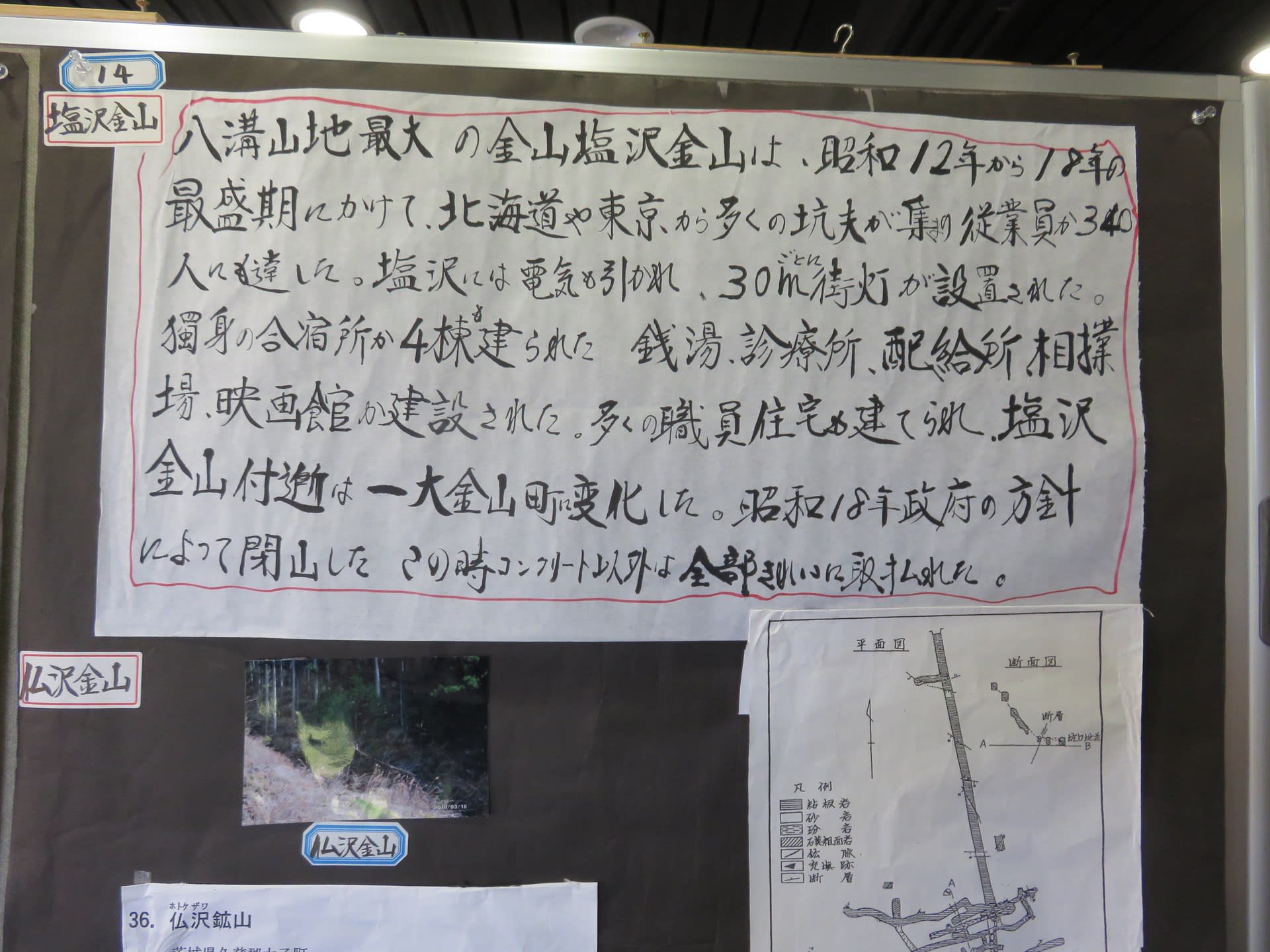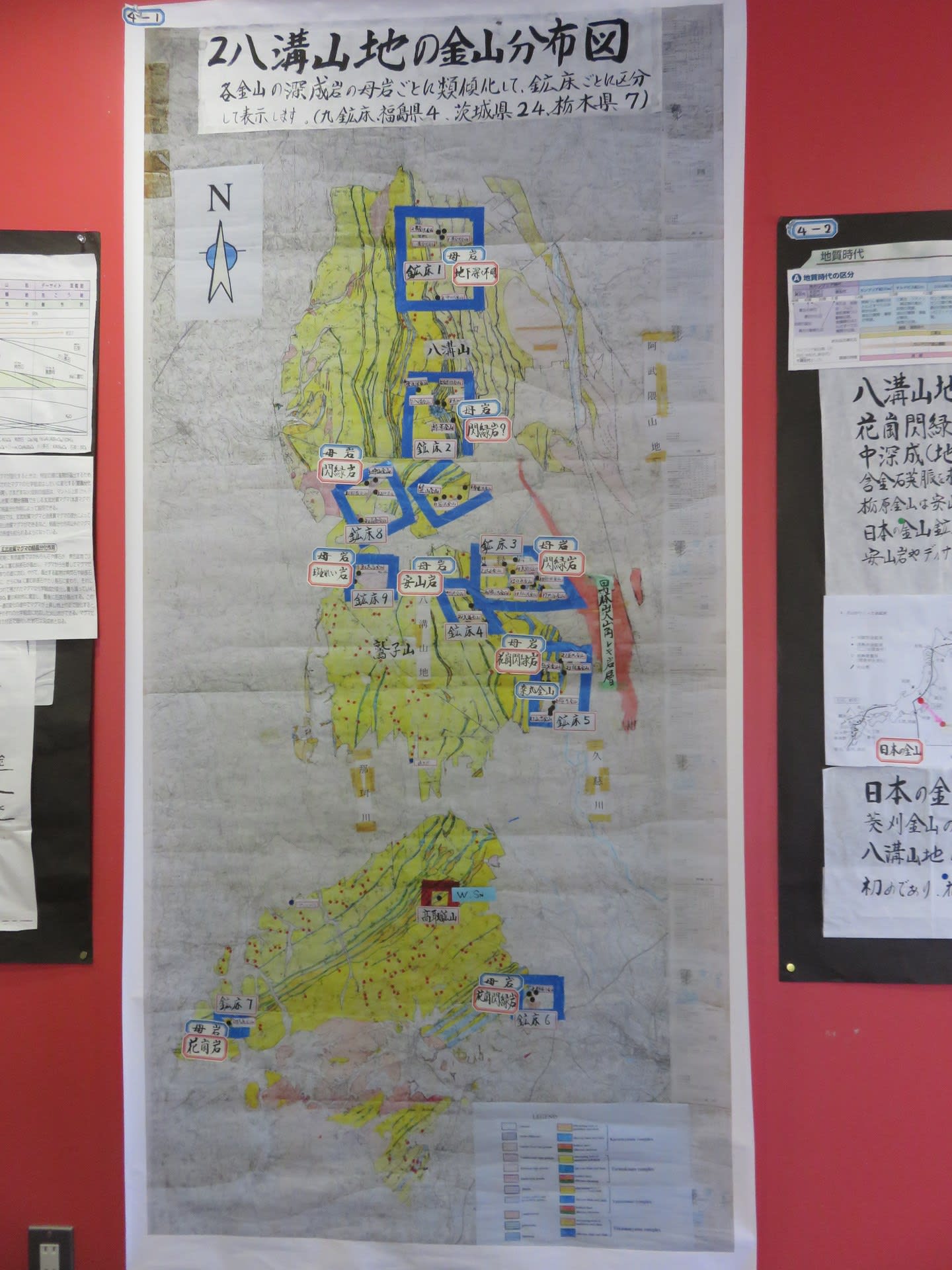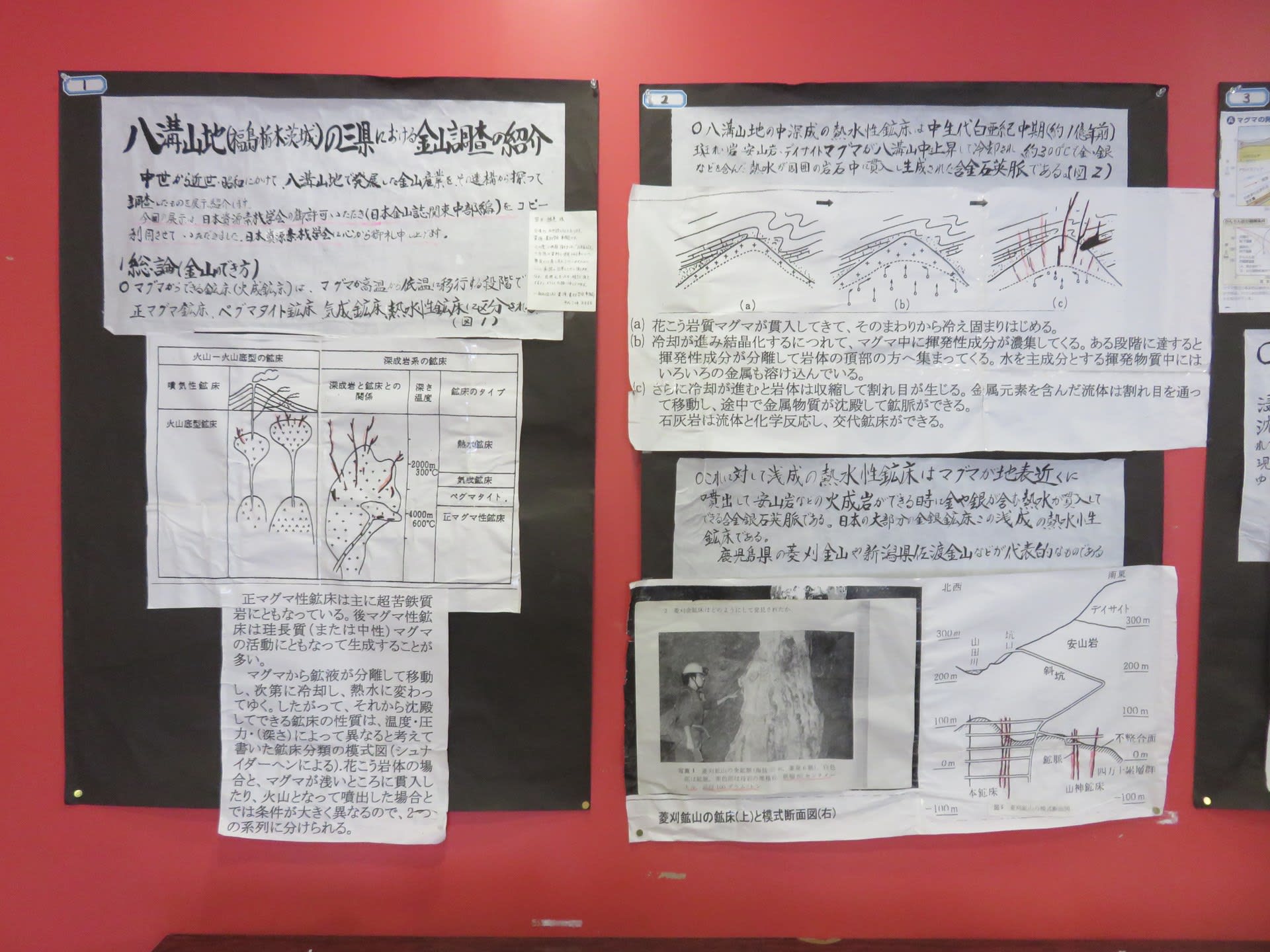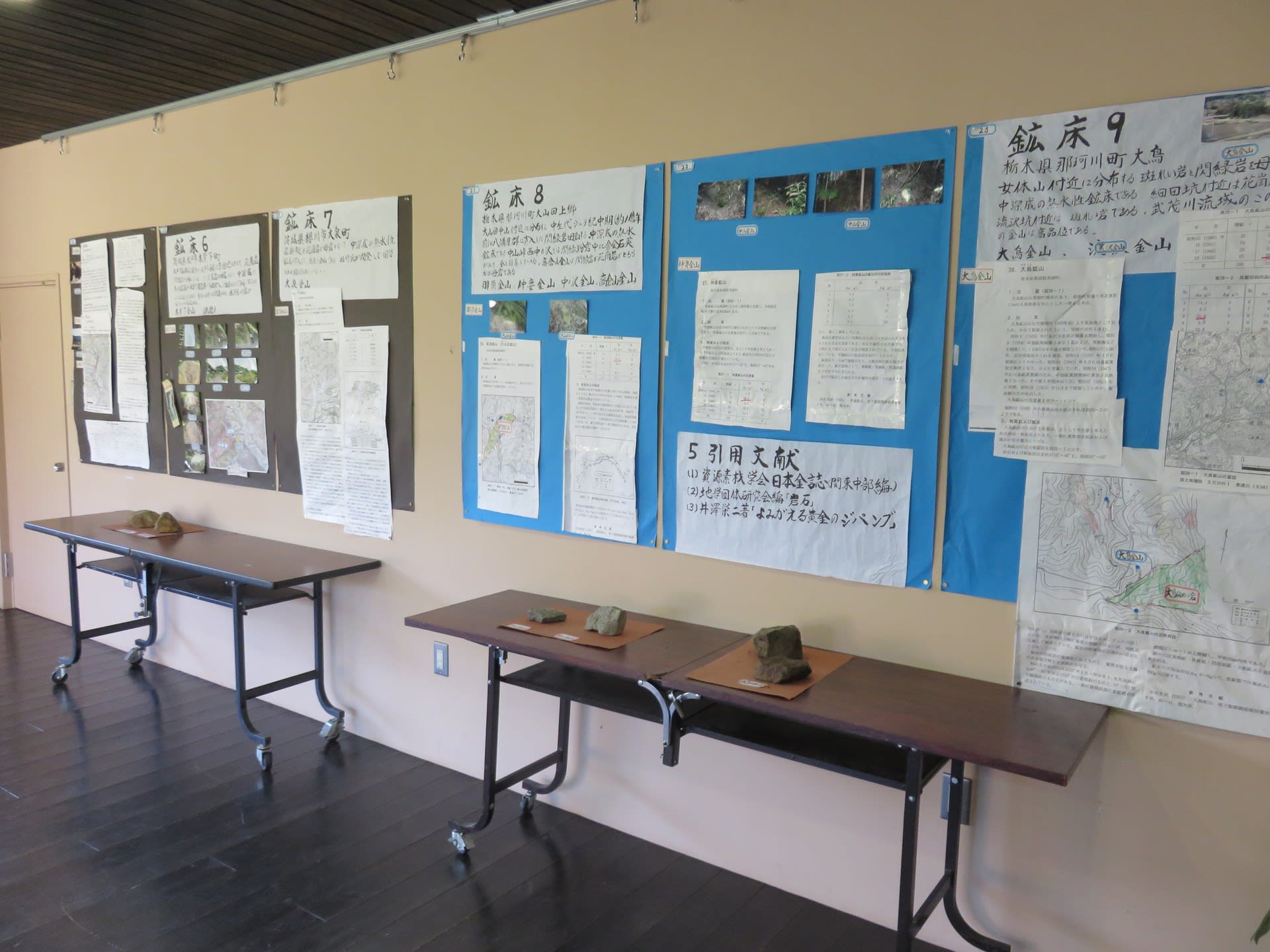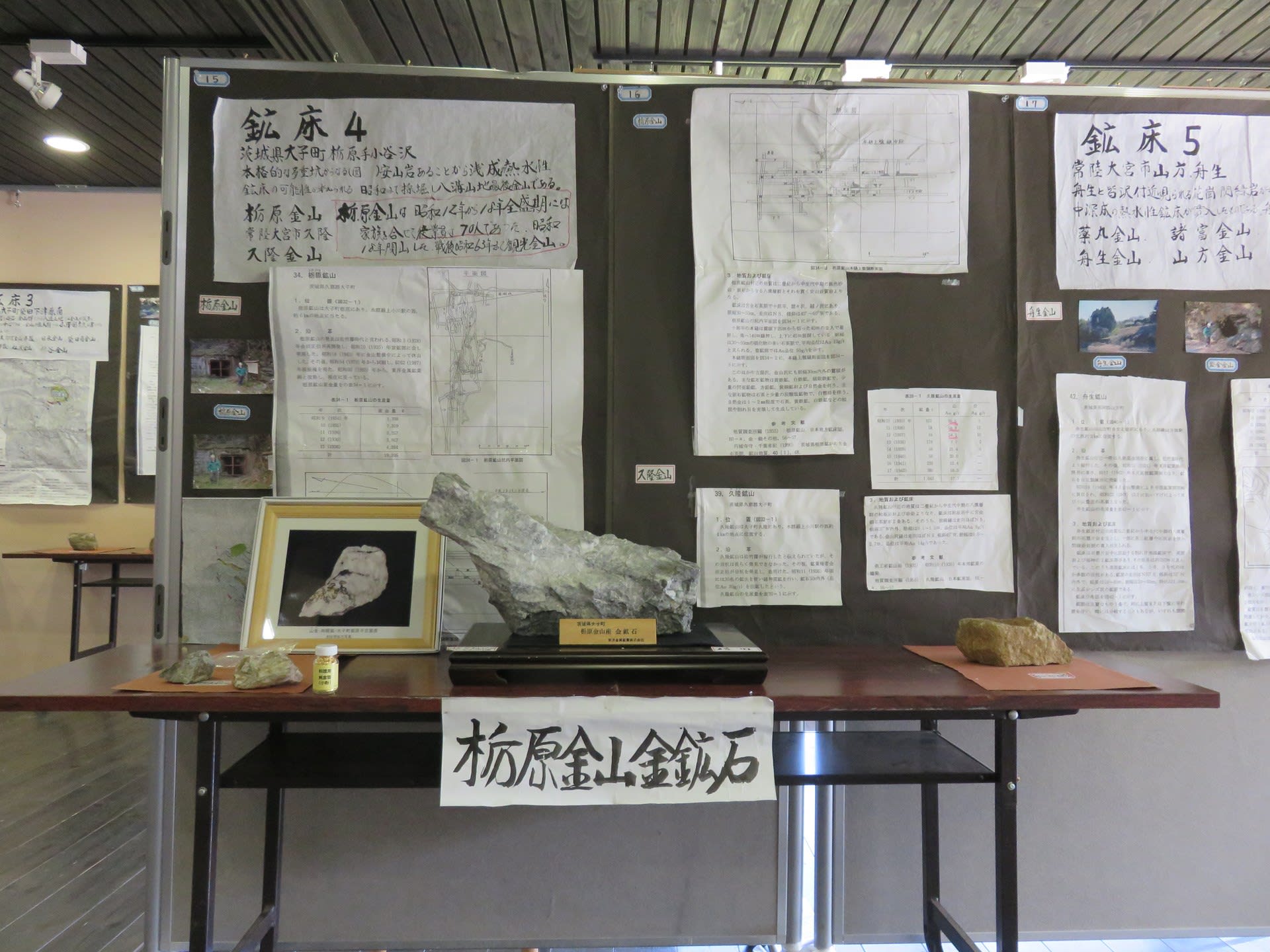赤十字奉仕団の意識高揚や団員同士の親睦を目的に実施された
目的地は東京都芝公園にある「日本赤十字社本社」
午前7時すぎ市役所へ、参加者は39名
団員は主に区長や民生委員、ボランティア活動に携わる人たちだ
高速道の渋滞もあり約3時間かけ首都高速の芝公園を降りた
日本赤十字社は都心の真ん中にあり、ここが赤十字社の本社?と
研修は赤十字の創始者アンリ・デュナンの説明から始まった
様々な業績、赤十字の役割と活動、災害地支援の現状などを約1時間30分かけ説明いただき
館内の見学を行った、会議室は有名な絵画が飾られシャンデリアで飾られていた
貴賓室は絨毯に傷がつくとして入口から眺める程度の見学だった
貧困や傷病に対処している赤十字の本社に「なぜこのような豪華な設備が必要か?」の痛切な疑問が残った!
午後、明治神宮へ参拝のため、向かった



今日はここで「高円宮家の三女絢子さまの結婚式」が行われていてたいへんな人出だった
警備もすごかったが、明治神宮につながる参道には数えきれないほどの奉祝提灯と日本国旗が飾れていた
結婚式が終わったころの参拝だったため、もう少しで絢子さまが出てこられると「大変な人垣」ができていたが、待つことなくバスに乗車した
目的地は東京都芝公園にある「日本赤十字社本社」
午前7時すぎ市役所へ、参加者は39名
団員は主に区長や民生委員、ボランティア活動に携わる人たちだ
高速道の渋滞もあり約3時間かけ首都高速の芝公園を降りた
日本赤十字社は都心の真ん中にあり、ここが赤十字社の本社?と
研修は赤十字の創始者アンリ・デュナンの説明から始まった
様々な業績、赤十字の役割と活動、災害地支援の現状などを約1時間30分かけ説明いただき
館内の見学を行った、会議室は有名な絵画が飾られシャンデリアで飾られていた
貴賓室は絨毯に傷がつくとして入口から眺める程度の見学だった
貧困や傷病に対処している赤十字の本社に「なぜこのような豪華な設備が必要か?」の痛切な疑問が残った!
午後、明治神宮へ参拝のため、向かった



今日はここで「高円宮家の三女絢子さまの結婚式」が行われていてたいへんな人出だった
警備もすごかったが、明治神宮につながる参道には数えきれないほどの奉祝提灯と日本国旗が飾れていた
結婚式が終わったころの参拝だったため、もう少しで絢子さまが出てこられると「大変な人垣」ができていたが、待つことなくバスに乗車した