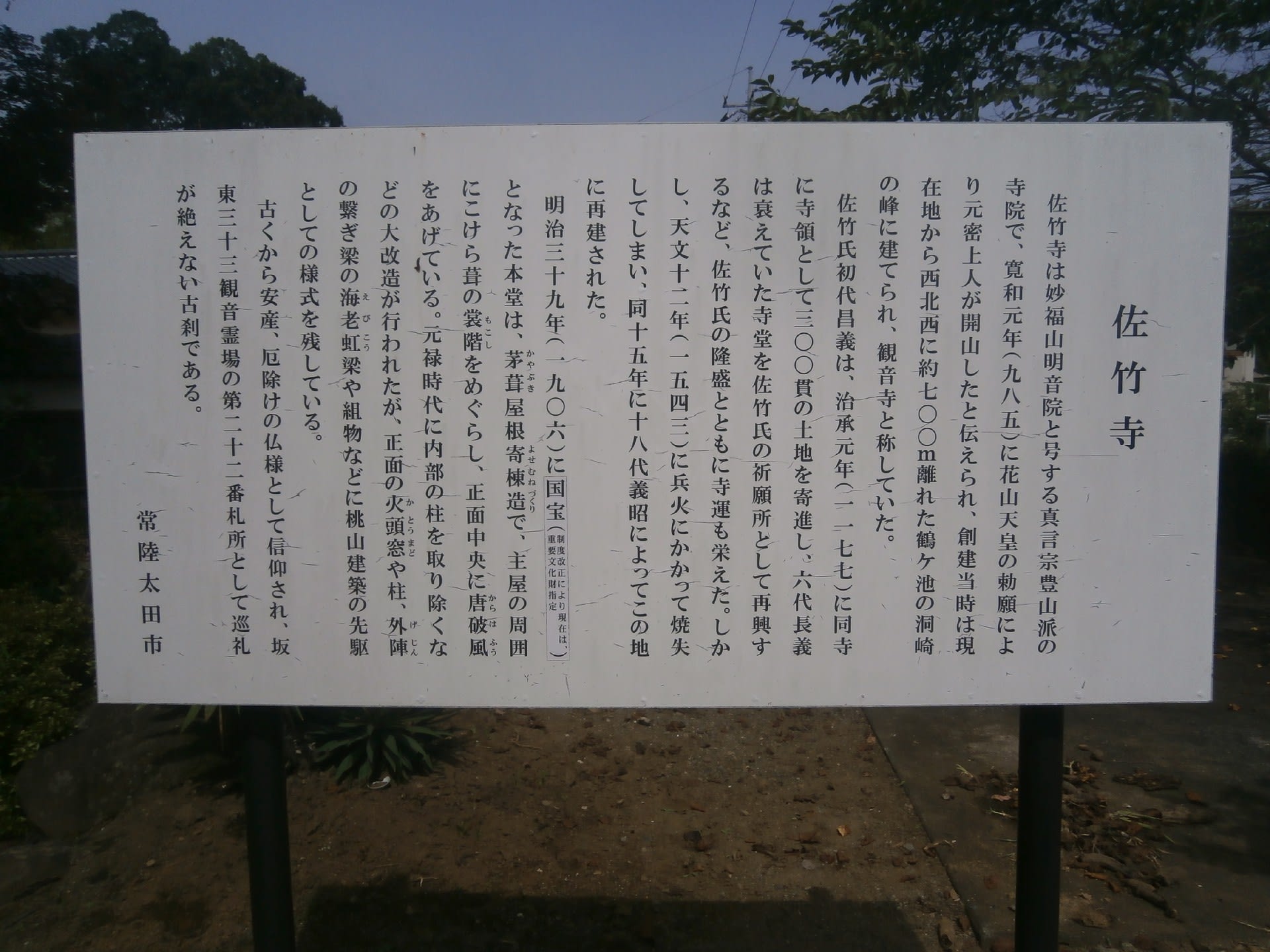日輪寺は坂東三十三観音の第21番札所
茨城県久慈郡大子町の栃木・福島県境にある「八溝山」の中腹より山頂に近い場所にある
宗派は「天台宗」
本尊は十一面観音菩薩だ
創立は西暦673年
八溝山の標高は1022mなので約300mほど下った場所にあるが、大子町を走る国道118号の分岐から入ること約20㎞
道路はやや狭くなるが完全舗装で、車の量も少なく快適な自動車登山ができる
日輪寺は「八溝知らずの偽坂東」と言われ遥拝で済ませる人も多かったほど坂東札所第一の難所だったと言われている
火災など幾多の災難を経て、昭和49年六間四面の観音堂が全国からの浄財で完成した
やっと到着し参拝しようと階段を登った

ところが「受付」の場所がないばかりか「本堂は戸閉」、御朱印はいただけないと覚悟した
しかし、本堂の扉に「留守の場合の連絡先電話番号」が貼ってあり、すぐに☎すると携帯の電波が弱く繋がらない
やむを得ず八溝山頂に向かい展望台に行くと「緊急事態宣言発令中」のため立ち入り禁止と
下山
携帯電話の感度が良くなったところで再び☎
すると住職の奥方らしき方が出て、丁寧に「御朱印は差し上げられます!」と
ナビに今から言う住所を入れて来て下さい と
言われた住所は八溝山から遠く離れた大子町池田地内
約30分ほど走り到着した
対応いただいた奥方は「今、住職は病院に出かけていて申し訳ありません!」と
それでも御朱印帳に御朱印をいただき目的を達成することができた
思いがけなく本堂および住職の住所を知ることになった