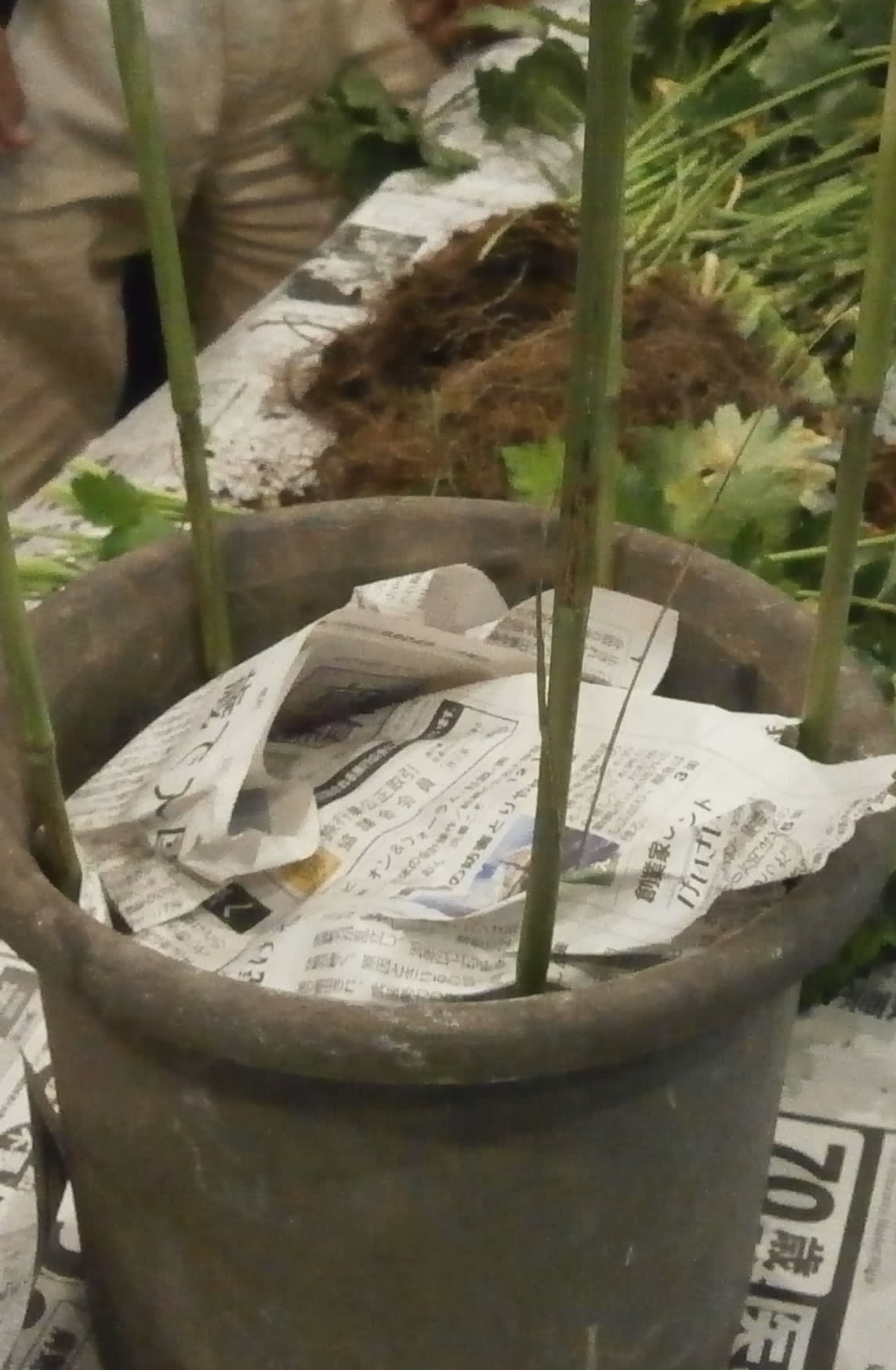毎月1回わくわく講座で園芸講座が開かれ、今日は出席した
みっちり午前10時から午後3時までの座学だった

講師の佐々木茂雄先生は「何でも知っている」
元々県の農業改良普及センター長などを歴任し、水戸市植物園では長年「みどりの相談員」などを勤めてこられた
「蘭」の研究家でもあり、水戸徳川家で所有していた膨大な「蘭」を見事に再見させたのも先生だ!
先生のもとにはたくさんの生徒もいて講師に引っ張りだこだが、いつも一生懸命だ
講座がある時は自宅で栽培し、実証済の野菜などを持参し配ってくれる
3年間先生の教えを受け、多くの野菜を栽培しそれなりの成果を得ることができた
しかし、野菜づくりは奥が深い!
土づくり、肥料、種まき、保温、水やり、摘果、追肥、殺虫殺菌、収穫など丁寧に指導をいただいた
様々な質問にも間髪を入れず即答してくれ嬉しかった!
来月は恒例のそば打ち講習会が予定されている
講座の会場はいつも水戸市小吹町にある「水戸市植物公園研修室」だった
広大な敷地には大温室をはじめ、多種多様な植物が植えられ入園者を喜ばせてくれている
その中、研究室前の池の周囲には「落羽松(らくうしょう)」があり、今丁度紅葉を迎えていた



「松」でありながら落葉する、湿潤地における生育に適しており、長期間の水没に耐えることができる。
普通の場所に植栽すると気根を出すことはないが、湿潤地に生育すると独特の気根を形成する。
新緑も見事だが紅葉も見ごたえがあった
ぜひ訪ねてほしい
みっちり午前10時から午後3時までの座学だった

講師の佐々木茂雄先生は「何でも知っている」
元々県の農業改良普及センター長などを歴任し、水戸市植物園では長年「みどりの相談員」などを勤めてこられた
「蘭」の研究家でもあり、水戸徳川家で所有していた膨大な「蘭」を見事に再見させたのも先生だ!
先生のもとにはたくさんの生徒もいて講師に引っ張りだこだが、いつも一生懸命だ
講座がある時は自宅で栽培し、実証済の野菜などを持参し配ってくれる
3年間先生の教えを受け、多くの野菜を栽培しそれなりの成果を得ることができた
しかし、野菜づくりは奥が深い!
土づくり、肥料、種まき、保温、水やり、摘果、追肥、殺虫殺菌、収穫など丁寧に指導をいただいた
様々な質問にも間髪を入れず即答してくれ嬉しかった!
来月は恒例のそば打ち講習会が予定されている
講座の会場はいつも水戸市小吹町にある「水戸市植物公園研修室」だった
広大な敷地には大温室をはじめ、多種多様な植物が植えられ入園者を喜ばせてくれている
その中、研究室前の池の周囲には「落羽松(らくうしょう)」があり、今丁度紅葉を迎えていた




「松」でありながら落葉する、湿潤地における生育に適しており、長期間の水没に耐えることができる。
普通の場所に植栽すると気根を出すことはないが、湿潤地に生育すると独特の気根を形成する。
新緑も見事だが紅葉も見ごたえがあった
ぜひ訪ねてほしい