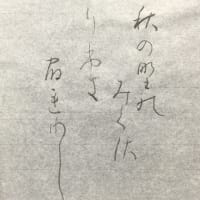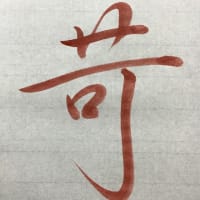まず姿勢をチェックしてみましょう。
机と身体の間は、こぶし一つ分空けましょう。
机の高さがおへその位置にくるように座りましょう。
机と両肩が平行になるようにしましょう。
その姿勢のまま、上体を前に軽く倒します。
お殿様のように背筋が床に垂直な状態で、腕を伸ばしきっては書けませんからねwww
次は、紙の位置をチェックしましょう。
筆先を利き目の下で書くのがよいとされていますから、姿勢を崩さずに書けるよう紙の位置を決めてください。
紙の上に書くなら、下敷きごと下げてください。
右に書くなら左に、左に書くなら右に紙をずらしてください。
これで、利き目の下で筆先を捉える事ができるようになります。
慣れてくるとご身体を少しずらす事で対処できるようになりますからご安心ください。
さらに慣れてくるとと、お殿様状態でも書けるようになりますから面白いですね。
もっとも、書の面白さはそこじゃありませんけれどねw
これで基本姿勢が整いました。
後は、筆を持つ親指の関節を伸ばすだけ!
それだけで肩の力が抜けるのですから不思議~
つまり、筆をガッチリ握りしめる行為が肩に力を入れてしまうことになり、上半身が固まってしまっていた原因だったのです。
筆を持つ親指を伸ばすと、力が入らなくなるので、指、肘、肩をリラックスさせて書くことができるのです。
筆を軽く握ることで、新たな書技も身につけられるようになり、書の奥義掴むには親指伸ばすことが必須条件なのです。
さあ、今日から親指伸ばしてみましょうね!
あ、ちなみに、親指の長い方は、筆管の上の方に親指を移動させるとよいでしょう。
それが次第に、手首を持ち上げて書く書法、撥鐙法(はっとうほう)に向かっていくのです。
机と身体の間は、こぶし一つ分空けましょう。
机の高さがおへその位置にくるように座りましょう。
机と両肩が平行になるようにしましょう。
その姿勢のまま、上体を前に軽く倒します。
お殿様のように背筋が床に垂直な状態で、腕を伸ばしきっては書けませんからねwww
次は、紙の位置をチェックしましょう。
筆先を利き目の下で書くのがよいとされていますから、姿勢を崩さずに書けるよう紙の位置を決めてください。
紙の上に書くなら、下敷きごと下げてください。
右に書くなら左に、左に書くなら右に紙をずらしてください。
これで、利き目の下で筆先を捉える事ができるようになります。
慣れてくるとご身体を少しずらす事で対処できるようになりますからご安心ください。
さらに慣れてくるとと、お殿様状態でも書けるようになりますから面白いですね。
もっとも、書の面白さはそこじゃありませんけれどねw
これで基本姿勢が整いました。
後は、筆を持つ親指の関節を伸ばすだけ!
それだけで肩の力が抜けるのですから不思議~
つまり、筆をガッチリ握りしめる行為が肩に力を入れてしまうことになり、上半身が固まってしまっていた原因だったのです。
筆を持つ親指を伸ばすと、力が入らなくなるので、指、肘、肩をリラックスさせて書くことができるのです。
筆を軽く握ることで、新たな書技も身につけられるようになり、書の奥義掴むには親指伸ばすことが必須条件なのです。
さあ、今日から親指伸ばしてみましょうね!
あ、ちなみに、親指の長い方は、筆管の上の方に親指を移動させるとよいでしょう。
それが次第に、手首を持ち上げて書く書法、撥鐙法(はっとうほう)に向かっていくのです。