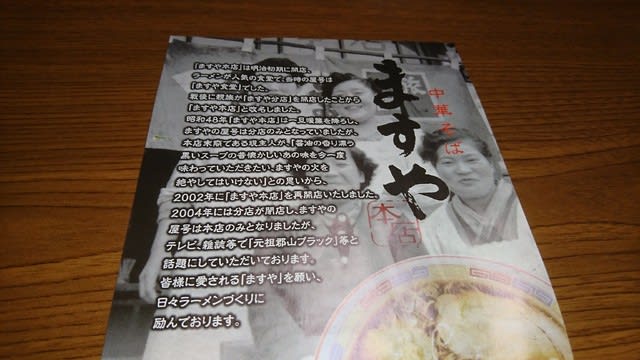山形東高校といえば、山形屈指の進学校である。
なかなか簡単には入れないが、一旦入学できれば
将来は前途洋々にちがいない。
勿論本人の努力次第だが、両親が過度に期待するのも事実だ。
東高校では来年の入試から探求科80人を募集する。
これは、平成32年度から実施される、「大学入試共通テスト」に向けての対策の一環らしい。
このテストは、思考力、判断力、表現力で評価され、より主体的に、協働的に行動することが必要になる。
数学や国語は記述式試験も導入される方向性だ。
理系は理科や数学の研究に多くの時間が費やされるらしい。
文系は国際力を強化する意味で、英語のコミュニケーション能力を磨いていくらしい。
現在の授業も教師が黒板に向かって一方的に説明するやり方から、グループセッションや教師が学生に問題点などを直接問いかける内容にシフトしてきているらしい。
東高校の学生もより考えなければならないので、だいぶ疲れるようだ。
グループで考えることも大事だが、一人個人の意見をしっかり話す習慣も重要だと思う。
話は戻るが、探求科設置によって、東大の推薦合格者も見込んでいることだろう。
東高校では、東大に10人現役合格、東北(トンペイ)には
50人現役合格を目標に掲げているそうだ。
山形東高校ならば、現実的な数字に思う。
なかなか簡単には入れないが、一旦入学できれば
将来は前途洋々にちがいない。
勿論本人の努力次第だが、両親が過度に期待するのも事実だ。
東高校では来年の入試から探求科80人を募集する。
これは、平成32年度から実施される、「大学入試共通テスト」に向けての対策の一環らしい。
このテストは、思考力、判断力、表現力で評価され、より主体的に、協働的に行動することが必要になる。
数学や国語は記述式試験も導入される方向性だ。
理系は理科や数学の研究に多くの時間が費やされるらしい。
文系は国際力を強化する意味で、英語のコミュニケーション能力を磨いていくらしい。
現在の授業も教師が黒板に向かって一方的に説明するやり方から、グループセッションや教師が学生に問題点などを直接問いかける内容にシフトしてきているらしい。
東高校の学生もより考えなければならないので、だいぶ疲れるようだ。
グループで考えることも大事だが、一人個人の意見をしっかり話す習慣も重要だと思う。
話は戻るが、探求科設置によって、東大の推薦合格者も見込んでいることだろう。
東高校では、東大に10人現役合格、東北(トンペイ)には
50人現役合格を目標に掲げているそうだ。
山形東高校ならば、現実的な数字に思う。