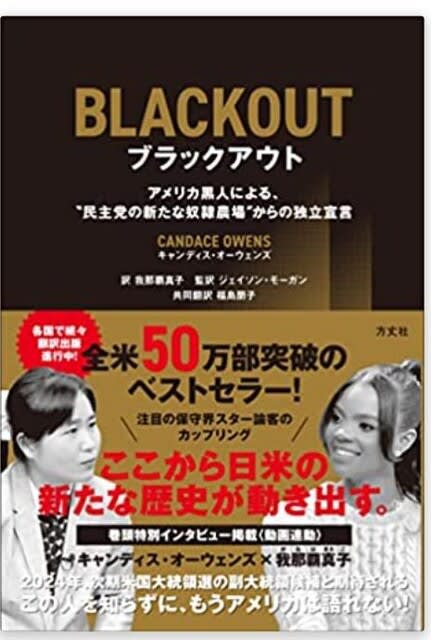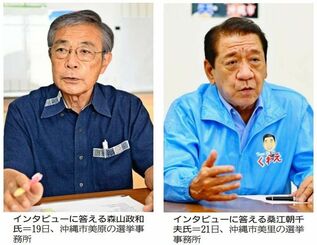先日、台湾と沖縄を行き来して徳永弁護士の「台湾人国籍取得訴訟」を支援している台湾人のKさんと台湾有事について語る機会があった。
筆者が「中国が近々台湾を侵攻すると思うか」と質問したら、Kさんは「侵攻しない」と意外な答えをした。 ロシアのウクライナ侵攻で、ロシアがNATОを中心に世界の批判を浴びて、ウクライナ陥落に苦戦している現状を同じ専制国家で核保有国の中国は学習したというのだ。 しかし「侵攻しない」とは素振りも見せず「あいまい政策」で「現状維持」で対応するのが中国にとって得策、というのだ。 その一方、台湾を守る立場の米国も「台湾を守るか否か」を明確にしない曖昧政策に徹するべきだという。
これは勿論Kさんが現在進行形のロシアのウクライナ攻撃を目の当たりにしての結果論だ。
だが、前回言及した『ラストエンペラー習近平』の著者・ルトワック氏は、ロシアのウクライナ侵攻の約1年前に、軍事大国が軍事小国を侵攻したら失敗する例を、「戦略のパラドックス」として解説している。

先ずルトワック氏は「大国・中国」が弱くなった理由をリーマンショック後の中国が実行した根本的誤りに求めている。
習近平はリーマンショックの後、経済力の規模がそのまま国力と勘違いした。
リーマンショックでアメリかが経済的ダメージを受けている間に、習近平は経済力でアメリカを抜き、世界一の経済大国になること目論んだ。
中国は、南シナ海、東シナ海をはじめ、日本、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、インドと領土をめぐる紛争を繰り返し、大規模な戦略である「一帯一路」ではパキスタンやスリランカの港の操業権を押さえ、アフリカの国々を負債漬けにするなど、国外に向かっても、その影響力を拡大しようとしている。
そして経済大国・中国が経済的小国を侵略するときは事前に経済的に縛り上げ、中国の意のままに従わせる。
この例として、ルトワック氏は「いきなり殴りつけておいてから、1万円札を出してお礼を要求するくらい間違っている」という。
日本流に言えば「札束で頬を叩いて言うこと聞かす」だろう。
■戦略的国力
戦略の観点からみた「国力」とは総合力である。
それは単なる軍事力でもなければ、もちろん経済力でもない。 たとえば今日のイギリスのGDPはおよそ2兆8000億㌦で、イタリア(約2兆1000億㌦)を多少上回っている程度だが、その国際的影響力はおそらく10倍以上違うだろう。
その差は外交力、政治力、さらには「大国的精神」などによるものだ。
さらにルトワック氏は、大国が小国に勝てない理由として同盟国の支援を挙げている。
2カ国目は「日英同盟」の「英国」だ。
4カ国目の「米国」は、太平洋での覇権を確立するために「強くない方を勝利させようとして」日本を支援することにした。日本が勝てば、太平洋で米国の地位を確立できるからだ。ポーツマス条約を仲介したのも米国なので、米国の貢献は大きかった。
ここでも同盟がうまいのはイギリスでだ。
ヨーロッパを席巻したナポレオンを相手に、反仏同盟をつくりあげ、ワーテルローの戦いに勝利したのである。 その際に見事だったのは、どんな弱い国でも同盟相手として排除しなかったことだった。 「あんなちっぽけなところでも加えてもらえるのか」と、躊躇していた国が次々と参加してきたのである。>
現在進行中のウクライナ戦争で「NTОの東方拡大」を恐れたプチーんが犯したもう一つの誤算は、藪を突いてヘビを出したことだ。
これまで軍事大国と国境を接していた軍事小国のフィンランドが、従来の現状維持策」による微妙なバランスを破ってNTО加盟を決意したのだ。
高まるロシア脅威論 伝統の中立政策転換も―フィンランド
2022年04月03日14時18分
1917年にロシア帝国から独立したフィンランドは、第2次大戦中にソ連と2度にわたり戦火を交えた。最初の「冬戦争」(39~40年)では奮闘の末に独立を守ったものの、東部カレリア地方など国土の1割を奪われた。
こうした歴史から、ソ連を刺激する政策を避け、冷戦終結後も米国主導のNATOに加盟しない道を選択。西欧民主主義に共鳴しながらも、対ロ関係も重視する中立の立場を貫き続けた。国民の意識としても中立の考え方は根付いている。
ところが、ウクライナ侵攻で路線修正を求める声が強まっている。少数派だったNATO加盟支持は、2月の侵攻開始直後の世論調査で初めて過半数(53%)を記録。3月半ばには62%に達した。
政府機関に勤務する首都ヘルシンキ出身のマティさん(60)は「歴史的経緯や地政学的な問題から、フィンランド人のウクライナ情勢への関心は非常に高い」と指摘。「人々は(ロシアの行動を)憂慮し、それが国の将来にどのような影響を及ぼすかを案じている」と語った。また、ヘルシンキ郊外の保育園勤務の女性は「ロシアに心を許してはならない」と述べ、「(侵攻されたら)もちろん戦う」と断言した。
政府は慎重姿勢を保ちながら、NATO加盟論議を進めていく方針。ニーニスト大統領は3月半ば、「結論を出すのは代替策とリスクを分析してからだ。政策見直しは注意深く行う」と述べつつも、国の将来にとって「安全な解決策」を見つける必要があると強調した。
一方、フィンランド安全保障情報庁は声明で、NATO加盟の政策決定に影響を与えようと、ロシアがさまざまな試みを仕掛けてくる可能性があると言及。サイバー攻撃を含む介入に警戒を呼び掛けた。












 ⇒最初にクリッ
⇒最初にクリッ