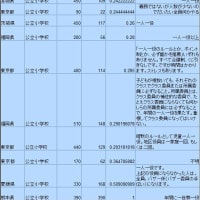前回(3)に引き続き、ディベートをしています。
PTAは民主主義を守る牙城?
たどころ:
理念からいえば、PTAや自治会は、日本に草の根の民主主義を根づかせるためのものです。
教科書的な言い方になりますが、民主主義はただで手に入ったものではなく、先人が血を流して、国家から勝ち取った権利です。
その権利の維持にもコストがかかります。民主主義を維持するために、相応のコストを支払わねばならないのではないでしょうか。
ぶきゃこ:
そうですね。ですから選挙は真摯に参加すべきでしょうね。
たどころ:
自治会やPTAを衰退させないことも、あがなわねばならないコストだと、考えられませんか。
ぶきゃこ:
それは、さまざまな見方があるところではないでしょうか。現状の自治会やPTAが民主主義の実現のツールかどうかは、意見の分かれるところだと思いますし…。一政党がどれだけ「これが理想の社会だ」と唱えても賛否はあるのと同じように、自治会やPTAをそこまで信奉する価値観は私にはありません。
自治組織のない国や低調な国もあるでしょうし、自治組織絶対主義というのはよくわかりませんね、私には。
日本人に民主主義を定着させることを目指すのであれば、グルーピングよりまず均質主義の日本の教育を変えて、自分の頭でものを考え、意見を言う訓練をしていくようにしなければ、本当の意味での「自治」はできないと思いますし、逆に「隣組」のように国家の装置となり、民主主義を抑圧する機能を果たしかねません。
現に、いま稼働している自治会やPTAのなかには、「自治」とはほど遠い実態のものも、少なくないのではないかと私は思っています。
たどころ:
「自治」について考えてみたいです。
私たちにとって「自治」は、とても大切な概念です。
たとえば、家庭内の教育方針や慣習や思想・信条・宗教の自由について、他人から指示命令されるのは嫌なものですよね。
「自治」の最小単位は「個人」ですが、「夫婦」になり「子ども」を持った場合、「家族」内での「自治」も重要になります。
「よそはよそ、うちはうち」とは、よく聞く言葉ですが、「家庭」内での納得があれば、「裸族」でも「菜食主義」でも「新興宗教」でも自由なわけです。
そこで、一足とびに話が大きくなるように感じられるかもしれませんが、「自治会」は「地域」の「自治」、「PTA」は「学校に関係する保護者」の「自治」を担っているとも、考えられます。現行の自治会やPTAが、どれだけ「自治」できているかはおいといて、そういう理念はあるし、そういう考え方をする人はいるわけです。
現状のPTAが、あまり発言権を持っていないという点には同意しますが、ほぼすべての保護者が加入している団体である限り、たとえば、教科書の選択にしろ、行事の内容にしろ、それこそ組体操の可否にしろ、部活動の強制にしろ、口を出すことが出きます。
実際に、私の所属していた幼稚園PTAでは、親子遠足を廃止しようとした幼稚園の決定を覆させたことがあります。
ですから、任意性を主張して、自治会やPTAを縮小させる方向性よりは、理念により即した方向性で活性化させるほうがよいのではないでしょうか。
ぶきゃこ:
まず、たどころさんの仰っている内容から判断するに、今回の「自治」の定義は、
①構成員の行動規範を定める議決手段と実効性を持つこと
②構成員内議決ルールにのっとって決定されたことは、すなわち構成員全体(自治単位)
の意思決定であることにすること
というふうに理解しましたがそれはよろしいでしょうか?
そう考えますと、たとえば「組体操は危険だってマスコミで言われてるんだから、今年からやめませんか?」というようなことを学校に申し入れしたい、と考えた人がいたとき、ただ単に個人で申し入れるよりは、PTA内でとりまとめて意見具申したほうが、はるかに真剣に検討してもらえる、というのはそのとおりです。
しかし、そこには「組体操自体は大きな学びになるものだ。安全基準を詳細に検討する姿勢もなく、危ないからやめてしまえは教育の否定ではないか」というような意見を持つ個人も、たぶんいるわけです。
そのような少数意見が、なかったことにされてしまうのが上記の②の作用ですから、それを「影響力が強くなるのだからいいことだ」と単純に言えるのか、私は疑問です。
幼稚園の親子遠足廃止を阻止して、「よかったよかった」と思うのは、保護者の時間に余裕もありハッピーな家庭であり、親子遠足に同伴するためのコンディションを整えるのにものすごく苦労しなければいけない家庭とか、かえって子どもが傷付く状況を作る場合も実はあるかもしれないと思うんです。
うちの近所の幼稚園は、児童養護施設から通っている子もいるんですが、親子遠足はありません。もしあったら、子どもにとっては辛いし、別に施設の子でなくても、家庭状況が辛い子もあるかもしれません。そういう状況を園だけが把握していて、「親子遠足はない方がいい」と判断した可能性もあると思います。
親子遠足が辛くてたまらない行事だった家庭にとってみれば、PTAのやったことは「数の暴力」かもしれませんよね。
私は「自治はよくないことだ」と否定してるわけではまったくありませんが、「自治」はひじょうに慎重に、人道的に行われなければいけないと思うし、「自治」に背を向ける人がいてもその人の人権は尊重するという謙虚さが必要だと思っています。日本に蔓延する「中間集団自治」のようすをみるとそう思います。
ですから、「縮小するより活性化した方がいい」と一律に考えることは、とうていできません。
たどころ:
そうですね。親子遠足についても、両方の意見はあったと思いますし、少数派(マイノリティー)の声を聞くことは大切です。
しかし、それはPTAや自治会のような中間団体でもできることではないでしょうか?
国や市のような大きな組織は、地域の人々の声を拾うことは難しいのではないですか。
中間団体の「自治」を否定して、「自治なんかいらない、ぜんぶ学校=行政が決めてくれ」という人が大勢を占める将来は、なんとなく恐ろしい気がします。
ぶきゃこ:
自治礼賛に疑念を持つことが、決定権(このばあい、学校運営への参政権)を放棄する態度である、という考え方自体がよくわかりません。
学校=行政は、もちろん信頼できない部分もたくさんありますが、それでもいちおう、国民の意見を反映して作られたシステムであり国民の資源を投入して設立された環境ですよね?
採用する教師の水準も、(実態はどうあれ)担保されているはずです。学校評価アンケートや評議会など、保護者が参加するルートもいちおう確保されています。
教育委員会というシステムにも問題は感じていますが、それでも現状では国民の合意でそのような組織になっています。
それがそもそも信用できない、その決定に従えない、別なところで別の基準で決定すべきだ、ということになれば、国という大きな自治の否定なのではないですか?
なぜ、大きな自治に対抗するために小さな自治がないと困る、という話になるのかが根本的によくわからないんですよ。
私の言っていることは、「ぜんぶ行政が決めてくれ。国の決めたことは絶対だ」と、自分の参政権を放棄する態度でしょうか?
私は「自治なんかいらない」とは思いません。あってもかまわないと思います。けれど絶対なくてはならないとは思わないし、小さな自治に重きを置かない人や、別の単位の自治(たとえば、個人)を大切にする人が、無責任かというと、それもまた違うと思います。
どんな段階においても、「政治の論理」や「多数決の力」をもちこみたがる人はいます。
「ひとりで言うより、おおぜいで言った方が力が持てる」ということ自体は事実でしょうが、「だからそれが善」かどうかはまた別の話だと思ってます。
PTAにはアマチュアの限界がある?
ぶきゃこ:
「小さな自治によって自分の主張を通したい」と一生懸命になる人生もあるのでしょうが、私はそういう生き方がおもしろいとあまり考えたことがありません。好みの違いかもしれませんが。
現状で、最大に少数派に配慮し、最大に憲法の精神に近い運営ができているのが、「国単位の自治」だと考えています。
地方自治体ですら、小諸市のような暴走をする可能性を否定できませんし、「自治だけでは人権は守りきれない」という考え方が出した結論が「三審制度」だと、いまのところ思っています。
大きな自治にしろ小さな自治にしろ、自分の主張や趣味嗜好のみが通らないのが「社会」であり、「公益」ということをどのようにとらえるのか、個人の考えかたに違いはあると思います。
「大きな自治にしたがうべきだ。それが社会秩序を重んじる態度だ」と考えている人を、「小さな自治権を放棄する無責任な態度だ」と指摘するのはなんだか違う気がします。「小さな自治」好きなタイプの方の中に、「なんでもかんでも“ぜんぶ”人任せなんだな!」と極端に決めつけてくる人がときどきいるのも奇妙な気がします。
総括して、もっとひらたい言葉で手短に言うと、「プロとアマチュアは決定的に違うものであり、アマチュアがプロに恣意的に口出し出来て政治力が持てるのは『民主主義』ではなく『ムラ社会』」というふうに私は考えている、と表現することもできます。
アマチュアはときに、ひとつの例ですが「会員でなければ権利がないのは当然だ。だから、会員の子だけ卒業式の花がなくても当然だ。」というような結論を出してしまいがちです。そして十分な影響力を学校内で持っていた場合、実際に恐ろしいことが実行されてしまいます。
私が「アマチュアの活性化が望ましいと単純に言うことは出来ない」と思うのはそういうときでもあります。
それは、アマチュアの否定ではないし、アマチュアなりの良さも、すぐれた判断もあると思うのですが、しょせんアマチュア団体ですからコミットするかどうかは個人の自由、の域を出ないし、それが「あるべき姿だ」と私は考えているし、その自覚のない「中間集団自治」はときに危険だ、ということです。
たどころ:
たしかに、「家庭」という単位であっても、子どもへの虐待や育児放棄があったときには、行政が介入して、児童養護施設に引き取ることもできるようです。
それは国の功績でしょうし、独居老人をケアする自治会の民生委員が国の委託事業であることもすでに述べたとおりです。
しかし、中間団体が暴走するのだとしたら、国家だって暴走するでしょう?
いわゆるリベラルは「国家権力は信用できない」と感じている人が多いと思います。PTAの自由化を求めるぶきゃこさんは、むしろ、中間団体(ムラ社会)の自治より、国際的な人権意識や制度が確立した国単位の自治のほうが、よほど信頼できると考えているわけでしょうか。左右の枠組みや建前にとらわれない新しい考え方で、非常に興味深く思います。
私もいいかげんおっさんなので、表現が古くなって申し訳ないですが、ぶきゃこさんの言うのは「狭いムラ社会の一員である以前に、世界市民でありたい」というところでしょうか。
ところで、「現状で、最大に少数派に配慮し、最大に憲法の精神に近い運営ができている」のは「国単位の自治」とのことですが、むしろ現状のPTAや自治会は、国→学校(地域)→PTA(自治会)という流れのなかで、「国単位の自治」の下請け機関のようになっているような気もします。だとしたら国≒PTAとも言えますよね。
ぶきゃこ:
まあ、PTAは国が維持コントロールしたがっているという実態があると思っていますので、多くのPTAを「下請け」と呼んでもあながち間違いではないかもしれません。
しかし、私の言っているのは、小さい自治より大きい自治の方が、現状の日本ではよりフェアにやれていると思う、という話であって、「自分たちで考えるより国の言うことを聞いた方がいい」ということとはまったく違いますね。
PTAの活動にかんして言えば、自主的なもののほうがずっとモチベーションは上がるし良いと思うのですが、国の基準を無視してもいい(つまり、会の基準>国の基準になって、会員の子だけ学校行事で優遇するようなことをやる)ということになるのはまずいんじゃないの、という話です。
国民としてのコンプライアンスを学ばずに市民活動をすることはむずかしい時代がやってきている、と既に述べた通りです。
たどころ:
これはまったく仮定の話ですし、そうはなってほしくないのですが、もし、PTAが「国単位の自治」の下請け機関という位置づけならば、「国民の義務」的に、参加が必須の方向性も考えられるような気がします。PTA会費は、社会保険と同様に、一種の税金という見方もできますし。
ぶきゃこ:
それはそれで、そうなるなら仕方ないんじゃないでしょうかね。そのような政治を行う国に住んでいるということですから。PTAの活動を、国民の義務と出来るほど標準化できるものならやってみればいいと思いますし、かえって苦情の持って行き先がはっきりしていいような気もします。
国民一人一人からいくら税金を取るべきかを公平に決定する過程について、国はものすごいコストかけていますよね(結果的に本当に公平にできているのかはまた別問題として)。
PTA会費を税金にするなら、そのスキームにちゃんと乗るということですから、「“一種の”税金です」と手前理屈で保護者同士を相互監視させて同調圧力で徴収し、しかも国が「知りません。口は出せません」と逃げている現状より、よっぽどましだと思います。
たまに事件になる、教員のPTA会費使い込みなんかも、私金じゃなく税金の横領ですから、謝って返せばなんとかなる話でもなくて、重罪になりますよね。
たどころ:
強引にまとめると、「望ましくないことが起こらないようにちゃんと選挙に行こう」という話ですね。
PTAや自治会が本当に必要な部分はどこ?
たどころ:
しかし、「国単位の自治」を信頼するにしても、現場で動く中間団体(自治会やPTA)は必要になってくるのではないですか?
たとえば自治会の民生委員とか、防災委員とか、自治体から自治会へ下ろされる地域の仕事を指しています。
災害時に、学校などの避難場所で、テントを設営したり、物資を配ったりするのは、役所の公務員と自治会の役員が一緒に行っていると思います(少なくとも、防災訓練はそのような想定で行われています)。
それらの「仕事」をすべて公務員にやらせることは経済的に不可能ではないですか?
ぶきゃこ:
そうでしょうか?
業務の性質的に(地域に根ざす必要があるため)難しいということであればわからなくもないですが、経済的に=予算的に不可能、というのはそんなに簡単に結論の出せる話でしょうか?
昔は「そんなものに予算が付くなんて考えられなかった」ものが、予算が付くようになったケースはいくらでもありますよね。
「不可能」と仰るからには、何らかのエビデンスが必要なのではないでしょうか。
国や自治体の予算というものは、企業の予算と違って「利益」という明確な目標がないですから、企業のそれよりずっと柔軟というか、政治によって(政治のみではありませんが)左右されるものだと思います。
「先生は仕事が大変だし学校はお金がないでしょ? だからPTAがやるしかない」のようなことを信念でお持ちの方も「不可能」という結論が根拠を持って出せているわけではなくて、PTAや自治会のような中間団体は予算を引っ張るような政治活動が出来ないから「そこには手はつけようがありません」だから「依頼が来た仕事はこなすしかありません」というのが事実に近い感覚のような気がします。
「反社会的団体の見張り」をお母さんたちが交代でやってるPTAも聞いたことあります。こういう仕事が必要だ、でもそんな予算はない、でも見張らないと子供たちが心配ではありませんか?と言われたら、やるしかなくなりますよ。
たどころ:
なるほど、まあ、地方自治体に十分な予算権限があって、北欧のように税金が高く高福祉の社会であれば、地域に根差した活動に報酬を支払うことも「不可能」とは言い切れないかもしれないですね。
でも、現状ではそうなっていませんし、今のところ自治会やPTAは、社会の公的なシステムに組み込まれているので、動かしづらい気がします。
ぶきゃこ:
それは感じますよ。現状、国家の装置になっているというのは私も理解しています。その理解と、その装置は一定の強制や侵害があったとしても維持すべきだ、他の方法はないと考えるかどうかは、また別の話です。
たどころ:
国家の装置というよりは、社会の装置ですよね。社会を円滑に回すための仕組みとして、やはりPTAや自治会は必要とされているのではないでしょうか。
ぶきゃこ:
PTAや自治会って「雇用をするほど安定したミッションがあるわけではないが、委員的なものが地域に設置されていると何かと便利なもの」のことですよね。
そうであっても、「必要」というのは言い過ぎではないかと思います。「そういう役割を地域で設置できるシステム(つまり自治会など)があったらよりいい」ものではあるにせよ。
消防団なんかが良い例ですね。全体主義的に考えれば「そりゃないよりあったほうがいいだろう」となりますが、実際には人の確保が大変で、PTAより酷い人権侵害が行われているケースもあるそうです。実家のほうの話なので全国的な問題かは分かりませんが。
実際の消火活動でもやはりアマチュアの手伝い的な位置づけにおかれる(当然ですが)ようですし、やはり、どうしても「必要」だとは私は思いません。
“「必要」だとは思わない”が、イコール“不要だと思う”ではありませんが、いずれにしても任意活動の域を出ないと思います。
本当に「必要」なものだとしたら、現状で、自治会にもPTAにも属さない国民というのはいっぱいいるわけですが(私はそうですが)、その人たちはどういう位置づけになりますか?
たどころ:
自治会やPTAは、会員のみにサービスを提供しているわけではないと思います。
自治会やPTAに属していなくても、自治会の町内清掃やPTAの校庭の草むしりの恩恵は間接的に受けていますよね?
地震などの災害が起きた時に、自治会に入っていない人は助けない、ということもないと思います。
自治会やPTAは、会員ではなく、地域や学校に奉仕するものですから。
非会員の位置づけは、地域や学校の一員ではあるけれども、活動をしない人という位置づけでしょうか。
なぜ「思いやり」が「押しつけ」にすりかわるの?
たどころ:
非会員について話をしていくと、ときどき「フリーライダー」論が出てくるわけですが、それについてはどうお考えでしょうか?
ぶきゃこ:
たとえば自治会が町内清掃を行っているから、そこを通過する他地域のかたも恩恵を受けているという意味ですか? それはそうですが、では自治会は通行する人をフリーライダーと呼んでいいかというとそうは思いません。
奉仕でもボランティアでも善意でも協力でも、呼びかたはなんでもいいでしょうが、社会というのはなにかちょっと助け合ったり、少しおせっかいを焼いたり、気持ちよく挨拶したり、それぞれのできる時間を割いたり、働いたお金のいくぶんかを寄付したりして、より良い社会をつくろうとする人たちでより良く成り立つ、と思います。
しかし、「恩恵を受けた人は恩を返せ、返すべきだ」と言うのがフリーライダー論者であり、それはもはや「善意」ではなく「契約」の主張だと思うんですね。
ただの「恩着せたがり」はおいとくとして、本気で「返すべきだ」を正当な主張だと思っている思考のことですが。
私は、一方的な「契約」は不当であると思います。
「サービスの購入」であれば契約書(実際に書面が存在するかどうかはまた別として)が必要なはずで、それがないのに一方的にサービスをして代償を要求するというのは不当な債権の主張であり、もはや「社会をより良く成り立たせるための善意」とは言えないと思います。
そのサービスに受け手が価値を感じるかどうかも、不明なのですし、一方的に「価値があるだろ?」と決めつけるわけにはいきませんよね?
「善意」「恩恵」という「愛」の話で始まったはずが、いつのまにか「愛をただ受けるなんて、私達にタダでサービスしろってこと?」と「契約」の話にすりかえられるというのは、大変気持ち悪いものですね。
PTA問題が、「任意加入のはずだ」と一種の「契約論」で語られるのは、正しくもあるのですが、「本当はそういう話じゃないんだよなあ」という心の呟きがいつもついて回るんです、私。
たどころ:
仰るとおりで「フリーライダー」という言葉は、いささか下品だと思います。
ですから、ほとんどの自治会もPTAも、非会員に対して「ただのり」だとは思っていないし、地域や学校の一員として、仲間意識は持っていると思います。
ぶきゃこ:
さあそれはどうでしょうか。かなり疑問ですね。
そのように仰いますと、あたかも自治会やPTAは広い心で仲間になろうとしているのに、偏屈な変わり者が法律を盾に取ってさわぎ、自分だけの権利を主張して入会しない、かのようですね?(笑)
実際は違うと思いますよ。自治会は任意加入が比較的浸透していると思いますが、PTAは、入らない、と言ったとたん、「ただのり」させまいとする(というより、不公平だとかずるいとか、その子にも記念品を配るのはおかしいとかいう他の保護者の声を抑える説得力を持たない)PTAがまだまだ多いんじゃないでしょうか?
たどころ:
たしかに、つっこんで話を聞いていくと「モンスター・ペアレンツ」とか「一部の極端な意見」とか、そういった「いじめ」や「排除」の論理を持つ言葉を口にするPTA関係者は多いですね。それでも、同じ「保護者同士」「住民同士」という共同体意識があることは信じたいですけどね。
ただ、「でも、ときどきは手伝ってほしいなあ」と思うのも人情ですし、「近くに存在しているんだから、交流があったほうが何かとやりやすいんだけどなあ」と思うのも自然なことじゃないでしょうか。
ですから「まあ、入会とか退会とか固いことを言わずに、まんざら知らない間柄でもないし、とりあえずみんなで集まって入っておこうよ」みたいな、世間知を持つ横丁のじいさんの価値観でやってきたんじゃないかと思うのですが、それはもう通用しないんですかねえ。
ぶきゃこ:
それな(笑)
小学校PTAの本部役員を長年やっている人が私の友達なんですけれども、彼女は本部と私の、実費支払いがどうのこうのというやり取りをしら~っとした気持ちで見てたと思うんですよ。彼女は自分も役員ですが、そういう態度をとる役員の人たちともそんなに仲は良くない(笑)
彼女は「会員とか会員じゃないとか、んなこたどうでもいいじゃないの。子供たちのためにできることを少しずつ手伝えばいいだけじゃん」と言う。本当に、彼女がいちばんまっとうだと思うんですよね。
ただ、もうほとんどのPTAは横丁の集まりではなくて、組織を持つ事業になってしまってます。やってる実態は横丁レベルなのに、ゆがみますよ、それは。
退会するというと、「どうしましたか?」より、「登校見守りにきてもらっても保険は対象外ですから!」みたいなことを言いたいのが先に来てしまう。
別にこちらは「動員させられるならそちらの責任で保険付けてよ」なんて言ってないんですけどね。もう、三丁目の夕日からどんどん遠ざかる。(笑)
たどころ:
たしかに組織の論理に流されていくPTAも多いですね。映画の『三丁目の夕日』だって、あれは懐古趣味のフィクションで、実際の昭和三十年代は抑圧がひどくて、嫌な時代だったって声はありますからね。
任意加入になったら「やる気」が必要になる?
たどころ:
で、ぶきゃこさんは、それならばいっそのこと「雇用」とか「正当な報酬」と仰るわけですが、それはちょっとギスギスした感じがしませんか。
お醤油が切れたときに、お隣にもらいにいって、「代金」を払うわよといったら、「水臭い」と言われそうな気がします。
それと同じで、PTAや自治会の活動に「正当な報酬」を発生させることを好まない人も多くいるような気がします。
ぶきゃこ:
あ、いえいえ。私が「PTA活動をそんなに担保したいなら本来雇用すべき」みたいなことを言うのは、PTAや自治会の活動に正当な報酬が支払われるべきだ、ということではありません。
正当な報酬が支払われるような種類の市場価値のものではないもの(価値がないということではなく、貨幣価値として測定しづらいということです)を、「義務」とか「責任」とか「やらないのは不公平」とか「仕事は個人の都合でしょ」とか「毎年やるって決まってる地域活動は低下させてはならない」などと無理くり優先させようとするのは、「労働力の市場価値」=人を拘束するには本来報酬が発生しなければならないことだ、という認識が、(「主婦労働は無償」の考え方がおそらくベースにあると思うのですが)立ち後れているのではないかと思うからなのです。
PTAがそんなに押しつけ合いになるなら報酬を払えば良い、というアイデアはちらほら聞かれますが、私は否定的です。
ただ、従来からの「奉仕活動に報酬を要求するのはぎすぎすしたこと」という価値観の押しつけは、女性の無償労働にバックアップされて社会で報酬や承認をがっつり得ている「男」が言いがちなことであったとは思っています。
たどころ:
ああ、たしかにそれはあるかもしれませんね。私は以前に主夫をしていたこともあるのですが、あれは辛かったですね。自分の家事能力が低すぎて(笑)。
PTAは女性ばかりの組織なのに、なぜかPTA会長だけが男性というのも少し変な感じがしますね(女性の中にやりたい人がいないため、男性にお願いしているという見方もありますが)。
それはそれとして、お金の介在しないボランティアというゆるさがあるからこそ、ちょっと遅刻しても、多少非効率でも、おしゃべりに花が咲いても許されて、それがいいという人がいる。
任意加入にしたいという人の中には、「やる気」があって効率化を求める人もいるように見えますが、それが現行のPTAと相性が悪そうに見えることもあります。
ぶきゃこ:
仰る通り、私みたいな“非効率さを楽しめる”適性が環境的にも性格的にもない人を「ほんわかゆるゆる親睦重視の会社ごっこ」にむりやり巻き込んだらブラック化のもとですし、実際、しょうもない細部(と私には見える)ことにうだうだとこだわりたっぷり時間を使って先に進めないタイプの優雅な方とは、いっしょに活動やっても非常に相性悪かったですね。
疲れ切って保育園にお迎え行った後で夜の7時に帰り着き、上の子たちが口々にいろんなことを堰を切ったように話しかけてくるのをうんうん聞きながら、洗濯物を取り込んで風呂を洗って、とにかく先にご飯の下ごしらえを…とあせる中で子どもがしょうもない物の取り合いで喧嘩になったり、お母さん○○がない!とか言われて対応したり、そんな中で料理の最中にPTAの電話がかかってきて、講演会の動員の電話連絡網(しかも要領を得ない)をえんえんメモとらされたら、ぶち切れる程度には私はじゅうぶん狭量です(笑)。
ま、でもこういうことを「つらい」と訴えても、「大変なのはみんな一緒」「そういう状態にしてる自分が悪い」と自己責任論を言われるのがPTAという場でしたけどね、私にとっては。
私が言っているのは、当事者にならないとわからないメンタル状態もあり、それを無視して「理想のPTA」だけ語ってもそのように運営されるのは実際なかなかむずかしいし、むずかしいことは日本中で証明されている、ということです。
たどころ:
お話しはよくわかりました。本当は、いろんなタイプの人を包含するのがダイバーシティの面からも理想なんですけど、一緒にやりたくないと言われると辛いですね。
ぶきゃこさんの言うように、加入を任意にすることで、市場原理が働いて、活動が自浄化するというのは、その通りだと思うんです。任意でも入会してもらわなければならないとすれば、それだけ「魅力的な団体」になる必要がありますから。
しかし、それこそ営利目的ではない、報酬ももらわないボランティアのPTA本部役員に、そこまで市場原理に沿うことを求められるでしょうか?
お金をもらっていてすら、市場で勝つためのビジネスは難しいものです。ストレスもたまります。
改革や改善を必須にしたら、それこそ本部役員の成り手がいなくなるかもしれません。
今年の本部役員がだらしないから会員が減ったとか、そんなこと言われるなら、やりたくないですよね。
前例踏襲でゆるくやってもいいと思われているから、なんとか成り手が見つかっているのでは?
ぶきゃこ:
ボランティアでやってくれてるのに、「会員が減らないように営業努力する責任」をしょわせるのは酷、という話ですよね。
わからなくはないですし気の毒ではありますけれども、だからと言って自動加入で前年踏襲の比較的楽な運営方法を許せ、それが平穏に運営されるように保護者は協力しろ、となるとちょっと「無理を通そうとしすぎ」なんじゃないかと思いますよ。
それはこの社会において「そういう主張はちょっと無理では…」と思うからなのですが、それ(任意性の知識がひろまり安定運営が脅かされること)を「退会する保護者」の責任に帰す論調もあって、そうなると容易に「自分の都合の主張のし合い」「人格攻撃の応酬」になっちゃいますね。
まあ残念ながら、お金を管理し団体活動をおこなうということは、いろんな言葉も浴びる可能性があるってことですよね。
前例踏襲イコールゆるい、とも限らないでしょう。
むしろ、非難を浴びないことを眼目にやっていると、だんだん膨張してくるのがPTA活動の傾向のような気がします。
恵まれている人にはPTA問題がわからない?
ぶきゃこ:
PTAがゆるゆるを維持できるとしたら、ベタな言葉ですが「思いやり」ですよね。
役員さんありがとう、役員さんにそこまで求めたら酷、そういう思いやりをなくしてしまわないために、私はPTAと保護者を企業と客、あるいは使用者と労働者のような関係にする「対話のない自動加入」とそれに裏打ちされた「強制的な文言のプリントを配布したり、反応のない保護者に督促したり再配布する行為」について、まったくもって賛同できないでいるわけですね。
たどころ:
「思いやり」が必要という意見には全面的に賛同します。
PTAの役員だって、たまたま役員になっているだけの保護者で、自分がされたくないことは人にしたくないのではないでしょうか。
最初からギスギスしたい人がいないのに険悪になっているのであれば、それはどちらかがどこかで相手の感情を害して、ケンカになっているような気がします。
ぶきゃこ:
そうです。ですから私は「まぎらわしい手を使って自動入会させるのはやめようね。きちんと説明するのは礼儀だよね」とずーっと言っているわけです。それが始まりですから。
たとえば、お手伝いの依頼のプリントを配布して、挨拶も返信もなくスルーする人がおおぜいいるときに、役員の皆さんは「失礼ね」とか「ひどい」と感じていらっしゃいませんか?
その「ひどい」に感情を奪われているときに、そもそも自動入会させていることや、Noの選択肢がない希望票を一方的に期限を切って出すように求めていることの暴力性を、あわせて考慮できる人は、どのくらいいるのでしょう。
たどころ:
ああ、それは仰るとおりですね。
ぶきゃこ:
自分が「されたくないけど義務だからがんばってやった」と思えば、容易に「他人もやるべきだ」と思うようになりますよ。
人は「自分がされたくないことは人にしたくない」と思う、というのが常に変わらぬ真理なら、なぜ、世の中からいじめはなくならないのでしょうね? 大人の世界でもいじめ、たくさんありますよ。
どんなに理性のある大人でも、ストレスはいじめを誘発します。
もし「強要されている」と肌で感じられないのであれば、そのPTAの活動にそもそもストレス発生量が少ないからとか、男性はストレスのはけ口にされにくいとか、それなりに要因があると思います。
PTA被害が「共感できない」「イメージできない」ということであり、なおかつ「あなたはそう感じるんですね」という他者尊重よりも「何かをやらせたい(入会させたい、協力させたい)」が優先されるのであれば、「話し合いによる相互理解」はなかなかむずかしく、法に拠って解決するしかないのではないかと思います。
たどころ:
そういうお話しを聞いていると、PTA問題は格差問題という気がしてきますね。男女格差、経済格差、社会格差があって、PTA会長や自治会長に推薦されがちな、社会的に恵まれている層には現場の痛みがなかなかわかりづらいのだと。
まあ、私がお会いしたPTA会長さんの中には、地元の名士だけれども、家業は負債だらけだという人もいたので、格差問題も単純ではないような気もします。
いずれにしろ、PTA活動に困難を感じない恵まれている人が、困っている人の存在に気づきづらいのは普遍的な事実だと思います。
どこまで届くのかはわかりませんが、これを結びの言葉として、この対談を終わりにしたいと思います。読んでくださった方、長々とおつきあいいただき、どうもありがとうございました。
PTAは民主主義を守る牙城?
たどころ:
理念からいえば、PTAや自治会は、日本に草の根の民主主義を根づかせるためのものです。
教科書的な言い方になりますが、民主主義はただで手に入ったものではなく、先人が血を流して、国家から勝ち取った権利です。
その権利の維持にもコストがかかります。民主主義を維持するために、相応のコストを支払わねばならないのではないでしょうか。
ぶきゃこ:
そうですね。ですから選挙は真摯に参加すべきでしょうね。
たどころ:
自治会やPTAを衰退させないことも、あがなわねばならないコストだと、考えられませんか。
ぶきゃこ:
それは、さまざまな見方があるところではないでしょうか。現状の自治会やPTAが民主主義の実現のツールかどうかは、意見の分かれるところだと思いますし…。一政党がどれだけ「これが理想の社会だ」と唱えても賛否はあるのと同じように、自治会やPTAをそこまで信奉する価値観は私にはありません。
自治組織のない国や低調な国もあるでしょうし、自治組織絶対主義というのはよくわかりませんね、私には。
日本人に民主主義を定着させることを目指すのであれば、グルーピングよりまず均質主義の日本の教育を変えて、自分の頭でものを考え、意見を言う訓練をしていくようにしなければ、本当の意味での「自治」はできないと思いますし、逆に「隣組」のように国家の装置となり、民主主義を抑圧する機能を果たしかねません。
現に、いま稼働している自治会やPTAのなかには、「自治」とはほど遠い実態のものも、少なくないのではないかと私は思っています。
たどころ:
「自治」について考えてみたいです。
私たちにとって「自治」は、とても大切な概念です。
たとえば、家庭内の教育方針や慣習や思想・信条・宗教の自由について、他人から指示命令されるのは嫌なものですよね。
「自治」の最小単位は「個人」ですが、「夫婦」になり「子ども」を持った場合、「家族」内での「自治」も重要になります。
「よそはよそ、うちはうち」とは、よく聞く言葉ですが、「家庭」内での納得があれば、「裸族」でも「菜食主義」でも「新興宗教」でも自由なわけです。
そこで、一足とびに話が大きくなるように感じられるかもしれませんが、「自治会」は「地域」の「自治」、「PTA」は「学校に関係する保護者」の「自治」を担っているとも、考えられます。現行の自治会やPTAが、どれだけ「自治」できているかはおいといて、そういう理念はあるし、そういう考え方をする人はいるわけです。
現状のPTAが、あまり発言権を持っていないという点には同意しますが、ほぼすべての保護者が加入している団体である限り、たとえば、教科書の選択にしろ、行事の内容にしろ、それこそ組体操の可否にしろ、部活動の強制にしろ、口を出すことが出きます。
実際に、私の所属していた幼稚園PTAでは、親子遠足を廃止しようとした幼稚園の決定を覆させたことがあります。
ですから、任意性を主張して、自治会やPTAを縮小させる方向性よりは、理念により即した方向性で活性化させるほうがよいのではないでしょうか。
ぶきゃこ:
まず、たどころさんの仰っている内容から判断するに、今回の「自治」の定義は、
①構成員の行動規範を定める議決手段と実効性を持つこと
②構成員内議決ルールにのっとって決定されたことは、すなわち構成員全体(自治単位)
の意思決定であることにすること
というふうに理解しましたがそれはよろしいでしょうか?
そう考えますと、たとえば「組体操は危険だってマスコミで言われてるんだから、今年からやめませんか?」というようなことを学校に申し入れしたい、と考えた人がいたとき、ただ単に個人で申し入れるよりは、PTA内でとりまとめて意見具申したほうが、はるかに真剣に検討してもらえる、というのはそのとおりです。
しかし、そこには「組体操自体は大きな学びになるものだ。安全基準を詳細に検討する姿勢もなく、危ないからやめてしまえは教育の否定ではないか」というような意見を持つ個人も、たぶんいるわけです。
そのような少数意見が、なかったことにされてしまうのが上記の②の作用ですから、それを「影響力が強くなるのだからいいことだ」と単純に言えるのか、私は疑問です。
幼稚園の親子遠足廃止を阻止して、「よかったよかった」と思うのは、保護者の時間に余裕もありハッピーな家庭であり、親子遠足に同伴するためのコンディションを整えるのにものすごく苦労しなければいけない家庭とか、かえって子どもが傷付く状況を作る場合も実はあるかもしれないと思うんです。
うちの近所の幼稚園は、児童養護施設から通っている子もいるんですが、親子遠足はありません。もしあったら、子どもにとっては辛いし、別に施設の子でなくても、家庭状況が辛い子もあるかもしれません。そういう状況を園だけが把握していて、「親子遠足はない方がいい」と判断した可能性もあると思います。
親子遠足が辛くてたまらない行事だった家庭にとってみれば、PTAのやったことは「数の暴力」かもしれませんよね。
私は「自治はよくないことだ」と否定してるわけではまったくありませんが、「自治」はひじょうに慎重に、人道的に行われなければいけないと思うし、「自治」に背を向ける人がいてもその人の人権は尊重するという謙虚さが必要だと思っています。日本に蔓延する「中間集団自治」のようすをみるとそう思います。
ですから、「縮小するより活性化した方がいい」と一律に考えることは、とうていできません。
たどころ:
そうですね。親子遠足についても、両方の意見はあったと思いますし、少数派(マイノリティー)の声を聞くことは大切です。
しかし、それはPTAや自治会のような中間団体でもできることではないでしょうか?
国や市のような大きな組織は、地域の人々の声を拾うことは難しいのではないですか。
中間団体の「自治」を否定して、「自治なんかいらない、ぜんぶ学校=行政が決めてくれ」という人が大勢を占める将来は、なんとなく恐ろしい気がします。
ぶきゃこ:
自治礼賛に疑念を持つことが、決定権(このばあい、学校運営への参政権)を放棄する態度である、という考え方自体がよくわかりません。
学校=行政は、もちろん信頼できない部分もたくさんありますが、それでもいちおう、国民の意見を反映して作られたシステムであり国民の資源を投入して設立された環境ですよね?
採用する教師の水準も、(実態はどうあれ)担保されているはずです。学校評価アンケートや評議会など、保護者が参加するルートもいちおう確保されています。
教育委員会というシステムにも問題は感じていますが、それでも現状では国民の合意でそのような組織になっています。
それがそもそも信用できない、その決定に従えない、別なところで別の基準で決定すべきだ、ということになれば、国という大きな自治の否定なのではないですか?
なぜ、大きな自治に対抗するために小さな自治がないと困る、という話になるのかが根本的によくわからないんですよ。
私の言っていることは、「ぜんぶ行政が決めてくれ。国の決めたことは絶対だ」と、自分の参政権を放棄する態度でしょうか?
私は「自治なんかいらない」とは思いません。あってもかまわないと思います。けれど絶対なくてはならないとは思わないし、小さな自治に重きを置かない人や、別の単位の自治(たとえば、個人)を大切にする人が、無責任かというと、それもまた違うと思います。
どんな段階においても、「政治の論理」や「多数決の力」をもちこみたがる人はいます。
「ひとりで言うより、おおぜいで言った方が力が持てる」ということ自体は事実でしょうが、「だからそれが善」かどうかはまた別の話だと思ってます。
PTAにはアマチュアの限界がある?
ぶきゃこ:
「小さな自治によって自分の主張を通したい」と一生懸命になる人生もあるのでしょうが、私はそういう生き方がおもしろいとあまり考えたことがありません。好みの違いかもしれませんが。
現状で、最大に少数派に配慮し、最大に憲法の精神に近い運営ができているのが、「国単位の自治」だと考えています。
地方自治体ですら、小諸市のような暴走をする可能性を否定できませんし、「自治だけでは人権は守りきれない」という考え方が出した結論が「三審制度」だと、いまのところ思っています。
大きな自治にしろ小さな自治にしろ、自分の主張や趣味嗜好のみが通らないのが「社会」であり、「公益」ということをどのようにとらえるのか、個人の考えかたに違いはあると思います。
「大きな自治にしたがうべきだ。それが社会秩序を重んじる態度だ」と考えている人を、「小さな自治権を放棄する無責任な態度だ」と指摘するのはなんだか違う気がします。「小さな自治」好きなタイプの方の中に、「なんでもかんでも“ぜんぶ”人任せなんだな!」と極端に決めつけてくる人がときどきいるのも奇妙な気がします。
総括して、もっとひらたい言葉で手短に言うと、「プロとアマチュアは決定的に違うものであり、アマチュアがプロに恣意的に口出し出来て政治力が持てるのは『民主主義』ではなく『ムラ社会』」というふうに私は考えている、と表現することもできます。
アマチュアはときに、ひとつの例ですが「会員でなければ権利がないのは当然だ。だから、会員の子だけ卒業式の花がなくても当然だ。」というような結論を出してしまいがちです。そして十分な影響力を学校内で持っていた場合、実際に恐ろしいことが実行されてしまいます。
私が「アマチュアの活性化が望ましいと単純に言うことは出来ない」と思うのはそういうときでもあります。
それは、アマチュアの否定ではないし、アマチュアなりの良さも、すぐれた判断もあると思うのですが、しょせんアマチュア団体ですからコミットするかどうかは個人の自由、の域を出ないし、それが「あるべき姿だ」と私は考えているし、その自覚のない「中間集団自治」はときに危険だ、ということです。
たどころ:
たしかに、「家庭」という単位であっても、子どもへの虐待や育児放棄があったときには、行政が介入して、児童養護施設に引き取ることもできるようです。
それは国の功績でしょうし、独居老人をケアする自治会の民生委員が国の委託事業であることもすでに述べたとおりです。
しかし、中間団体が暴走するのだとしたら、国家だって暴走するでしょう?
いわゆるリベラルは「国家権力は信用できない」と感じている人が多いと思います。PTAの自由化を求めるぶきゃこさんは、むしろ、中間団体(ムラ社会)の自治より、国際的な人権意識や制度が確立した国単位の自治のほうが、よほど信頼できると考えているわけでしょうか。左右の枠組みや建前にとらわれない新しい考え方で、非常に興味深く思います。
私もいいかげんおっさんなので、表現が古くなって申し訳ないですが、ぶきゃこさんの言うのは「狭いムラ社会の一員である以前に、世界市民でありたい」というところでしょうか。
ところで、「現状で、最大に少数派に配慮し、最大に憲法の精神に近い運営ができている」のは「国単位の自治」とのことですが、むしろ現状のPTAや自治会は、国→学校(地域)→PTA(自治会)という流れのなかで、「国単位の自治」の下請け機関のようになっているような気もします。だとしたら国≒PTAとも言えますよね。
ぶきゃこ:
まあ、PTAは国が維持コントロールしたがっているという実態があると思っていますので、多くのPTAを「下請け」と呼んでもあながち間違いではないかもしれません。
しかし、私の言っているのは、小さい自治より大きい自治の方が、現状の日本ではよりフェアにやれていると思う、という話であって、「自分たちで考えるより国の言うことを聞いた方がいい」ということとはまったく違いますね。
PTAの活動にかんして言えば、自主的なもののほうがずっとモチベーションは上がるし良いと思うのですが、国の基準を無視してもいい(つまり、会の基準>国の基準になって、会員の子だけ学校行事で優遇するようなことをやる)ということになるのはまずいんじゃないの、という話です。
国民としてのコンプライアンスを学ばずに市民活動をすることはむずかしい時代がやってきている、と既に述べた通りです。
たどころ:
これはまったく仮定の話ですし、そうはなってほしくないのですが、もし、PTAが「国単位の自治」の下請け機関という位置づけならば、「国民の義務」的に、参加が必須の方向性も考えられるような気がします。PTA会費は、社会保険と同様に、一種の税金という見方もできますし。
ぶきゃこ:
それはそれで、そうなるなら仕方ないんじゃないでしょうかね。そのような政治を行う国に住んでいるということですから。PTAの活動を、国民の義務と出来るほど標準化できるものならやってみればいいと思いますし、かえって苦情の持って行き先がはっきりしていいような気もします。
国民一人一人からいくら税金を取るべきかを公平に決定する過程について、国はものすごいコストかけていますよね(結果的に本当に公平にできているのかはまた別問題として)。
PTA会費を税金にするなら、そのスキームにちゃんと乗るということですから、「“一種の”税金です」と手前理屈で保護者同士を相互監視させて同調圧力で徴収し、しかも国が「知りません。口は出せません」と逃げている現状より、よっぽどましだと思います。
たまに事件になる、教員のPTA会費使い込みなんかも、私金じゃなく税金の横領ですから、謝って返せばなんとかなる話でもなくて、重罪になりますよね。
たどころ:
強引にまとめると、「望ましくないことが起こらないようにちゃんと選挙に行こう」という話ですね。
PTAや自治会が本当に必要な部分はどこ?
たどころ:
しかし、「国単位の自治」を信頼するにしても、現場で動く中間団体(自治会やPTA)は必要になってくるのではないですか?
たとえば自治会の民生委員とか、防災委員とか、自治体から自治会へ下ろされる地域の仕事を指しています。
災害時に、学校などの避難場所で、テントを設営したり、物資を配ったりするのは、役所の公務員と自治会の役員が一緒に行っていると思います(少なくとも、防災訓練はそのような想定で行われています)。
それらの「仕事」をすべて公務員にやらせることは経済的に不可能ではないですか?
ぶきゃこ:
そうでしょうか?
業務の性質的に(地域に根ざす必要があるため)難しいということであればわからなくもないですが、経済的に=予算的に不可能、というのはそんなに簡単に結論の出せる話でしょうか?
昔は「そんなものに予算が付くなんて考えられなかった」ものが、予算が付くようになったケースはいくらでもありますよね。
「不可能」と仰るからには、何らかのエビデンスが必要なのではないでしょうか。
国や自治体の予算というものは、企業の予算と違って「利益」という明確な目標がないですから、企業のそれよりずっと柔軟というか、政治によって(政治のみではありませんが)左右されるものだと思います。
「先生は仕事が大変だし学校はお金がないでしょ? だからPTAがやるしかない」のようなことを信念でお持ちの方も「不可能」という結論が根拠を持って出せているわけではなくて、PTAや自治会のような中間団体は予算を引っ張るような政治活動が出来ないから「そこには手はつけようがありません」だから「依頼が来た仕事はこなすしかありません」というのが事実に近い感覚のような気がします。
「反社会的団体の見張り」をお母さんたちが交代でやってるPTAも聞いたことあります。こういう仕事が必要だ、でもそんな予算はない、でも見張らないと子供たちが心配ではありませんか?と言われたら、やるしかなくなりますよ。
たどころ:
なるほど、まあ、地方自治体に十分な予算権限があって、北欧のように税金が高く高福祉の社会であれば、地域に根差した活動に報酬を支払うことも「不可能」とは言い切れないかもしれないですね。
でも、現状ではそうなっていませんし、今のところ自治会やPTAは、社会の公的なシステムに組み込まれているので、動かしづらい気がします。
ぶきゃこ:
それは感じますよ。現状、国家の装置になっているというのは私も理解しています。その理解と、その装置は一定の強制や侵害があったとしても維持すべきだ、他の方法はないと考えるかどうかは、また別の話です。
たどころ:
国家の装置というよりは、社会の装置ですよね。社会を円滑に回すための仕組みとして、やはりPTAや自治会は必要とされているのではないでしょうか。
ぶきゃこ:
PTAや自治会って「雇用をするほど安定したミッションがあるわけではないが、委員的なものが地域に設置されていると何かと便利なもの」のことですよね。
そうであっても、「必要」というのは言い過ぎではないかと思います。「そういう役割を地域で設置できるシステム(つまり自治会など)があったらよりいい」ものではあるにせよ。
消防団なんかが良い例ですね。全体主義的に考えれば「そりゃないよりあったほうがいいだろう」となりますが、実際には人の確保が大変で、PTAより酷い人権侵害が行われているケースもあるそうです。実家のほうの話なので全国的な問題かは分かりませんが。
実際の消火活動でもやはりアマチュアの手伝い的な位置づけにおかれる(当然ですが)ようですし、やはり、どうしても「必要」だとは私は思いません。
“「必要」だとは思わない”が、イコール“不要だと思う”ではありませんが、いずれにしても任意活動の域を出ないと思います。
本当に「必要」なものだとしたら、現状で、自治会にもPTAにも属さない国民というのはいっぱいいるわけですが(私はそうですが)、その人たちはどういう位置づけになりますか?
たどころ:
自治会やPTAは、会員のみにサービスを提供しているわけではないと思います。
自治会やPTAに属していなくても、自治会の町内清掃やPTAの校庭の草むしりの恩恵は間接的に受けていますよね?
地震などの災害が起きた時に、自治会に入っていない人は助けない、ということもないと思います。
自治会やPTAは、会員ではなく、地域や学校に奉仕するものですから。
非会員の位置づけは、地域や学校の一員ではあるけれども、活動をしない人という位置づけでしょうか。
なぜ「思いやり」が「押しつけ」にすりかわるの?
たどころ:
非会員について話をしていくと、ときどき「フリーライダー」論が出てくるわけですが、それについてはどうお考えでしょうか?
ぶきゃこ:
たとえば自治会が町内清掃を行っているから、そこを通過する他地域のかたも恩恵を受けているという意味ですか? それはそうですが、では自治会は通行する人をフリーライダーと呼んでいいかというとそうは思いません。
奉仕でもボランティアでも善意でも協力でも、呼びかたはなんでもいいでしょうが、社会というのはなにかちょっと助け合ったり、少しおせっかいを焼いたり、気持ちよく挨拶したり、それぞれのできる時間を割いたり、働いたお金のいくぶんかを寄付したりして、より良い社会をつくろうとする人たちでより良く成り立つ、と思います。
しかし、「恩恵を受けた人は恩を返せ、返すべきだ」と言うのがフリーライダー論者であり、それはもはや「善意」ではなく「契約」の主張だと思うんですね。
ただの「恩着せたがり」はおいとくとして、本気で「返すべきだ」を正当な主張だと思っている思考のことですが。
私は、一方的な「契約」は不当であると思います。
「サービスの購入」であれば契約書(実際に書面が存在するかどうかはまた別として)が必要なはずで、それがないのに一方的にサービスをして代償を要求するというのは不当な債権の主張であり、もはや「社会をより良く成り立たせるための善意」とは言えないと思います。
そのサービスに受け手が価値を感じるかどうかも、不明なのですし、一方的に「価値があるだろ?」と決めつけるわけにはいきませんよね?
「善意」「恩恵」という「愛」の話で始まったはずが、いつのまにか「愛をただ受けるなんて、私達にタダでサービスしろってこと?」と「契約」の話にすりかえられるというのは、大変気持ち悪いものですね。
PTA問題が、「任意加入のはずだ」と一種の「契約論」で語られるのは、正しくもあるのですが、「本当はそういう話じゃないんだよなあ」という心の呟きがいつもついて回るんです、私。
たどころ:
仰るとおりで「フリーライダー」という言葉は、いささか下品だと思います。
ですから、ほとんどの自治会もPTAも、非会員に対して「ただのり」だとは思っていないし、地域や学校の一員として、仲間意識は持っていると思います。
ぶきゃこ:
さあそれはどうでしょうか。かなり疑問ですね。
そのように仰いますと、あたかも自治会やPTAは広い心で仲間になろうとしているのに、偏屈な変わり者が法律を盾に取ってさわぎ、自分だけの権利を主張して入会しない、かのようですね?(笑)
実際は違うと思いますよ。自治会は任意加入が比較的浸透していると思いますが、PTAは、入らない、と言ったとたん、「ただのり」させまいとする(というより、不公平だとかずるいとか、その子にも記念品を配るのはおかしいとかいう他の保護者の声を抑える説得力を持たない)PTAがまだまだ多いんじゃないでしょうか?
たどころ:
たしかに、つっこんで話を聞いていくと「モンスター・ペアレンツ」とか「一部の極端な意見」とか、そういった「いじめ」や「排除」の論理を持つ言葉を口にするPTA関係者は多いですね。それでも、同じ「保護者同士」「住民同士」という共同体意識があることは信じたいですけどね。
ただ、「でも、ときどきは手伝ってほしいなあ」と思うのも人情ですし、「近くに存在しているんだから、交流があったほうが何かとやりやすいんだけどなあ」と思うのも自然なことじゃないでしょうか。
ですから「まあ、入会とか退会とか固いことを言わずに、まんざら知らない間柄でもないし、とりあえずみんなで集まって入っておこうよ」みたいな、世間知を持つ横丁のじいさんの価値観でやってきたんじゃないかと思うのですが、それはもう通用しないんですかねえ。
ぶきゃこ:
それな(笑)
小学校PTAの本部役員を長年やっている人が私の友達なんですけれども、彼女は本部と私の、実費支払いがどうのこうのというやり取りをしら~っとした気持ちで見てたと思うんですよ。彼女は自分も役員ですが、そういう態度をとる役員の人たちともそんなに仲は良くない(笑)
彼女は「会員とか会員じゃないとか、んなこたどうでもいいじゃないの。子供たちのためにできることを少しずつ手伝えばいいだけじゃん」と言う。本当に、彼女がいちばんまっとうだと思うんですよね。
ただ、もうほとんどのPTAは横丁の集まりではなくて、組織を持つ事業になってしまってます。やってる実態は横丁レベルなのに、ゆがみますよ、それは。
退会するというと、「どうしましたか?」より、「登校見守りにきてもらっても保険は対象外ですから!」みたいなことを言いたいのが先に来てしまう。
別にこちらは「動員させられるならそちらの責任で保険付けてよ」なんて言ってないんですけどね。もう、三丁目の夕日からどんどん遠ざかる。(笑)
たどころ:
たしかに組織の論理に流されていくPTAも多いですね。映画の『三丁目の夕日』だって、あれは懐古趣味のフィクションで、実際の昭和三十年代は抑圧がひどくて、嫌な時代だったって声はありますからね。
任意加入になったら「やる気」が必要になる?
たどころ:
で、ぶきゃこさんは、それならばいっそのこと「雇用」とか「正当な報酬」と仰るわけですが、それはちょっとギスギスした感じがしませんか。
お醤油が切れたときに、お隣にもらいにいって、「代金」を払うわよといったら、「水臭い」と言われそうな気がします。
それと同じで、PTAや自治会の活動に「正当な報酬」を発生させることを好まない人も多くいるような気がします。
ぶきゃこ:
あ、いえいえ。私が「PTA活動をそんなに担保したいなら本来雇用すべき」みたいなことを言うのは、PTAや自治会の活動に正当な報酬が支払われるべきだ、ということではありません。
正当な報酬が支払われるような種類の市場価値のものではないもの(価値がないということではなく、貨幣価値として測定しづらいということです)を、「義務」とか「責任」とか「やらないのは不公平」とか「仕事は個人の都合でしょ」とか「毎年やるって決まってる地域活動は低下させてはならない」などと無理くり優先させようとするのは、「労働力の市場価値」=人を拘束するには本来報酬が発生しなければならないことだ、という認識が、(「主婦労働は無償」の考え方がおそらくベースにあると思うのですが)立ち後れているのではないかと思うからなのです。
PTAがそんなに押しつけ合いになるなら報酬を払えば良い、というアイデアはちらほら聞かれますが、私は否定的です。
ただ、従来からの「奉仕活動に報酬を要求するのはぎすぎすしたこと」という価値観の押しつけは、女性の無償労働にバックアップされて社会で報酬や承認をがっつり得ている「男」が言いがちなことであったとは思っています。
たどころ:
ああ、たしかにそれはあるかもしれませんね。私は以前に主夫をしていたこともあるのですが、あれは辛かったですね。自分の家事能力が低すぎて(笑)。
PTAは女性ばかりの組織なのに、なぜかPTA会長だけが男性というのも少し変な感じがしますね(女性の中にやりたい人がいないため、男性にお願いしているという見方もありますが)。
それはそれとして、お金の介在しないボランティアというゆるさがあるからこそ、ちょっと遅刻しても、多少非効率でも、おしゃべりに花が咲いても許されて、それがいいという人がいる。
任意加入にしたいという人の中には、「やる気」があって効率化を求める人もいるように見えますが、それが現行のPTAと相性が悪そうに見えることもあります。
ぶきゃこ:
仰る通り、私みたいな“非効率さを楽しめる”適性が環境的にも性格的にもない人を「ほんわかゆるゆる親睦重視の会社ごっこ」にむりやり巻き込んだらブラック化のもとですし、実際、しょうもない細部(と私には見える)ことにうだうだとこだわりたっぷり時間を使って先に進めないタイプの優雅な方とは、いっしょに活動やっても非常に相性悪かったですね。
疲れ切って保育園にお迎え行った後で夜の7時に帰り着き、上の子たちが口々にいろんなことを堰を切ったように話しかけてくるのをうんうん聞きながら、洗濯物を取り込んで風呂を洗って、とにかく先にご飯の下ごしらえを…とあせる中で子どもがしょうもない物の取り合いで喧嘩になったり、お母さん○○がない!とか言われて対応したり、そんな中で料理の最中にPTAの電話がかかってきて、講演会の動員の電話連絡網(しかも要領を得ない)をえんえんメモとらされたら、ぶち切れる程度には私はじゅうぶん狭量です(笑)。
ま、でもこういうことを「つらい」と訴えても、「大変なのはみんな一緒」「そういう状態にしてる自分が悪い」と自己責任論を言われるのがPTAという場でしたけどね、私にとっては。
私が言っているのは、当事者にならないとわからないメンタル状態もあり、それを無視して「理想のPTA」だけ語ってもそのように運営されるのは実際なかなかむずかしいし、むずかしいことは日本中で証明されている、ということです。
たどころ:
お話しはよくわかりました。本当は、いろんなタイプの人を包含するのがダイバーシティの面からも理想なんですけど、一緒にやりたくないと言われると辛いですね。
ぶきゃこさんの言うように、加入を任意にすることで、市場原理が働いて、活動が自浄化するというのは、その通りだと思うんです。任意でも入会してもらわなければならないとすれば、それだけ「魅力的な団体」になる必要がありますから。
しかし、それこそ営利目的ではない、報酬ももらわないボランティアのPTA本部役員に、そこまで市場原理に沿うことを求められるでしょうか?
お金をもらっていてすら、市場で勝つためのビジネスは難しいものです。ストレスもたまります。
改革や改善を必須にしたら、それこそ本部役員の成り手がいなくなるかもしれません。
今年の本部役員がだらしないから会員が減ったとか、そんなこと言われるなら、やりたくないですよね。
前例踏襲でゆるくやってもいいと思われているから、なんとか成り手が見つかっているのでは?
ぶきゃこ:
ボランティアでやってくれてるのに、「会員が減らないように営業努力する責任」をしょわせるのは酷、という話ですよね。
わからなくはないですし気の毒ではありますけれども、だからと言って自動加入で前年踏襲の比較的楽な運営方法を許せ、それが平穏に運営されるように保護者は協力しろ、となるとちょっと「無理を通そうとしすぎ」なんじゃないかと思いますよ。
それはこの社会において「そういう主張はちょっと無理では…」と思うからなのですが、それ(任意性の知識がひろまり安定運営が脅かされること)を「退会する保護者」の責任に帰す論調もあって、そうなると容易に「自分の都合の主張のし合い」「人格攻撃の応酬」になっちゃいますね。
まあ残念ながら、お金を管理し団体活動をおこなうということは、いろんな言葉も浴びる可能性があるってことですよね。
前例踏襲イコールゆるい、とも限らないでしょう。
むしろ、非難を浴びないことを眼目にやっていると、だんだん膨張してくるのがPTA活動の傾向のような気がします。
恵まれている人にはPTA問題がわからない?
ぶきゃこ:
PTAがゆるゆるを維持できるとしたら、ベタな言葉ですが「思いやり」ですよね。
役員さんありがとう、役員さんにそこまで求めたら酷、そういう思いやりをなくしてしまわないために、私はPTAと保護者を企業と客、あるいは使用者と労働者のような関係にする「対話のない自動加入」とそれに裏打ちされた「強制的な文言のプリントを配布したり、反応のない保護者に督促したり再配布する行為」について、まったくもって賛同できないでいるわけですね。
たどころ:
「思いやり」が必要という意見には全面的に賛同します。
PTAの役員だって、たまたま役員になっているだけの保護者で、自分がされたくないことは人にしたくないのではないでしょうか。
最初からギスギスしたい人がいないのに険悪になっているのであれば、それはどちらかがどこかで相手の感情を害して、ケンカになっているような気がします。
ぶきゃこ:
そうです。ですから私は「まぎらわしい手を使って自動入会させるのはやめようね。きちんと説明するのは礼儀だよね」とずーっと言っているわけです。それが始まりですから。
たとえば、お手伝いの依頼のプリントを配布して、挨拶も返信もなくスルーする人がおおぜいいるときに、役員の皆さんは「失礼ね」とか「ひどい」と感じていらっしゃいませんか?
その「ひどい」に感情を奪われているときに、そもそも自動入会させていることや、Noの選択肢がない希望票を一方的に期限を切って出すように求めていることの暴力性を、あわせて考慮できる人は、どのくらいいるのでしょう。
たどころ:
ああ、それは仰るとおりですね。
ぶきゃこ:
自分が「されたくないけど義務だからがんばってやった」と思えば、容易に「他人もやるべきだ」と思うようになりますよ。
人は「自分がされたくないことは人にしたくない」と思う、というのが常に変わらぬ真理なら、なぜ、世の中からいじめはなくならないのでしょうね? 大人の世界でもいじめ、たくさんありますよ。
どんなに理性のある大人でも、ストレスはいじめを誘発します。
もし「強要されている」と肌で感じられないのであれば、そのPTAの活動にそもそもストレス発生量が少ないからとか、男性はストレスのはけ口にされにくいとか、それなりに要因があると思います。
PTA被害が「共感できない」「イメージできない」ということであり、なおかつ「あなたはそう感じるんですね」という他者尊重よりも「何かをやらせたい(入会させたい、協力させたい)」が優先されるのであれば、「話し合いによる相互理解」はなかなかむずかしく、法に拠って解決するしかないのではないかと思います。
たどころ:
そういうお話しを聞いていると、PTA問題は格差問題という気がしてきますね。男女格差、経済格差、社会格差があって、PTA会長や自治会長に推薦されがちな、社会的に恵まれている層には現場の痛みがなかなかわかりづらいのだと。
まあ、私がお会いしたPTA会長さんの中には、地元の名士だけれども、家業は負債だらけだという人もいたので、格差問題も単純ではないような気もします。
いずれにしろ、PTA活動に困難を感じない恵まれている人が、困っている人の存在に気づきづらいのは普遍的な事実だと思います。
どこまで届くのかはわかりませんが、これを結びの言葉として、この対談を終わりにしたいと思います。読んでくださった方、長々とおつきあいいただき、どうもありがとうございました。