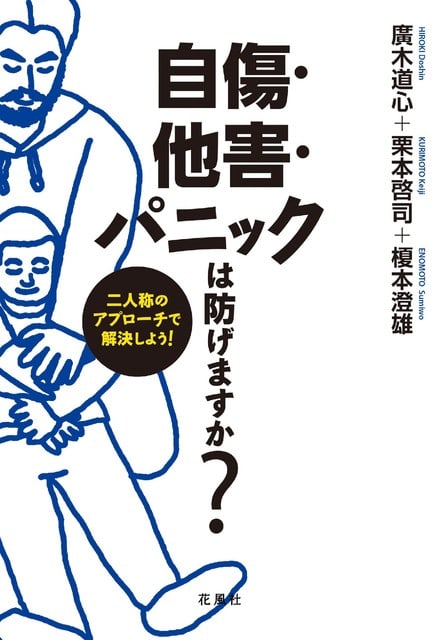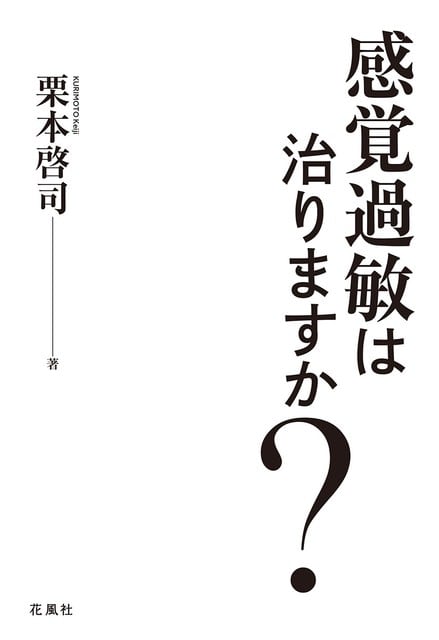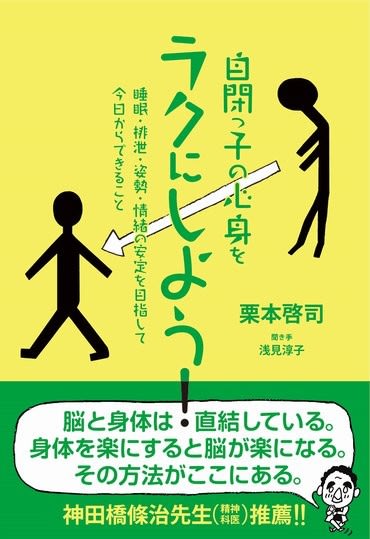今日も朝から子どもの遊ぶ声が聞こえます。うちの前、公園なんです。
しかもイマドキなんにも禁止していない公園で、三角ベースボールとかやってることもある。昭和かよ、っていう風景です。
都内でも、そしてそれどころか感染のぐっと少ない地方でも、公園の遊具を縛るという愚行が繰り返されたらしく、私は子どもたちがかわいそうでかわいそうで、時々早朝散歩して自粛警察警察をやっていました。
幸いうちの辺では遊具縛りもなかったし、マスクなしで遊び回る子どもたちに目くじら立てる大人もいなかったようです
ニキさんは聴覚過敏で子どもの声が苦手とか言っていましたけど、それって実にかわいそうだと正直思います。
私にとって子どもの声は平和の象徴です。
昼下がり、自分が仕事しているとき前の公園から立ち上がってくる子どもの声には心和みます。
コロナ休暇のときの街の風景について、母がこう言っていました。
「戦時中を思い出したけど、あのときとは違ったことが一つある。それは父親たちが家にいたこと。あのときはどの家庭にも父親はいなかった」
戦争にかり出されていたからですね。
それに比べて、今度のパンデミックでは父親たちは家にいた。っていうかいつもより家にいた。都会の真ん中で親子で夢中で木登りする姿とかをみて、いいなあと思ったもんです。できれば今後もあのお父さんたちが今までよりおうちで過ごせる時間が増えますように。多摩川の向こうの昼間人口を減らすためにもね。
ところで
この文章、発表されたときの一般の反応と私の反応は大分違って
なんかさ~プロらしくない発言。
それに「底意地悪いなあ」でした。なんて底意地悪い人たちなんだろう。
こういう発言が、玩具を縛らせたりする愚行を産むのではないだろうか。
私の感覚が変わっていたのかもしれませんが
今読んだら皆さんはどう思うんだろう。
私の感じ方はそれほど特殊ですかね?
子どもに八つ当たりすることはないと思うんですが、この国は実に子どもへの八つ当たりが得意だし正当化されますね。おそらく学校が始まっても色々制度として子どもをいじめる施策が続くと思います。
それには声を上げていきましょう。
しかもイマドキなんにも禁止していない公園で、三角ベースボールとかやってることもある。昭和かよ、っていう風景です。
都内でも、そしてそれどころか感染のぐっと少ない地方でも、公園の遊具を縛るという愚行が繰り返されたらしく、私は子どもたちがかわいそうでかわいそうで、時々早朝散歩して自粛警察警察をやっていました。
幸いうちの辺では遊具縛りもなかったし、マスクなしで遊び回る子どもたちに目くじら立てる大人もいなかったようです
ニキさんは聴覚過敏で子どもの声が苦手とか言っていましたけど、それって実にかわいそうだと正直思います。
私にとって子どもの声は平和の象徴です。
昼下がり、自分が仕事しているとき前の公園から立ち上がってくる子どもの声には心和みます。
コロナ休暇のときの街の風景について、母がこう言っていました。
「戦時中を思い出したけど、あのときとは違ったことが一つある。それは父親たちが家にいたこと。あのときはどの家庭にも父親はいなかった」
戦争にかり出されていたからですね。
それに比べて、今度のパンデミックでは父親たちは家にいた。っていうかいつもより家にいた。都会の真ん中で親子で夢中で木登りする姿とかをみて、いいなあと思ったもんです。できれば今後もあのお父さんたちが今までよりおうちで過ごせる時間が増えますように。多摩川の向こうの昼間人口を減らすためにもね。
ところで
この文章、発表されたときの一般の反応と私の反応は大分違って
なんかさ~プロらしくない発言。
それに「底意地悪いなあ」でした。なんて底意地悪い人たちなんだろう。
こういう発言が、玩具を縛らせたりする愚行を産むのではないだろうか。
私の感覚が変わっていたのかもしれませんが
今読んだら皆さんはどう思うんだろう。
私の感じ方はそれほど特殊ですかね?
子どもに八つ当たりすることはないと思うんですが、この国は実に子どもへの八つ当たりが得意だし正当化されますね。おそらく学校が始まっても色々制度として子どもをいじめる施策が続くと思います。
それには声を上げていきましょう。