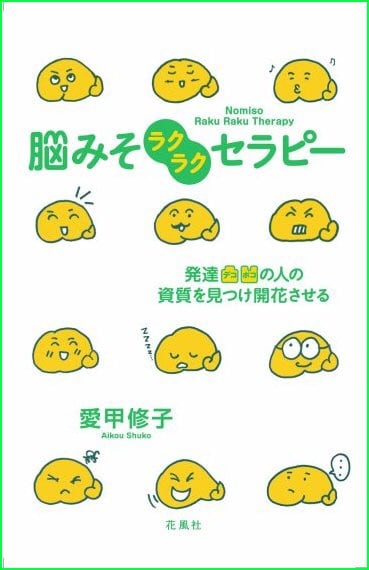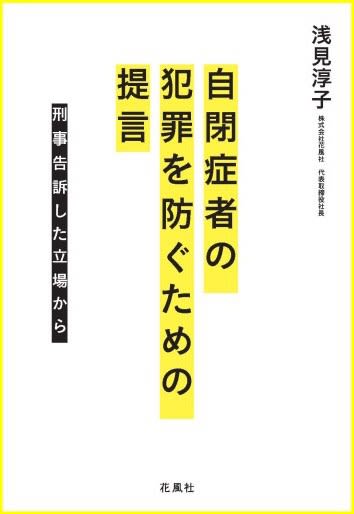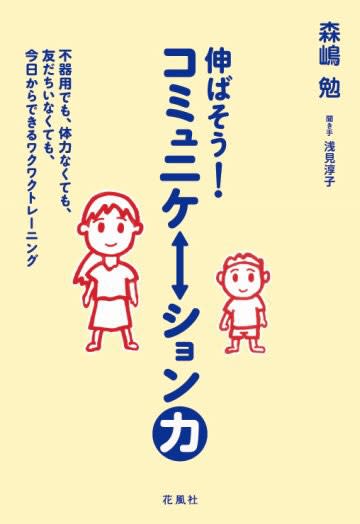今日はちょこっと保存版的なことを書きます。
猫本の感想とともに送られてきたメールを読んで
「身体アプローチに興味を持って取り組んでいても、何がどう効くかをわかって使い分けないと遠回りになるから、今の時点で私が各種身体アプローチをどう位置付けて本を出しているか説明しておいた方がいいかな」と思ったのです。
これは浅見私見です。
身体アプローチをしている人たちの本意ではないかもしれません。
それはそれでいいのです。なぜなら再三言っているように「本は著者のために出すものではない。読者のために出すものだ」なので、そしてうちで本を出す人にはそれをきっちり了解してもらっているので、「花風社がどうしてこの人たちの本を出すのか」に関しては私が独裁的に決めていいのだと理解してもらっているはずです。
では、以下、プライバシーに触れるところを隠しつつ、読者メールをご紹介させていただきます。
=====
猫本ふくめまして4冊、購入してよかったと思っております。
(中略)男子の母です。
ご多忙中恐縮ですが、御礼申し上げたくメール差し上げました。
特に猫本の漫画とポストカード、涙しました。
3歳ごろ、朝五時に日の出を見に行ったことを思い出しました。
その時はまったく自閉症だということに気がついていなくて、子育てって大変だな、
と思っていました。
でも夜明けの空は美しくて、子育てって知らないことをどんどん連れてくるものだな、
おもしろいなとも思っていました。
幼稚園もなかなか慣れないなど、いろいろありながらも、いつでも少しずつ成長して
きましたし、やること、話すこと、とにかくいつも発見があり、おもしろい子だなと思って
一緒に歩んできました。
(中略)
小学校は普通級で入学しましたが、第一週目から大きくつまづき、学校から受診を勧められ、
自閉症スペクトラムと診断を受けました。
字も書けず、本も読めずで、ディスレクシアかも?と(こちらの知識はありました)
(中略)
キャッチボールしたり、道具を工夫したり、作文のスモールステップを考えたり、
徹底して興味ある分野の本を集めたりするなど、学習障害へのアプローチは取り組め、
効果も出てきて、ずいぶん学校でも過ごしやすくなりました。
ただ体験記などを読むと、どれも「悲愴」な雰囲気。
はちゃめちゃな日々だけど、少しずつ伸びていくのはうれしく、けっこう楽しいことも
多いので、違和感を持ちました。
将来、こんなに悲惨になるの?と、読むほど沈んでいくといいますか・・・。
そんな中、(中略)本棚で見つけたのが花風社の本でした。
二年生から支援級に入級し、少しずつ付き添いを減らしながら、
ほぼ休みなしで通学しています。
先生たちには本当に成長しましたね!と言われるのですが、
親としてまだまだ課題が多く、一番むずかしいなと思っているのが他害の問題です。
先生は減ったと認識されていますが、私の方針は、小さなことも、一つも無視しない、
根は深いと感じています。
息子の場合は、空間感覚のズレが一番の要因となっています。
例えば教室を移動するとき。
これから体重測定など憂うつなことが待っていると、
行列を作った時にまわりの子どもに挟まれるのが苦しくなります。
そして特に男子との距離が数センチになると、反射的に払う。
「たたかれた!」
まず本人に絶対に人をたたいてはいけないことを伝えます。
そして先生にも一緒にその旨を伝え、しばらくの間は一番端っこに並ばせてもらったり、
女子の後ろに並んでもOKにしてもらい、女子にも了解してもらうようにお願いしました。
運動会の綱引きでも、最初は普通に並んでみましたが、前の子が綱を引っ張るのに
熱中して結果的に体をおしつけてくると「やめて!」と蹴ってしまう。
最後尾に変えてもらい、さらに綱も少し延長して引っ張りやすくして、参加しました。
この経験は、後に劇などでの位置取りにも応用できました。
もちろん人生でずっとこのように配慮し続けてもらうことは期待できません。
将来的には感覚統合的なアプローチで楽になっていこう(スルー力を身につけよう)と
本人、先生とも認識を共有しつつ、現時点では配慮してもらう。
またいずれ対話が上手になって「自分はこういう感覚を持ってるから、少し離れて並びます」と
自分で説明できるスキルも身につけていければと思っています。
授業参観など、緊張が高まる授業では、発言したいのに当ててもらえない時など
机をガタンっと蹴ってしまう、ということもまだまだあります。
モノに当たっても、結果的に他の子にぶつかりそうになって、静まり返る教室。
泣きたくなるシーンです。
でも冷静に「今どんな気もちだったか、どうすればよかったか、これからどうしたらいいか」
を、支援級の先生と一緒にその場で話しあいます。
(担任の先生はそのまま授業を続けているので、流れを止めずにすみます。
こういう時に支援級に入ってよかったと思います。)
頭ではしてはいけないと分かっていても、「腹が立った時」には「頭より体が先に
動いてしまう」。
たぶん、他の子たちが、意識の中で“遠い”。
自分とつながりがある存在だという感覚が薄いのだと思います。
(自分の身体感覚が延長できていないと言うか、
定型発達の子だったら、他の子の痛みももう少し自分の痛みとして感じて、想像して、
行動が制御できるのではないか、と想像します。仮説ですが。)
担任の先生も、支援級の先生も「見逃さない。もし相手が痛みを感じることを
してしまったら必ず謝る」を徹底してくださっているので、一緒に取り組んでいます。
「頭より先に体が動く」、防衛的な時と攻撃的な時、両方あります。
話して諭すのも大事だし有効、だけど、身体感覚を養うことも絶対必要だなと感じています。
まずは毎日金魚体操、足裏を触って、地に足をつけるところから。
家ではおすもう遊び、キャッチボールなど、いろいろやりながら、
チットチャットの順番待ちをしています。
ブログで他害の話題が出ていたこともあり、長くなってしまいました。
猫本に戻りますが、子育てを楽しんでいたことを肯定されたように思いました。
うまく言えませんが、「自閉症の孫育てをしてみたい」という気持ち、うん、わかる!という
感じです。
私のカンも、まだまだ磨いていかねばと思っています。
親も運動、必要ですね。
こよりさま、浅見さま、ありがとうございました。
これから出る本も楽しみにしています。
=====
ということなのですが。
他害をしてしまう問題が身体にある、という認識は、おそらく芋づるの端っこ。そしてそういう認識を連れてきたというところで、感覚統合の視点の貢献は大きいのです。
でも感覚統合が置き去りにしているものがあります。
それは内臓方面なのです。
そして、「芋づる式に治そう」を読むと
「季節に変動されやすい」凸凹さんたちの問題は、空間認知ではもちろんなく、内臓方面から来ているのがわかると思います。そこに働きかけるアプローチで、今年は季節の乗り切りが上手になった人が多くなった年でした。かくいう私もそうです。年の初めの冬も、年末の冬も、静電気でぴりっときません。毎年秋口に出ていた咳が出ません。耳鼻科の診察券をしまったまま秋を過ごしました。冬からコンディショニングを始め、自閉っ子の鬼門である新学期を崩れることなく過ごした自閉っ子ママたちからの声が花風社にはたくさん届きました。そういう一年だったから、私は晴れ晴れとした気分で年末を迎えているのです。
そして他害。
これが身体アプローチでどうにかできるのは確かだと思うのですが
少なくとも
「友だちをぶちません」とか視覚支援したり、一粒の卵ボーロで子どもを買収する犬の曲芸方面よりはるかに「他害をしないですむ身体」を作ってあげたほうが近道だと思うのですが
他害が起きてしまうのは空間認知だけではなく、内臓方面に不全感があるかも、というのがコンディショニングの視点なのです。
でもそれに薬を入れる必要はない。整えていけばいいのです。そのための黄色本芋本に載っているアプローチなのです。
チットチャットでは、本当に効果があるSSTができます。
それは奴隷道徳の丸暗記みたいなSSTではなく
生き物としてもっと土台に働きかけるSST。
今になってつくづく、あの本を「伸ばそう! コミュニケーション力」と名付けた自分に感心します。まるでその後の展開が見えていたように。たぶん自閉の神様の仕業でしょう。
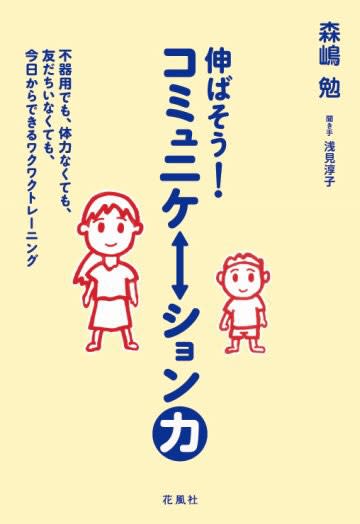
そしてその順番待ちをしながら、ご家庭で色々取り組まれている。だからこそ世にあまたある悲愴な体験記とは違ってお子さんの成長が喜べる現状があるのでしょう。
そしてどちらかというと西日本の方だから、チットチャットが近いのでしょうが
なぜチットチャットで順番待ちをしなければいけないかというと、受給者証で受ける療育は官からお金が出ているから。血税使ってます。皆さんが無料または安価で療育を受けられるのは、他の誰かが税金を負担しているからです。だから定員があるのです。
官がお金出すところは、当然ですが定員を厳しく管理します。当たり前です。みんなのお金ですから。だから順番待ちが発生します。
でも栗本さんは個人で開業しています。官からお金が出ているわけではありません。だから順番待ちをしなくて済みます。空いている時間を調整すればいいだけです。
そして栗本さんのところでは、内臓方面へのアプローチが習えます。おうちでもできること。それで不登校の子が学校に行き始めたり、そういうことが起きています。
感覚統合で空間認知という視点を得られたことは素晴らしいことでした。
視覚支援と犬の曲芸で治らないから発達障害は治らないことにしてそれに胡坐をかいてきたギョーカイ。でも身体アプローチのとっかかりとして感覚統合は貢献したと思います。何より、「二覚」の存在に気づかせてくれたのは感覚統合の大きな仕事。
でも今は、感覚統合よりもっと、内臓方面に働きかけるアプローチが出てきているのです。そしてそれが行動上、情緒面での問題を解決していく。それが確かめられた年でした、今年は。それを実感し、伝道してくれる仲間がいっぱいできた年でした。南雲さんもそのおひとりです。
だから
チットチャットの順番待ちをしながらおうちで取り組み
その間に内臓方面でのアプローチも小田原で習うと最強だと思います。そして晴れてチットチャットの順番が回ってくれば、今度は「他人とともに暮らすこと」「頑張ること」を大脳皮質より下の土台の脳で覚える機会が得られます。
こうやって宣伝しているのは、もりしーさんのためでも栗本さんのためでもないんですね。このおっさんたちは私にはどうでもいい。このおっさんたちは、私がいなくても別に野垂れ死にしません。勝手に自分のするべき仕事をして世の中に受け入れられていくでしょうから。
私にとって大事なのは、子どもたちなのです。
そういう意味で私は南雲さんと同じように子ども原理主義です。
そしてその子どもたちのためにこそ、このおっさんたちと仕事をしているのですよ。そういう順番です。
はっきり言ってしまうと
感覚統合を否定はしません。大事な視点だと思いますが
「治す」という点にかけては
花風社は感覚統合を超えたのです、実は。
他害(等の問題行動)が空間認知、感覚過敏由来、であるのは間違いない。
そしてその根底に内臓の不全感がないか。そしてそれは治せるものなのではないか。
そういう段階に、花風社はいるのです。