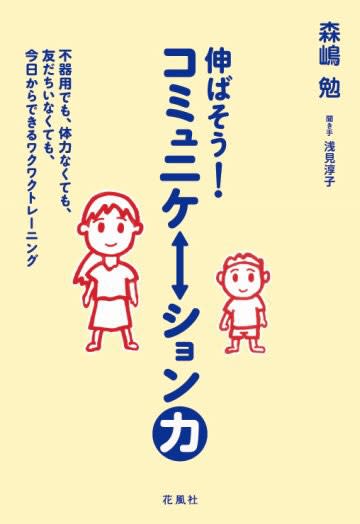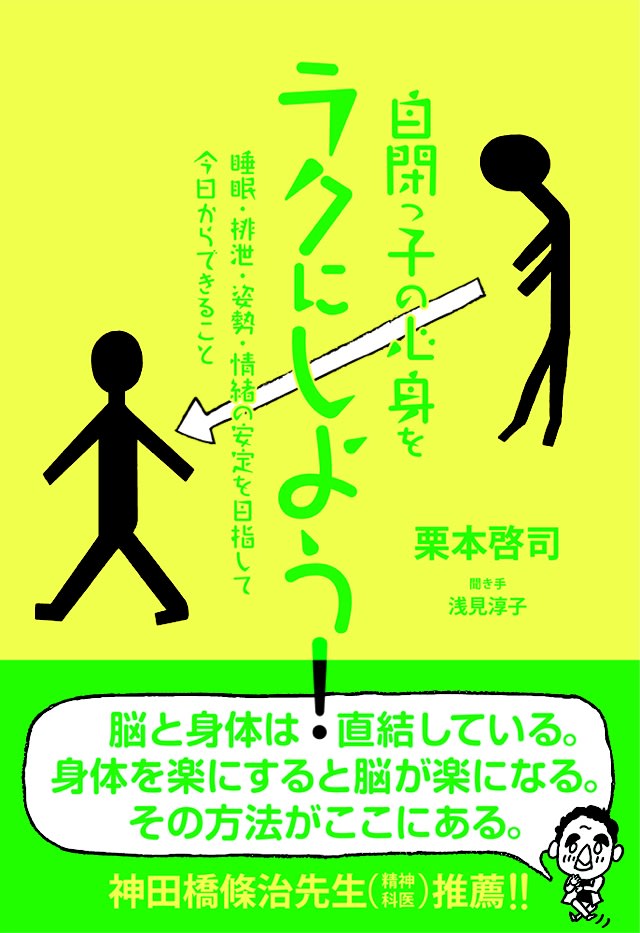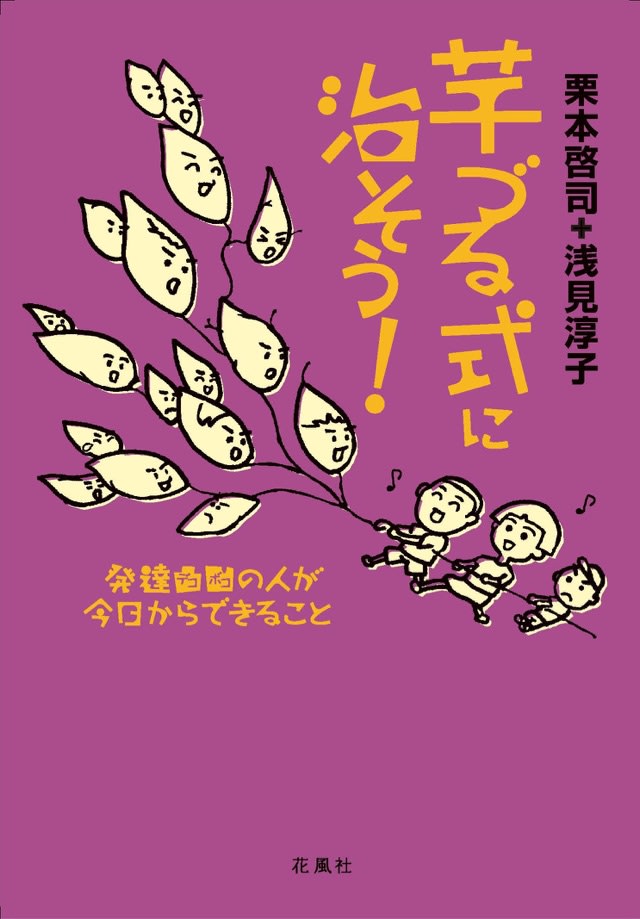さて、11月28日の講座、午前は埋まりました。以降キャンセル待ちでお受けいたします。
午後はまだ余裕があります。っていうほどないけど、まだお席あります。
はて。
正直、私がどちらかしか選べないとしたら、絶対午後の講座を選ぶんですけどね。わりと時間長い(部屋は五時まで借りてあるので毎回無制限な感じ)からその分お得だし、栗本さんになんでも質問できてその場で実演もしてもらえて、という意味では私が参加者なら午後にお得感を見出します。
でも
それって私が割合「正解幻想」から解き放たれている人だからかもしれないなあ、と思いました。午前はたしかにプログラムに乗っかってればいい。そして今度のテーマが金魚体操だから、「自分のやってる金魚が正しいのか」知りたいという需要が多い。
自閉の人って相当「正解幻想」にとらわれてて、それで苦しいんだといつも思うのですが、そもそも自閉でなくても今の学校教育やなんかをまともに受けていたら「正解は自分の外にあって、それを誰かが(この場合だと栗本さんが)知ってるはず」っていう思い込みにつながりますね。そして社会のなかでは、この「正解幻想」がわりと生きるのを困難にするよね。
金魚体操に関してこういう誤解しないでね、っていうのは黄色本にも芋本にも書いてあります。たとえば「ちゃんとうまくいくと揺らす方は疲れない」ことなんかかなりくどく入れてある。両腕で両足を振り回していたら親の方が腰をやられるでしょ。でもそうじゃないよ、ってくどくど書いてある。
あとはね、極端な話どういうやり方だろうと「ああ気持ちいい」でぐっすり眠れるのならそれがその人にとって正しいやり方なんですよ。
8の字に関して、動画にしてアップしてほしいという読者の方々の声を神田橋先生に伝えたら、それはやらないと言われたけどそれもたぶん同じ理由。
すごくみんな、型にこだわるの。
正解があるのだと正解さがしに躍起になるの。
その結果は好ましいものではない。
自分の身体の声を聴かなくなるから。
その金魚が合ってるかどうか知ってるのは
栗本さんより皆さんの身体なんですよ。
それがたぶん学校教育の悪しき産物だとして、どうして私はそこから自由なのかなと考えたら
私は学校教育に関しては「要領のいい劣等生」だったなあと思いました。
学校教育に染められることはなかった。でも取り立てて反抗的じゃなかったよ。反抗することなく、面従腹背でした。ああこのプロセス(学校生活)どうやら通んなきゃいけないみたいだしこの人たち(教師)ともつきあわなきゃいけないみたいだからてきとーにこなしてもらえるもの(知識とか学歴とか)はもらっとこう、みたいな。
そして社会人になると正解なんて誰も知らなくて、自分で手探りで仮説を立てては永遠の試行錯誤を繰り返すのが当たり前なので
「誰かが正解を知っている」と素朴に信じられる人は、もしかしてある意味では苦労していないのかな、とか思ったりします。もちろん私とは違う苦労を味わってきたのでしょうけどね。
まあともかく
ぶっちゃけた話、私が花風社の読者で、黄色本芋本読んで「自分の金魚がちゃんとやれているかどうか知りたい!」って思ったら
そして第一部第二部どちらかしか出られないということなら
第二部に出てその場で栗本さんに自分のやっている金魚見せてアドバイスもらいますね。
午前に出た人しか、金魚習えないんじゃないのよ。
午後はなんでも質問していい会なんだから、「私の金魚これでいいでしょうか?」もありなのよ。そうしたら栗本さんはプロなんだから「それでもいいけど、この人はこちらに揺らすといいかも」とかアドバイスしてくれる、とかそういう流れになるわよ。
そういう「なんでもありなんだ」「自分に合ってるものが正解なんだ」「正解にたどりつうためにプロの力を借りるけど、最終的には正解は自分の中にあるんだ」みたいな発想が自然にわいてくるようになると、たぶん療育はラクになると思います。
まあこれを一番自覚していないの、紋切り型支援者かもしれないけど。その辺は南雲さんが本に書いてるね。