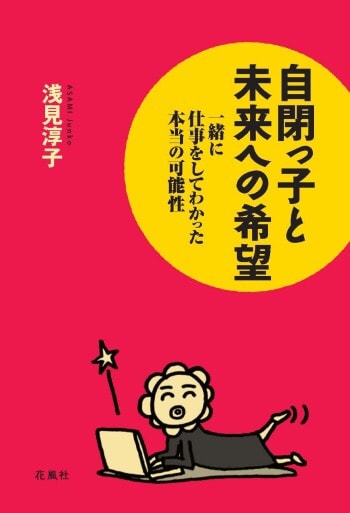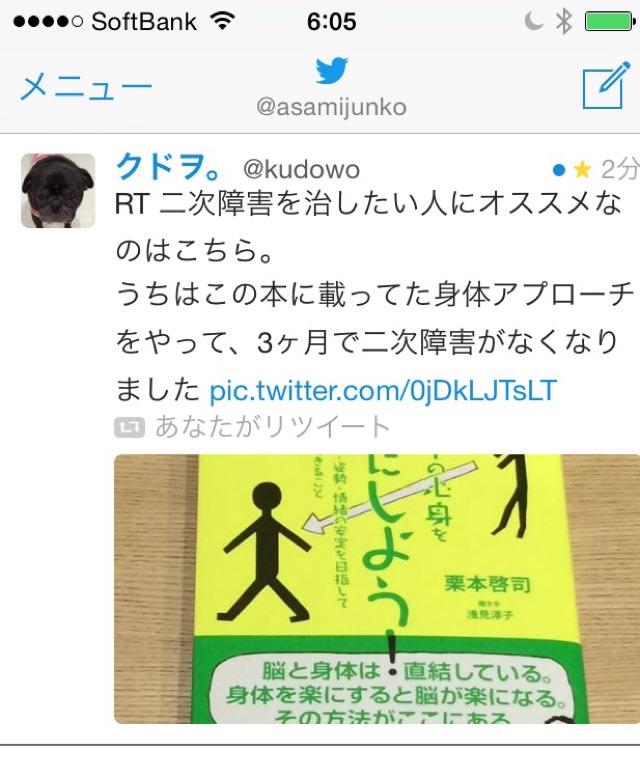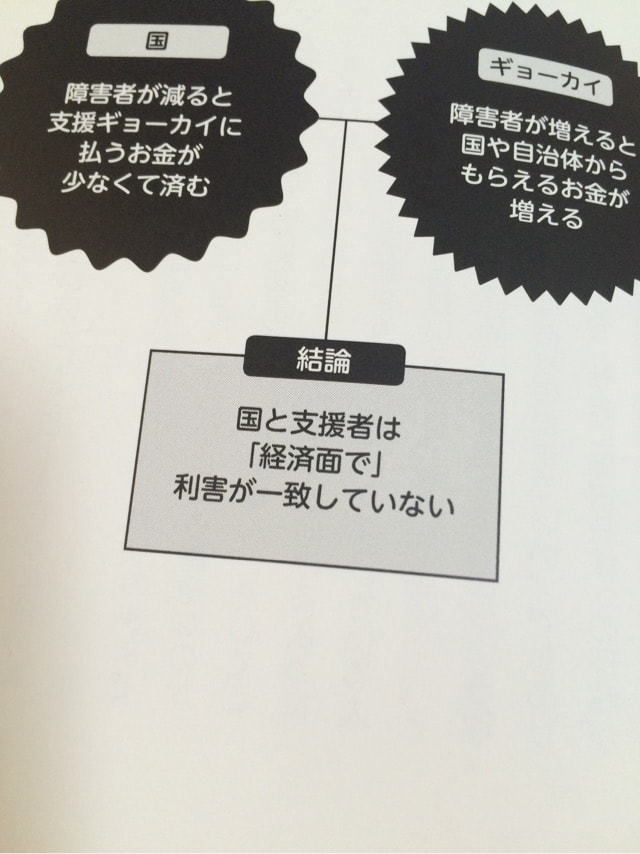さて、昨日書いた通り誤学習は治るんですけど
それをどう説明しようか今日考えてました。
正直、誤学習の予防(親御さん)
と
誤学習の解毒(成人当事者)
にはニキさんのこの四冊に勝るものはないと思うんですけど

そして私自身、ニキさんの誤学習が解けてく瞬間に立ち合ったりもしたのですが
ニキさんに真っ先に学んで誤学習を解いていった人の一人がちゅん平さんだということを思い出しました。
彼女のひ弱さが強さに変わっていったのには身体アプローチの効果ももちろんあるんだけど
誤学習が解けていって余計な体力使わなくなったっていうのもとても大きいのです。
その成長を語る四冊。
ちゅん平さんがどんな風に誤学習を解いていったのか、この本たちを読むとわかります。
とくに、左上から時計回りで読むと追っかけやすいかも。

それをどう説明しようか今日考えてました。
正直、誤学習の予防(親御さん)
と
誤学習の解毒(成人当事者)
にはニキさんのこの四冊に勝るものはないと思うんですけど

そして私自身、ニキさんの誤学習が解けてく瞬間に立ち合ったりもしたのですが
ニキさんに真っ先に学んで誤学習を解いていった人の一人がちゅん平さんだということを思い出しました。
彼女のひ弱さが強さに変わっていったのには身体アプローチの効果ももちろんあるんだけど
誤学習が解けていって余計な体力使わなくなったっていうのもとても大きいのです。
その成長を語る四冊。
ちゅん平さんがどんな風に誤学習を解いていったのか、この本たちを読むとわかります。
とくに、左上から時計回りで読むと追っかけやすいかも。