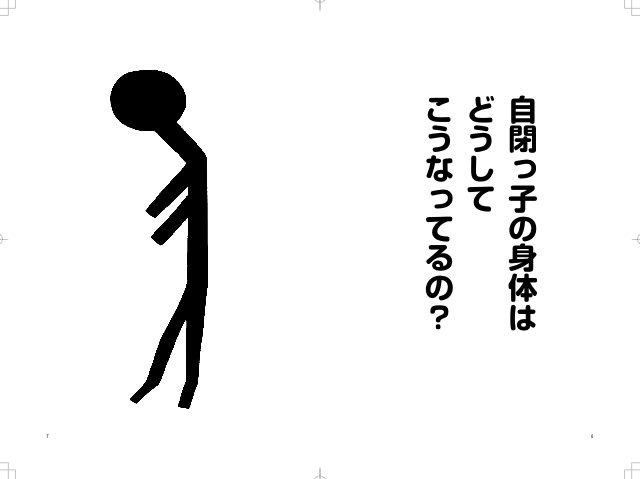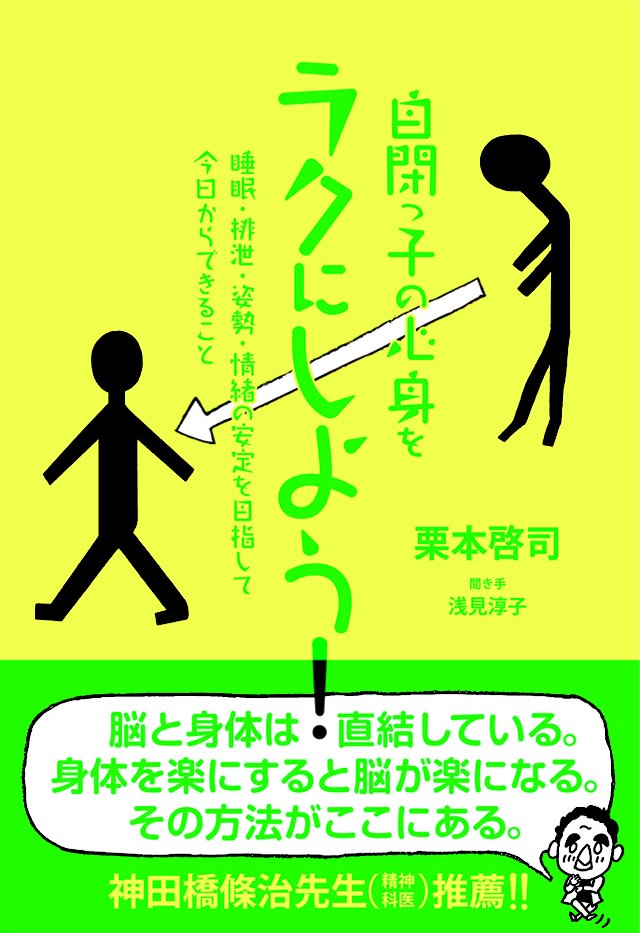感覚過敏のほとんどない私が、なぜ人々に五感の違いがあることをあっさり飲み込めたかというと
我々にとってはぬるいジャグジーであちちと言っている白人の皆様、みたいに人種や生活習慣に由来する違いって大きいんだなあと感じたこともあるけど
そのずっと前から、両親のボリューム争いを見て育ったせいかもしれない。
父と母は適切なテレビのボリュームが違うようでした。
父が一人で家にいるところに帰宅すると、すごく大きい音でテレビを見ている。
母はそれを聞いて「なんでこんな大きい音で!」となる。
私は幼い頃から二人を見ていて、たんに快適な音が違うだけなのになあと思っていた。
そして私はどっちに近いかというと、どっちもまったく平気なのであった。
三人の中で一番スイートスポットが広いのかも知れない(聴覚面では)。
さてそんな私がデジタル耳栓に興味を持ったのは、ASDの人に聴覚過敏があって、その聴覚過敏を持つ人たちがこれだけ助かっているという情報を手に入れたからです。脳が楽になるらしい。
身体で実験する派としての私としては、ぜひ実験してみようと思った。
あと一つ、耳栓を手に入れたかったのには理由がある。
家族の中の五感の違い。それはトラブルにもなりうるが、メリットもある。我が家がそうだ。
まぶしがり屋気味で仕事部屋は北側を好む夫と、お日様原理主義の私。
私は争うことなく、大好きな南側の仕事部屋を手に入れた。
丹沢と富士山とみなとみらいが見える自慢の仕事部屋である。
前は市営の公園。午後になると子どもたちの声が聞こえてくる(まあこれも聴覚的に耐えられない人もいるみたいだけど、私にとっては心地よい音)。
ところがこの公園の半分で、今は工事をしている。なんか地下に治水設備を作っているらしい。すでにその成果が現れていて、雨が降っても水はけがよくなったと近所の人が言っていた(私は気づかない)。
エアコンつけずに開け放つことの好きな私だが、工事の音のために窓を閉めることが増えていた。
デジタル耳栓があれば、窓を開けていられるのではないかと思ったのだ。
そしてデジタル耳栓が来て。
聴覚過敏のない人としての感想です。
え~と、これでうるさい音が消える、っていうことは
聴覚過敏の人は、相当つらいんだと思います。ふだん。
なぜなら私のつけた感想は
「全然聞こえなくならない」なんですよ。
逆に言うとこの耳栓が消す生活ノイズ(エアコンとか)を私の耳は全く無視しているんだと思いました。
そもそもこの耳栓には飛行機マークがついていて、飛行機に乗ったときの使用も想定されているみたいなんですけど
飛行機って乗ってるとうるさいですかね? 私、感じたことないんですけど。
飛行機で眠れないっていう経験もまずないし。
って思いながら、昨日一駅だけ新幹線に乗って、こんでいたのでデッキに立っていて
ああ、ここもたしかに音がするなあ、こういうのが気になるのが聴覚過敏なんだな、って思いました。
でもやっぱり私の耳は、そういう情報は自動的にはじいているらしいです。
そして肝心の工事の音ですが
聞こえる。
でもたしかに、若干丸くなる。
つまり、窓を開けていられる時間が長くなる。
っていう感じかな。
というわけで私がデジタル耳栓を使った感想は
「これで助かるということは、聴覚過敏ってやっぱり大変なんだな」でした。
そして「自閉っ子の心身をラクにしよう!」の中で栗本さんが一つ
聴覚過敏への対策を仮説としてあげてるでしょ。
岩永先生に献本するときお手紙に書いたんですけど
「これって現場では気づかれているのかも知れませんけど、活字にはなかなかしにくいですよね。でもしちゃいました」みたいなことを書いておきました。
それで助かる人が一人でも増えればいいと思ってね。
どっちみちそっち方面にコンディショニングするのは身体全体にとって健康なことだし。
そして瀧澤久美子さんにこの話したとき「それで治る子がちょっとでもいればいいですね」と言われたときに
本当にそうだなと思ったのです。
デジタル耳栓みたいな便利なものの出現は喜ばしいとして
やっぱり耳栓つけなくて良くなる方法があれば、試してみたいですよね。


我々にとってはぬるいジャグジーであちちと言っている白人の皆様、みたいに人種や生活習慣に由来する違いって大きいんだなあと感じたこともあるけど
そのずっと前から、両親のボリューム争いを見て育ったせいかもしれない。
父と母は適切なテレビのボリュームが違うようでした。
父が一人で家にいるところに帰宅すると、すごく大きい音でテレビを見ている。
母はそれを聞いて「なんでこんな大きい音で!」となる。
私は幼い頃から二人を見ていて、たんに快適な音が違うだけなのになあと思っていた。
そして私はどっちに近いかというと、どっちもまったく平気なのであった。
三人の中で一番スイートスポットが広いのかも知れない(聴覚面では)。
さてそんな私がデジタル耳栓に興味を持ったのは、ASDの人に聴覚過敏があって、その聴覚過敏を持つ人たちがこれだけ助かっているという情報を手に入れたからです。脳が楽になるらしい。
身体で実験する派としての私としては、ぜひ実験してみようと思った。
あと一つ、耳栓を手に入れたかったのには理由がある。
家族の中の五感の違い。それはトラブルにもなりうるが、メリットもある。我が家がそうだ。
まぶしがり屋気味で仕事部屋は北側を好む夫と、お日様原理主義の私。
私は争うことなく、大好きな南側の仕事部屋を手に入れた。
丹沢と富士山とみなとみらいが見える自慢の仕事部屋である。
前は市営の公園。午後になると子どもたちの声が聞こえてくる(まあこれも聴覚的に耐えられない人もいるみたいだけど、私にとっては心地よい音)。
ところがこの公園の半分で、今は工事をしている。なんか地下に治水設備を作っているらしい。すでにその成果が現れていて、雨が降っても水はけがよくなったと近所の人が言っていた(私は気づかない)。
エアコンつけずに開け放つことの好きな私だが、工事の音のために窓を閉めることが増えていた。
デジタル耳栓があれば、窓を開けていられるのではないかと思ったのだ。
そしてデジタル耳栓が来て。
聴覚過敏のない人としての感想です。
え~と、これでうるさい音が消える、っていうことは
聴覚過敏の人は、相当つらいんだと思います。ふだん。
なぜなら私のつけた感想は
「全然聞こえなくならない」なんですよ。
逆に言うとこの耳栓が消す生活ノイズ(エアコンとか)を私の耳は全く無視しているんだと思いました。
そもそもこの耳栓には飛行機マークがついていて、飛行機に乗ったときの使用も想定されているみたいなんですけど
飛行機って乗ってるとうるさいですかね? 私、感じたことないんですけど。
飛行機で眠れないっていう経験もまずないし。
って思いながら、昨日一駅だけ新幹線に乗って、こんでいたのでデッキに立っていて
ああ、ここもたしかに音がするなあ、こういうのが気になるのが聴覚過敏なんだな、って思いました。
でもやっぱり私の耳は、そういう情報は自動的にはじいているらしいです。
そして肝心の工事の音ですが
聞こえる。
でもたしかに、若干丸くなる。
つまり、窓を開けていられる時間が長くなる。
っていう感じかな。
というわけで私がデジタル耳栓を使った感想は
「これで助かるということは、聴覚過敏ってやっぱり大変なんだな」でした。
そして「自閉っ子の心身をラクにしよう!」の中で栗本さんが一つ
聴覚過敏への対策を仮説としてあげてるでしょ。
岩永先生に献本するときお手紙に書いたんですけど
「これって現場では気づかれているのかも知れませんけど、活字にはなかなかしにくいですよね。でもしちゃいました」みたいなことを書いておきました。
それで助かる人が一人でも増えればいいと思ってね。
どっちみちそっち方面にコンディショニングするのは身体全体にとって健康なことだし。
そして瀧澤久美子さんにこの話したとき「それで治る子がちょっとでもいればいいですね」と言われたときに
本当にそうだなと思ったのです。
デジタル耳栓みたいな便利なものの出現は喜ばしいとして
やっぱり耳栓つけなくて良くなる方法があれば、試してみたいですよね。