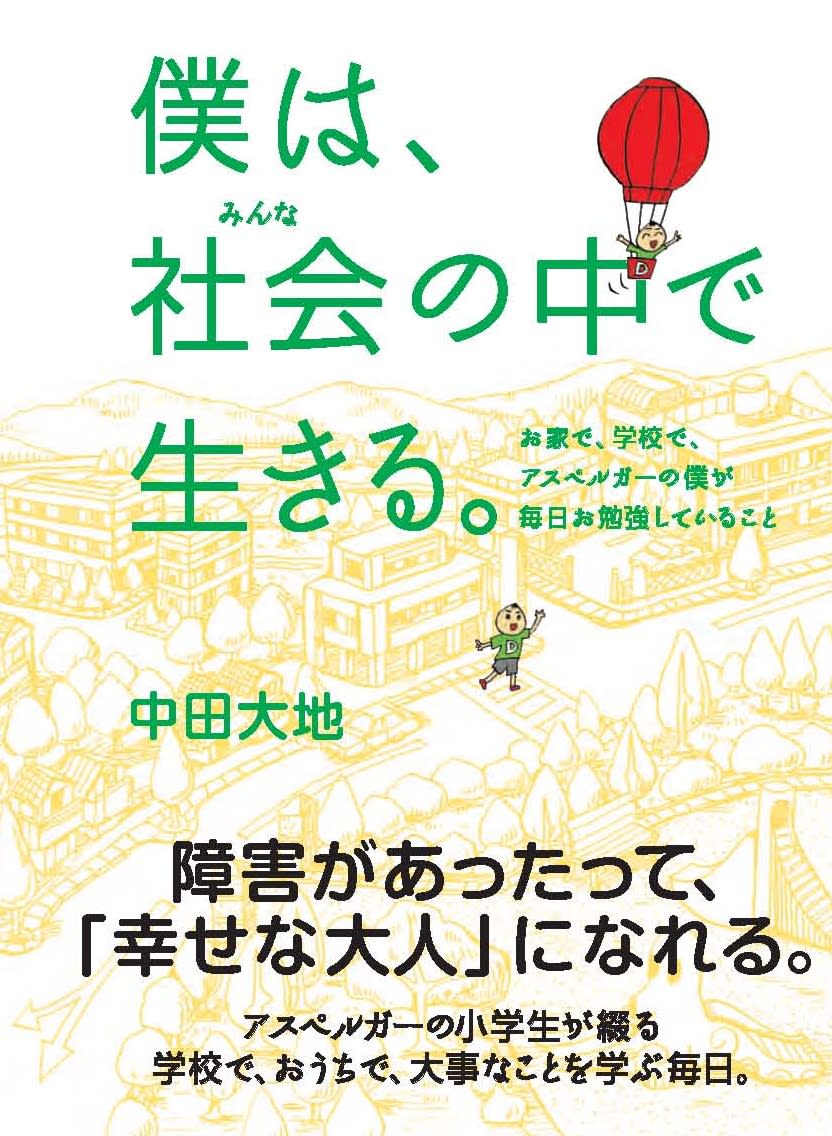さて、感覚統合学会のランチタイムにカツ丼を完食したちゅん平さん。
「しかもお箸ですよ」という。
おお、たしかに。
ちゅん平はきちんとお行儀をしつけられて育った人なので、もちろんお箸は使えます。
でも苦手。あれも運動企画だし。とくに疲れたときにはお箸で食事をするのはきついことのようでした。
刺激物にとても弱い人だったのに、外食でよくカレーを選んでいたのは、スプーンで食べられるからだろうなあと思っていました。
でもカツ丼のぽろぽろこぼれるご飯をちゃんとお箸で完食。
そうだなあ、これも発達。
そういえば、と思って
先日長沼先生に習った「一秒でわかる筋肉状態テスト」をやってもらいました。
札幌の講演来てた方はわかりますね。
私はお医者じゃないので、ここで詳しく書くことはしませんが
長沼先生から習いました、と他のドクターに先日お見せしたら「おお、たしかにわかるねえ」と言われましたよ。
郡司先生が「学校の教師でも使えるアセスメント方法ありませんか?」ってきいたら出てきたのよね。
こんな簡単な方法で、その子の体性感覚の大事な一部がわかるなんて
ニキさんじゃないけど「専門家の皆さん、そういう大事なことは早く言ってください」って感じだわ。
まあともかく、この一秒でわかる筋肉状態テストを私がやるとこういう感じ。
画伯に頼むほどのことじゃないので私がiPadで描きましたよ。

これはきわめてふつうみたいです。
で、ちゅん平さんがやるとこういう感じ。

長沼先生が言ってたなあ。低緊張の人はこうだって。
つまりちゅん平さんはやっぱり自然にしていると低緊張だから
お箸はそうじゃない人より重労働なわけですね。
これは運動方面の問題ですけど
今度の感覚統合学会では、専門家の皆さんが「感覚調整障害の存在証明」を一生懸命やってらっしゃいましたが
私が自閉症の人とつきあいはじめてまず気付いたのはそこというか
彼我の一番の違いは三つ組以前にそこだろう、と思っていたので
私には存在証明必要ありません。
でもわかんない人が世の中にはいっぱいいて、だから先生たち必死なんだろうなあと思いました。
私は最初から気づいていました。
それに名前がついていて、研究している先生たちがいると知ったのがあとの話ですからね。
「しかもお箸ですよ」という。
おお、たしかに。
ちゅん平はきちんとお行儀をしつけられて育った人なので、もちろんお箸は使えます。
でも苦手。あれも運動企画だし。とくに疲れたときにはお箸で食事をするのはきついことのようでした。
刺激物にとても弱い人だったのに、外食でよくカレーを選んでいたのは、スプーンで食べられるからだろうなあと思っていました。
でもカツ丼のぽろぽろこぼれるご飯をちゃんとお箸で完食。
そうだなあ、これも発達。
そういえば、と思って
先日長沼先生に習った「一秒でわかる筋肉状態テスト」をやってもらいました。
札幌の講演来てた方はわかりますね。
私はお医者じゃないので、ここで詳しく書くことはしませんが
長沼先生から習いました、と他のドクターに先日お見せしたら「おお、たしかにわかるねえ」と言われましたよ。
郡司先生が「学校の教師でも使えるアセスメント方法ありませんか?」ってきいたら出てきたのよね。
こんな簡単な方法で、その子の体性感覚の大事な一部がわかるなんて
ニキさんじゃないけど「専門家の皆さん、そういう大事なことは早く言ってください」って感じだわ。
まあともかく、この一秒でわかる筋肉状態テストを私がやるとこういう感じ。
画伯に頼むほどのことじゃないので私がiPadで描きましたよ。

これはきわめてふつうみたいです。
で、ちゅん平さんがやるとこういう感じ。

長沼先生が言ってたなあ。低緊張の人はこうだって。
つまりちゅん平さんはやっぱり自然にしていると低緊張だから
お箸はそうじゃない人より重労働なわけですね。
これは運動方面の問題ですけど
今度の感覚統合学会では、専門家の皆さんが「感覚調整障害の存在証明」を一生懸命やってらっしゃいましたが
私が自閉症の人とつきあいはじめてまず気付いたのはそこというか
彼我の一番の違いは三つ組以前にそこだろう、と思っていたので
私には存在証明必要ありません。
でもわかんない人が世の中にはいっぱいいて、だから先生たち必死なんだろうなあと思いました。
私は最初から気づいていました。
それに名前がついていて、研究している先生たちがいると知ったのがあとの話ですからね。