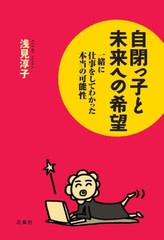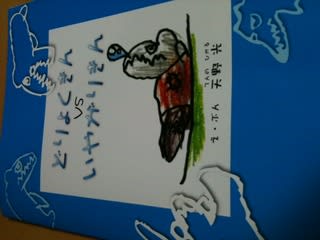12月28日のエントリー「おまわりさんにつかまるよ」に関して
国家資格を持って地域支援に当たられている読者の方からこういうアドバイスをいただきました。
色々謎が解けた思いがしますので、皆様とこれを分かち合いたいと思います。
=====
自閉症スペクトラムの男性で、多動や自制が困難などの理由で、(おそらく知能面で
問題がある人の方が多いと思いますが、)自分の男性器をいじってしまう人はわりと
います。
そして、自閉症スペクトラムは、遺伝が関連していると思われる人が、もちろんすべ
てではありませんが、いくらかの割合います。
そのため、発達や知的障害の人の支援に関わっていると、両親のいずれかが、どこか
変わっている面があって、一緒に関わっていくことが難しいと感じさせられることが
あります。
自閉症スペクトラムの本人は、むしろ純粋な人が多いのです。
> 自分の見方が世界で唯一だと思い込んでいるらしく、
これも、おそらく何らかの障害による認識の偏りではないでしょうか。違う見方が極
端にできない人っています。
また、その概念が、歳をとっても現実的になるということが難しい人もいます。
> いい加減自分の「想像力の障害」に気づけばいいのに、と思って見ていた。
そういう人は、自分の思い込みや予想と違っても、自分の見方が間違っていたと、そ
う簡単には気づけません。
あと、「一部にはそういう人もいるという意味の文を、全員がそうだと思い込む」よ
うに、一部と全体との違いを区別することが苦手な人は、普通の人でもいるのです
が、その程度が極端という人もいます。
例えば、「この例がそうだから、このような障害を持っている人は、すべてそうであ
る」というように思い込んでしまい、それと矛盾する考えを受け入れないといった具
合です。
そして、本人の意識では、おそらくそのような矛盾した考え、予想と違った事情を受
け入れられる余地がなく、自力では、いつまでたってもその不快感を解消できないの
だろうと思います。
そのような場合、いわゆるパニックになって、混乱がなかなか止まらなくなるという
人もいますが、中には、自己を正当化すべく、他人を非難するという方向に向いてし
まう人もたまにいます。
そのような非難で、そう簡単に解決されるはずもなく、その攻撃が執拗になってしま
います。
そうなると非難された人は、ものすごく困ります。
また、このタイプの人の中には、どこか子どもじみた部分、例えば、普通の大人なら
しない意地悪をしたり、ズルをしてまでも自己を正当化しようとするという気質を持
ち合わせている人もいます。
あと、このタイプの人は、現実の世界は、自分の思い込みに反し、生きづらいもので
あることも多いはずので、社会に適応が難しく、二次的にうつになる人も多いわけで
す。
それらのことが、自力ではコントロールできないからこそ、障害なわけです。
お子さんが性器を出すことを抑制できなったのと、同様かどうかはわかりませんが、
とにかくお父様も、自制困難ということでは、共通しているのでは?
それよりも、多くの人が、花風社の本によって、実のある情報を得ているという現実
が、桁違いに素晴らしいのではと思います。
私も、花風社の本をきっかけに、感覚統合などの知識を得て、それによって今までの
疑問が説明できたというようなことも多いのです。
来年も、ご活躍を期待しております。
=====
なるほど。
「なぜ司法という手段を選ばなければいけなかったか」については新刊にも書いたけど
今度も私が裁判を起こした相手と同じパターンだな。
その他にも、このメールでのアドバイスをいただいてわかったことが大きく言って二つあった。
一つはうつになりやすい人ってどういう人か。
脳内理想と現実に齟齬がある人はうつになりやすいんだな。
私がうつにならないわけだなあ。
自分が邪魔されなければ、人はどうでもいいからね。
社会は思い通りにはならないのは知っている。
でもだからといって「社会がひどいところだ」とは思っていない。
自分は自分にできることをやる。
邪魔をされればやり返す。それだけ。
もう一つ。
親の側に、あまりにかっちりした自閉症療育へのこだわりがあると
地域支援の人たちにとってはやりづらい面があるのかもね。
柔軟な提案ができにくくなるのかもね。
ここのうちでも「父親が足を引っ張っている」って周囲から見えるのは、そういうことなのかもしれない。
この父親がうちを攻撃していたとき
「よそんちはよそんちだとほうっておけばいいのになんであんなしつこいんでしょう」という意見を多数いただいたが
どうもそういうことができにくい脳の人がいるんだな。
そしてそういう人たちは、こちらの主張が自分に押し付けられていると思うのかもね。
本を読みもせずにね。本を読まずにあてずっぽうで難癖つけられても、こちらとしては反論の仕様がない。
藤居が「立ち読み」して大地君の本を批判したときのように
「一体何食ったらああいう思考回路になるのかね」(友だちのぶんパパの名言)としか思えない。
読まなかったり立ち読みしたりって、要するにお客じゃない。
なのにどうして相手にしてもらえると思うのかしら。不思議。
でももちろん読めということではない。
民間企業の出す本なのだから、いやなら読まなければいい、実践に取り入れなければいいだけの話。
読んで喜んで成果をあげている読者の邪魔をしなければそれでいい。
この性器露出少年の父は、今年私の話し相手もさんざんいじってくれた。
大地君までもね。
私が「支援者じゃない」と断言するのは、私にはこういう人たちが支援では救えないからです。
取れる手段は支援じゃない。以前は司法だった。とにかく支援以外の手段でしかこういう横暴な行為をストップできない。
自閉症にかかわる人だからといって、うちの本が全員を救えるわけじゃないから。
私が出版する本によって多少なりとも支援みたいなことができるとしても、それは本を読んでくれて賛同してくれる人だけ。
それ以外の人はアウト・オブ眼中。はっきりいって、どうなってもいい。っていうか、どうなっても自分の力の及ぶ範囲ではない。
別の方法が見つかってよくなるならそれでハッピーだろうし、うまくいかなくても私にはどうにもできない。
版元っていうのは。そこが支援者との違い。
もう一つ、特別支援学校の先生から簡潔な的を射た反応をいただきました。
=====
浅見さん、人前で性器を出してはいけない、当たり前のことです。
我々は指導します。
罪になるからです。
=====
そうですよ、先生。
それが私たちが公教育に期待していることなの。
来年も官民協力して共存しやすい社会を作りましょう。
国家資格を持って地域支援に当たられている読者の方からこういうアドバイスをいただきました。
色々謎が解けた思いがしますので、皆様とこれを分かち合いたいと思います。
=====
自閉症スペクトラムの男性で、多動や自制が困難などの理由で、(おそらく知能面で
問題がある人の方が多いと思いますが、)自分の男性器をいじってしまう人はわりと
います。
そして、自閉症スペクトラムは、遺伝が関連していると思われる人が、もちろんすべ
てではありませんが、いくらかの割合います。
そのため、発達や知的障害の人の支援に関わっていると、両親のいずれかが、どこか
変わっている面があって、一緒に関わっていくことが難しいと感じさせられることが
あります。
自閉症スペクトラムの本人は、むしろ純粋な人が多いのです。
> 自分の見方が世界で唯一だと思い込んでいるらしく、
これも、おそらく何らかの障害による認識の偏りではないでしょうか。違う見方が極
端にできない人っています。
また、その概念が、歳をとっても現実的になるということが難しい人もいます。
> いい加減自分の「想像力の障害」に気づけばいいのに、と思って見ていた。
そういう人は、自分の思い込みや予想と違っても、自分の見方が間違っていたと、そ
う簡単には気づけません。
あと、「一部にはそういう人もいるという意味の文を、全員がそうだと思い込む」よ
うに、一部と全体との違いを区別することが苦手な人は、普通の人でもいるのです
が、その程度が極端という人もいます。
例えば、「この例がそうだから、このような障害を持っている人は、すべてそうであ
る」というように思い込んでしまい、それと矛盾する考えを受け入れないといった具
合です。
そして、本人の意識では、おそらくそのような矛盾した考え、予想と違った事情を受
け入れられる余地がなく、自力では、いつまでたってもその不快感を解消できないの
だろうと思います。
そのような場合、いわゆるパニックになって、混乱がなかなか止まらなくなるという
人もいますが、中には、自己を正当化すべく、他人を非難するという方向に向いてし
まう人もたまにいます。
そのような非難で、そう簡単に解決されるはずもなく、その攻撃が執拗になってしま
います。
そうなると非難された人は、ものすごく困ります。
また、このタイプの人の中には、どこか子どもじみた部分、例えば、普通の大人なら
しない意地悪をしたり、ズルをしてまでも自己を正当化しようとするという気質を持
ち合わせている人もいます。
あと、このタイプの人は、現実の世界は、自分の思い込みに反し、生きづらいもので
あることも多いはずので、社会に適応が難しく、二次的にうつになる人も多いわけで
す。
それらのことが、自力ではコントロールできないからこそ、障害なわけです。
お子さんが性器を出すことを抑制できなったのと、同様かどうかはわかりませんが、
とにかくお父様も、自制困難ということでは、共通しているのでは?
それよりも、多くの人が、花風社の本によって、実のある情報を得ているという現実
が、桁違いに素晴らしいのではと思います。
私も、花風社の本をきっかけに、感覚統合などの知識を得て、それによって今までの
疑問が説明できたというようなことも多いのです。
来年も、ご活躍を期待しております。
=====
なるほど。
「なぜ司法という手段を選ばなければいけなかったか」については新刊にも書いたけど
今度も私が裁判を起こした相手と同じパターンだな。
その他にも、このメールでのアドバイスをいただいてわかったことが大きく言って二つあった。
一つはうつになりやすい人ってどういう人か。
脳内理想と現実に齟齬がある人はうつになりやすいんだな。
私がうつにならないわけだなあ。
自分が邪魔されなければ、人はどうでもいいからね。
社会は思い通りにはならないのは知っている。
でもだからといって「社会がひどいところだ」とは思っていない。
自分は自分にできることをやる。
邪魔をされればやり返す。それだけ。
もう一つ。
親の側に、あまりにかっちりした自閉症療育へのこだわりがあると
地域支援の人たちにとってはやりづらい面があるのかもね。
柔軟な提案ができにくくなるのかもね。
ここのうちでも「父親が足を引っ張っている」って周囲から見えるのは、そういうことなのかもしれない。
この父親がうちを攻撃していたとき
「よそんちはよそんちだとほうっておけばいいのになんであんなしつこいんでしょう」という意見を多数いただいたが
どうもそういうことができにくい脳の人がいるんだな。
そしてそういう人たちは、こちらの主張が自分に押し付けられていると思うのかもね。
本を読みもせずにね。本を読まずにあてずっぽうで難癖つけられても、こちらとしては反論の仕様がない。
藤居が「立ち読み」して大地君の本を批判したときのように
「一体何食ったらああいう思考回路になるのかね」(友だちのぶんパパの名言)としか思えない。
読まなかったり立ち読みしたりって、要するにお客じゃない。
なのにどうして相手にしてもらえると思うのかしら。不思議。
でももちろん読めということではない。
民間企業の出す本なのだから、いやなら読まなければいい、実践に取り入れなければいいだけの話。
読んで喜んで成果をあげている読者の邪魔をしなければそれでいい。
この性器露出少年の父は、今年私の話し相手もさんざんいじってくれた。
大地君までもね。
私が「支援者じゃない」と断言するのは、私にはこういう人たちが支援では救えないからです。
取れる手段は支援じゃない。以前は司法だった。とにかく支援以外の手段でしかこういう横暴な行為をストップできない。
自閉症にかかわる人だからといって、うちの本が全員を救えるわけじゃないから。
私が出版する本によって多少なりとも支援みたいなことができるとしても、それは本を読んでくれて賛同してくれる人だけ。
それ以外の人はアウト・オブ眼中。はっきりいって、どうなってもいい。っていうか、どうなっても自分の力の及ぶ範囲ではない。
別の方法が見つかってよくなるならそれでハッピーだろうし、うまくいかなくても私にはどうにもできない。
版元っていうのは。そこが支援者との違い。
もう一つ、特別支援学校の先生から簡潔な的を射た反応をいただきました。
=====
浅見さん、人前で性器を出してはいけない、当たり前のことです。
我々は指導します。
罪になるからです。
=====
そうですよ、先生。
それが私たちが公教育に期待していることなの。
来年も官民協力して共存しやすい社会を作りましょう。