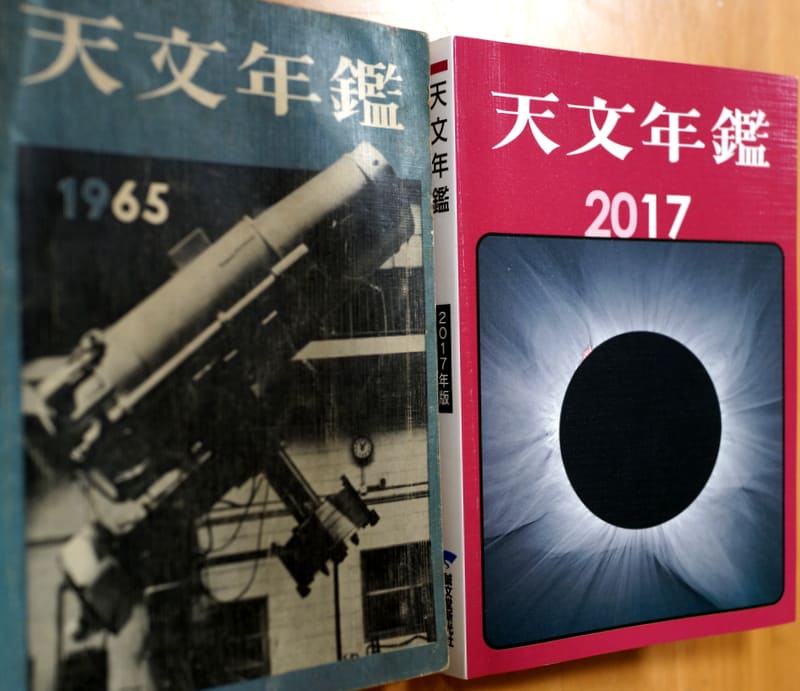安倍政権が「神武天皇は実在した」を本気で喧伝、産経もトンデモ神武本出版! 神話で国民を支配するカルト国家化
リテラ 宮島みつや著
とうとう、ここまできたか──。日に日にエスカレートしていく安倍政権の歴史修正主義だが、いよいよ連中は「神武天皇は実在した」なるトンデモまで喧伝しだしたらしい。
念のため最初に言っておくと、神武天皇は8世紀の「古事記」「日本書紀」(あわせて記紀という)を基にした“初代天皇”だが、もちろん実在したとは立証されておらず、ときの政治権力である朝廷がその支配の正当性を説くために編み出した“フィクション”というのが歴史学の通説だ。
ところが最近、安倍政権周辺から「神武天皇は実在の人物でその建国の業績を讃えるべき」という主張が次々飛び出してきているのだ。
自民党の三原じゅん子参院議員が、先の参院選投開票日のテレビ東京の選挙特番で、VTR取材中に「神武天皇の建国からの歴史を受け入れた憲法を作りたい」と発言していたことについて、MCの池上彰から神武天皇は実在の人物だったとの認識かを問われ、「そうですね。そういう風に思ってもいいのではないか」と“珍回答”。池上が呆れて「学校の教科書でも神武天皇は神話の世界の人物ということになってますが?」とツッコんだのは記憶に新しい。
このトンデモ発言にはさすがの有権者も「まあ、三原じゅん子だから」と一笑に付したが、しかし、どうもこの神武天皇実在論は、安倍政権の中枢にしかと根付いているようだ。
たとえば今月、11月3日の「文化の日」を「明治の日」に改称すべしとの運動を展開している「明治の日推進協議会」なる団体が都内で決起集会を行った。同団体の役員名簿には小田村四郎、小堀桂一郎、大原康男、伊藤哲夫、百地章など、おなじみの日本会議系人物がちらつく。その集会に、安倍首相の盟友である古屋圭司自民党選対委員長、稲田朋美防衛相らが参加。稲田は壇上でこう息巻いたという。
「神武天皇の偉業に立ち戻り、日本のよき伝統を守りながら改革を進めるのが明治維新の精神だった。その精神を取り戻すべく、心を一つに頑張りたい」(朝日新聞11月2日付)
……おいおいマジかよ?と突っ込まざるをえないが、この安倍政権の神武天皇ゴリ推しを“機関紙”の産経新聞もバックアップしている。今年8月には『神武天皇はたしかに存在した』(産経新聞取材班/産経新聞出版)なる書籍を出版。記紀にある日向(現在の宮崎県)から大和(奈良県)までの「神武東征」を追いかけるルポだが、完全に神武実在が前提になっており、置いてけぼり感満載の一冊に仕上がっている。
しかし、繰り返すが、神武天皇について直接的に伝えるのは記紀だけであり、その記述は完全に“神話”の域を出ないものだ。たとえば「日本書紀」の記述は天地開闢から始まる神武以前が神代、神武以降が人世の歴史とされているが、明治政府は神武天皇即位の年=皇紀元年を紀元前660年とした。実に縄文時代後期である。
そんな、人々はもっぱら狩猟採集生活で文化といえば土器みたいな時代に、神武天皇は「天下を治めるためには東に行けばいいんじゃないか」と思いついて、大和までの長い旅に出たというのだが、記紀が描く道中の出来事はあからさまに現実味がない。
たとえば、亀の甲羅に乗った釣り人(地元の神)に明石海峡から浪速までの海路を案内してもらったり、突如、助っ人が神のお告げで天の神がつくった剣を持ってきてくれたり、かと思えば神の仰せで八咫烏が吉野まで先導してくれたり、はたまた天の神がやってきて証拠の宝物を見せて神武に仕えたりと、「史実」とみなすには神がかり過ぎている。
さらにいえば、神武を含む古代天皇の年齢も解釈に苦しむ。たとえば「日本書紀」によれば、神武天皇崩御時の年齢は127歳で、「古事記」では137歳とある。そんな超長寿なんてありえないだろう。年齢を2で割ると丁度良くなるとする説もあるが、すると逆に皇紀自体がおかしくなってくる。なお、初代天皇となった神武の後を継いだ綏靖天皇から開化天皇までの8人については、なぜか、その実績がほとんど記されていない。この「欠史八代」はあまりにも有名な記紀の謎として知られている。
結局のところ、神武天皇及び欠史八代は創作で“虚構の天皇”だとするのが一般的な古代史研究者の見解である。では、なぜ安倍政権はいま、こんな神武天皇実在説というトンデモを言いふらしているのか。
その目的を、前述した稲田朋美の「神武天皇の偉業に立ち戻り、日本のよき伝統を守りながら改革を進めるのが明治維新の精神」という言葉が、端的に表している。
実は、神武天皇の陵墓は、たとえば天武、天智、持統天皇などの陵墓と比べて軽視されており、中世まで始祖として崇め奉られていた形成はほぼない。それが一転、江戸中期の国学を経て尊皇思想の核となり、明治維新は王政復古の建前のもと幕府を転覆させた。ようは、“クーデター”のため「万世一系」たる天皇の権威を超越的なものとして再興し、利用したのだ。
また、このとき明治政府は、それまで民間信仰であった神道を天皇崇拝のイデオロギーとして伊勢神宮を頂点に序列化、“日本は世界無比の神の国”という「国体」思想を敷衍した。そうした流れのなかで、日本書紀などについて批判的研究を行った津田左右吉に対し、東京地検が尋問を行い、『神代史の研究』など4冊を「皇室ノ尊厳ヲ冒涜シ、政体ヲ変壊シ又ハ国憲ヲ紊乱セムトスル文書」として発禁押収。後日、津田と版元が出版法違反で起訴されるという事件も起きている(佐藤卓己『物語 岩波書店百年史』2巻/岩波書店)。
一方、1945年の敗戦後にGHQが神道指令を発布、国家と神社神道の完全な分離を命じると、津田の学説は学会の主流派となり実証主義的な記紀研究が活性化。その蓄積を踏まえ、今日では神武天皇は実在しないというのが定説となっているわけだが、これを面白く思わないのが日本会議ら極右界隈と、それに支えられる安倍政権だ。
彼らにとって天皇は「万世一系」でなければならない。それは前述のとおり、日本を万邦無比の「神国」とし、天皇を超越的な存在として再び支配イデオロギーの頂点に置いて政治利用するために他ならない。だからこそ、記紀は史実であり、神武天皇は実在すると主張するのだ。
すると必然的に、神武天皇は記紀にあるように神話的でありながら同時に存在を認めるという、矛盾めいたことになる。三原じゅん子が「神話の世界の話であったとしても、そう(実在したと)いう考えであってもいいと思う」と池上彰に応答したのはまさに典型だ。ようは政治的な目的ありき。だからこういう発言になる。
事実、安倍晋三は下野時の2012年、民主党(当時)による女性宮家創設議論および皇室典範改正に反対し、こう述べていた。
「私たちの先祖が紡いできた歴史が、一つの壮大なタペストリーのような織物だとすれば、中心となる縦糸こそが、まさに皇室であろう」
「二千年以上の歴史を持つ皇室と、たかだか六十年あまりの歴史しかもたない憲法や、移ろいやすい世論を、同断に論じることはナンセンスでしかない」(「文藝春秋」12年2月)
見ての通り、立憲主義もクソもない。こんな人間がいま日本の総理であることにあらためて戦慄するが、一方、安倍のブレーンである八木秀次が天皇・皇后の護憲発言に対して「宮内庁のマネジメントはどうなっているのか」と猛批判したように、実際には、安倍は天皇に対する敬愛などほとんどもっていない。そこにあるのは、天皇の政治利用、もっと言えば、皇国史観と「万世一系」イデオロギーの復活による大衆支配の欲望だけだ。
そう考えてみてもやはり、わたしたちは表出する神武天皇実在論を笑って済ませておくわけにはいかない。戦前回帰を目論む安倍政権のプロパガンダの一種として、十分に警戒しておく必要がある。
リテラ
(宮島みつや)