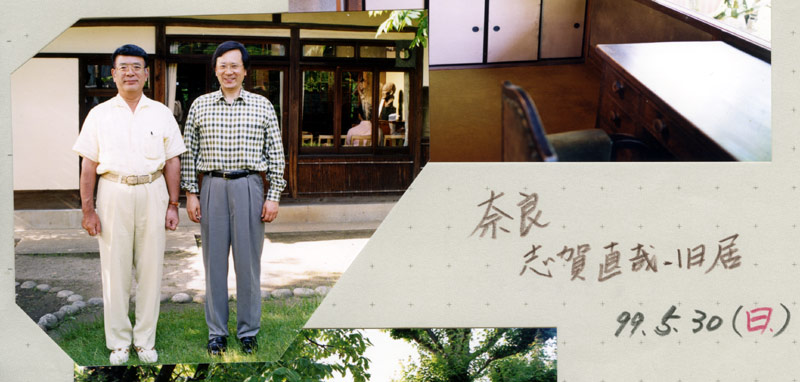わたしは、
白樺文学館の「誕生秘話」(2)で、
ブレイクの石版画を、2000年(平成12年)の『古書七夕大入札会』(明治古典会主催)で入手したことを記しましたが、
実は、この同じ入札会に、文学史上有名な、小林多喜二に宛てた志賀直哉の書簡も出品されました。わたしはどうしても落札したいと思い、八木書店の取締役で古書部の店長である八木朗さん(※注1) にその旨を伝えました。
毎年7月に行われる「古書七夕入札会」は、個人で入札するのではなく、こちらが指名する業者(明治古典会会員の古書店・三十数社の内)に入札を依頼するシステムになっています。会場は、神田小川町の東京古書会館です。
ベテランの八木さんに託しましたが、落とせるかどうかは蓋を開けてみなければ分からないので、ドキドキです。後は祈るのみでした。結果はわずか8000円の差で(二百万円以上での8000円!です)入手できました。ホッとして全身の力が抜けたのを今でも覚えています(「競り」ではないので、落札できるかどうかは、文字通り蓋を開けるまで分からないのです)。
以上が、入手の経緯です。
ところが、
5月27日(水)の朝日新聞・「ニッポン 人・脈・記」に、白樺文学館オーナーで二代目館長だった佐野力さんのインタビュー記事として、朝日の早野透さんは、2001年9月より館の運営を佐野さんから任された渡辺貞夫さん(小樽商科大学の同級生)を紹介した後に「この人の快挙は、志賀直哉が小林多喜二に書いた手紙を館の宝にしたことである(※注2)『売りに出たのを、いくらかかっても手に入れたいと競り落としました』と佐野。」(5月27日朝日新聞)と書いています。
これでは、「
この人」(ふつうに読めば渡辺さん、全体の文を見ると佐野さん)が入手したことになってしまいます。どうしてこんな「ストレートな嘘」が新聞記事になるのか?また、佐野さんの発言にある「競り落とした」というのも間違いです。とにかく「歴史の改ざん」はよくありません。今年4月1日から我孫子市が税金を使って運用する施設に変わったのですから、「事実」をそのまま伝えることが必要です。結果としてではあれ、公共の文化施設が「つくり話」を流布することになったのでは困ります。
(※注1)八木書店ー千代田区神田神保町1-1.八木朗さんには、わたしがお願いして2001年1月1日の白樺文学館開会式にも出席して頂きました。
(※注2)渡辺貞夫さんという方は、白樺文学館の創成時(1999年2月~2001年1月)においては、文学館とは何の関わりもなく、わたしがはじめて彼の存在を知ったのは、開館から半年後の2001年7月でした。9月から二代目館長に就任することになった佐野力さんが、運営を任せる人として私に紹介したのです。
武田康弘
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下は、コメント欄のコピーです
文学館の歴史について (荒井達夫)
渡辺貞夫さんは、現在、文学館の顧問(公務員)です。市民の税金で報酬を受けながら、自らが担当する市の文化施設の歴史について嘘の話を伝えることは、違法であり、許されません。朝日新聞社に対して、ご本人が訂正を申し出るべきです。
我孫子市白樺文学館条例は、文学館を市の施設とする目的を「市民の文化の向上に寄与するため」と規定していますが、そのためには、文学館の設立の経緯について市民に正確に伝えることが不可欠です。文学館の顧問がこのような状況では、条例目的の達成はまったく不可能になります。市の担当部局も、放置しておくことは許されません。速やかな対応を求めます。
------------------------
武田さんはなぜやめられたのですか? (黒古寿夫)
2009-06-17 11:50:36
白樺文学館はその性格がよくわからない存在ですね。
「文学館」といいながら、文学にはあまり興味なく、陶芸の比重が高いように見えます。
それにしても武田さんはなぜ、館長をやめられたのですか?
--------------------------
お応え (タケセン)
2009-06-18 00:44:50
わたしが館長を辞したのは、オーナーであった佐野力さんとの基本姿勢の相違からですが、
『白樺文学館創成記』の「誕生秘話」をお読み頂ければと思います。よろしければぜひご覧ください。