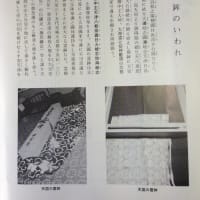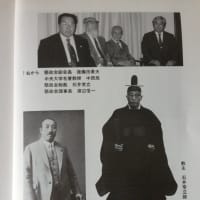谷口雅春先生は立教当初、生命感あふれる詩をつぎつぎと『生長の家』誌に発表されてゐる。例へば「夢を描け」「生きた生命」「光明と暗黒」「光明の国」「或る日の生命の国」といった詩である。それらは谷口先生の脳裡に霊感的にひらめいて来だのを書きつづった一種の自由詩であった。これらの詩は最初。”生長の家の歌”として創刊号から発表されてゐるが、当時書かれた自由詩は全部、のちに『生命の實相』の”聖詩篇”や『ひかりの語録』にやはりその頃谷口先生の脳裡にひらめいて来たところの短蔵言である。”智慧の言葉”と共に収められてゐる。
ところで、それらの自由詩のなかでも最も長篇の詩が「甘露の法雨」であった。この詩は、昭和五年十二月一日発行の『生長の家』誌に「生長の家の歌」の題で”神” ”霊” ”物質”の三章が発表され、昭和六年二月一日発行の同誌には「甘露の法雨」と題して”実在” ”智慧” ”無明” ”罪” ”人間”が発表され、昭和七年二月一日発行の同誌に「甘露の法雨」と題して。生長の家’が発表されたのであった。最後に発表された”生長の家”の詩は、今日、聖経『天使の言葉』となってゐるものであるが、そもそも「甘露の法雨」と「天使の言葉」は、谷口雅春先生がインスピレ-ションによって一気に書かれたところの自由詩であったのである。
谷口雅春先生は、この詩が「甘露の法雨」として掲載された時の『生長の家』誌において次のやうにこの詩を説明してをられる。
《……「生長の家の歌」三篇「神」「霊」「物質」の続篇にして、この三篇と共に生命の真理を霊感によって書かしめられたものであります。「生長の家」では所与の経典のほかに神仏の祭壇に対って之を朗読することにしてゐます。病人に対して又は、病人自身が繰返し朗読すれば病ひが不思議に癒え、障りの霊に対して読誦すれば、障りの霊が悟りを開いて守護の霊にかはる助けとなります。それ故これは誠に生長の家の経典とも云ふべきものであります》
この言葉どほり誌友の間には「甘露の法雨」を読誦することによって病気が治癒し、家庭が調和するなどの体験が相ついで起った。やがてこの「甘露の法雨」の詩は、昭和十年六月、当時京都に於ける熱心な誌友である工学博士小木虎次郎氏が「甘露の法雨」の詩を『生長の家の歌』といふ詩集の中にのみ収めておいては、功徳のあることを知らない人が多いから、ハッキリとこれは聖経であると明示して、折本型の経本として発行すれば、功徳を受ける人が多いであらうと、生長の家京都教化部から経本式折本として発行されることになった。
かうして『甘露の法雨』が経本になって頒布されるや、陸続として功徳を受ける人が現はれた。さらには、それを携帯するだけで、交通事故に遭ひながら微傷も負はなかった人が出て来たりもしたのである。そこで京都の教化部ではこれを京都のみで独占すべきものでないと、その出版権を昭和十一年末に、光明思想普及会に移すことになったのである。その後聖経『甘露の法雨』は、さらにその功徳を発揮して、多くの人々をさまざまな人生苦から解放して行ったのであるが、その功徳の及ぼす範囲は、単に個人だけでなく、後に述べるやうに、あの大東亜戦争の終結には国家の危機を未然に救ふ働きをも果すまでになるのである。
ところで谷口先生は『甘露の法雨』の功徳についてのちにつぎのやうに記してをられる。
《どうして『甘露の法雨』にこのやうな偉大な功徳が生ずるのであらうか。私は、それをただ霊感で詩作するときに、ふと感じてその詩の題を「甘露の法雨」としたに過ぎないのであって、別に『法華経』の観世音菩薩の普門の功徳を説いた”普門品”に連関して詩の題を「甘露の法雨」と題したのでもなかったし、観世音菩薩が教への本尊として門脇観次郎氏の霊眼に見れるなどといふことも全然予想もしなかった。ところが私の著書や執筆の雑誌を読んで功徳を得た人にあらはれる色々の霊顕や現象が次第に観世音菩薩が生長の家の本尊であり、その観世音菩薩が、『法華経』の”普門品第二十五”にある通り「甘露の法雨を澎ぎ給うて煩悩の炎を滅除し給ふ」のであることを証明するやうになったのである。聖経『甘露の法雨』の功徳はそれをお説きになった観世音菩薩の妙智力と引き離して考へてはならないのである》
(「神秘面より観たる生長の家四十年史」)