
日経電子版が昨年連載していた「ネット興亡記」に、LINEの物語があった。なかなか面白いので、メモった。今や国民的アプリとなったメッセージサービスLINEには、2人の男の敗北の歴史があったという。
LINEの軍師と言われるCSMO(最高戦略マーケティング責任者)の舛田淳。LINE誕生に深くかかわった舛田は、高校を中退し、バイクのエンジン工場などで働いていたが「違う世界を見たい」と一念発起して早稲田大学に進んだ。
そこで出会ったのが1学年上の山田進太郎だった。後のメルカリ創業者である。いち早く自力でインターネットのサービスを作っていた山田の姿に衝撃を受けた。
「進太郎さんはサークル活動にもインターネットとパソコンを持ち込んで『早稲田大学のデジタル化』を進めていた。『(先に)やられちゃったな』と思いました。憧れと少しの悔しさがありました」
放送作家の卵として働きながらも次第にインターネットの世界にのめり込むようになった舛田。会社を転々としていた時に、中国・検索最大手百度(バイドゥ)の創業者、李彦宏から誘われた。日本進出を狙う百度。検索の王者として君臨する米グーグルに「四つ相撲は無理でも一刺しできるのではないか」と考えた舛田は27歳で百度に移った。だが、そこでグーグルの威力を思い知ることになる。
「やっぱりグーグルはすごいのひと言です。世界中から天才たちが集まり、最高の環境でひとつのミッションに従ってやっている。ちょっとやそっとじゃ歯が立たない。『全体で勝てないなら局地戦だ』と画像検索に力を入れたり色々なことをやりましたが、結局は『これは勝てない』と。もう、勝負をする前に負けている状態でした」
打ちのめされた舛田は百度を後にする。そこに声をかけたのが韓国の検索最大手ネイバーの日本法人社長、森川亮だった。ネイバーは2000年に日本に進出したがグーグルに蹴散らされるように05年に撤退。だが森川によると再上陸を計画していると言う。
「百度とネイバーが違うのは、ネイバーが一度負けているということです。負けた反省点に立っていたことに共感できました。しかも、口で言うだけでなく実践しようとしていました」
日本で勝つには「本国からエースが来ないとダメだ」と言う舛田に対し、森川は検索の絶対的エースが韓国から来ると力説した。それがシン・ジュンホだった。舛田に会ったシンは「僕は成功するまで韓国には帰らない」と言う。その言葉に、心が動いた。
「この人とならもう一回チャレンジできるんじゃないかと、スイッチが入りました。それにやっぱり心残りでした。こんなに負けきったことはないとまで思わされていましたから」
08年10月、ネイバージャパンに入社した舛田に、森川とシンは「あなたの仕事は(グーグルに)勝つために必要なことすべてです」と言う。とはいえ、グーグルの壁は高く厚い。どうすれば今度こそ、その壁を破れるか――。舛田はひとつの会社に出合うことになる。かつて「ヒルズ族」の象徴のように語られたライブドアだ。
■ライブドアにラブコール

舛田氏は最高戦略マーケティング責任者としてLINEをけん引する
社長の堀江貴文らが証券取引法違反の疑いで逮捕されてから3年近く。旧知のライブドア幹部から売却の入札にかけられている事実を聞いたが、「最初は『ないわ』と思いました」。だが、よくよく調べると腕利きのエンジニアたちがそっくりそのまま残っていることに気づいた。
「最初に聞いた時は冗談かと思って『いやいや』と(お茶を濁した)。でも、会社のデータを夜中に1人で見ながら『おおっ!』と思いました。キーマンたちがそのまま残っている。これは意外でしたね。すぐに森川とシンに『買いましょう』と提案すると、『いきましょう』と返ってきました」
ただ、実はライブドア首脳陣の思いは違った。モバイル部門を率いていた出沢剛が社長に就任し、黒字化を果たしていたのだが、出沢には秘めた野望があったのだ。
(出沢)「実はネイバーと一緒になるというのは我々が望んだ形ではなかったのです。あの事件の後、つらい時期を乗り越えてきた強い絆で結ばれたメンバーで次の勝負をしたいと思っていました。我々としてはMBO(経営陣による買収)をして独立したかった。だから本当は(ネイバーによる買収は)がっかり。『夢破れて……』という感じが正直、あったのです」
そこで舛田が提案したのが「5つの約束」だった。ライブドアのブランド、雇用、経営体制、経営ポリシーを維持し、成長を支援する。要するにネイバーが買収しても独立を守るという意味だった。
(舛田)「最初は(旧知のライブドア幹部に)入札に参加してくれと言われて手を挙げたのに、その後には我々がラブコールを送っていた。出沢からも聞きました。『本当は嫌だった。本当は独立したかった』と。だから、これは妻にも言ったことがないんですが、(ライブドア側には)『僕たちが幸せにします』と言いました」
「その時はお酒も入っていたので『何がダメなんですか。僕たちが絶対に幸せにする自信があります』と。もう、全力で口説いていましたね。そこまで言ったのは、大事なのは一緒にチャレンジするメンバー(社員)だと思ったから。お金でハコは買えるけど、それじゃ魂が残らないから」
■「もう限界です」

出沢氏(右)が社長を務めていたライブドアはNHNジャパン(現LINE)に買収された(2010年、左は森川氏)
こうして10年にネイバーはライブドアを買収した。だが、グーグルの壁が崩れる気配はいっこうにしない。
(出沢)「まるで壁に卵を投げつけているようでした。その壁が倒れる気配はないけど、投げ続けないといけないんだと……。みんなが疲れていくのが手に取るように分かる。プレッシャーと徒労感。組織がどんどん暗くなっていきました」
(舛田)「正直、途方に暮れていました。ある時、幹部から『もう限界です』と言われました。それを聞いた時には、もう限界がそばに来ていると強く感じました。すべてが暗闇です」
「韓国ネイバー創業者のイ・ヘジンからは『孫の代までかかってもいい』と言われましたが、それって優しくもあり厳しい言葉です。リングを下りることを許さないと。でも、現実にはリングに登っても、登っても、勝てない。勝たせてあげられない。チームを率いてきた自分たちが責任を取らないといけないと思いました。心が折れそうになっていました。もう、自分は辞めた方がいいんじゃないかと」
当時、社内のごく少人数で調査していたのが、メッセージアプリだった。いくつかある開発案件の中でも優先度は3~4番目。そんなときに日本を悲劇が襲った。東日本大震災である。ここで舛田やシンは「親しい人に限られた閉ざされたコミュニケーション」の重要性に気づく。これがLINE誕生につながるのだが、そこには大きな決断が伴っていた。検索でいつかグーグルを超えてやろうという悲願との決別だった。
(舛田)「それまではグーグルと同じ土俵で、オープンなインターネットの中で戦おうとしていた。LINEはその真逆でクローズド(閉ざされている)。つまり、検索できないものです。グーグルに恋い焦がれてリスペクトし続け、チャレンジする相手だと思い続けていたのに、そうじゃない戦略を選んだのです」
「私たちは検索のために集まった。だから検索のチームからは『あの人たちは何をやっているんだ』と思われていたようです。社内に不満はあったと思いますよ」

「スタンプ」は偶然の産物だった(人気キャラ「ムーン」の初期デザイン、LINE提供)
こうして生まれたLINEは瞬く間にユーザーを獲得していった。起爆剤となったのが、かわいらしいイラストの「スタンプ」だ。日本の絵文字文化を踏まえたと紹介されることが多いが、実は偶然の産物だったと言う。
(舛田)「デザイナーがたまたますごく大きなイラストのデータを送ってきたのですが、それが面白かった。インパクトがあったんです。デザインチームでピクセル単位で検証したところ、日本人らしいなと。それは何かと言えば、イエスかノーが明確な欧米系の言語に対して日本人はある種のあいまいさを持っている。それをスタンプが表しているんじゃないかと。でも、それって知らない人同士では成り立たない。知っている者同士(のLINE)だからできること。スタンプは偶然の産物から確信に変わりました」
■「LINE or Not」
LINEが次に目指したのが、メッセージツールを核としつつ様々なコンテンツをつないでいくプラットフォーム化だった。そもそも「LINE」の名に込められた意図は、色々なコンテンツやサービスを線(LINE)でつなぐということだった。ここで登場したのがライブドアの「残党」たちだ。
(舛田)「LINEをメッセンジャーだけで終わらせるつもりはなかった。なぜなら我々はもともと、検索をやりたかった。(検索を中心に)ポータルサイトのように色々なものをつないでいくサービスを目指していました。でも、そうなると圧倒的にリソースが足りない。採用しても人が追いつかない。その時、私は答えを出せずにいた」
ここで動いたのがライブドアをまとめる出沢だった。「LINE or Not」を宣言する。LINEか否か……。選択すべきはLINEだという意味だ。それは実質的に自ら再建したライブドアを捨てる決断だった。
(出沢)「僕が入社した(ライブドアの前身の)オン・ザ・エッヂ時代にコーポレートミッションがあった。『世界中の人たちが僕たちが作ったサービスを知らず知らずのうちに使ってくれるといいよね』。もう、堀江さんも忘れていると思いますが、私が『インターネットっていいな』と思ったのはそこでした。ごく少人数の若くて何も持たない人たちが世の中に力を与えたり、世界中の人たちの人生をちょっとだけ変えたりする」
「LINEはそうなりつつあった。だったらそれを手伝わない理由はない。根回しとかしません。『みんな分かってるよね。これだけ大きなチャンスがあったら乗らない理由はないよね』と。普通の会社ならゆっくり方向転換するけど、ライブドアで学んだのは、徐々にやっていたら世の中は待ってくれないということです。急ブレーキや急ハンドルを恐れてはいけない」
舛田が示した「5つの約束」を自ら破棄したのだ。これには舛田も思わず「えっ、いいの?」と返したという。ライブドアの力を得てLINEはプラットフォーム戦略を推し進め、国民的アプリの地位を築いていった。
(出沢)「巡り合わせの不思議です。誰も想像できなかった展開。僕たちはすごくピカピカなチームじゃない。みんな失敗を経験して苦しい思いを味わってきた」
(舛田)「時代がLINEをつくったんでしょうね。もっと遠くに、もっと早く行くために、もっと違う景色を見るために、仲間が必要だったのです」
ネイバーとライブドア。インターネットの歴史の中で忘れることのできない敗北を経験したふたつの会社が手を取り合ってつくり上げたのがLINEだった。15年に森川が社長を退任すると、シンと舛田は後任社長に出沢を推した。

LINEはヤフーとの経営統合の道を選んだ(2019年11月、記者会見で握手する出沢社長(右)とヤフーの親会社Zホールディングスの川辺社長)
そこまでして作ったLINEは、日本のネットの巨人であるヤフーとの経営統合を選んだ。LINE誕生の立役者となった舛田はこう語る。
「我々が描く世界に対してのステップとして唯一無二の戦略カードだと思うんです。それに日本は今まさにコロナ禍に直面している。『3.11』に直面してLINEを生み出した時と同じマインドです。戦後の焼け野原から日本が復興した時のように、今まさに世界が新しいものをつくろうとしている。その発想をするのが、インターネットで働いている人間の宿命だと思うんです」
かつての敗者たちはLINEという新しい価値を世に送り出した。次は、どんな景色を我々に見せてくれるのだろうか。














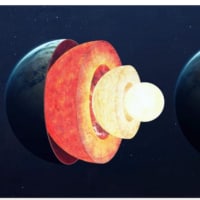


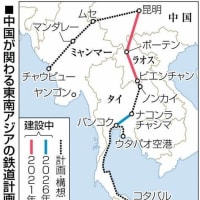

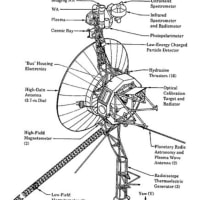
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます