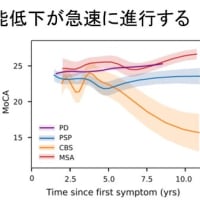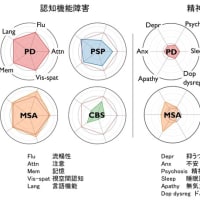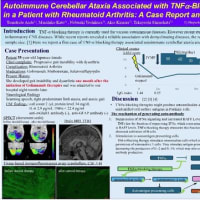今回のキーワードは,無症状感染者の特徴とPCR陽性期間,退院後PCR再陽性からは感染しなさそう,抗凝固療法下の深部静脈血栓症の進行,がん患者における死亡率への影響因子,MRIで初めて描出された嗅覚神経路異常,多彩な神経合併症(PRES,ステロイド反応性脳症,深部白質・両側淡蒼球病変),中国発アデノウイルス・ベクター化COVID-19ワクチンの第1相試験成功です.
私達も神経合併症としてMERS(可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎・脳症)を報告しましたが(J Neurol Sci),神経合併症の多彩さに驚きます.図1に示すようにウイルス受容体ACE2が脳の様々な部位(運動皮質,後帯状皮質,脳室,黒質,嗅球,中側頭回,延髄腹外側野,孤束核,迷走神経背側運動核)の,さまざまな細胞に存在することを存在することを考えれば,①ウイルス感染による直接伝播は容易に思いつきます.加えて,②parainfectious(傍感染性)の病態,③凝固異常症,④血管内皮細胞障害に伴う血液脳関門破綻や自動血圧調節能の破綻も生じ,多様な神経合併症をもたらすものと予想されます.

◆やはり無症状感染者は多い.21日間の旅程でアルゼンチンを出発したクルーズシップに乗船した217名に対してPCR検査を行ったところ,128名(59%)が陽性であった.このうち発症者は24名(19%)のみで,残り104名(81%!)は無症状であった.下船後の感染伝播を防ぐためには全員の検査が不可欠である.→ 無症状感染者が多いというCOVID-19の特徴は,規制が緩和された状況において,あらためて認識する必要がある.Thorax. May 27, 2020(doi.org/10.1136/thoraxjnl-2020-215091)
◆無症状感染者の特徴.武漢の1施設からの報告.入院患者26名の濃厚接触者調査で,PCR陽性となった78名のうち,無症状感染者33名(42.3%)と発症者45名(57.7%)の臨床的な違いを検討した報告.無症状感染者は発症者と比較して,若く(中央値37歳対56歳),女性が多く(67%対31%),肝障害が少なく(3%対20%),回復期のCD4細胞数が多く(719対474 /microL),そして鼻咽頭拭い液PCRの陽性期間が短かった(8日対19日;と言っても8日間も持続する).CD4細胞数の結果から,無症状感染者では免疫系の障害がより軽度であることが示唆された.→ やはり若年者では無症状感染者になりやすい.濃厚接触者には無症状であってもPCRを確実に行うことが感染拡大防止に必要である.JAMA Netw Open. May 27, 2020(doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.10182).
◆無症状感染者のPCR陽性(=ウイルスRNA検出)は,感染曝露から22日間と長い.中国からの報告で,無症状感染者24名において,PCR陽性の期間を検討した.感染曝露した日から2回連続陰性となった初日までの間隔は平均22.0日(標準偏差7.1日)であった.初回PCR陽性から数えると平均7.9日(標準偏差3.5日)で,前述の研究の8日とほぼ同じ結果である.PCRによるウイルスRNA検出は,必ずしも感染性を意味するわけではないことから,まず感染性を有する期間を明らかにする必要がある.Crit Care 24, 245 (2020). (doi.org/10.1186/s13054-020-02952-0)
◆退院後に再度PCR陽性となった患者からは感染しない?韓国からの報告.PCR陰性となり退院した患者60名に対してPCR検査を行ったところ,10名(16.7%)が,退院後4~24日目(最長感染から56日目)にPCRが陽性になった(鼻咽頭拭い液5名,肛門拭い液6名)(図2).臨床的にはこの10名のうち,2名がたまに咳をする程度であった.また別の1名は,退院後のPCR陽性が判明する前に,重症患者に使用するための血漿を献血していた.その際,個人防護具不十分な医療スタッフ9名が関わったが,その後,2ヶ月間,そのスタッフには症状はなく,PCRも陰性であった.→ 退院後再陽性患者では,ウイルスコピー数が少なく,感染力が乏しいのかもしれない(もしくはすでに死滅したウイルスを検出しているだけかもしれない).ただし,感染性が完全に否定されたわけではないため,患者回復血漿を採血する際,医療者は感染対策を行う必要がある(JAMA Netw Open. 2020;3(5):e209759;doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.9759).

一方,中国からも退院後のPCR再陽性について報告された.退院患者69名のうち11名(16%)が,退院後9~17日目にPCRが再陽性になった.全例で症状はなかった.PCR再陽性患者は,そうならなかった患者と比較し,疲労を呈する頻度が高く,初発症状の数が多く,CK値が高値という特徴を認めた(JAMA Netw Open. 2020;3(5):e2010475;doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.10475).
◆深部静脈血栓症は多く,かつ急速に進行する.COVID-19における血栓形成傾向は注目されているが,深部静脈血栓症(DVT)の頻度や予測因子は不明である.フランスから34名を対象とした検討(26名がPCR陽性,8名は臨床診断)が報告された.DVTは入院時に22名(65%)に認めた.ICU入室後,抗凝固療法(詳細不明)を開始したにも関わらず,わずか48時間で27名(79%)に増加した.18名(53%)は両側性,9名(26%)は近位部の血栓だった.DVTを認める症例の特徴として,D-dimer高値,フィブリノゲン減少,CRP高値が認められた.→ 早期にDVTを発見し,十分な抗凝固療法を行う必要がある.JAMA Netw Open. 2020;3(5):e2010478(doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.10478)
【以下,私見】ちなみに静脈血栓塞栓症(VTE)は,おもに深部静脈血栓症と肺血栓塞栓症からなり,先天性要因と後天性要因の相互作用により発症する.5月23日の当科抄読会でも議論になったが,欧米白人に比べて,日本人を含むアジア人のVTE罹患率は低いが,先天性血栓性素因に人種差が存在することが明らかになっている.例えば欧米白人に同定されたVTE発症に関連する遺伝子多型のFV LeidenやFII G20210Aは,アジア人には同定されない.アジア人でCOVID-19の死亡が少ない理由は,このような遺伝子が一因ではなかろうか?
◆癌患者における感染後の死亡率は高い.米国,カナダ,スペインからのがん患者928名において,COVID-19感染の影響を調べるコホート研究.主要評価項目である感染から30日目の全死亡率は13%!(121/928名)と高かった.死亡率を高める要因としては,進行性がん(調整オッズ比5.20),2つ以上の併存症(4.50),がん特異的パフォーマンス・ステータス(3.89),ヒドロキシクロロキンとアジスロマイシン併用治療(2.93),加齢(10歳の上昇で1.84),男性(1.63),喫煙(1.60)が認められた.これらは,がん治療の継続や緩和ケアを決定する上で重要な情報となる.Lancet. May 28, 2020(doi:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31187-9)
◆神経症状(1)嗅覚神経路のMRI異常信号の初めての描出.COVID-19病棟に勤務する25歳の放射線技師が,発症から1日後に無嗅症を呈した.4日後の頭部MRI,FLAIR画像で,右直回と両側の嗅球に高信号病変を呈した(図3).無嗅症が改善した発症28日後のMRIでは,これらの異常信号は消失した.→ やはり嗅上皮から感染したSARS-CoV-2は,嗅覚神経路を上行性に感染伝播するようだ.JAMA Neurol. May 29, 2020(doi:10.1001/jamaneurol.2020.2125)

◆神経症状(2)後部可逆性脳症症候群(PRES).米国の2症例(58歳男性,57歳女性)の報告.いずれの患者も,人工呼吸器装着中に,著明な上昇を伴う血圧変動を呈していたが,人工呼吸器離脱後に意識障害をきたした.頭部MRIでは後頭葉白質を中心とした可逆性の異常信号を認め(図4),PLESと診断された.SARS-CoV-2感染に伴う血管内皮細胞障害により,血圧の自動調節能の障害が生じたものと考えられた.意識障害の原因としてPLESも考慮すべきで,人工呼吸器装着中の血圧コントローは厳格に行う必要がある.J Neurol Sci. May 22, 2020(doi.org/10.1016/j.jns.2020.116943)

◆神経症状(3)炎症性サイトカイン関連・ステロイド反応性脳炎.イタリアからの報告.60歳男性.易刺激性と混迷にて発症し,5日後に意識障害にて入院,脳炎に伴う無動性無言を呈した.発熱や呼吸症状は認めなかった.頭部MRIでは異常所見はないものの,脳波は全般性徐波を呈していた.鼻咽頭拭い液PCRは陽性であったが,髄液では陰性であった.髄液細胞数18/micro-L↑,蛋白69.6 mg/dL↑さらにIL-8とTNFaも上昇していた.既知の感染症や自己抗体関連脳炎は否定された.パルス療法により意識障害は速やかに改善し,また髄液所見も改善した(図5).ウイルスの直接浸潤は否定できないものの,中枢神経のサイトカイン関連炎症過剰状態が示唆された.COVID-19に伴う脳炎では,ステロイドに対し治療反応性のことがある.medRxiv. May 14, 2020(doi.org/10.1101/2020.04.12.20062646)

◆神経症状(4)深部白質・両側淡蒼球病変.54歳女性.呼吸器症状で発症後,意識障害を呈した.鼻咽頭拭い液PCR陽性,髄液traumatic tap(血清髄液).発症7日目の頭部MRIでは,テント上に,点状ないし腫瘤形成性(tumefactive)病変を,大脳深部白質や淡蒼球に認めた(図6).一部は造影効果あり.両側性,非対称性で脳室周囲の深部白質病変は急性脱髄を示唆する.もしくは血管内皮障害に伴う中枢神経小血管炎の可能性もある.Neurol Neuroimmunol Neuroinflam. May 22, 2020(doi.org/10.1212/NXI.0000000000000777)

◆新規治療(1)中国におけるワクチン開発.SARS-CoV-2のスパイク糖タンパク質を発現する組換えアデノウイルス5型(Ad5)ベクターを用いたワクチンの第1相試験.目的は安全性,忍容性,免疫原性の評価である.非盲検,無作為化にて行われた.主要評価項目はワクチン接種後7日間の有害事象とした.健常者108名を3群に分けて,用量別にワクチンを接種したところ,1回以上の副作用が報告されたのは,低用量群83%,中用量群83%,高用量群75%であった.注射部位の副作用で最も多かったのは痛みで54%.全身性の副作用としては発熱46%,倦怠感44%,頭痛39%,筋肉痛17%を認めた.ほとんどの有害事象の重症度は軽度~中等度であった.接種 28 日以内の重度の有害事象なし.ELISAで測定した特異抗体,およびウイルス中和試験やシュードウイルス中和試験で検出した中和抗体は,14日目に有意に増加し,28日目にピークとなった.酵素結合免疫スポットおよびフローサイトメトリーアッセイによる特異的T細胞応答は,14日目がピークとなった.Ad5ベクター化COVID-19ワクチンは有望で,現在,第2相試験が進行中である.Lancet. May 22, 2020(doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31208-3)
◆新規治療(2).レムデシビル続報.Gilead Sciences社によるレムデシビルのオープンラベル第3相試験.対象は試験開始時に人工呼吸器を要さない重症患者とした.397名を5日間の静注群(200名)と,10日間の静注群(197名)に無作為に割付けたが,開始時において10日間群のほうが有意に臨床的に重症であった(P=0.02).14日の時点で,7ポイントスケールで,2ポイント以上改善した頻度は,5日間群で64%,10日間群で54%であった.開始時の重症度にて調整すると,両者の改善率に有意差はなかった.副作用はいずれも70%台と高率で,内訳は嘔気9%,呼吸器症状の増悪8%,肝障害7%,便秘7%であった.RCTによる評価が望まれる.NEJM. May 27, 2020(doi: 10.1056/NEJMoa2015301).
私達も神経合併症としてMERS(可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎・脳症)を報告しましたが(J Neurol Sci),神経合併症の多彩さに驚きます.図1に示すようにウイルス受容体ACE2が脳の様々な部位(運動皮質,後帯状皮質,脳室,黒質,嗅球,中側頭回,延髄腹外側野,孤束核,迷走神経背側運動核)の,さまざまな細胞に存在することを存在することを考えれば,①ウイルス感染による直接伝播は容易に思いつきます.加えて,②parainfectious(傍感染性)の病態,③凝固異常症,④血管内皮細胞障害に伴う血液脳関門破綻や自動血圧調節能の破綻も生じ,多様な神経合併症をもたらすものと予想されます.

◆やはり無症状感染者は多い.21日間の旅程でアルゼンチンを出発したクルーズシップに乗船した217名に対してPCR検査を行ったところ,128名(59%)が陽性であった.このうち発症者は24名(19%)のみで,残り104名(81%!)は無症状であった.下船後の感染伝播を防ぐためには全員の検査が不可欠である.→ 無症状感染者が多いというCOVID-19の特徴は,規制が緩和された状況において,あらためて認識する必要がある.Thorax. May 27, 2020(doi.org/10.1136/thoraxjnl-2020-215091)
◆無症状感染者の特徴.武漢の1施設からの報告.入院患者26名の濃厚接触者調査で,PCR陽性となった78名のうち,無症状感染者33名(42.3%)と発症者45名(57.7%)の臨床的な違いを検討した報告.無症状感染者は発症者と比較して,若く(中央値37歳対56歳),女性が多く(67%対31%),肝障害が少なく(3%対20%),回復期のCD4細胞数が多く(719対474 /microL),そして鼻咽頭拭い液PCRの陽性期間が短かった(8日対19日;と言っても8日間も持続する).CD4細胞数の結果から,無症状感染者では免疫系の障害がより軽度であることが示唆された.→ やはり若年者では無症状感染者になりやすい.濃厚接触者には無症状であってもPCRを確実に行うことが感染拡大防止に必要である.JAMA Netw Open. May 27, 2020(doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.10182).
◆無症状感染者のPCR陽性(=ウイルスRNA検出)は,感染曝露から22日間と長い.中国からの報告で,無症状感染者24名において,PCR陽性の期間を検討した.感染曝露した日から2回連続陰性となった初日までの間隔は平均22.0日(標準偏差7.1日)であった.初回PCR陽性から数えると平均7.9日(標準偏差3.5日)で,前述の研究の8日とほぼ同じ結果である.PCRによるウイルスRNA検出は,必ずしも感染性を意味するわけではないことから,まず感染性を有する期間を明らかにする必要がある.Crit Care 24, 245 (2020). (doi.org/10.1186/s13054-020-02952-0)
◆退院後に再度PCR陽性となった患者からは感染しない?韓国からの報告.PCR陰性となり退院した患者60名に対してPCR検査を行ったところ,10名(16.7%)が,退院後4~24日目(最長感染から56日目)にPCRが陽性になった(鼻咽頭拭い液5名,肛門拭い液6名)(図2).臨床的にはこの10名のうち,2名がたまに咳をする程度であった.また別の1名は,退院後のPCR陽性が判明する前に,重症患者に使用するための血漿を献血していた.その際,個人防護具不十分な医療スタッフ9名が関わったが,その後,2ヶ月間,そのスタッフには症状はなく,PCRも陰性であった.→ 退院後再陽性患者では,ウイルスコピー数が少なく,感染力が乏しいのかもしれない(もしくはすでに死滅したウイルスを検出しているだけかもしれない).ただし,感染性が完全に否定されたわけではないため,患者回復血漿を採血する際,医療者は感染対策を行う必要がある(JAMA Netw Open. 2020;3(5):e209759;doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.9759).

一方,中国からも退院後のPCR再陽性について報告された.退院患者69名のうち11名(16%)が,退院後9~17日目にPCRが再陽性になった.全例で症状はなかった.PCR再陽性患者は,そうならなかった患者と比較し,疲労を呈する頻度が高く,初発症状の数が多く,CK値が高値という特徴を認めた(JAMA Netw Open. 2020;3(5):e2010475;doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.10475).
◆深部静脈血栓症は多く,かつ急速に進行する.COVID-19における血栓形成傾向は注目されているが,深部静脈血栓症(DVT)の頻度や予測因子は不明である.フランスから34名を対象とした検討(26名がPCR陽性,8名は臨床診断)が報告された.DVTは入院時に22名(65%)に認めた.ICU入室後,抗凝固療法(詳細不明)を開始したにも関わらず,わずか48時間で27名(79%)に増加した.18名(53%)は両側性,9名(26%)は近位部の血栓だった.DVTを認める症例の特徴として,D-dimer高値,フィブリノゲン減少,CRP高値が認められた.→ 早期にDVTを発見し,十分な抗凝固療法を行う必要がある.JAMA Netw Open. 2020;3(5):e2010478(doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.10478)
【以下,私見】ちなみに静脈血栓塞栓症(VTE)は,おもに深部静脈血栓症と肺血栓塞栓症からなり,先天性要因と後天性要因の相互作用により発症する.5月23日の当科抄読会でも議論になったが,欧米白人に比べて,日本人を含むアジア人のVTE罹患率は低いが,先天性血栓性素因に人種差が存在することが明らかになっている.例えば欧米白人に同定されたVTE発症に関連する遺伝子多型のFV LeidenやFII G20210Aは,アジア人には同定されない.アジア人でCOVID-19の死亡が少ない理由は,このような遺伝子が一因ではなかろうか?
◆癌患者における感染後の死亡率は高い.米国,カナダ,スペインからのがん患者928名において,COVID-19感染の影響を調べるコホート研究.主要評価項目である感染から30日目の全死亡率は13%!(121/928名)と高かった.死亡率を高める要因としては,進行性がん(調整オッズ比5.20),2つ以上の併存症(4.50),がん特異的パフォーマンス・ステータス(3.89),ヒドロキシクロロキンとアジスロマイシン併用治療(2.93),加齢(10歳の上昇で1.84),男性(1.63),喫煙(1.60)が認められた.これらは,がん治療の継続や緩和ケアを決定する上で重要な情報となる.Lancet. May 28, 2020(doi:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31187-9)
◆神経症状(1)嗅覚神経路のMRI異常信号の初めての描出.COVID-19病棟に勤務する25歳の放射線技師が,発症から1日後に無嗅症を呈した.4日後の頭部MRI,FLAIR画像で,右直回と両側の嗅球に高信号病変を呈した(図3).無嗅症が改善した発症28日後のMRIでは,これらの異常信号は消失した.→ やはり嗅上皮から感染したSARS-CoV-2は,嗅覚神経路を上行性に感染伝播するようだ.JAMA Neurol. May 29, 2020(doi:10.1001/jamaneurol.2020.2125)

◆神経症状(2)後部可逆性脳症症候群(PRES).米国の2症例(58歳男性,57歳女性)の報告.いずれの患者も,人工呼吸器装着中に,著明な上昇を伴う血圧変動を呈していたが,人工呼吸器離脱後に意識障害をきたした.頭部MRIでは後頭葉白質を中心とした可逆性の異常信号を認め(図4),PLESと診断された.SARS-CoV-2感染に伴う血管内皮細胞障害により,血圧の自動調節能の障害が生じたものと考えられた.意識障害の原因としてPLESも考慮すべきで,人工呼吸器装着中の血圧コントローは厳格に行う必要がある.J Neurol Sci. May 22, 2020(doi.org/10.1016/j.jns.2020.116943)

◆神経症状(3)炎症性サイトカイン関連・ステロイド反応性脳炎.イタリアからの報告.60歳男性.易刺激性と混迷にて発症し,5日後に意識障害にて入院,脳炎に伴う無動性無言を呈した.発熱や呼吸症状は認めなかった.頭部MRIでは異常所見はないものの,脳波は全般性徐波を呈していた.鼻咽頭拭い液PCRは陽性であったが,髄液では陰性であった.髄液細胞数18/micro-L↑,蛋白69.6 mg/dL↑さらにIL-8とTNFaも上昇していた.既知の感染症や自己抗体関連脳炎は否定された.パルス療法により意識障害は速やかに改善し,また髄液所見も改善した(図5).ウイルスの直接浸潤は否定できないものの,中枢神経のサイトカイン関連炎症過剰状態が示唆された.COVID-19に伴う脳炎では,ステロイドに対し治療反応性のことがある.medRxiv. May 14, 2020(doi.org/10.1101/2020.04.12.20062646)

◆神経症状(4)深部白質・両側淡蒼球病変.54歳女性.呼吸器症状で発症後,意識障害を呈した.鼻咽頭拭い液PCR陽性,髄液traumatic tap(血清髄液).発症7日目の頭部MRIでは,テント上に,点状ないし腫瘤形成性(tumefactive)病変を,大脳深部白質や淡蒼球に認めた(図6).一部は造影効果あり.両側性,非対称性で脳室周囲の深部白質病変は急性脱髄を示唆する.もしくは血管内皮障害に伴う中枢神経小血管炎の可能性もある.Neurol Neuroimmunol Neuroinflam. May 22, 2020(doi.org/10.1212/NXI.0000000000000777)

◆新規治療(1)中国におけるワクチン開発.SARS-CoV-2のスパイク糖タンパク質を発現する組換えアデノウイルス5型(Ad5)ベクターを用いたワクチンの第1相試験.目的は安全性,忍容性,免疫原性の評価である.非盲検,無作為化にて行われた.主要評価項目はワクチン接種後7日間の有害事象とした.健常者108名を3群に分けて,用量別にワクチンを接種したところ,1回以上の副作用が報告されたのは,低用量群83%,中用量群83%,高用量群75%であった.注射部位の副作用で最も多かったのは痛みで54%.全身性の副作用としては発熱46%,倦怠感44%,頭痛39%,筋肉痛17%を認めた.ほとんどの有害事象の重症度は軽度~中等度であった.接種 28 日以内の重度の有害事象なし.ELISAで測定した特異抗体,およびウイルス中和試験やシュードウイルス中和試験で検出した中和抗体は,14日目に有意に増加し,28日目にピークとなった.酵素結合免疫スポットおよびフローサイトメトリーアッセイによる特異的T細胞応答は,14日目がピークとなった.Ad5ベクター化COVID-19ワクチンは有望で,現在,第2相試験が進行中である.Lancet. May 22, 2020(doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31208-3)
◆新規治療(2).レムデシビル続報.Gilead Sciences社によるレムデシビルのオープンラベル第3相試験.対象は試験開始時に人工呼吸器を要さない重症患者とした.397名を5日間の静注群(200名)と,10日間の静注群(197名)に無作為に割付けたが,開始時において10日間群のほうが有意に臨床的に重症であった(P=0.02).14日の時点で,7ポイントスケールで,2ポイント以上改善した頻度は,5日間群で64%,10日間群で54%であった.開始時の重症度にて調整すると,両者の改善率に有意差はなかった.副作用はいずれも70%台と高率で,内訳は嘔気9%,呼吸器症状の増悪8%,肝障害7%,便秘7%であった.RCTによる評価が望まれる.NEJM. May 27, 2020(doi: 10.1056/NEJMoa2015301).