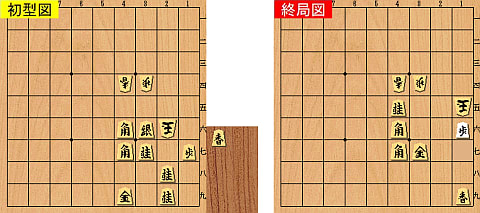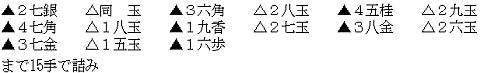ホラーなのか喜劇なのか。ジャック・ニコルソンが喜劇に出演するのも考えにくいが、純粋ホラー映画のように体に寒気が走るような怖さはこない。現実と少し離れた話だからだ。
主人公のウィル(演:ニコルソン)は、ある夜に運転中にオオカミに衝突してしまう。倒れていたオオカミに近付くと、まだ生きていたオオカミにガブられたわけだ。
そして、彼の体は少しずつオオカミに近付いていくわけだ。
初老の文芸雑誌の編集者だったウィルは、売れ行き不振のため、社長から左遷を言い渡される。アメリカ国内ではなく、行き先は東ヨーロッパ。地球儀で見ると右方面なので右遷というべきかもしれないが、断固断わり退職を決意するが、徐々にオオカミ的に研ぎ澄まされた彼には、知らなくてもいいようなことがわかってくる。別室の内緒話も聞こえてしまうし、妻の衣類からは不倫相手の匂いがわかってしまう。
さらに最悪は、夜になって月を見ると、オオカミになってしまうわけだ。動物園に侵入して動物たちを恐怖に落とし込んだり、自然公園で小鹿を殺したり。四つ足で駆けまわったり。
そして生え代わっていく体毛を処理しないといけない。
そして、殺人事件が起きるわけだが、途中で若い男性一名と若い女性1名にかみついてしまうのだが、それによってオオカミ人間が増殖を始めたわけだ。
基本的に喜劇なのだろうが、ニコルソンが演じると迫真さでハラハラしてしまう。
日本にはオオカミはいないので、本邦版をつくるとなると熊だろうか。ただ、熊はオオカミより怖いのだが、そんなに凶暴な顔ではないし、体つきもスマートではないので別の狂暴生物を使わないといけないだろう。日本で最も狂暴そうな役に相応しいのは、一番は人間に間違いないが、二番目はなんだろうか。結局、ゴジラとかになるのかもしれない。
主人公のウィル(演:ニコルソン)は、ある夜に運転中にオオカミに衝突してしまう。倒れていたオオカミに近付くと、まだ生きていたオオカミにガブられたわけだ。
そして、彼の体は少しずつオオカミに近付いていくわけだ。
初老の文芸雑誌の編集者だったウィルは、売れ行き不振のため、社長から左遷を言い渡される。アメリカ国内ではなく、行き先は東ヨーロッパ。地球儀で見ると右方面なので右遷というべきかもしれないが、断固断わり退職を決意するが、徐々にオオカミ的に研ぎ澄まされた彼には、知らなくてもいいようなことがわかってくる。別室の内緒話も聞こえてしまうし、妻の衣類からは不倫相手の匂いがわかってしまう。
さらに最悪は、夜になって月を見ると、オオカミになってしまうわけだ。動物園に侵入して動物たちを恐怖に落とし込んだり、自然公園で小鹿を殺したり。四つ足で駆けまわったり。
そして生え代わっていく体毛を処理しないといけない。
そして、殺人事件が起きるわけだが、途中で若い男性一名と若い女性1名にかみついてしまうのだが、それによってオオカミ人間が増殖を始めたわけだ。
基本的に喜劇なのだろうが、ニコルソンが演じると迫真さでハラハラしてしまう。
日本にはオオカミはいないので、本邦版をつくるとなると熊だろうか。ただ、熊はオオカミより怖いのだが、そんなに凶暴な顔ではないし、体つきもスマートではないので別の狂暴生物を使わないといけないだろう。日本で最も狂暴そうな役に相応しいのは、一番は人間に間違いないが、二番目はなんだろうか。結局、ゴジラとかになるのかもしれない。