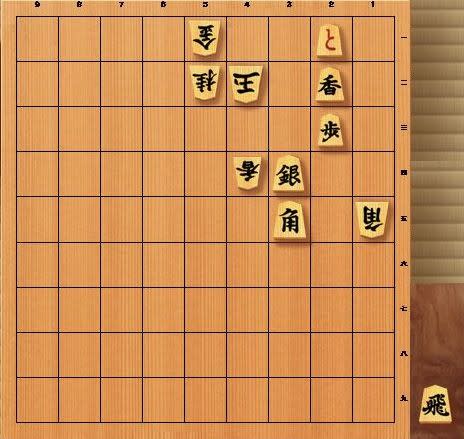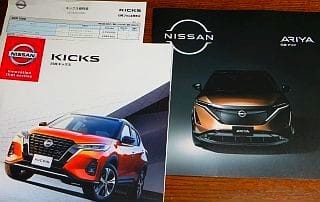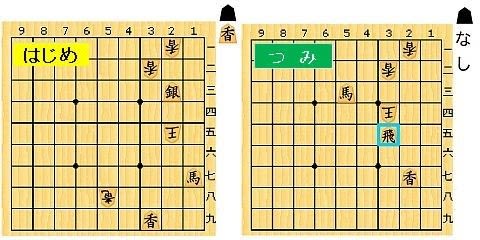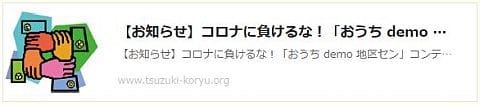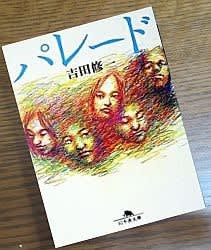総裁選については、その決め方すら厳密なルールがないということらしい。もっとも党員ではないので、いずれにしても関係ないので、誰がなるのか注視することぐらいしかできることはない。(ほとんどの国民もそうだろう)
振り返ると2012年の安倍内閣(2nd)誕生の時は5人の立候補者がいて、第一次投票の一番は石破氏、二番が安倍氏、三番が石原氏、4位町村氏、5位林氏。事前の安倍石原合意で2位3位連合が決まっていて、石原票が安倍支持に回り安倍内閣が誕生した。つまり、一回目の投票の2位争いが重要だったわけだ。今回も、場合によっては候補乱立の結果、思いもかけない力学が働くかもしれないし、結果として新党誕生に発展するかもしれない。
さて、とりあえず、巷間言われる広義の総裁候補について、ある法則で二分割してみた。政治記者ではないので、無責任な分割に、安易にWIKIPEDIA情報を利用したので、文句はそちらの方に。
グループA(敬称略・順不同)
麻生・下村・西村・菅・加藤・岸田・石破・稲田・野田
グループB(敬称略・順不同)
河野・小泉・石原
グループA・Bに分けた理由は二つある。
1.日本会議国会議員連盟に入っている(A)か、いない(B)か
2.父親が、存命の大政治家(B)か、そうではない(A)か
*理屈としては、
いかなる形での選挙も行われずに、「現総理大臣職務続行不能につき、序列一位の麻生副総理が就任すべきところ、事前に副総理を辞職していたので、繰り上がり1位の菅官房長官が自動的に総理大臣になります!」という手もあるわけだ。
振り返ると2012年の安倍内閣(2nd)誕生の時は5人の立候補者がいて、第一次投票の一番は石破氏、二番が安倍氏、三番が石原氏、4位町村氏、5位林氏。事前の安倍石原合意で2位3位連合が決まっていて、石原票が安倍支持に回り安倍内閣が誕生した。つまり、一回目の投票の2位争いが重要だったわけだ。今回も、場合によっては候補乱立の結果、思いもかけない力学が働くかもしれないし、結果として新党誕生に発展するかもしれない。
さて、とりあえず、巷間言われる広義の総裁候補について、ある法則で二分割してみた。政治記者ではないので、無責任な分割に、安易にWIKIPEDIA情報を利用したので、文句はそちらの方に。
グループA(敬称略・順不同)
麻生・下村・西村・菅・加藤・岸田・石破・稲田・野田
グループB(敬称略・順不同)
河野・小泉・石原
グループA・Bに分けた理由は二つある。
1.日本会議国会議員連盟に入っている(A)か、いない(B)か
2.父親が、存命の大政治家(B)か、そうではない(A)か
*理屈としては、
いかなる形での選挙も行われずに、「現総理大臣職務続行不能につき、序列一位の麻生副総理が就任すべきところ、事前に副総理を辞職していたので、繰り上がり1位の菅官房長官が自動的に総理大臣になります!」という手もあるわけだ。