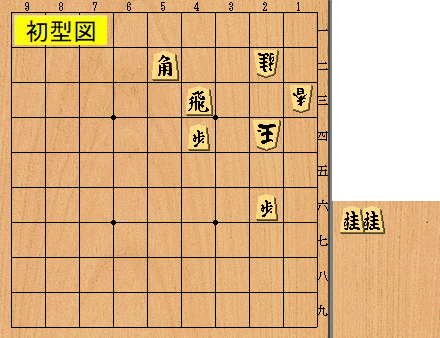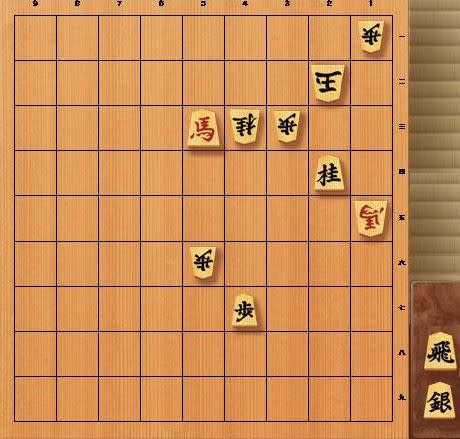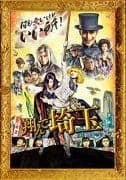1965年が初版の新書なので、コロナウイルスはまだ発見されていない。つまり、この本を読んだからと言って、昨今の事情に何か役に立つことはまったく書けないし、当時のウイルス学の一人者のレベルよりワイドショーのコメンテーターの方が詳しい(あるいは同等)ような気がする。
ただ、当時の「NHK日曜大学」の4回分のテキストということで、比較的易しく、むしろウイルス発見の歴史といったところが、現在に耐えうる部分と思う。

そして、本稿の最後に、個人的に驚いたことを書くことにする。
まず、ウイルスの存在のことだが、光学顕微鏡しかなかった時代には、発見するには大変困難な時代だった。(本には書かれていないが、野口英世先生は黄熱病の研究でノーベル賞候補にもなっていたのだが、ウイルスではなく細菌性と考えていたようで、ある意味、受賞されなくてよかったのかもしれない)
最初にウイルスの手掛かりをつかんだのは1898年のこと。牛痘の研究をしていたレフトルとフロッシュという二人の学者が牛の水泡液を濾過した液にまだ病原があることに驚く。細菌より小さいものがあるというのが新発見だった。その後、同様の細菌より小さなサイズの病原体が何種類もあるのではないかと多くの学者が考え始めた。その結果、病気ごとに見えないほど小さな病原体があるだろうと推測されることになった。(素粒子論みたいな展開だ)
そして、ウイルスに大きく近づいたのが1935年のスタンレーによる「タバコ・モザイク・ウイルス」の発見だった。一般に植物を宿主とするウイルスは大きく、このタバコ・モザイク・ウイルスは特異的に大きいサイズだった。これを遠心分離器で寄せ集めて束にして結晶化したものを光学顕微鏡で見ることができたわけだ。
ちょうどその頃、電子顕微鏡が使われるようになり、1938年にはウイルスの全体像を見ることができるようになる。といってもそのタンパク質の内部構造が解明されるのは、ずっとずっと後になる。
最初の頃は、ウイルスは細長い紙巻きたばこのような形だと思われていたのだが、より小さなウイルスを見ることができるようになると、かなり様々な形があり、様々な異なる特性があることがわかってくる。
その後、DNAの二重らせんが発見された頃、ウイルスにはDNAかRNAのどちらかが含まれているものの、そのウイルス単体では増殖できず、他の生物の細胞を壊しながら増殖することがわかってきた。といっても寄生虫のようなものではなく、直接細胞の中のたんぱく質を壊してウイルスの増殖に使うという狂暴性があるわけだ。
本書の中では、ウイルスの起源については、DNAとRNAが不完全であることから、ウイルスから生命が発生したという説と、生命の中の不完全なものがウイルスになったという二つの説のうち、後者の方を支持している。
ところで、1965年に初版が刊行された本書だが、著者の川喜田愛郎氏の略歴を調べているうちに大いに驚いたことがあった。生没は(1909年~1996年)ということで、東京帝大医学部卒業後、1949年に千葉大学医学部教授、1968年学長となっている。WHOの技術専門職でカイロに勤務されたことがあるそうだ。本書は56歳の時で、3年後に千葉大の学長になっている。
実は、千葉に住んでいたことがあるのだが、住居のすぐそばの広い敷地に豪邸があって、頑丈な門の表札に「川喜田」と書かれていた。近所の方の話では千葉大学の学長をされていた人と言われていた。住人を見たことはないのだが、おそらくはご子息と思われる人物が住んでいて、迷惑なことに大音量のロックミュージックやエレキギターの音をウイルスのように近所にまき散らしていた。おそらく父親がカイロに勤務していた時だったのかもしれない。
ただ、当時の「NHK日曜大学」の4回分のテキストということで、比較的易しく、むしろウイルス発見の歴史といったところが、現在に耐えうる部分と思う。

そして、本稿の最後に、個人的に驚いたことを書くことにする。
まず、ウイルスの存在のことだが、光学顕微鏡しかなかった時代には、発見するには大変困難な時代だった。(本には書かれていないが、野口英世先生は黄熱病の研究でノーベル賞候補にもなっていたのだが、ウイルスではなく細菌性と考えていたようで、ある意味、受賞されなくてよかったのかもしれない)
最初にウイルスの手掛かりをつかんだのは1898年のこと。牛痘の研究をしていたレフトルとフロッシュという二人の学者が牛の水泡液を濾過した液にまだ病原があることに驚く。細菌より小さいものがあるというのが新発見だった。その後、同様の細菌より小さなサイズの病原体が何種類もあるのではないかと多くの学者が考え始めた。その結果、病気ごとに見えないほど小さな病原体があるだろうと推測されることになった。(素粒子論みたいな展開だ)
そして、ウイルスに大きく近づいたのが1935年のスタンレーによる「タバコ・モザイク・ウイルス」の発見だった。一般に植物を宿主とするウイルスは大きく、このタバコ・モザイク・ウイルスは特異的に大きいサイズだった。これを遠心分離器で寄せ集めて束にして結晶化したものを光学顕微鏡で見ることができたわけだ。
ちょうどその頃、電子顕微鏡が使われるようになり、1938年にはウイルスの全体像を見ることができるようになる。といってもそのタンパク質の内部構造が解明されるのは、ずっとずっと後になる。
最初の頃は、ウイルスは細長い紙巻きたばこのような形だと思われていたのだが、より小さなウイルスを見ることができるようになると、かなり様々な形があり、様々な異なる特性があることがわかってくる。
その後、DNAの二重らせんが発見された頃、ウイルスにはDNAかRNAのどちらかが含まれているものの、そのウイルス単体では増殖できず、他の生物の細胞を壊しながら増殖することがわかってきた。といっても寄生虫のようなものではなく、直接細胞の中のたんぱく質を壊してウイルスの増殖に使うという狂暴性があるわけだ。
本書の中では、ウイルスの起源については、DNAとRNAが不完全であることから、ウイルスから生命が発生したという説と、生命の中の不完全なものがウイルスになったという二つの説のうち、後者の方を支持している。
ところで、1965年に初版が刊行された本書だが、著者の川喜田愛郎氏の略歴を調べているうちに大いに驚いたことがあった。生没は(1909年~1996年)ということで、東京帝大医学部卒業後、1949年に千葉大学医学部教授、1968年学長となっている。WHOの技術専門職でカイロに勤務されたことがあるそうだ。本書は56歳の時で、3年後に千葉大の学長になっている。
実は、千葉に住んでいたことがあるのだが、住居のすぐそばの広い敷地に豪邸があって、頑丈な門の表札に「川喜田」と書かれていた。近所の方の話では千葉大学の学長をされていた人と言われていた。住人を見たことはないのだが、おそらくはご子息と思われる人物が住んでいて、迷惑なことに大音量のロックミュージックやエレキギターの音をウイルスのように近所にまき散らしていた。おそらく父親がカイロに勤務していた時だったのかもしれない。