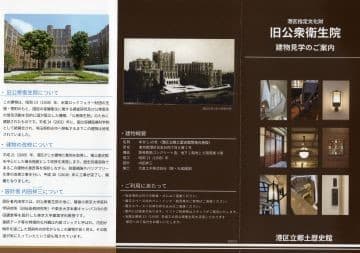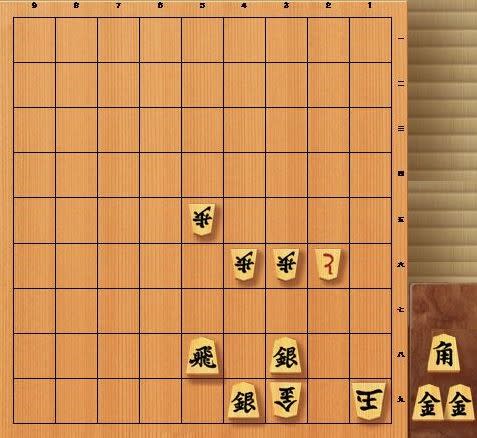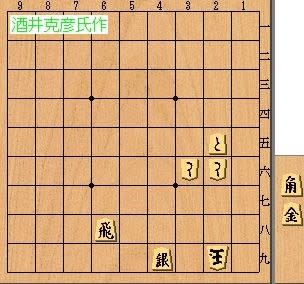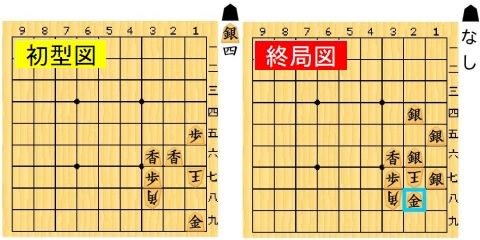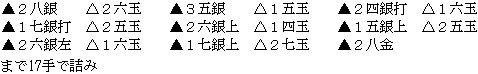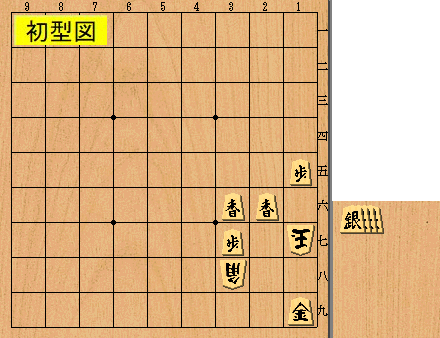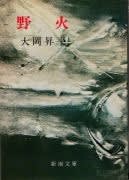実話は、モータウンレコードのトップスターだったダイアナ・ロスとスープリームズのことだそうだ。ただ、かなり実際は異なる部分が多いようだ。三人組のアフリカ系の少女がオーディションで落選したのに、社長に目をつけられて、ジミーという男性シンガーのバックコーラスから、少しずつ這い上がっていくストーリーなのだが、元々、歌のうまいリーダーが、ルックス重視と言うことで、リーダーを交代させられる。
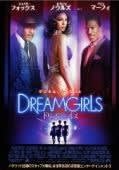
そのうち、グループ間のひび割れが徐々に大きくなって、ついに爆発。脱退ということになる。よくある話だ。そして組み直したグループはソフィストケートされたヒット曲を次々に並べていくわけだ。
ビオンセが新グループのリーダー役を演じるのだが、本映画では、それほど歌がうまいことにはなっていない。しかもダイアナ・ロスとはまったく違うような気がする。(もっとも、ダイアナ・ロスも映画『ビリー・ホリデー物語』の主演だったが、本物とはかなり違うと言われた)
実在モデルはいないが、エディ・マーフィーが演じるジミーだが、おそろしくソウルっぽい歌唱力が高い。とても俳優とは思えない。彼は黒人であるからこそアカデミー賞に縁がないが、例外的にこの映画で助演男優賞を得ているのだが、この映画の中の役の重要度から言うと5番目位だから、いかにミュージカルが得意かが知れてくる。歌手をやるべきなのではないだろうか。映画よりも差別は少ないような気がする。
歌手が俳優(女優)より上手に役を演じ、俳優が歌手よりも上手に歌を歌う。要するに多芸タレントが集まったわけだ。
本映画は、楽しいミュージカルになっていて、ウキウキした気分で劇場を出られるように、初期にグループから脱退した女性も最後に一緒に歌うことになっているが、実話では、落ち込んだまま若くして世を去っている。
まったく映画とは関係ないのだが、出演した主要メンバーは揃ってソウルフルでパワフルに歌う。もし自分も彼らのように歌がうまければ、全く違う人生になったのだろうなと、今さら思ってしまう。スターダムか道端の枯れすすきか。
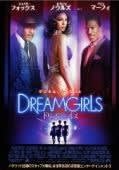
そのうち、グループ間のひび割れが徐々に大きくなって、ついに爆発。脱退ということになる。よくある話だ。そして組み直したグループはソフィストケートされたヒット曲を次々に並べていくわけだ。
ビオンセが新グループのリーダー役を演じるのだが、本映画では、それほど歌がうまいことにはなっていない。しかもダイアナ・ロスとはまったく違うような気がする。(もっとも、ダイアナ・ロスも映画『ビリー・ホリデー物語』の主演だったが、本物とはかなり違うと言われた)
実在モデルはいないが、エディ・マーフィーが演じるジミーだが、おそろしくソウルっぽい歌唱力が高い。とても俳優とは思えない。彼は黒人であるからこそアカデミー賞に縁がないが、例外的にこの映画で助演男優賞を得ているのだが、この映画の中の役の重要度から言うと5番目位だから、いかにミュージカルが得意かが知れてくる。歌手をやるべきなのではないだろうか。映画よりも差別は少ないような気がする。
歌手が俳優(女優)より上手に役を演じ、俳優が歌手よりも上手に歌を歌う。要するに多芸タレントが集まったわけだ。
本映画は、楽しいミュージカルになっていて、ウキウキした気分で劇場を出られるように、初期にグループから脱退した女性も最後に一緒に歌うことになっているが、実話では、落ち込んだまま若くして世を去っている。
まったく映画とは関係ないのだが、出演した主要メンバーは揃ってソウルフルでパワフルに歌う。もし自分も彼らのように歌がうまければ、全く違う人生になったのだろうなと、今さら思ってしまう。スターダムか道端の枯れすすきか。