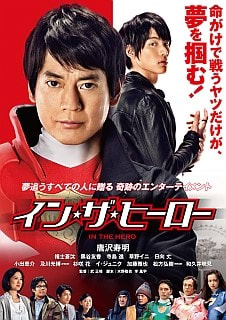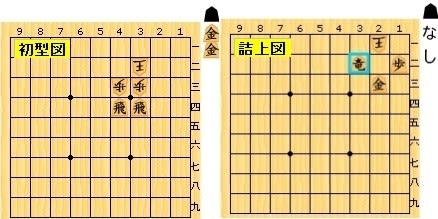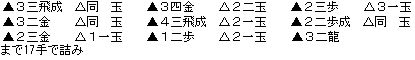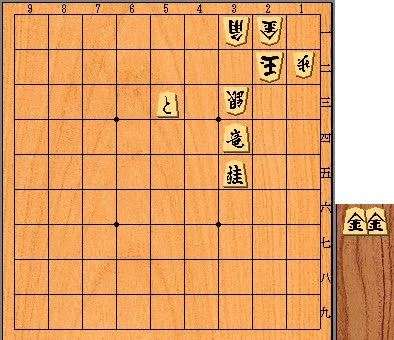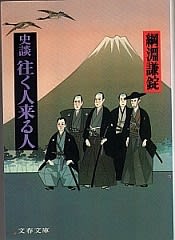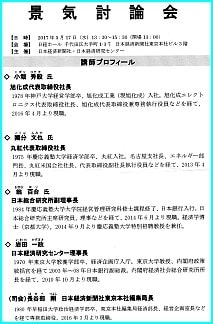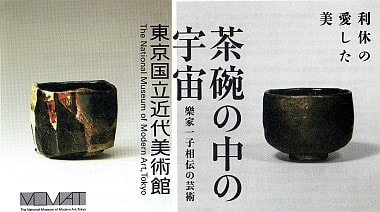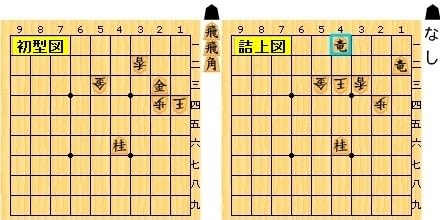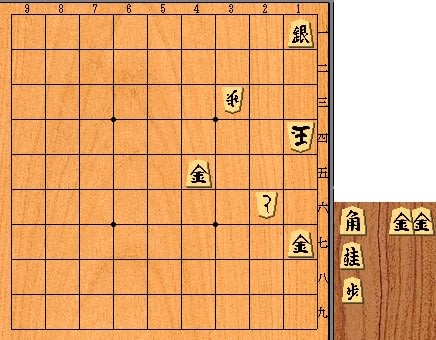明石城に隣接して明石市立文化博物館がある。明石は古来より交通の要所であり、歴史上の財産は多くあるのだろうが、幸か不幸かもっと重大な物件が発見されたことで有名になっている。

それは、明石原人と呼ばれる人類の腰骨なのである。
考古学上有名でありまた残念で謎に包まれたこの骨については松本清張も小説にしているほどミステリアスである。
発見されたのは1931年。アマチュアの考古学ファンである直良信夫が明石市の西八木海岸の崩れかけた崖から、発掘したものである。直良は、同地で発見されている動物化石や石器などからして後期石器時代(5万年前~10万年前あたり)の原人と主張。しかし、調査した東京帝国大学を頂点とする考古学会は、直良説を無視し、この骨を直良に返却。石膏型だけが東大に残り、化石は直良の東京の自宅に保管されていた。
そして、昭和20年に米軍機による空襲によって、明石原人の化石は直良の自宅ごと焼失してしまった。
ところが、焼失の2年後、東大に放置されていた石膏型を東大の某教授が発見し、この腰骨の研究をしたところ、古い人類のものと主張されることになり、元に戻って西八木海岸の発掘が行われたのだが、巨費を投じたにもかかわらず、東大と直良の感情がもつれたまま、別の場所を掘ってしまう。ナッシングだった。
さらに、事情は複雑で、古い人類の特徴があると思われていたが、逆に現代人よりも未来人(腰骨が縦長)に近いということになり、旧人否定論も登場。そもそも最初の化石が、骨なのか石なのかということがわからなくなる。化石化する過程で骨が変形することもあるのだが、石膏型をみてもわからない。
当時は、日本には石器時代人はいなくて、縄文時代に南方から、弥生時代に中国方面から人類が日本に来た、と考えられていたため、いかにも邪論のように思われたようだ。
しかし、現在は旧石器時代人が日本にいたのは確実と思われているのだが、実は少し前に手製のニセ石器をバラマク考古学者が現れて、石器時代の考古学研究は完全に破壊されてしまったわけだ。

それは、明石原人と呼ばれる人類の腰骨なのである。
考古学上有名でありまた残念で謎に包まれたこの骨については松本清張も小説にしているほどミステリアスである。
発見されたのは1931年。アマチュアの考古学ファンである直良信夫が明石市の西八木海岸の崩れかけた崖から、発掘したものである。直良は、同地で発見されている動物化石や石器などからして後期石器時代(5万年前~10万年前あたり)の原人と主張。しかし、調査した東京帝国大学を頂点とする考古学会は、直良説を無視し、この骨を直良に返却。石膏型だけが東大に残り、化石は直良の東京の自宅に保管されていた。
そして、昭和20年に米軍機による空襲によって、明石原人の化石は直良の自宅ごと焼失してしまった。
ところが、焼失の2年後、東大に放置されていた石膏型を東大の某教授が発見し、この腰骨の研究をしたところ、古い人類のものと主張されることになり、元に戻って西八木海岸の発掘が行われたのだが、巨費を投じたにもかかわらず、東大と直良の感情がもつれたまま、別の場所を掘ってしまう。ナッシングだった。
さらに、事情は複雑で、古い人類の特徴があると思われていたが、逆に現代人よりも未来人(腰骨が縦長)に近いということになり、旧人否定論も登場。そもそも最初の化石が、骨なのか石なのかということがわからなくなる。化石化する過程で骨が変形することもあるのだが、石膏型をみてもわからない。
当時は、日本には石器時代人はいなくて、縄文時代に南方から、弥生時代に中国方面から人類が日本に来た、と考えられていたため、いかにも邪論のように思われたようだ。
しかし、現在は旧石器時代人が日本にいたのは確実と思われているのだが、実は少し前に手製のニセ石器をバラマク考古学者が現れて、石器時代の考古学研究は完全に破壊されてしまったわけだ。