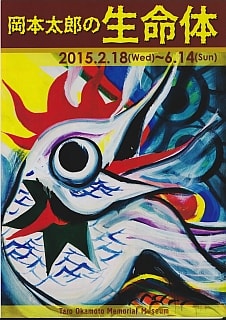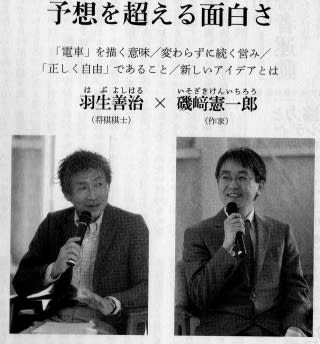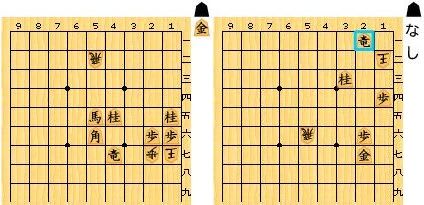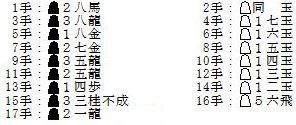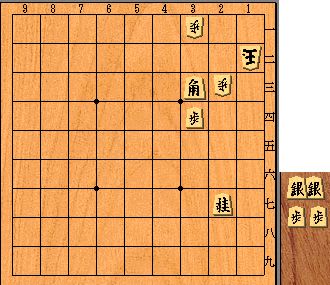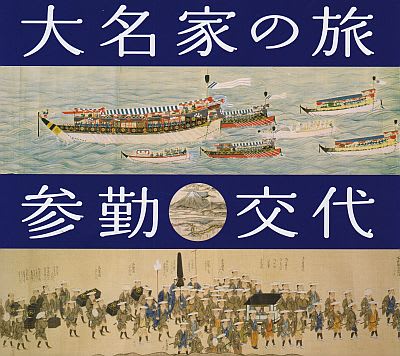千代田区立日比谷図書文化館で開催中(~6/19)のルドゥーテ「美花選」展へ。日比谷公園の中ということで、日比谷公園が花に包まれる時期に特別展が開かれている。
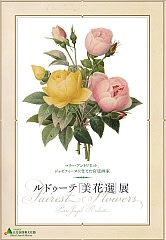
このルドゥーテさんだが、マリー・アントワネット、ジョゼフィーヌに仕えた宮廷画家ということであるが、マリー・アントワネットとジョゼフィーヌと一言でいうけれどその間にはフランス革命があって、次々とギロチンの上下運動が行われている。生年月日をみると、マリー・アントワネットが1755年生まれ、ルドゥーテは1759年生まれ、ジョゼフィーヌは1763年生まれ。ちょうど間である。マリー・アントワネットが捕まった時には故郷のベルギーに逃げていたのだろうか。

そして、彼の作品は基本的に「版画」である。それも「点刻彫版」という技法で、特徴は、花弁や葉の輪郭を線で描くのではなく、無数の小さな点を刻んで表現する方法である。結果として緻密で繊細優美ということになる。デジカメの画素みたいな技法なのだろう。

さらに、刷り上がった作品に、うっすらと着色をしているそうだ。初期の頃は肉筆も描いていたようだ。
チューリップとバラの品種改良はヨーロッパ文明の象徴ともいえるだろうが、特に描くのを得意としていた。そのあたりが宮廷画家の本領なのだろうか。
なお、本展覧会の付帯行事の一環の中に、定員40名、参加費500円で、「大人の塗り絵、ルドゥーテのバラを塗ってみよう!」というのがあるようだが、「それはまったく違うでしょ」と言いたい。
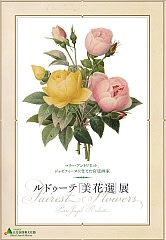
このルドゥーテさんだが、マリー・アントワネット、ジョゼフィーヌに仕えた宮廷画家ということであるが、マリー・アントワネットとジョゼフィーヌと一言でいうけれどその間にはフランス革命があって、次々とギロチンの上下運動が行われている。生年月日をみると、マリー・アントワネットが1755年生まれ、ルドゥーテは1759年生まれ、ジョゼフィーヌは1763年生まれ。ちょうど間である。マリー・アントワネットが捕まった時には故郷のベルギーに逃げていたのだろうか。

そして、彼の作品は基本的に「版画」である。それも「点刻彫版」という技法で、特徴は、花弁や葉の輪郭を線で描くのではなく、無数の小さな点を刻んで表現する方法である。結果として緻密で繊細優美ということになる。デジカメの画素みたいな技法なのだろう。

さらに、刷り上がった作品に、うっすらと着色をしているそうだ。初期の頃は肉筆も描いていたようだ。
チューリップとバラの品種改良はヨーロッパ文明の象徴ともいえるだろうが、特に描くのを得意としていた。そのあたりが宮廷画家の本領なのだろうか。
なお、本展覧会の付帯行事の一環の中に、定員40名、参加費500円で、「大人の塗り絵、ルドゥーテのバラを塗ってみよう!」というのがあるようだが、「それはまったく違うでしょ」と言いたい。










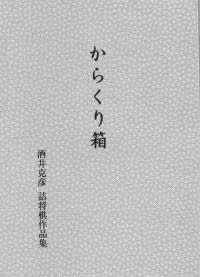
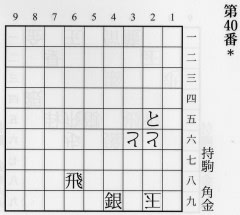
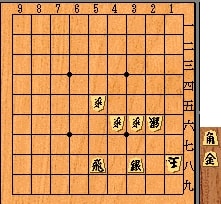
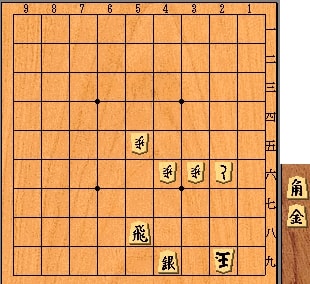
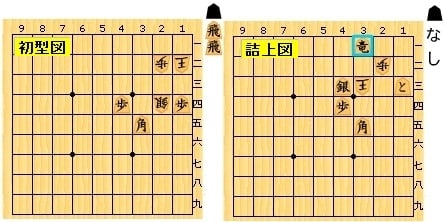
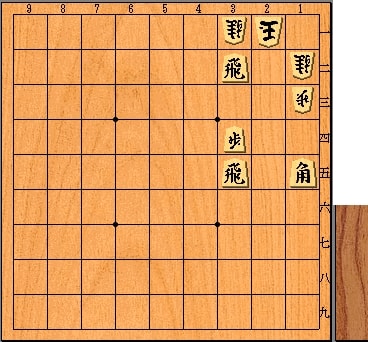


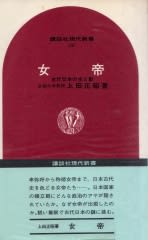 日本の女帝問題というと、イコール皇太子ご長女さまの問題と捉えられかねないが、本著が書かれたのは昭和46年。その時、現皇太子さまは10歳で、現皇太子妃は7歳で、現皇太子弟親王は6歳で現皇太子弟親王妃は5歳位のはずで、その後、こういう展開になろうとは想像していなかっただろう。
日本の女帝問題というと、イコール皇太子ご長女さまの問題と捉えられかねないが、本著が書かれたのは昭和46年。その時、現皇太子さまは10歳で、現皇太子妃は7歳で、現皇太子弟親王は6歳で現皇太子弟親王妃は5歳位のはずで、その後、こういう展開になろうとは想像していなかっただろう。