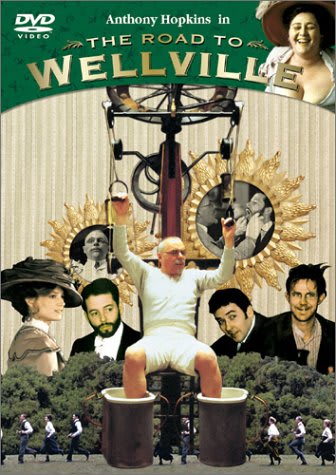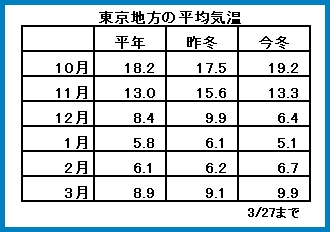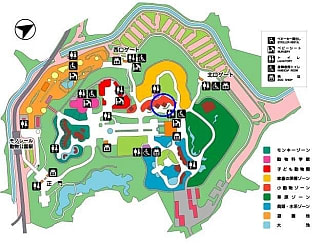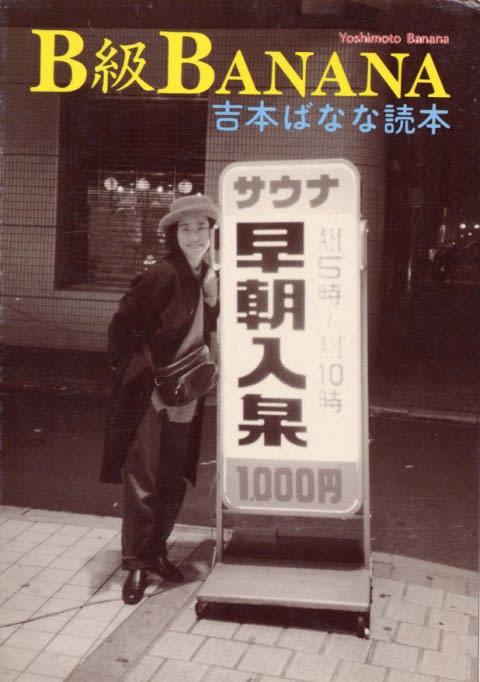郊外の街道をクルマで走ると、時々見かけていたのだが、とんかつチェーン「かつや」が新橋駅前の雑居ビル1階に出店されたので昼食に通ってみる。どうも、運転中にトンカツを食べると、胃にもたれそうで、その気分にならないのだが、街中ならどうでもいい。眠くなったら個室型のネットカフェで昼寝をすれば、・・・という理想のサラリーマンにはなり切れないのだが。
郊外の街道をクルマで走ると、時々見かけていたのだが、とんかつチェーン「かつや」が新橋駅前の雑居ビル1階に出店されたので昼食に通ってみる。どうも、運転中にトンカツを食べると、胃にもたれそうで、その気分にならないのだが、街中ならどうでもいい。眠くなったら個室型のネットカフェで昼寝をすれば、・・・という理想のサラリーマンにはなり切れないのだが。まず、大型の食券販売機がある。メニューはトンカツでも結構多い。基本は、「カツどん」、「ソースカツどん」「ロース定食」「ヒレ定食」「カツカレー」それらに、大中小といったところか。カツ丼の普通サイズが490円。カウンターの空いた席に座ると、女性店員兼日本語学校学生がお茶を出してくれる。調理は男性数名(たぶん日本人)。もちろん昼間はオーダーを聞いてからカツを揚げたりしないから、数分ででてくる。1回目はカツどん。
「かつや」がどうやってキャベツを刻んでいるかよくわからないが、実は、なるべくとんかつ屋でキャベツを食べないことにしている。以前、あるとんかつ屋で聞いた(&見た)のだが、キャベツを縦に二つに割り、「電動キャベツスライサー」で千切りにする。電気ノコギリと電気カンナを足して二で割ったような調理器具だが、問題はキャベツの葉を一枚ずつ洗えないことだ。一つは残留農薬の問題が気になる。そして、もう一つは芋虫さんのこと。キャベツの奥底に身を隠すど根性芋虫さんもまず助からない。ちょっと嫌だ。だから、カツ丼にするわけだ。
そして、もちろんチェーン店はマニュアル通り調理するのだから、できあがりは美しい。そして、衣はしっかりとして、肉質はあくまでも柔らかい。というか、これは規格化された工業製品という感じだ。店内の表示を見ると、カナダポークと書かれている。厚いのに前歯で噛み切れる(マックのハンバーガーみたいだ)。粗い筋もない。最近はこういうソフィストケイトされたのがいいのかなって思うとともに、やはり荒っぽい手揚げのトンカツ屋も残るのだろうと、思う。こういう、品質の一元化で豚肉の完成品作り上げる、というのは、何かトヨタのクルマに乗りすぎて、誤った日本人像を作り上げた、カナダ人の勘違いだろうと思ってしまう。味覚は刺激を求めるものだし、それは規格に対するプラスマイナスのムラの中にあるのだろう。まあ、この値段ではこのやり方が正しいのだろうけど。
二日ほどして、また行って今度はヒレカツを注文したのだが、まあ、見解は同様。ただし、定食だったので千切りキャベツがどっと盛られていた。しょうがない。
後日、ホームページを確認したら、アークランドサービスと言う会社が経営していた。以前、CASAのドミナントだったらしい。現在、全国130店超に成長していた。
牛肉消費量の下落は豚肉消費量の増で埋められているということだが、牛丼チェーンの顧客をこういうところで吸収しているのだろう。よく見ると、イメージカラーもオレンジ色ということで、某チェーンと似ている。
さらに、トンカツの記事を読んでいると、豚肉は指定産地で品質管理されているそうだ。納得。さらに、コメはコシヒカリの独自ブレンドということだ。もともと新潟の会社だったそうなので、各種のコシヒカリの秘密に明るいのだろうと納得。そして、パン粉は生パン粉使用で無添加という。無添加を強調するということは、添加パン粉というのがあるのだろうか??そして、もっとも知りたいキャベツの秘密は?どこにも書かれていない。