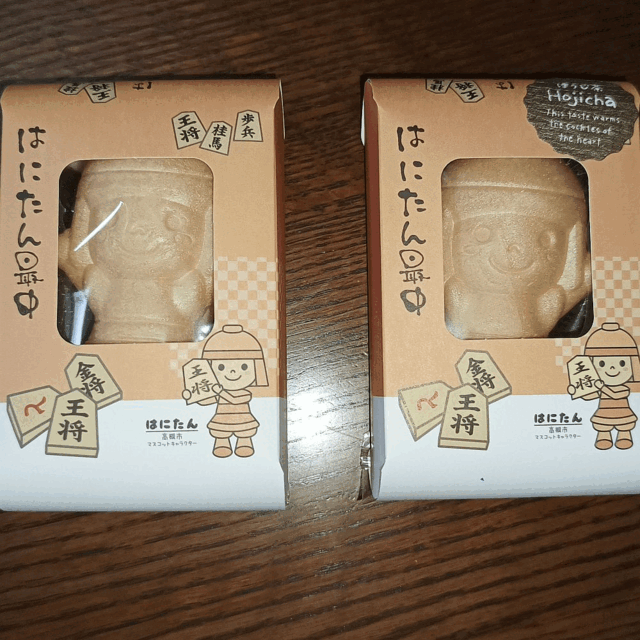横浜市産の果実で有名なのが、梨と葡萄かもしれない。浜なし、浜ぶどうと言われている。郊外の道路端では「浜なし」というようなノボリが出ていて、横浜市から出身地の親戚に梨を贈る人が多い。
ところが梨の生産では、途中で摘果したり、傷んだものがあったりと、最終的に販売に回さないものがでる。地元の菓子店ではそういうものを引き取って洋菓子の材料につかったりしているが、KIRINの氷結にmottainaiシリーズがあり、梨果汁0.2%入っているお酒が売り出された。

ところが、ちょっと口に合わないような感じだった。
何しろ、梨の特徴である、ザラザラ感がない。あえていうと甘いドリンクであるが、梨の味という感じがないわけだ。
せっかくの企画なのだろうが、mottainai がmottainai と思った。ザラザラな感じを残すならジャムとかどうだろう。
ところが梨の生産では、途中で摘果したり、傷んだものがあったりと、最終的に販売に回さないものがでる。地元の菓子店ではそういうものを引き取って洋菓子の材料につかったりしているが、KIRINの氷結にmottainaiシリーズがあり、梨果汁0.2%入っているお酒が売り出された。

ところが、ちょっと口に合わないような感じだった。
何しろ、梨の特徴である、ザラザラ感がない。あえていうと甘いドリンクであるが、梨の味という感じがないわけだ。
せっかくの企画なのだろうが、mottainai がmottainai と思った。ザラザラな感じを残すならジャムとかどうだろう。